
R-2021-050
岸田政権の下での成長戦略によって経済成長率はどの程度上昇すると見込まれるのか。わからないとすれば、何をすべきか。
2022年に入り、政府による「中長期の経済財政に関する試算」(2022年1月14日)が公表された。試算は、政府が取り組む経済再生と財政健全化に向けた政策の進捗状況を評価するとともに、今後の政策の検討に必要となる基礎データの提供を目的として、我が国の中長期的な経済財政の姿を展望するものとなっている。政府により年2回(通常、年初と年央)公表されるが、この1月に公表された今回の試算は岸田政権の下での初めての試算となった。
前号では、「岸田政権の下での成長戦略によって経済成長率はどの程度上昇すると見込まれるのか。わからないとすれば、なぜか」といった問題意識の下、成長政策がその主たる政策目的である生産性に対して与える効果をきちんと計測できない、という我が国の成長政策の課題を論じた。その際の議論の最後に、新たに発足した岸田政権による成長政策への取組を読み解く1つの鍵として今回の試算に触れたが、以下では試算の中身を確認しつつ、前号に引き続き、成長政策の課題を論じていきたい。
| ・変わらぬ将来の経済成長の姿 ・なぜ、異なる政権の異なる成長政策の下でも将来の経済成長の姿が変わらないのか ・成長政策の課題 ・成長政策にこそEBPMの徹底を |
変わらぬ将来の経済成長の姿
試算の中では、「政府が掲げるデフレ脱却・経済再生という目標に向けて、政策効果が過去の実績も踏まえたペースで発現する姿」(「成長実現ケース」)として、2031年度までのおよそ10年間にわたる将来の経済成長の推移が示されている。
ここで言う政策効果とは、まさに、岸田政権の下での「新しい資本主義」の起動により期待される効果であり、試算の中では、こうした新たな取組により、潜在成長率が2020年度の0.5%から2025年度以降には成長目標である2%に増加していく姿が示されている[1]。実質GDP成長率についても、そうした潜在成長率へと徐々に収れんしていく中、やはり2025年度以降に持続的に2%に達する姿となっている(下図を参照)[2]。

(出所)内閣府資料(「国民経済計算」、「中長期の経済財政に関する試算」)より作成. 実線は実績値、破線は将来の値を表す.
こうした経済成長の姿について、経済財政諮問会議の議論(「中長期の経済財政運営に向けて」(2022年1月14日))の中では、「取組を強化することで実現可能」とされ、我が国の成長政策が目指すべき目標として位置づけられている。前号では、この10年間実現されてこなかった「実質2%を上回る成長の実現」といった成長目標について、筆者は「真に目指すべきものなのか、我が国の成長期待のアンカーとして据えるべきものなのか、それとも、財政健全化に向けた議論の1つのシナリオにすぎないのか」といった問題提起を行ったが、今回の政府による一連の議論を見ると、目指すべき目標、ということであった。
他方、2025年度以降に2%に達するといった将来の経済成長の姿は、実は、岸田政権以前に展望されたもの(2021年7月に公表された前回試算)から変わっていない(下図を参照)。

(出所)内閣府資料(「中長期の経済財政に関する試算」)より作成.
なぜ、異なる政権の異なる成長政策の下でも将来の経済成長の姿が変わらないのか
変わっていないということは、岸田政権の下での政策であっても、菅政権の下での政策であっても将来の経済成長に与える影響が同じであることを意味するが、こうしたことは、なぜ起こるのか。
これは、前号で成長政策の課題として議論したように、成長政策は、主に、生産性の向上を目的として実施されるが、それにも関わらず、政策によりどの程度生産性が上昇すると見込まれるのかがわからないことに起因している。「取組を強化することで実現可能」としつつも、試算の中では、時々の成長戦略の効果を見積もることができず、将来の経済成長の姿については外生的に取り扱わざるを得ないのである。具体的には、成長政策の主たる政策目的であるとともに将来の潜在成長の姿を規定するTFP(全要素生産性)について、新政権の下で初めてとなる今回の試算においても、前政権下での前回の試算と全く同じ想定を置くことで、同じ潜在成長の姿が得られている[3]。
「目指すべき目標であるなら、岸田政権の下での取組が進められる中で、実現に向けた具体的な道筋が多少とも見えるとよい」とは前号の問題提起であるが、「実現可能」といった評価がなされる一方、2%を上回るといった成長目標の実現に向けた具体的な道筋が描かれることはなかった。岸田政権の下で実施される「デジタル」、「気候変動」、「経済安全保障」、「科学技術・イノベーション」といった成長政策が、日本経済の“どの分野”に、“どの程度”の影響を与えるか、わからないのである。
成長政策の課題
前号の繰り返しとなるが、成長政策における課題は、政策効果をきちんと計測できないこと、その結果、より生産性の高い経済の実現に向けた政策の検証、議論が進みにくいことであると考えている。
政府はEBPM(証拠に基づく政策立案)を推進する下で、成長政策についてもKPI(成果目標)を設け、施策の進捗状況を確認・評価する中で取り組んできた。2%を上回るといった成長目標を実現する上で鍵となる生産性については、労働生産性[4]をKPIとして掲げ、「製造業の労働生産性について年間2%を上回る向上」、「サービス産業の労働生産性の伸び率が2.0%となることを目指す」といったように、経済活動を製造業とサービス産業に分け、そのそれぞれについて、おそらく経済全体の成長目標との整合性を考慮する中、2%といった目標を設けて取組を進めてきた。
前号でみたとおり、この10年間、2%を上回るといった経済全体の成長目標が達成されない中で、こうしたKPIも達成されてこなかったが、EBPMの議論の中では、どのように評価・分析されてきたのであろうか。実際、政府は、2020年11月に、KPIの達成に向けた進捗が十分でないものとして、上記2つを挙げている(下図を参照)。

(備考)「成長戦略のKPIの達成に向けた進捗状況について」(2020年11月6日)より抜粋.
これによれば、KPIとして設定された労働生産性上昇率は、2016年から2018年の3か年平均で、製造業については1.1%、サービス産業については-0.03%とされ、2%の目標を達成していない。そこで、未達成であることへの政府の評価を確認するために「課題分析」欄を見ると、計算方法と労働投入、アウトプットそれぞれの期間中の動きについての記述はあるが、なぜ労働投入の増加に比してアウトプットが十分に増加していないのか(つまり、生産性が上昇していないのか)といった重要部分についての政策の影響を含めた評価・分析が行われていない。やはり、わからないのである[5]。
試算の中では2025年度以降に成長目標が達成される姿が示されているが、こうした状況を鑑みると、仮に、岸田政権の下で成長政策を5年続けたとして、5年後、2%を上回るといった成長目標の達成状況について意味のある評価ができるだろうか。もし、成長目標を達成できていなかった時、成長政策の何が問題で、どこを改善すべきかといった検証、議論をエビデンスに基づいて行うことができるだろうか。
成長政策にこそEBPMの徹底を
上述のとおり、過去、生産性が十分に上昇してこなかった背景・理由を定量的な根拠をもとに評価・分析することができない、また、将来についても、成長政策の効果を見積もることができない、といったことは、成長政策を進めていくことの難しさを表している。
そうした困難な政策分野にもかかわらず、数値目標を定め、かつ、それを「実現可能」として目指すのであれば、その進捗について定量的に評価できる仕組みを検討する必要があろう。まずは、利用可能なデータをもとに、経済のどの分野で生産性が上昇/低下したのかといったファクトを整理するとともに、その背景に関する評価・分析から始めてはどうか。製造業、サービス産業といった分類での評価が難しいのなら、定量的に把握可能な範囲で分野を更にブレイクダウンするなど、政策が“どの分野”に影響を及ぼしてきたのか、及ぼすことになるのかといった基本的な問いに答えるための基礎作業が求められる。
加えて、政策が“どの程度”の影響を及ぼすかといった点についても知りたいと思えば、まず、試算で用いている仮定の検証をしてはどうか。「日本経済がデフレ状況に入る前に実際に経験した上昇幅とペース」として将来のTFPの上昇を見込むのであれば、そうした非デフレ期におけるTFP上昇のメカニズム(なぜTFPは上昇したのか)、また、アベノミクスの下、デフレではない状況となるにも関わらず過去の非デフレ期で経験したTFPの上昇が見られない背景(なぜTFPは上昇しないのか)などを検証することを通じて、我が国における実態を反映したTFP上昇の姿について示唆を得ることはできないだろうか。過去を知ることは、将来を知る上でも重要な手掛かりになると考えている。
経済財政諮問会議における議論の中では、財政健全化政策については、「エビデンスに基づく効果的・効率的な支出の実行」、「試算からの乖離の要因についてレビュー」とEBPMが高く意識されているが、2%を上回る成長を実現可能として目指し、取り組むのであれば、成長政策にこそ、そうした徹底したEBPMの適用が求められる。
実は、こうした点について、経済財政諮問会議(令和4年第1回、2022年1月14日)における個々の発言まで見ると、民間有識者からも同様の問題意識が指摘されていることに気づく。有識者の一人は、「(前略)今まで成長実現ケースというのを示してきているが、これがなかなか実現できていなかったというのも事実で、なぜこれが乖離してきたのか、なかなか目標が達成できなかったのはどういう理由なのかをしっかりチェックをして(後略)」と指摘し、政策の効果検証を行う必要性を主張している。また、別の有識者も、将来の経済成長の姿について、「(前略)過去の試算と異なり今回は実現できるというなら何故できるのか、民間との試算の違いは何なのか、しっかりとマーケットと向き合ってコミュニケーションをする必要性があるのではないか」と成長目標の実現に向けた具体的な道筋を求めている。
上述のとおり、政策効果の検証も、具体的な道筋も、政策効果をきちんと計測できないことを背景に行われてこなかったわけだが、10年実現されてこなかった2%を上回るといった成長を真に目指すのであれば、わからないからできない、といった現状を変えていく必要があるということであろう。経済財政諮問会議や新しい資本主義実現会議における議論を含め、成長政策を進めていく上での政府の取組に見られる“変化”に着目し、引き続き、我が国の成長目標の意味を考えていきたい。
(「10年変わることのない日本の成長目標の意味を改めて考える(3)」に続く)
[1] 試算の中では、「成長実現ケースについては、『成長と分配の好循環』に向けて、『科学技術立国の実現』、地方を活性化し、世界とつながる『デジタル田園都市国家構想』、『経済安全保障』を3つの柱とした大胆な投資や、働く人への分配機能の強化等を推進することにより、所得の増加が消費に結び付くとともに、政策効果の後押しもあって民間投資が喚起され、潜在成長率が着実に上昇することで、実質2%程度、名目3%程度を上回る成長率が実現する。」と説明されている。
[2] 需要面から経済の短期的な変動も含めた動きを捉える実質GDP成長率は、供給面から経済の中長期的な成長力を測る潜在成長率の周りを、振幅を繰り返しながら推移するが、試算で示される将来の姿の中では、実質GDP成長率が潜在成長率に徐々に収れんしていく。これは、経済の需要側(実質GDP)と供給側(潜在GDP)の間に存在する乖離(不均衡)が徐々に解消されていくことを背景としているが、一度、両者が一致(均衡)した後は、供給側により経済が規定されることを示している。
[3] 今回試算、及び前回試算において、TFP上昇率は、「日本経済がデフレ状況に入る前に実際に経験した上昇幅とペース」(具体的には、1982年度から1987年度までの5年間に見られた0.9%程度の上昇)で、「足元の水準(0.4%程度)から1.3%程度まで上昇する」と仮定されている。
[4] 労働生産性は、TFPと資本と労働の比である資本装備率により表わされ、その上昇にはTFPが重要な役割を果たす。
[5] ちなみに、製造業については、「令和2年度革新的事業活動実行計画重点施策に関する報告書案」(2021年6月18日)の中で、「製造業の労働生産性は、2017 年から 2019年までの3か年で 2.2%の伸び率となり、KPIを上回っている」と報告され、「KPI の目標達成に向けて進捗している」と評価されている。他方で、本文のとおり、2016年から2018年の3か年平均では、1.1%とKPIを下回っていると評価されていた。EBPMは証拠に基づく政策立案を意味し、証拠の1つとしてデータが活用されているわけだが、1年期間を変えて計算し直すことにより評価が変わるようなものを、EBPMが求めているであろう政策手段と目的の安定的な関係性を裏付ける証拠として理解してよいか自信が持てない。











































































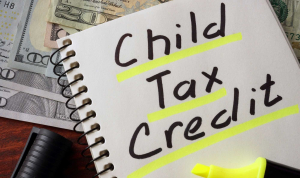
























































































































































































_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)





















_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)

































































