
R-2023-060
| ・
・
世界的なインフレ動学の不安定化 ・金融政策正常化に向けての課題 |
消費者物価の上昇率2%超が続く中で、日銀が金融政策の正常化をどのように進めるかに注目が集まっている。植田総裁の誕生から半年余り、この間に日銀が下した金融政策に関する決定の主なものは2つ、4月に1年から1年半をかけて過去25年間の金融政策に関して多角的レビューを行うと決めたことと、7月に長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)の弾力化を決定したことであった。このうち前者については、今後日銀のスタッフらによる研究成果が公表されていくほか、内外の研究者を集めたワークショップなどが開催される予定だという[1]。いかにも学者出身の総裁のイニシアティブという印象を与える。
しかし、より多くの人々の関心を引いたのは言うまでもなく、後者のYCC弾力化の方である。7月の決定の公表文はやや分かりにくいものだが[2]、実質的には日銀が容認する10年国債の利回りの上限を従来の0.5%から1.0%に引き上げたものと理解してよいだろう。この決定は、多くの市場参加者の予想を裏切るものであったが、結果的にこの措置は成功だったと評価できる。その後、長期金利が0.7~0.8%程度に上昇した事実を踏まえると、仮にこの時点でYCC弾力化が行われなかったならば、この夏にも昨年秋のように長期国債が売り込まれ、イールドカーブも大きく歪んでしまった可能性が高いからだ。
とはいえ、この間に総裁の金融政策に関する発言が大きく揺れたため、金融市場関係者が右往左往させられたことは否定できない。実際、総裁就任直後には金融緩和継続の必要性を強調して強いハト派の印象を与えた一方、YCC修正後の9月上旬に行われた読売新聞によるインタビューでは、物価上昇に確信が持てればマイナス金利解除も選択肢とした上で、その判断に必要なデータが年末までにそろう可能性まで示唆したからだ。
物価見通しに関する不確実性の高まり
この7月のYCC弾力化、およびその前後での植田総裁の発言の揺れの背景には、今年前半まで日銀が物価上昇を過少評価していた事実があったと筆者は考えている。生鮮食品を除いたコアCPIの前年比は今年1月の+4.3%がピークで8月には+3.1%まで低下しているが、これにはガソリンや電気・ガス料金への政府の補助金支給が影響しており、生鮮食品とエネルギーを除いたいわゆるコアコアCPIでみると、同期間に前年比は+3.2%から+4.3%へと大きく上昇していた。にもかかわらず、当時の日銀は「日本の物価高は、エネルギーや食料品などの国際市況高騰に伴う輸入インフレ」という説明を繰り返していた。そう考えるなら、輸入物価の前年比は昨年秋頃がピークで足もとは大きく低下していた(昨年9月+48.7%→今年8月-11.8%)から、物価高は一時的と判断するのも当然だっただろう。事実、日銀は4月の「展望レポート」では「今年度後半のインフレ率は1%台」として、23年度のコアCPI上昇率が+1.8%に低下する姿を描いていた。
しかし現実には、昨年7月まで前年比マイナスだったコアCPIサービスが8月には+2.0%(帰属家賃を除くと+3.0%)まで上昇するなど、人手不足の深刻化や今年の春闘での大幅な賃上げの実現に伴う賃金上昇が物価の押し上げに寄与し始めている。日銀はこの影響を過小評価していたのではないか[3]。実際、3カ月に一度公表される「展望レポート」に含まれる日銀のコアCPI見通しと毎月公表される民間見通しを比べてみると(図表1)[4]、今年前半は民間見通しが着実に上方修正される中で日銀見通しはやや足踏みしていたことが分かる。

想像するに、総裁就任後日銀のスタッフから慎重な物価見通しを聞かされた植田総裁がハト派発言を繰り返していると、現実の物価統計は予想以上に強かった。このため、急いでYCC修正に踏み切ったということではないか(事実、日銀は7月の「展望レポート」では今年度の物価見通しを+2.5%へと大幅に引き上げている)。9月の金融政策決定会合後の記者会見で、植田総裁が金融政策の先行きについて「到底決め打ちはできない」と繰り返したのも、物価見通しの不確実性を強調したかったのだと思う。
世界的なインフレ動学の不安定化
しかし、ここ2~3年でインフレ予測を大きく誤ったのは日銀だけではない。例えば、米国でインフレ率が急速に高まり始めたのは一昨年の春頃で、サマーズ元財務長官らがインフレのリスクに警鐘を鳴らし始めていたが、当時FRB(連邦準備理事会)のパウエル議長は「インフレは、サプライチェーン障害などに伴う一時的なもの(transitory)」との説明を繰り返していた。その後、物価高はより広範囲に広がったが、FRBがインフレの持続性を認めたのは同年の秋、インフレ抑制のための利上げを開始したのは昨年の3月だった。こうした対応がbehind the curveになったと強く批判されたのは周知の通りであるが、実はインフレ見通しの過小評価と政策対応の遅れが問題になったのはFRBだけでなく、ECB(欧州中央銀行)やBOE(イングランド銀行)でも同じだった。
これらの背後にあるのはインフレ動学の不安定性、具体的に言えばフィリップス曲線の形状が大きく変化していることだろう。コロナ危機の前までは、日本だけでなく欧米でもフィリップス曲線が著しくフラット化し、多少景気がよくなっても物価はほとんど上がらない時期が長く続いた(これは、先進国全体が「日本化」している証拠と解釈された)。ところが、コロナ危機からの経済の正常化が始まると、日米欧を問わずフィリップス曲線が急激に立ち上がってきたのだ(図表2)[5]。

しかし、物価の先行きを予測する上で最も役に立つのはフィリップス曲線に関する経験則である。だから、ここが不安定化すると物価見通しが著しく難しくなることは避けられない。このため、一昨年から昨年にかけてFRBもECBもインフレ見通しを大きく過小評価した訳だが、同じことが遅れてインフレが始まった日本でも起きたと考えることができよう。
金融政策正常化に向けての課題
ここ半年余りの植田日銀の滑り出しはまず順調だったが、その先行きにはインフレ動学の不安定性が障害として立ちはだかると考える必要がある。差し当たり当面の10月だが、足もとまでの物価の動きを踏まえると、「展望レポート」での物価見通しはさらに引き上げる必要がある。その場合、ポイントとなるのはコアCPI上昇率の24年度見通しであり、これは7月時点で+1.9%だったから、少しでも引き上げれば3年連続の2%超になる[6]。しかし、「早過ぎるリスクの方が遅過ぎのリスクより大きい」と考える植田総裁は、来年の賃上げ持続が確認できない時点でマイナス金利解除することには慎重だと考えられる。そうなると、なぜ3年連続で物価上昇率が2%超でも、持続的・安定的な2%インフレでないのかを丁寧に説明する必要がある[7]。東京大学の渡辺努教授が指摘するように、政策据え置きを正当化するために物価見通しを意図的に低くすることはあってはならない[8]。
次は来春にかけて、賃金と物価の好循環が続くかどうかを見極めて、マイナス金利解除の是非を判断する正念場のタイミングを迎える。市場の反応にせよ政治からの圧力にせよ、日銀へのプレッシャーが極大化する中で、この難しい判断を下さなければならない。
仮にこの局面を乗り切っても、困難はその先にもある。日銀は現状、意図的に遅れ気味の金融正常化、言い換えるとビハインド・ザ・カーブ戦略を採っていると考えられるが、賃金と物価の好循環が確認できた後は、ある程度の利上げペースの加速が不可避になる。インフレ率2%超が続く中で、金利がいつまでもゼロ近傍ということはあり得ないからだ(これは、スピードの差はあっても、FRBが昨年中に金利水準のキャッチアップを進めたのと同じである)。しかし、日本では市場参加者の大半が「マイナス金利が終わっても、当分金利はゼロ近傍」と思い込んでいる現状を踏まえると、ここでは事前に周到なコミュニケーション戦略を用意して臨むことが求められよう。
なお、以上に述べた金融政策正常化は、「金利のほとんどない世界」から「金利のある世界」への回帰のみを考えたものだ。本来であれば、①短期金利引き上げが日銀の財務を毀損するリスク[9]、②金利上昇が政府財政の持続可能性に及ぼすリスク[10]、③日銀のバランスシートに大きく積み上がったETFの処理方法など、「異次元緩和」がもたらした負の遺産についても考える必要があるが、本稿でそこまで議論を拡げる余裕はない。
[1] 詳しくは、金融政策の多角的レビューの実施方針について (boj.or.jp)を参照。
[2] この時の公表文には「長期金利の変動幅は±0.5%を目途とし、長短金利操作について、より柔軟に運用する。10年物国債金利について1.0%の利回りでの指し値オペを、明らかに応札が見込まれない場合を除き、毎営業日、実施する」と書かれている。
[3] 筆者は今年2月の本欄、賃上げを促す2つの力 ―構造的人手不足に向かう日本経済― | 研究プログラム | 東京財団政策研究所 (tkfd.or.jp)で、賃金上昇が物価の押し上げに寄与する可能性を指摘していた。なお、ここで紹介した東大 川口大司教授の言う「ルイスの転換点」の可能性に関して最新の状況を述べておくと、①女性の労働参加率は、アベノミクス期と比べ大幅に減速しつつも上昇トレンドは維持されている。しかし、1人当たりの労働時間がさらに減少している(ここには「年収の壁」が影響している可能性)ため、労働投入量は増えていない。②高齢者の労働参加率上昇はストップしているということである。
[4] 民間見通しは、40弱の民間調査機関が作成した経済見通しを日本経済研究センターがまとめたESPフォーキャスト調査ESPフォーキャスト調査 | 公益社団法人 日本経済研究センター (jcer.or.jp)によるもの。
[5] 日本のフィリップス曲線は、昨年12月に本欄に書いた不確実性高まるインフレ動学 | 研究プログラム | 東京財団政策研究所 (tkfd.or.jp)にも示しているが、当時と比べてもフィリップス曲線はさらに大きく立ち上がっている。米国のフィリップス曲線については、米国インフレ、高止まりのリスク | 研究プログラム | 東京財団政策研究所 (tkfd.or.jp)を参照。
[6] ここでは、政府がガソリンへの補助金を延長した結果、23年度のCPIが押し下げられる一方、24年度のCPI上昇率は押し上げられることに注意。
[7] もちろん、25年度のインフレ率は1%台になるという見通しを示すことはできるが、22年度から24年度まで3年連続で見通しを実績が上回りそうな状況で、確たる根拠なく「2年先は1%台に戻る」と主張するだけでは十分に説得的とは言えまい。
[8] 日銀物価見通し、実態より低い数字で政策正当化に疑問-渡辺東大教授 - Bloomberg
[9] 日銀が大幅な利上げを行えば、巨額の赤字を計上し、債務超過に陥る可能性が高い。この問題に関連して植田総裁は、今秋の日本金融学会で「中央銀行の財務と金融政策運営」と題する講演を行っている【講演】植田総裁「中央銀行の財務と金融政策運営」(日本金融学会) : 日本銀行 Bank of Japan (boj.or.jp)。これによれば、純粋理論的には中央銀行が債務超過になっても金融政策の遂行能力には影響を及ぼさないと考えられる(実際、FRBは既に実質的な債務超過に陥っているが、ドルの信認は失われていない)。しかし現実には、中央銀行の収益悪化や債務超過をきっかけに通貨への信認が失われれば、(恐らく急激な円安を通じて)インフレ予想の大幅な上昇が生じ得るとも述べられている。
[10] この点については、インフレ率が高まると名目GDPが膨らむので、政府債務/名目GDP比率は低下するとの見方がある。しかし、金利が上昇して利払い費が膨らむと、毎年の新規国債発行額が急増してロールオーバ-が難しくしなる心配もある。結局は、中央銀行の財務と同様に、通貨や国家財政への信認が維持されるか否かに大きく依存するということだろう。この点に関して最近、ハーヴァード大学のロゴフ教授(かつてIMFでチーフエコノミストも務めた)が悲観的な見方を示している。The Bank of Japan’s Seductive Widow-Maker Trade by Kenneth Rogoff - Project Syndicate (project-syndicate.org)を参照。

































































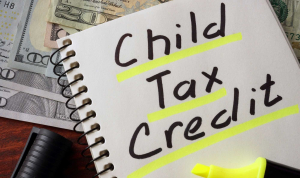























































































































































































_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)





















_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)


































































