
R-2024-083
本稿では「地方自治体におけるEBPM人材の育成」プログラムの一環として、市区町村別の空き家状況の特徴について考察する。2024年8月20日に開催した「第1回 地方自治体におけるEBPM活用研究会(於: 北海道上川郡東川町)」では都道府県単位での考察にとどまっていたが、その後、2024年9月に公表された「住宅・土地統計調査」(総務省統計局)の確報を踏まえ、市区町村別で見た日本の空き家の特徴について考察する。
|
・日本全体の空き家率は2023年10月1日現在で13.8% |
日本全体の空き家率は2023年10月1日現在で13.8%
日本国内で人が住まない「空き家」の増加やその処分が問題になっている。日本における住宅総数や空き家などの状況を把握しているのが「住宅・土地統計調査」(総務省統計局)である。この調査は1948年以来、5年に1回実施され、最新の2023年10月1日時点の調査結果の確定値は2024年9月に公表されている。2023年10月1日時点における日本の総住宅数は6502万戸。前回調査(2018年)に比べ4.2%(261万戸)増加した。
「住宅・土地統計調査」においては、総住宅数を居住世帯のある住宅、一時現在者のみ、空き家、建築中に大別している。注目度の高い空き家率(空き家数÷総住宅数×100)は13.8%と前回調査から0.2ポイント上昇しており、総住宅数とともに空き家率も年々上昇している(図表1)。
図表1 日本の住宅数と空き家率の推移

出所:「住宅・土地統計調査」(総務省統計局)
そもそも空き家とは何か
「住宅・土地統計調査」の用語の解説によれば、「居住している」とは原則として、調査日現在、当該住居に既に3ヵ月以上にわたって住んでいるか、あるいは調査日の前後を通じて3ヵ月以上にわたって住むことになっていることを指す。この定義に当てはまらない、「居住世帯のない住宅」から「一時現在者のみの住宅」(昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしているなど、そこにふだん居住している者が一人もいない住宅)と「建築中の住宅」を除いたものが「空き家」である。
このため、私たちがよくイメージする空き家のほかに、時々使用される別荘のような住宅も空き家に含まれることになる。実際、空き家は、「賃貸用の空き家」「売却用の空き家」「二次的住宅」(別荘など)、そして、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」に分類される。「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅、空き家の種類の判断が困難な住宅などを指し、新聞等では「放置空き家」などと称されている。
前述したように、日本全体の空き家率は13.8%であるが、総住宅数に占める賃貸用空き家の比率は6.8%、売却用空き家の比率は0.5%、二次的住宅の比率は0.6%、賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家の比率は5.9%である。日本全体で見ると、空き家問題とは、賃貸用空き家と賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家の問題であるといえよう。
都道府県別、市区町村別で異なる空き家問題
都道府県別に見ると、空き家率の内訳は異なる(図表2)。空き家率は西日本ほど高い傾向があるとよく指摘されるが、その傾向を作っているのは賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家の比率(図表2の赤色棒グラフ)である。一方、日本全体では目立たない、二次的住宅の比率(図表2の青色棒グラフ)が他の自治体に比べて高い県もある。長野県(5.39%)、山梨県(4.00%)、静岡県(2.17%)、栃木県(1.95%)、新潟県(1.91%)が上位5県であり、それぞれ有数の別荘地がある県である。長野県は空き家数に占める二次的住宅の比率が26.9%を占め、賃貸用(27.4%)とほぼ並ぶ。
図表2 都道府県別の空き家率とその内訳

出所:「住宅・土地統計調査」(総務省統計局)をもとに筆者作成
こうした空き家問題の違いは市区町村別で見るとより顕著になる。「住宅・土地統計調査」では、政令市の区も含めて集計結果を公表しているが、ここでは東京都の特別区を含み、政令市の区は除いて、1059市区町村のデータを加工・集計した。
図表3を見ると二次的住宅空き家率のばらつきの大きさがわかる。小さい方から数えてちょうど真ん中(中央値)が0.3%、小さい方から数えて75%(第3四分位)が0.7%であるのに対し、最大値は63%とかけ離れた値になっているためだ。二次的住宅空き家率が最大なのは長野県軽井沢町である。このほか、上位には栃木県那須町(41.7%)、山梨県北杜市(31.5%)、長野県茅野市(31.0%)、静岡県熱海市(29.7%)が続く。
図表3 市区町村別空き家率等の記述統計量

出所:「住宅・土地統計調査」(総務省統計局)をもとに筆者作成
こうした二次的住宅空き家率の高い市区町村は、空き家率全体でも上位に来る。空き家率の最大値(70.4%)は長野県軽井沢町であり、栃木県那須町(61.7%)、静岡県熱海市(53.4%)、長野県北杜市(46.1%)、和歌山県白浜町(43.2%)と続く。一方、放置空き家と問題になっている賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家率を見ると、長野県軽井沢町は6.0%であり、全市区町村の中央値(7.3%)を下回る。
このように、市区町村別で空き家動向を観察する際には、空き家率全体を見ることで現状を見誤る恐れがある。
売却用及び二次的住宅を除く空き家率の合計で市区町村を観察
そこで、賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家率と賃貸用空き家率の合計、すなわち、売却用及び二次的住宅を除く空き家率で、市区町村の動向を把握してみよう。売却用空き家率も二次的住宅と同様にばらつきが大きく、たまたま調査時点で分譲時期が来たというケースも考えられるためだ。なお、賃貸用空き家率のデータが存在しない町が2つある[1]ため、サンプル数は1057市町村に減る。
平均、中央値などは空き家率全体とはほぼ変わらないものの、二次的住宅を除いたことで最大値は小さくなっている。図表4のヒストグラムを見ると、多くの市区町村が5%から25%の間に収まっている一方で、比率が高く空き家問題が深刻な市区町村の存在が確認できる。
売却用及び二次的住宅を除く空き家率の高位10市区町村と低位10市区町村を見ると、高位には世帯総数[2]の少ない、言い換えれば人口の少ない市町村が並んでいる(図表5)。一方、低位10市区町村の第1位の沖縄県中城村、第2位の秋田県三郷町も世帯総数は少ない方である。世帯総数の多い福岡市(85万6400世帯)は82位の7.69%、横浜市(176万4700世帯)は106位の8.09%と必ずしも上位ではなく、東京都特別区では江東区(27万800世帯)は103位の8.01%である。ちなみに、空き家率全体では第1位となった長野県軽井沢町(8290世帯)は、売却用及び二次的住宅を除く空き家率で見ると、低位で62番の7.09%である。
図表4 売却用及び二次的住宅を除く空き家率

出所:「住宅・土地統計調査」(総務省統計局)をもとに筆者作成
図表5 売却用及び二次的住宅を除く空き家率の高位、低位市町村

出所:「住宅・土地統計調査」(総務省統計局)をもとに筆者作成
1057市区町村のうち、約半数の世帯総数が2万未満である。世帯総数2万未満に絞って、売却用及び二次的住宅を除く空き家率と世帯総数の散布図を描くと図表6のようになり、明確な関係がうかがえない。相関係数を確認しても-0.168と低い。同じ世帯総数でも空き家率が高い市区町村もあれば低い市区町村もある。この違いは何によって生じているのか、今後、分析を進めたい。
図表6 世帯総数と売却用及び二次的住宅を除く空き家率の関係

出所:「住宅・土地統計調査」(総務省統計局)をもとに筆者作成
[1] 奈良県平群町(空き家率4.3%)、和歌山県有田川町(同20.5%)の2町である。
[2] ここでは、「住宅・土地統計調査」の主世帯数を用いている。


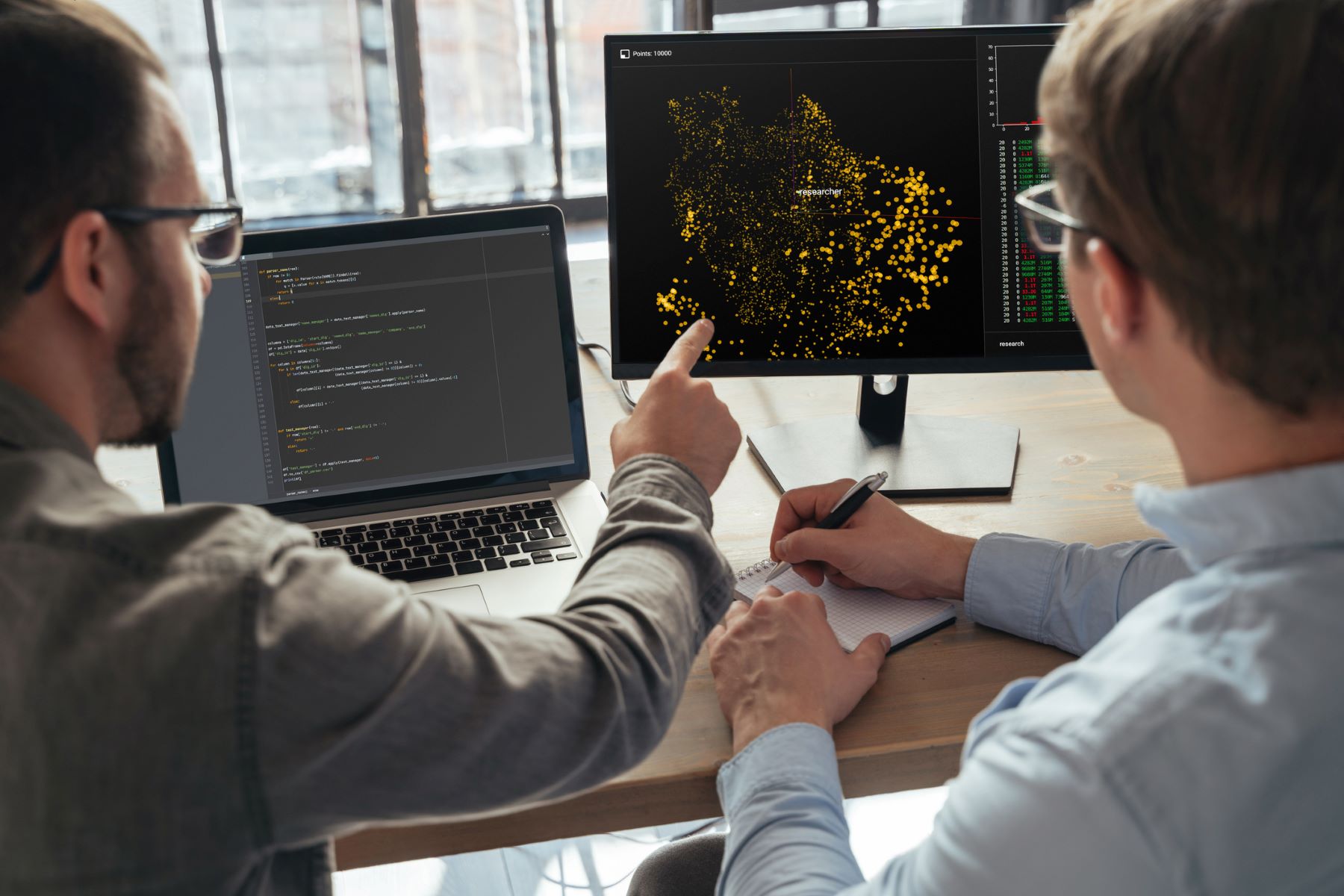























































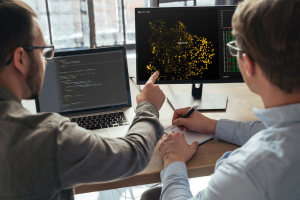



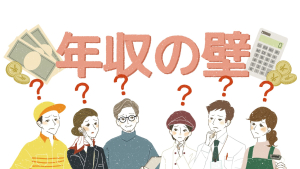



























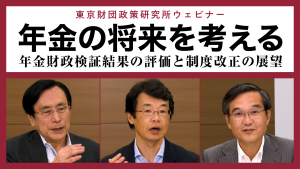

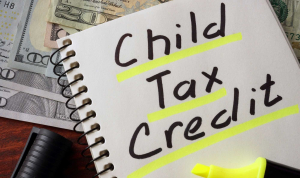









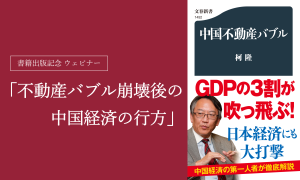
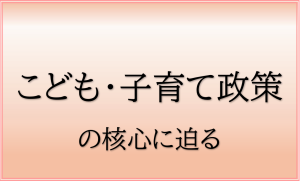













































































































































































_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)





















_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)


































































