 2017年も残すところあとわずか。皆さんは、今年1年どんな本に出会いましたか。東京財団研究員らが、今年読んだ本からおすすめの一冊を紹介する年末恒例の書評特集です。研究員の横顔がうかがえる選書と専門家ならではの鋭 い分析・論評に加え、今年は、研究員がこの一年を一言で総括した「私の2017年」もあわせてお楽しみください。
2017年も残すところあとわずか。皆さんは、今年1年どんな本に出会いましたか。東京財団研究員らが、今年読んだ本からおすすめの一冊を紹介する年末恒例の書評特集です。研究員の横顔がうかがえる選書と専門家ならではの鋭 い分析・論評に加え、今年は、研究員がこの一年を一言で総括した「私の2017年」もあわせてお楽しみください。
評者から選ぶ(50音順)
| 小黒一正 | 川出真清 | 小松正之 | デビッド・サスマン | 舘祐太 | 鶴岡路人 | 冨田清行 | 八田達夫 | 平沼光 | 福島安紀子 | 星岳雄 | 森信茂樹 | 吉原祥子 |
書籍から選ぶ
財政と政治はどこに向かうのか 
評者 小黒一正 東京財団税・社会保障調査会メンバー 、法政大学教授
ジェームズ・M・ブキャナン、リチャード・ワグナー著、大野 一訳『赤字の民主主義 ケインズが遺したもの』 (日経BPクラシックス、2014)

本書は、公共選択論を提唱し、1986年にノーベル経済学賞を受賞したアメリカの財政学者であるブキャナン氏らが執筆した名著である。アメリカの経済政策を1970年代に批判的に考察しつつ、民主主義が財政赤字を生み出すメカニズムを深い洞察力で分析しており、巨額の債務を抱える現代の日本にも通用する内容である。
2017年刊行の共著 『財政と民主主義 ポピュリズムは債務危機への道か』 (日本経済新聞出版社)の出版後に読み返したが、ブキャナン氏らの指摘は、金融政策と財政規律との関係や、金融引締めと政治、政府と中央銀行の関係などについても考察しており、現在の日銀と日本財政の関係や将来的な予測の検討材料として、改めて気づかされる部分も多い。
不況期に財政出動を行い、好況期に増税などで財政再建を進めるというケインズの処方箋の前提には、公正無私な知的エリート層で適切な経済政策を実行できるという「ハーベイロードの前提」(Harvey Road presumption)が存在するが、財政のみでなく、金融政策においても、この前提が本当に成立するのか評者は疑問である。
しかし、民主主義の下、選挙がある政治も財政再建を先送りする傾向が強い。本書でブキャナン氏らが指摘するように、「現実の民主主義社会では、政治家は選挙があるため、減税はできても増税は困難。民主主義の下で財政を均衡させ、政府の肥大化を防ぐには、憲法で財政均衡を義務付けるしかない」のかもしれない。2018年では憲法改正の議論もスタートする可能性があり、財政と政治の関係に関する理解を深めるため、改めて読んでおきたい一冊である。
原著 James M. Buchanan and Richard E. Wagner, Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes (Liberty Fund; Volume 8, 2000)
私の2017年 常備不懈
人生100年時代における新たな社会保障フレームを検討する必要性があり、財政の視点からその土台となる哲学や仕組みについての検討を徐々に開始。
個人主義から多様化へ――経済的合理性のひろがり
 評者 川出真清上席研究員
評者 川出真清上席研究員 国内外で台頭している「ポピュリズムをどうすべきか」という問いには、非合理的で感情的だという一般的な判断に基づき、感情的な大衆を、冷静かつ、合理的な視点に引き戻すことが重要だと言う結論になりがちだ。そんな論調に対して、本書は行動経済学やゲーム理論という経済学的なロジックを用いて、感情もやはり合理的であり、いわゆる合理的分析では不充分であることを有名な最後通牒ゲームなどを用いて一般読者にわかりやすいかたちで解説する。
国内外で台頭している「ポピュリズムをどうすべきか」という問いには、非合理的で感情的だという一般的な判断に基づき、感情的な大衆を、冷静かつ、合理的な視点に引き戻すことが重要だと言う結論になりがちだ。そんな論調に対して、本書は行動経済学やゲーム理論という経済学的なロジックを用いて、感情もやはり合理的であり、いわゆる合理的分析では不充分であることを有名な最後通牒ゲームなどを用いて一般読者にわかりやすいかたちで解説する。
そこには、これまで経済学が依拠してきた個人主義的合理性(ホモ・エコノミクス)以外に、個の集合体であるコロニー全体を一つと考えた時に生じる合理性、体格や風土など制約された条件下での合理性といった、様々な合理性が存在することを指摘する。そして、個人や集団の中に複数存在する様々な合理性を、個人や集団の中で最適なかたちで組み合わせることによって、その個人や集団の感情として表出されるとする。
経済学は合理性を用いて社会現象を説き起こすが、これまで経済学が依拠してきた「個の合理性」に縛られず、多様な合理性からの解釈へ扉を開く意味で、経済学に疑問を感じていた一般読者にも納得いく答えを与える優れた書籍だと言える。
原著 Eyal Winter, Feeling Smart: Why Our Emotions Are More Rational Than We Think (PublicAffairs, 2014)
私の2017年 ジム通い
今年の夏から、メタボ対策でジム通いをはじめた。週3日のペースだが、ストレッチやウェイトトレーニングで体が痛み、億劫にもなる。怪我や病気でリハビリをなさる方々に及ぶべくもないが、その苦労がわずかながら理解できた。
富裕層と軍閥寄りの米大統領 搾取される弱者
 評者 小松正之上席研究員
評者 小松正之上席研究員 Howard Zinn, A People's History of the United States (Harper Perennial Modern Classics, 2005)

ハーワード・ジンは造船所労働者から空軍勤めし、軍奨学金で大学に行きコロンビア大学で博士号を取得したのち大学教授になったが、学生を支援し大学当局から解雇された。ジンは米国は統治者が弱者を搾取する歴史であると喝破している。英国からの米国の独立運動も米大陸で財産をなした富裕移民と、英国王と結びついた富裕特権階級との権力闘争であったとみる。
ジョージ・ワシントン指揮の下で戦ったのは庶民・貧困層だった。哲学者トマス・ペインの著した『コモンセンス』は、米独立は常識(コモンセンス)と説き、彼らは応じ戦い死んだ。
対して、ロスチャイルド財閥(欧州)、ロックフェラー、バンダービルトやカーネギーなどの財閥は石炭と石油資源開発で巨大な富を得て、販売市場でまた巨万の富を築く。果たして、米独立宣言の「自由と平等」には米インディアンも黒人も含まれない。白人のみであった。アイルランド系、イタリア系や東欧系も差別された。最近では南米系とイスラム系が差別されている。
就任後の米大統領は、「米社会は庶民や貧困層」の為というより「軍事的関心や財閥」の利益を優先すると本書は主張する。
私の2017年 Bucket List
9月に滝や小川が美しく人情が豊かなフェロー諸島を訪れた。機内誌では同地訪問はBucket List(死ぬ前にやるべきこと)と解説していた。同名の映画も見ていた。私のそれは、いつか英オックスフォード大学で哲学の勉学を通じ人生とは何かを考えること。
生涯続く日々の学び
 評者 デビット・サスマン リサーチ・アソシエイト
評者 デビット・サスマン リサーチ・アソシエイト Thomas M. Nichols, The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters (Oxford University Press, 2017)
 米国のメディア・議会など、世論における議論の質は、残念ながら低下・粗野化の一途をたどっている。トム・ニコルズ米海軍大学教授(国家安全保障)は著書 The Death of Expertise (専門的見解の死)の中で、米国の国民の間に、専門家を信じない風潮が蔓延していること、さらに専門的見解そのものへの強い反発が広がっていることを危惧している。著者は高等教育やインターネット・メディアの役割の重要性を訴え、根拠なき意見への追随が民主主義を脅かすと警鐘を鳴らす。
米国のメディア・議会など、世論における議論の質は、残念ながら低下・粗野化の一途をたどっている。トム・ニコルズ米海軍大学教授(国家安全保障)は著書 The Death of Expertise (専門的見解の死)の中で、米国の国民の間に、専門家を信じない風潮が蔓延していること、さらに専門的見解そのものへの強い反発が広がっていることを危惧している。著者は高等教育やインターネット・メディアの役割の重要性を訴え、根拠なき意見への追随が民主主義を脅かすと警鐘を鳴らす。
他人へ不信感が増え、またfake(偽)ニュースがはびこる現代社会の実情を鑑みれば、これらの所感は多くの賛同を得るだろうが、そもそも著者の主張自体に「専門的見解」が足りないようにも感じる。事例はいくつも紹介しているが、概してデータに基づく根拠が乏しいのだ。分析も説得力に欠け、結論ありきで書かれた感は否めない。
もちろん、専門家に対する不信は増えたとしても、この激動の時代を生き抜くためには研究や経験に基づく専門的見解は不可欠だ。大きく移り変わりゆく現代社会に十分対応するために、一個人としても日々の生活の中で常に探求と学びを心がけたい。
私の2017年 Transition
振り返ってみれば変化の多い一年だった。個人的には数ヶ月の間に結婚、(妻の出身国である)日本への引越し、そして新天地で新しい仕事を経験した。また、トランプ大統領の就任により、今までの社会常識が大きく覆された。新大統領は前任者の成果を否定し、今までの寛容な政策を転換することにより、米国の民主主義を根底から揺るがした。まさに新しい時代への移り変わりを感じる一年となった。
サーベイ調査のトリセツ
 評者 舘祐太 データ・アナリスト
評者 舘祐太 データ・アナリスト Johnny Blair, Ronald F. Czaja, and Edward A. Blair, Designing Surveys: A Guide to Decisions and Procedures (SAGE Publications, Inc; 3rd edition, 2014)
 今年の10月に行われた衆議院選挙は、新聞社などが実施した事前の情勢調査のとおり、与党の勝利で幕を閉じた。このような選挙における情勢や内閣支持率など、人々の意識を調査するうえで欠かせないのがサーベイ調査である。本書は、その方法論や調査票を作成する際の注意点などを幅広く取り上げ、詳細に解説を行った書籍である。
今年の10月に行われた衆議院選挙は、新聞社などが実施した事前の情勢調査のとおり、与党の勝利で幕を閉じた。このような選挙における情勢や内閣支持率など、人々の意識を調査するうえで欠かせないのがサーベイ調査である。本書は、その方法論や調査票を作成する際の注意点などを幅広く取り上げ、詳細に解説を行った書籍である。
サーベイ調査によって、知りたいことを正確に把握するためには適切な調査設計が必要である。サンプルの設計においてヒアリングを行う人々を偏りなく選定することはよく言われるが、質問に用いる語句や順番の構成などにも注意深く気を配らないと、調査の結果が真の姿からずれてしまう可能性がある。また、日本において、マスコミの世論調査による内閣支持率の数字が、報道する会社ごとに異なることが時々話題となるが、わからないと答えた人に重ね聞きをするか、回答を拒否した人にもう一度ヒアリングを行うかといった、それぞれの実施方法に関する細かな違いも見逃してはならない点であろう。
日常においてサーベイ調査を目にすることが多い中、調査作成に携わることのない人にとってもためになる一冊になるのではないか。
私の2017年 人
「人と人とが支え合って…」といわれるように、多くの人に支えられ、助けていただいた1年であった。この漢字の成り立ちは、人が立っている姿をあらわす象形文字。しっかりと地に足をつけて立てるように研鑽を積み、いただいたご厚意に応えていければと思う。
ポピュリズムはなぜ民主主義への脅威なのか
 評者 鶴岡路人研究員
評者 鶴岡路人研究員 ヤン=ヴェルナー・ミュラー著、板橋拓己訳『ポピュリズムとは何か』(岩波書店、2017)
 2017年もまた、「ポピュリズム」という言葉を無視しては過ごせない年になってしまった。フランスの大統領選挙ではマクロン候補の勝利により極右国民戦線の大統領誕生が阻止されたものの、火種は各国でくすぶっている。
2017年もまた、「ポピュリズム」という言葉を無視しては過ごせない年になってしまった。フランスの大統領選挙ではマクロン候補の勝利により極右国民戦線の大統領誕生が阻止されたものの、火種は各国でくすぶっている。 ポピュリスト勢力とともに、ポピュリズム批判も巷に溢れているが、そもそもポピュリズムとは何なのか。民主主義を活性化させるために、大衆の声を聞くという意味のポピュリズムはむしろ有用なのではないかとの声もある。そうした、「ポピュリズムも必要悪」といった見方を一刀両断にし、ポピュリズムは民主主義への脅威であると明確に位置づけるのがミュラーの議論である。
著者は、「自分たちが、それも自分たちだけが真正な人民を代表する」というポピュリストの主張こそが最も危険だという。それは、自らに反対する勢力はすべて異端で正統ではないとの考えそのものであり、反多元主義であるがゆえに、民主主義とは根本的に相容れないというのである。与党と野党が存在し、様々な意見が許されるのが民主主義の根幹であり、ミュラーの指摘は重い。
こうした真剣な警告も、欧米諸国と比較してポピュリスト勢力が成功していない日本ではあまり響かないかもしれない。しかし、重大な出来事が起きてから慌てないためにも、今の段階から考えを深め、対策を考えておくべきだろう。
原著 Jan-Werner Müller, What Is Populism? (The University of Pennsylvania Press, 2016)
私の2017年 心機一転
私事で恐縮だが4月に新しい職場に移った。職場環境が変わると同時に、見えてくる世界も変わり、まさに心機一転。同時に、研究対象の一つである欧州統合も、マクロン仏大統領の誕生で心機一転を目指している。新年にはともに飛躍したいものである。
選択を委ねることと自らの自由を確保すること
 評者 冨田清行研究員
評者 冨田清行研究員 キャス・サンスティーン著、伊達尚美訳『選択しないという選択』(勁草書房、2017)
 何かを選択することは、時間も労力も要し、その結果の責任を負うことである。限りある自分の時間や能力を有効に使うために、何を選択することに配慮すべきなのかを本書は考えさせる。
何かを選択することは、時間も労力も要し、その結果の責任を負うことである。限りある自分の時間や能力を有効に使うために、何を選択することに配慮すべきなのかを本書は考えさせる。
いまや、私たちの生活はあらゆる面で初期設定に左右されているといっても過言でない。情報端末などの機器やオンラインサービスのみならず、制度も初期設定を置き、物事を事細かに自分で決めなくてもよい社会になっている。果たして今後、ビッグデータや行動経済学、心理学などの叡智が蓄積して初期設定が精緻化していくことが、個人や社会全体にとって望ましい結果をもたらすのであろうか。本書は様々な事例を挙げて、選択を委ねることと自分の自由を確保することの関係に言及する。
自分の判断をどこまで他人(あるいは機械)に委ねてよいか、また、自分自身で決めたいことは何か。サイバー空間に自分の情報が蓄積され、また、政府の役割が次第に大きくなっている今だからこそ、自分が物事を決めることの意味を考える機会を本書は与えてくれる。
中国の未登記取引市場はなぜ円滑に機能してきたのか
 評者 八田達夫名誉研究員
評者 八田達夫名誉研究員 Shitong Qiao, Chinese Small Property: The Co-Evolution of Law and Social Norms (Cambridge University Press, 2017)

中国では、1978年の鄧小平による改革以来、土地の未登記所有が急激に増加した。例えば、深圳では未登記住宅の割合は過半に及ぶ。それにもかかわらず、中国では、円滑な土地取引の市場が形成されている。
本書は、中国の深圳における未登記住宅取引の市場を調査し、この市場がなぜ円滑に機能しているかを巧みに説明している。時の権力者によって予期せぬかたちで急激に変更されたり、行政官によって恣意的に運用されたり、場所や状況によって矛盾した形で執行されたりしているような法制度は、人々から信用されず、それゆえに法的な拘束力を失っている。それに対して、人々の暗黙の合意が形成されている取引形態は、かえって強い拘束力をもっている。本書はこの状況を協調ゲームのフォーカル・ポイントとして捉えて説明している。
深圳では、地方政府が、法的な制度を現実の未登記不動産取引形態に近づけていることさえ観察されている。多くの途上国で、大都市の発展過程で、土地の所有権が正式に登記されないまま不法占拠されている。本書は、この状況の改善方策についても示唆を与える歴史的意義をもつ研究である。
私の2017年 ワイヤレス電源供給
着実に現実に近づく限界費用ゼロの社会
 評者 平沼光研究員
評者 平沼光研究員 ジェレミー・リフキン著、柴田裕之訳『限界費用ゼロ社会 〈モノのインターネット〉と共有型経済の台頭』(NHK出版、2015)
 著者のジェレミー・リフキンはEU委員会やメルケル独首相をはじめ、世界各国の首脳・政府高官の政策アドバイザーを務めた経歴をもつ米国の著名な文明評論家、著作家である。
著者のジェレミー・リフキンはEU委員会やメルケル独首相をはじめ、世界各国の首脳・政府高官の政策アドバイザーを務めた経歴をもつ米国の著名な文明評論家、著作家である。
本書では、IoT(モノのインターネット接続化)の発展は、情報、エネルギー、輸送の各分野を接続したインテリジェント・インフラの形成をうながし、効率性と生産性が飛躍的に高められることで限界費用が限りなくゼロに近づく社会が創出されることが述べられている。既にエネルギー分野では、再生可能エネルギーの大幅なコスト低下と電力系統のスマートグリッド(電力の流れを供給側と需要側の双方から制御し、最適化する送電網)化によって、限界費用ゼロの再生可能エネルギーの普及が現実のものとなっている。2015年の発刊から3年近くたった本書であるが、あらためて読み返してみても近未来の社会像を考察するうえで十分示唆に富んだものと言える。
原著 Jeremy Rifkin, The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism (St. Martin's Press, 2014)
私の2017年 懸念
パリ協定発効を経た本年は、再生可能エネルギーの一層の普及拡大、電気自動車などの省エネ高効率機器の本格普及など、新たなエネルギーや技術を市場化する世界の動きが鮮明になった。一方、日本はいまだに世代遅れの技術に依存し、国力低下が懸念される一年であった。
地政学的変化を踏まえ日米関係の今後を読む
 評者 福島安紀子上席研究員
評者 福島安紀子上席研究員 James L.Schoff, Uncommon Alliance for the Common Good: The United States and Japan After the Cold War (Carnegie Endowment for International Peace, 2017)
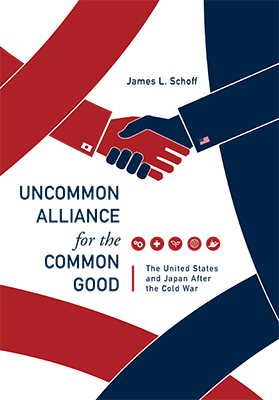 2017年は、北朝鮮のミサイル開発及び核兵器開発とその頻繁な発射や実験が地域安全保障さらには国際安全保障上の懸念として耳目を集めた。そして、トランプ政権の発足や中国の党大会における「強国」路線の発表など目まぐるしい国際情勢の変化の中で、日米同盟とその新たな価値が一層追究されている。
2017年は、北朝鮮のミサイル開発及び核兵器開発とその頻繁な発射や実験が地域安全保障さらには国際安全保障上の懸念として耳目を集めた。そして、トランプ政権の発足や中国の党大会における「強国」路線の発表など目まぐるしい国際情勢の変化の中で、日米同盟とその新たな価値が一層追究されている。
このような時期にあっては、直近の情勢に目を奪われがちであるが、歴史的な日米同盟の変遷を踏まえつつ軍事的な安全保障と包括的安全保障への両面からのアプローチを分析し、同盟の将来像を考察することが求められる。
2017年に刊行されたジェームズ・L・ショフ米国カーネギー平和財団上級研究員の著書は、同氏の長年の研究、日本における経験に基づいた分析であり、多くの示唆を与えてくれる。同書は、日米同盟を冷戦時代の片務性、経済・技術・外交も含めた同盟マネージメント、冷戦後の同盟漂流、近年の日本の安全保障政策にまつわる変化と日米防衛協力の軌跡を辿ったうえで、日米関係の今後を提言している。一例として中国に隣接する東南アジアを地中海に模して、日米が東南アジアの安定に貢献する方向性が提案されている。
同書は今後のアジアの地政学的な変化を踏まえつつ、日米同盟とそれに基づく日米関係の発展を考えるうえで多くの思索の種を提供してくれる一冊である。私の2017年 軸
2017年ほど様々に変化する世界情勢を読み解くことに骨が折れた年はなかった。世界は予測不可能性の中で不安感を募らせた。このような時には研究者として事象に翻弄されない思索の軸の重要性を再び痛感した。私にとっては歴史と理論が軸である。
シェークスピア、密輸マフィア、そしてナチスドイツの暗号分析を通じて現代暗号学の基礎を構築した女性
 評者 星岳雄理事長
評者 星岳雄理事長 Jason Fagone, The Woman Who Smashed Codes: A True Story of Love, Spies, and the Unlikely Heroine Who Outwitted America’s Enemies (HarperCollins Publishers, 2017)
 “Top Secret”と刻印された木箱が、アメリカ政府のひっそりした倉庫の奥に運ばれていく。インディアナ・ジョーンズの最初の映画“Raiders of the Lost Ark”(レイダース/失われたアーク《聖櫃》)の最終シーンを覚えている人も多いだろう。この本の主人公エリザベス・フリードマンが、アメリカのために行った暗号解読の記録を整理して政府に保管のために引き渡した時にも、そのようなシーンを思い浮かべたに違いない。浮かんだ言葉は、“government tombs”(政府による墓場)だったと言う。
“Top Secret”と刻印された木箱が、アメリカ政府のひっそりした倉庫の奥に運ばれていく。インディアナ・ジョーンズの最初の映画“Raiders of the Lost Ark”(レイダース/失われたアーク《聖櫃》)の最終シーンを覚えている人も多いだろう。この本の主人公エリザベス・フリードマンが、アメリカのために行った暗号解読の記録を整理して政府に保管のために引き渡した時にも、そのようなシーンを思い浮かべたに違いない。浮かんだ言葉は、“government tombs”(政府による墓場)だったと言う。 彼女はひょんなことから大富豪ジョージ・ファビアンのリバーバンク研究所で、シェークスピアの著作に隠されたメッセージを読み解くというプロジェクトに参加することになり、後に夫となるウィリアム・フリードマンと出逢うが、この本は、エリザベスの生涯を追うことによって、現代の情報通信技術の重要な基礎である暗号学の発展に、エリザベスと彼女の夫のウィリアムがどれだけ大きな貢献をしたか、そしてその貢献、特にエリザベスの貢献が第二次大戦後どうして忘れ去られてしまったのかを明らかにする。
様々な偶然が歴史的背景と絡みあいながら、彼女を第二次大戦中のアメリカの暗号解読の中心人物に仕立てたが、戦後はその貢献に見合った脚光を浴びせることはなかった。この本によって多くの人達が彼女の業績を知ることを願いたい。
私の2017年 Unthinkable
「思いもよらない」「あり得ない」といった意味である。想像を超えるようなことが頻繁に起こるようになった。トランプが大統領になったことなどその最たるもので、大統領就任後も変わらず、その言動は過激化した部分もあった。技術進歩も思いもよらない速さで進展している。Alpha Go(コンピュータ囲碁プログラム)が人間の名人に勝ったのは2016年。2017年には、Alpha Goより強いAlpha Go Zeroが開発された。
「ガリレオ」の湯川教授曰く、「あり得ないなんてことはあり得ない」。Unthinkableな事態に直面しても慌てずに対応できるように、準備しておくべきなのだろう。想像力を一層たくましくして。
AIとBI(ベーシック・インカム)
 評者 森信茂樹上席研究員
評者 森信茂樹上席研究員 井上智洋著『人工知能と経済の未来――2030年雇用大崩壊』(文春新書、2016)
 この本を読むきっかけは、「人工知能と経済」という組み合わせに惹かれたためである。
この本を読むきっかけは、「人工知能と経済」という組み合わせに惹かれたためである。
内容は、ディープラーニングが新たなブレイクスルーをもたらしたこと、AIが発達しても、技術進歩に応じて需要が増大していかなければ失業が解消されず何らかの対策が必要であることなどをわかりやすく解説している。
そのうえで、AIの発達した将来像を、「2045年の未来では、ロボットが商品を作る無人工場があり、それを所有する資本家のみが所得を得て、労働者は所得を得られないかもしれない」としてディストピアを予測し、それを避けるための政策としてベーシック・インカム(以下、BI)の導入を主張する。思想としては頭から否定すべきものではない。
問題は、その実現性である。著者は、一律25%の所得税を国民全員に課すことを財源にあげているが、このあたりから本書は一気に非現実的な内容に変わっていく。せっかくの良書が画竜点睛を欠く内容になった。私の2017年 築城3年、落城1日
今年はこの言葉を連日のように見聞きした。安倍政権のモリカケ問題も、小池希望の党も、そして不倫で話題になった政治家や芸能人も、この言葉をかみしめているに違いない。もっとも「人のうわさも七十五日」とも言うが…。
平穏な日常の大切さ
 評者 吉原祥子研究員
評者 吉原祥子研究員 朽木祥著『海に向かう足あと』(角川書店、2017)
 北朝鮮の核開発がエスカレートし、世界各地でテロが頻発する中、私たちの平穏な日常はいつまで続くだろうか。本書はいま多くの人々が抱いている漠然とした不安感を巧みにすくい上げる一冊だ。
北朝鮮の核開発がエスカレートし、世界各地でテロが頻発する中、私たちの平穏な日常はいつまで続くだろうか。本書はいま多くの人々が抱いている漠然とした不安感を巧みにすくい上げる一冊だ。
物語は、30代半ばの照明デザイナーである主人公・村雲を中心に年代も職業もばらばらな登場人物たちが、小笠原諸島近くの小島で行われるヨットレースに向け意気揚々と準備を始めるところから幕を開ける。ヨットに熱い思いを傾ける主人公と仲間たち。レースに向けてトレーニングを重ねる中で築かれる友情や育まれる愛情。おしゃれな海洋小説かと見せて、しかし、登場人物たちの日常には次第に不穏な兆候が見え隠れし始める。原因不明の体調不良や、テロの多発、核ミサイル開発に関する断片的な情報、一部の政府関係者の間で有事を想定した極秘プロジェクトが進んでいるらしいことなどだ。主人公たちが海に思いをはせている間に、国際情勢は核兵器を使った壊滅的な事態へと突き進んでいたのである。
物語では主人公たちの結末は明かされない。その先を思い描くことをゆだねられた読者は、そこで戦慄することになる。いまの国際情勢を見渡せば、これは単なる絵空事ではない、近い将来、自分の身に十分起き得ることだと実感するからだ。
年末年始に読むには不向きかもしれないディストピア小説だが、望まぬ未来を阻止するために、いますべきことは何かを考えさせる一冊。私の2017年 第一歩
今年は東京財団がこれまで研究・発信してきた人口減少時代の土地問題が、政策課題として広く認知され、政策が動き始めた年だった。法制度の見直しに向け、年明けの通常国会から政策議論がいよいよ本格化していく。
