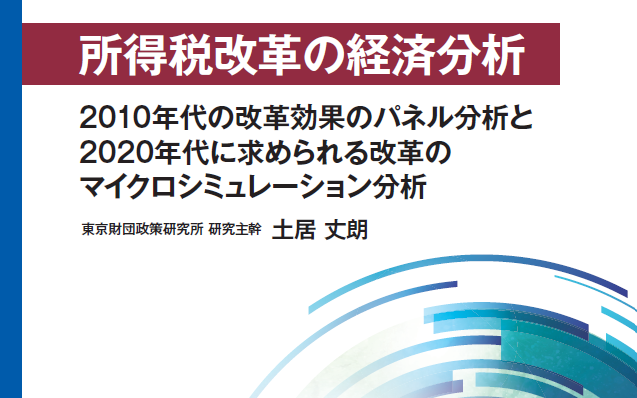R-2023-054
本稿では、児童手当の支給期間を18歳まで延長するとともに、16~18歳の扶養控除を廃止したなら、誰にどれだけの負担純増が及ぶかを明らかにする。
前稿の「18歳までの児童手当支給と扶養控除廃止なら誰にどれだけ負担純増となるか(その1)」においては、現在の16~18歳の扶養控除が適用された納税者の年齢構成と所得分布について、「日本家計パネル調査(JHPS/KHPS)」の2020年調査を基に考察した。16~18歳の扶養控除が適用された納税者は、40~59歳が大半で、わが国全体でみると相対的に所得が高い年齢層であることがわかった。
そこで、児童手当の支給期間を18歳まで延長するとともに、16~18歳の扶養控除を廃止したならどうなるかを分析しよう。
| ・扶養控除と児童手当の関係 ・16~18歳の扶養控除の適用額 ・16~18歳の扶養控除による税負担軽減額 ・18歳までの児童手当支給で給付の純増額はどうなるか |
扶養控除と児童手当の関係
まず、児童手当と、所得税・個人住民税の扶養控除との関係をおさらいしておこう。2010年に民主党政権において、旧児童手当を改編して「子ども手当」を創設するにあたり、所得制限をなくして支給する代わりに、図1のように15歳以下の扶養控除を廃止した。児童手当を所得制限なしに支給することと扶養控除の廃止はセットだった。ちなみに、16~18歳の扶養控除を25万円縮減したのは、高校授業料無償化の実施に伴う措置だった。
図1 所得税における扶養控除の見直し(2011年所得~)

出典:土居丈朗『入門財政学(第2版)』(日本評論社)
これとの平仄を合わせるならば、児童手当を18歳まで所得制限なしに支給する際には、現存する16~18歳の扶養控除も廃止しないと、所得税制において15歳以下との整合性が取れない。15歳までは扶養控除はないが児童手当を支給し、16~18歳の扶養控除がありながら児童手当も支給する、となると、制度として首尾一貫性がなくなる。
ただ、所得税制において扶養控除を廃止すれば、それだけ課税所得が増えて、所得税や個人住民税が増税となる。児童手当が新たに支給される一方で、扶養控除が廃止されれば、児童手当の支給による手取り所得の増加の効果が減殺される。
16~18歳の扶養控除の適用額
そこで、本稿では、児童手当の支給期間を18歳まで延長するとともに、16~18歳の扶養控除を廃止したなら、誰にどれだけの負担純増となるかを分析する。
分析にあたり、所得税の計算が複雑になるのを避けるため、すべての所得は給与所得で得ているとの想定で分析結果を示す。
ここで注意したいのは、共稼ぎ世帯では、夫婦のうちより高い所得を得た者(主たる稼ぎ手)に扶養控除が適用される(ことで、夫婦合計した所得税負担額を小さくできる)ことから、16~18歳の扶養控除が廃止されても、夫婦のうちより少ない所得を得た者は一切増税にならない。なぜならば、夫婦のうちより少ない所得を得た者には、そもそも扶養控除は適用されていないからである。
まず、給与所得者には、給与所得控除が適用される。給与所得控除が適用された後の所得(給与所得)から、基礎控除が差し引かれる。また、社会保険料を支払っている者には支払い実額を社会保険料控除として課税対象から差し引かれる。
その上で、扶養親族の年齢や人数に応じて、扶養控除が課税対象となる所得から差し引かれる。
所得税制における所得控除の適用には順番はない(ちなみに、給与所得控除は、(狭義の)所得控除ではなく、所得計算上の控除であり、(狭義の)所得控除よりも先に控除される)。所得税額を計算する際に、当該納税者が適用できる所得控除の合計額を計算した後に、課税対象となる所得からその所得控除の合計額を差し引く、その差額が課税所得となる。ただし、課税所得が0円未満(つまりマイナス)になるなら課税所得を0円として、支払う所得税がないと判定される。
ただ、本稿で検討しているのは、16~18歳の扶養控除の廃止の影響である。したがって、その影響額を見極めるには、まず16~18歳の扶養控除以外の所得控除をすべて適用した後に、残る課税対象となる所得があった場合にのみ、16~18歳の扶養控除を適用して、その結果として課税所得がいくらになるかを計算して、16~18歳の扶養控除の適用状況を見極める。
よって、16~18歳の扶養控除は、16~18歳の扶養親族を持つ所得税の納税者には、扶養親族1人につき38万円の扶養控除が与えられているというのが、所得税制に即した説明になるのだが、本稿の分析ではその目的に沿うとそうではない。16~18歳の扶養親族を持つ所得税の納税者であっても、16~18歳の扶養控除以外の所得控除をすべて適用した後に残る課税対象となる所得が0円以下であれば、16~18歳の扶養控除は、一切適用されていなかったとみなすのである。
なぜならば、16~18歳の扶養控除以外の所得控除をすべて適用した後に残る課税対象となる所得が0円以下ならば、この時点で既に所得税負担額は0円であり、もはや16~18歳の扶養控除があったとしても使い残してしまい、所得税負担額を軽減することはこれ以上できないからである。16~18歳の扶養控除以外の所得控除をすべて適用した後に残る課税対象となる所得が0円以下である者は、16~18歳の扶養控除が廃止されても、一切増税にはならない。
このように、本来は所得控除には適用の順番はないのだが、本稿での分析の目的に照らせば、16~18歳の扶養控除以外の所得控除を先に適用したものとし、最後に16~18歳の扶養控除を適用するという順に計算することによって、16~18歳の扶養控除の廃止の影響がきちんと見極められるのである。
では、給与所得者について、いくらの課税前収入の人に16~18歳の扶養控除がどれだけ適用されているかを確認しよう。それを示したのが、図2である。本稿では、2023年所得に適用される税制を基に試算している。

出典:筆者作成
まず、16~18歳の扶養控除以外の所得控除は、世帯構成によって異なる。したがって、本稿では次の4類型で試算することとする。それは、①大学生と高校生の子がいる片稼ぎ世帯、②大学生と高校生の子がいる共稼ぎ世帯、③高校生と中学生以下の子がいる共稼ぎ世帯、④高校生の子がいる共稼ぎ世帯である。ここでの高校生は、16~18歳の扶養控除の対象者である。
また、ここで16~18歳の扶養控除の適用を受ける者は、課税前給与収入が130万円以上となると、社会保険料を払う(被用者保険での被扶養者でなくなる)と仮定する。そして、支払う社会保険料は、課税前給与収入900万円以下は15%、900万円超1800万円以下は3%+108万円、1800万円超は162万円とする。その金額が、そのまま社会保険料控除の額となり、①~④のすべてに適用される。
①は、16~18歳の扶養控除以外の人的控除(世帯員に関連づいた所得控除)が、これらの中で最も多い世帯類型で、基礎控除と配偶者控除(ないしは配偶者特別控除)、大学生に対する19~22歳の特定扶養控除(63万円:図1参照)が適用される。②は、配偶者控除が適用されない共稼ぎ夫婦で、基礎控除と大学生に対する19~22歳の特定扶養控除が適用される。③と④は、16~18歳の扶養控除以外の人的控除は、基礎控除しかない(中学生以下には扶養控除がないことに注意:図1参照)。③と④の違いは、世帯人数が③は4人で④は3人である。これにより、個人住民税(所得割)の非課税限度額が異なり、4人の方が非課税限度額が高くなる。[1]
これら4類型で、主たる稼ぎ手の課税前給与収入を横軸に、所得税で適用される16~18歳の扶養控除の適用額を縦軸にとったのが、図2である。この横軸は、拙稿「18歳までの児童手当支給と扶養控除廃止なら誰にどれだけ負担純増となるか(その1)」で示した、16~18歳の扶養控除が適用された納税者の所得階級別累積構成比として表している。累積構成比(0%~100%)の目盛は、横軸直下に示している。前掲拙稿の表2にあるように、上位10%の所得階級は1200万円超の所得階級であるから、横軸の右端から10%のところに、主たる稼ぎ手の課税前収入が1200万円と目盛られている。対象者の所得の中央値は600万円強だから、横軸の中位を示す累積構成比50%のところは、課税前収入が600万円強となっている。[2]
ここで注意したいのは、横軸は、世帯収入ではなく、主たる稼ぎ手の課税前収入である。そもそも、扶養控除は、世帯収入に対して適用されるのではなく、主たる稼ぎ手に適用されるものである。
①の大学生と高校生の子がいる片稼ぎ世帯(青線)では、主たる稼ぎ手の課税前収入が285万円以下だと、16~18歳の扶養控除以外の所得控除をすべて適用した段階で課税所得は0円となる。したがって、その所得層では、16~18歳の扶養控除が与えられても使い残すことになり、事実上適用されないも同然となっている。286万円以上になると、16~18歳の扶養控除以外の所得控除をすべて適用してもなお残る課税対象となる所得が生じるため、課税所得が0円になる金額まで16~18歳の扶養控除が使われるが、満額の38万円には達しない。そして、355万円以上だと、16~18歳の扶養控除を満額の38万円使い切っても、課税所得は0円以上となる。
同様に、②の大学生と高校生の子がいる共稼ぎ世帯(赤線)でも、主たる稼ぎ手の課税前収入が216万円以下だと、16~18歳の扶養控除が事実上適用されないこととなる。そして、286万円以上だと、16~18歳の扶養控除を満額の38万円使い切っても、課税所得は0円以上となる。
③の高校生と中学生以下の子がいる共稼ぎ世帯(緑線)は、主たる稼ぎ手の課税前収入が103万円以下だと、16~18歳の扶養控除が事実上適用されないこととなる。104万円以上になると、課税所得が0円になる金額まで16~18歳の扶養控除が使われるが、満額の38万円には達しない。そこに、課税前収入が130万円以上となると、社会保険料を払うこととなるため、社会保険料控除が適用される。その際、16~18歳の扶養控除よりも先に社会保険料控除が適用されるため、16~18歳の扶養控除の適用額がその分だけ減少する。課税前収入が129万円では適用額は26万円だが、課税前収入が130万円では適用額は7.5万円となる。そして、170万円以上だと、16~18歳の扶養控除を満額の38万円使い切っても、課税所得は0円以上となる。
④の高校生の子がいる共稼ぎ世帯(茶線)は、③と同じである。扶養親族数の違いはここでは差異に現れない。
図2を全体的にみると、下位10~20%以下の所得階級では、16~18歳の扶養控除が与えられていながら控除を使い残しており、税負担軽減の恩恵に与れていないことがわかる。別の言い方をすると、16~18歳の扶養控除が廃止されても、税負担は一切増えないということになる。
これと同様に、個人住民税における16~18歳の扶養控除(33万円)の適用額も計算できるが、ここでは図示を割愛する。
ここで重要なことは、本稿での推計は、所得税だけでなく個人住民税の影響もすべて含めて分析していることである。[3] 16~18歳の扶養控除は、所得税にも個人住民税にもある。だから、16~18歳の扶養控除の廃止は、所得税にも個人住民税にも影響が現れる。したがって、本稿で分析することは、児童手当の18歳までの支給期間延長に伴う給付増と、16~18歳の扶養控除の廃止に伴う所得税と個人住民税の負担増の比較である。
16~18歳の扶養控除による税負担軽減額
では、16~18歳の扶養控除の廃止に伴う所得税と個人住民税の負担増はどうなるか。それは、現行の16~18歳の扶養控除によって、適用者が受けている所得税と個人住民税の負担軽減額に左右される。そこで、現行の16~18歳の扶養控除によって、適用者が受けている所得税と個人住民税の負担軽減額を示したのが、図3である。図3の横軸は、図2と同じである。
 出典:筆者作成
出典:筆者作成
図3には、図2で示した所得税における扶養控除だけでなく、個人住民税における扶養控除の効果も含まれている点に注意されたい。
そもそも、扶養控除をはじめとする所得控除の税負担軽減効果は、次のようになる。例えば、10万円の所得控除が与えられたときに、累進課税で10%の(限界)税率に直面している者がいるとする。このとき、この10万円の所得控除がないと、10万円課税所得が多くなるから、その多くなった10万円に10%の税率で所得税が課される。つまり1万円の税負担となる。しかし、10万円の所得控除が追加して与えられることによって、この1万円の税負担が軽減される。だから、所得控除の税負担軽減効果は、与えられた所得控除の額と直面する(限界)税率の積となる。さらなる詳細な説明は、拙著『入門財政学(第2版)』(日本評論社)を参照されたい。
図3において、①(青線)では、主たる稼ぎ手の課税前収入が235万円以下だと所得税も個人住民税も16~18歳の扶養控除以外の所得控除を適用した段階で課税所得は0円となり、16~18歳の扶養控除がもたらす税負担軽減額は0円である。236万円以上になると、個人住民税において、16~18歳の扶養控除以外の所得控除をすべて適用してもなお残る課税対象となる所得が生じるため、個人住民税の課税所得が0円になる金額まで16~18歳の扶養控除が使われる。それにより、個人住民税の税率10%相当分が税負担軽減額となる。286万円以上だと、図2でみたように、所得税において16~18歳の扶養控除が課税所得が0円になる金額まで使われる。それにより、個人住民税の税負担軽減額に、所得税の税負担軽減額が加わる。
295万円以上だと、個人住民税の16~18歳の扶養控除を満額の33万円使い切って、これ以上税負担軽減効果が大きくならなくなる。税率は10%だから、個人住民税の税負担軽減額は3.3万円で打ち止めとなる。ただ、所得税の16~18歳の扶養控除はまだ満額の38万円まで使い切っていないので、課税前収入が増えると所得税の税負担軽減効果は増える。そして、355万円以上だと、図2でみたように、所得税の16~18歳の扶養控除を満額の38万円使い切る。355万円での所得税の(限界)税率は5.105%(復興特別所得税を含む)であるから、所得税の税負担軽減額は約1.94万円である。図3には、所得税の税負担軽減額と個人住民税の税負担軽減額の合計額が縦軸として示されている。
ところが、所得税は累進課税されているので、(限界)税率は課税所得が上がると上昇する。①では、656万円で所得税の(限界)税率が10.21%に上がる。すると、同じ扶養控除によって生じる税負担軽減額は約7.18万円に増える。それと同様に、所得税の(限界)税率は、836万円で20.42%に、1198万円で23.483%に、1410万円で33.693%に、2321万円で40.84%に、4473万円で45.945%になる。それに連動して、所得税と住民税を合わせた税負担軽減額は836万円で約11.06万円に、1198万円で約12.22万円に、1410万円で約16.10万円に、2321万円で約18.82万円に、4473万円で約20.76万円になる。
16~18歳の扶養控除は、適用者全員に同額であるにもかかわらず、税負担軽減効果は、(限界)税率の違いから、高所得者ほど金額が多くなるのである。高所得者ほど税負担軽減効果が大きいということは、それだけ所得格差が是正できていないことを意味する。これが、16~18歳の扶養控除の経済効果である。
同様に、②~④についても、税負担軽減額を図3に示している。①と閾値の金額は異なるが、階段状になっているのは同様で、直面する(限界)税率が課税所得が上がるにつれて高まるからである。そして、図3を全体的にみると、適用者の上位10%にあたる1200万円以上の所得階級では、どの世帯類型でも16~18歳の扶養控除による税負担軽減額は12万円を超えていることがわかる。
18歳までの児童手当支給で給付の純増額はどうなるか
最後に、児童手当の支給期間を18歳まで延長するとともに、16~18歳の扶養控除を廃止した場合、給付増と負担増によって、給付の純増額はどうなるかを示したのが、図4である。ここでは、16~18歳の子1人につき児童手当を月1万円、つまり年12万円給付することを仮定している。図4の横軸は、図2及び図3と同じである。縦軸は、給付の純増額を示している。それがプラスならば児童手当の給付増が上回り、マイナスならば扶養控除の廃止に伴う負担増が上回っている。

出典:筆者作成
図4に現れた効果は、概ね、12万円の給付増に、図3の税負担軽減額が剥落して生じる負担増を合わせたものとなる。しかし、一部にまだ本稿で説明していない効果が混じっている。
図4において、①(青線)では、主たる稼ぎ手の課税前収入が271万円以下だと給付の純増額は12万円となっている。つまり、16~18歳の扶養控除の廃止に伴う負担増は皆無である。272万円になると、個人住民税の非課税限度額を超える。ただ、16~18歳の扶養控除があれば課税所得は0円となるため、非課税限度額を超えても個人住民税は0円だが、16~18歳の扶養控除が廃止されると課税所得が20.6万円となるため、2.06万円の個人住民税負担が突如生じることになる。これによって、給付の純増額は9.94万円となる。これは、16~18歳の扶養控除の廃止に伴い、課税所得が増えたことから、住民税の非課税限度額を超えたときの課税所得が増えるために、追加的な負担増が生じるという効果である。
273万円以上だと、図3で示したように、個人住民税、次いで所得税の16~18歳の扶養控除による税負担軽減額が剥落して生じる負担増によって、給付の純増は減少してゆく。そして、355万円以上だと、給付の純増額は約6.76万円となる。
598万円以上だと、16~18歳の扶養控除の廃止に伴い、課税所得が増えたことから、同じ課税前収入でも直面する所得税の(限界)税率がより高くなるために、追加的な負担増が生じる。598万円だと、所得税の(限界)税率は、16~18歳の扶養控除があれば5.105%だが、16~18歳の扶養控除が廃止されると10.21%となる。その効果は、655万円まで続く。そして、656万円以上だと、給付の純増額は約4.82万円となる。同様の所得税の(限界)税率の上昇は、787万円以上835万円以下などでも生じる。図4において、主たる稼ぎ手の課税前収入が400万円以上のところで、給付の純増額のグラフが右下がりになっているところでは、この効果が生じている。
そして、①においては、主たる稼ぎ手の課税前収入が1191万円を超えると、16~18歳の扶養控除の廃止に伴う負担増が12万円を超え、給付の純増はマイナス、つまり負担の純増となる。②(赤線)も、給付の純増額がマイナスとなる所得水準は、①と同じである。
それより高い所得では、所得税の累進課税により、より高い(限界)税率に直面することから、図3で示した税負担軽減効果が大きく、16~18歳の扶養控除の廃止に伴いその剥落が生じるため、負担の純増額はさらに大きくなる。
②~④についての給付の純増額も、同様に図4に示している。③(緑線)と④(茶線)における給付の純増額がマイナスとなる主たる稼ぎ手の課税前収入の水準は、1126万円である。[4] 巷間で、こうした負担の純増となるのは年収900万円以上の人といわれているが、そうではない。本稿では、当然として考慮すべき社会保険料控除を計算上含めているが、それが含まれていなかったためと思われる。
また、各所得水準における給付の純増額のより厳密な金額は、表1に示している。

出典:筆者作成
繰り返し留意を促すが、図2~4や表1における所得(横軸)は、世帯収入ではなく、主たる稼ぎ手の課税前収入である。特に、共稼ぎ世帯において、従たる稼ぎ手(夫婦のうち収入の少ない方)は、16~18歳の扶養控除が廃止されても、そもそもこの控除の適用を受けていないから、一切増税にはならない。
確かに、16~18歳の扶養控除の廃止に伴う負担増が、高所得者でより大きいから、負担の純増に直面する主たる稼ぎ手が存在する。ただ、その所得水準は、図4と表1に示した通り、1200万円弱であり、現在16~18歳の扶養控除の適用を受けている納税者の10%にすぎない。図3に示された通り、16~18歳の扶養控除による税負担軽減効果は、高所得者ほど大きくなっており、それだけ所得格差の是正を阻んでいる。
これを改めるには、18歳まで支給する児童手当に所得制限をなくすのに合わせて、16~18歳の扶養控除を廃止することが有効な方策である。
[1] 個人住民税(所得割)の非課税限度額は、給与所得(厳密には総所得金額等)が35万円×(扶養親族数+1人)+42万円である。ここでは、16歳以下の扶養親族も含める。
[2] 横軸を、単純に課税前給与収入の金額で目盛ると、その対象所得層にほとんど対象者がいないにもかかわらず横幅が大きく表示されることとなり、実態にそぐわずミスリードすることになる。
[3] 個人住民税は、前年の所得に対して課税されるが、本稿では課税される年を基準に推計した分析ではなく、当該年における所得に課される所得税と個人住民税を推計した分析である。また、所得税においては、復興特別所得税も含めて分析する。
[4] ③と④の違いは、個人住民税の非課税限度額に現れる。16~18歳の扶養控除が廃止されると、主たる稼ぎ手の課税前収入が、③は272万円、④は222万円になると個人住民税の非課税限度額を超えて、個人住民税が課税されるため、図4では給付の純増額が突如減少している。