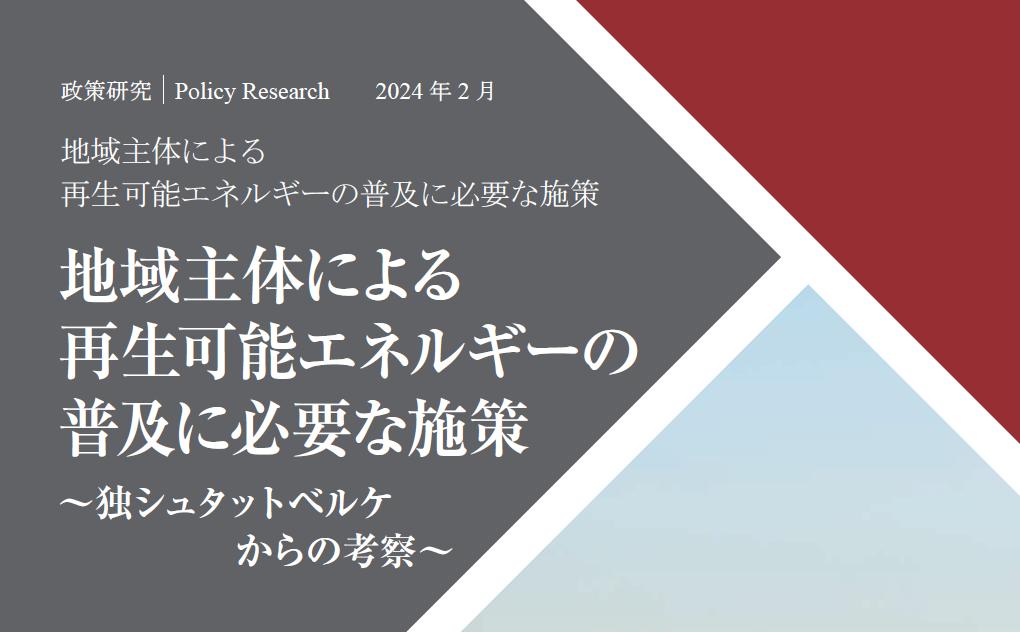平沼光
研究員
パリ協定の発効により、世界は再生可能エネルギー(以下、再エネ)の大幅な普及と石炭利用の削減を中心としたエネルギー転換の方向に大きくかじを切った。日本においても福島第1原発事故以降、再エネの固定価格買取制度(FIT制度)などにより急速に再エネの普及が進められている。しかし、メガソーラー設置による地域の自然環境・生活環境や景観への影響が問題視され、再エネ活用による地域への利益還元の構図が見えなければ、苦情や反対運動の件数も今後さらに増加すると懸念される。
再エネは、その地域に吹く風や照りつける太陽光、水力や地熱などがエネルギー源であるため、その活用には地域の理解と主体的な参加が必要になる。しかし、再エネを活用した再エネ発電事業を行うにしても、戦後およそ60年間にわたり電力事業は大手電力会社による独占体制が続いた日本では、地域に電力事業の経験が蓄積されているわけではない。ましてや普及途上の再エネ発電事業のノウハウを地域が持ち合わせていない場合も多い。再エネ発電事業を行おうとしても、地域の理解を得られないケースも起こってきている。
東日本大震災からの復興の一環として、「再生可能エネルギー先駆けの地」となることを目指し、再エネの普及に努めている福島県では、風力発電に否定的な住民意見が根強くあり、震災後に複数の風力発電計画が地元の反対により中止された。県では反対が起きた一因として、開発検討過程に地元企業や自治体などの地域住民の参画がなかったことを挙げる。現在は、県が地元企業の参加を条件に事業者を公募するなどして、合計300メガワットの風力発電事業について慎重に環境影響評価が進められている。
こうした状況から分かるように、再エネの普及においては経済的、技術的な課題とともに、地域の受容性をいかにして醸成していくかという点が、世界のエネルギー転換の中で今後対処していかなければならない新たな課題として浮上してきている。
地域の反対から始まった再エネ事業
では、地域の受容性を醸成し、地域主体の再エネ事業を創出するにはどうしたらよいか。再エネはいまだ普及途上であり、地域の再エネに対する受容性も課題となっているが、再エネの活用事例の中には長崎県雲仙市・小浜温泉における「温泉バイナリー発電事業」のように、地域の反対から始まり、その後成功しているものもある。
小浜温泉は、「肥前風土記」(713年)に記されているほど古くからあり、温泉宿などを営んできた住民が今日まで温泉を中心に地域の自治を担ってきた温泉街である。泉温約100度、1日の湧出量約1万5000トンという豊富な温泉資源を活用し、使われれず余って排水となる温泉水の熱を利用して沸点の低い触媒を沸騰させ、その蒸気の力でタービンを回して発電を行うバイナリー発電に地域が主体となって取り組んでいる。
小浜温泉では、バイナリー発電の実証実験に先駆的に取り組み、実験後は事業化にたどり着いているが、当初は温泉事業者をはじめとする地元住民による反対運動で頓挫した経緯がある。
温泉熱利用に対する住民の本格的な反対運動は、2004年に小浜町が構造改革特区に認定され小浜町と新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による発電計画が持ち上がった頃に始まっている。当初、計画の実施者である小浜町とNEDO、そして源泉所有者の間では、温泉掘削に係る協約書が取り交わされていたが、近隣の雲仙温泉が温泉への影響を懸念して「守る会」を結成、次いで小浜温泉でも守る会が結成され、地元の了解が得られず05年に計画は頓挫している。
源泉所有者との間に協約書が交わされていたにもかかわらず頓挫してしまったのは、①掘削地点についての十分な説明が実施者から住民に対してなされなかった②あくまで調査のためだったはずの掘削が恒常的営業運転のためだったことが判明した――という二つの理由による。これは、明らかに実施者(小浜町・NEDO)が住民からの理解を得ることに失敗した事例であり、地域で経験のない再エネの活用に取り組もうとする場合、地元関係者の理解を十分に図り、地域の受容性を構築することがいかに重要かということがわかる。
地域理解の促進による受容性の構築
一度は頓挫した小浜温泉の発電計画だが、07年に入って長崎大学環境科学部と長崎県雲仙市、そして長崎県の3者の間で、雲仙市を再エネの活用も含めた持続的な社会にすることを目的とした連携協定が締結された。排水となっている温泉をエネルギーとして活用したいという志を持った長崎大は、連携協定を実行するための体制として研究会を設立。再エネを活用する「地域新エネルギービジョン」の策定と、発電実証実験をするための環境省への申請作業を進めるとともに、地域住民の理解を得るために住民協議と実証実験に関するリレー講座やシンポジウムを開催した。
その結果、温泉熱の利用に反対だった温泉事業者や地域住民の理解が得られ、11年3月に温泉熱利用を促進する「小浜温泉エネルギー活用推進協議会(以下、協議会)が設立され、同年5月には、実行組織として温泉事業者と産学による「一般社団法人小浜温泉エネルギー」も設立された。さらに、これら組織を雲仙市と長崎県、国が支援するとともに、長崎大が研究成果の還元など専門的な知見により協力するという地域の連携体制が構築されている。
そして、同年11月には環境省の温泉発電実証事業に採択され、13年4月に「小浜温泉バイナリー発電所」を開設して実証実験を開始。実験は14年3月に無事終了し、町おこしの発電事業のモデル構築の意思を持つ事業者が発電所を引き継ぎ、15年9月から売電が開始され事業化に至っている。
小浜温泉バイナリー発電所は、一般家庭の約220世帯分の電気を賄う規模の発電所で、電力を地域内外へ供給するとともに、小浜温泉観光協会と協力して見学ツアーを企画するなど地域に利益を還元する事業に取り組んでいる。
さらに、発電後に排水される60~70度程度の温泉水を利用し、高級魚クエの陸上養殖など地域振興につなげるための施策を検討している。15年3月には、雲仙市の「雲仙市環境基本計画」に低炭素なまちづくりの一環として温泉エネルギーの活用が盛り込まれ、地域としても温泉熱を積極的に活用する方針が打ち出された。
地域主体の再エネ事業創出の要件
小浜温泉の事例から地域の再エネを活用する過程を考察すると、植物が種子から発芽し、成長して実を結ぶまでの過程に例えて、種子期、発芽期、成長期、結実期という四つの段階に区分けすることができる。
 取り組みの初めとなる種子期には長崎大のように地域の再エネを活用したいという意思のあるプレイヤーの存在が必要になる。
取り組みの初めとなる種子期には長崎大のように地域の再エネを活用したいという意思のあるプレイヤーの存在が必要になる。
しかし、いくらプレイヤーがいるからといってそれだけでは先に進まない。植物の種子が発芽するには水が必要なように、再エネ事業の経験のないプレイヤーが事業計画を立案する、すなわち事業を発芽させるには専門家の協力など専門的なノウハウへのアクセスが必要となり、この段階を発芽期とする。小浜温泉の事例ではプレイヤーである長崎大が専門的なノウハウを持ち合わせていたことが、バイナリー発電事業計画を立案するために重要な役割を果たした。
再エネ活用の事業計画ができたら、今度はそれを実行するためにプレイヤーが活動する場が地域に必要になる。植物が発芽し成長するには豊かな土壌が必要なように、地域におけるプレイヤーの活動の場は再エネ事業を実行し成長させる土壌である。小浜温泉の事例では長崎大というプレイヤーが住民理解の促進に努めたことにより協議会という活動の場の構築に成功しており、この段階が成長期となる。
植物が成長し結実して時代に種を持続させるように、種子期から成長期を経て創出された再エネ事業は一過性のものではなく持続的なものにする必要がある。そのためには再エネを活用する活動を地域が肯定化し、標準化する仕組みを確立する必要があり、この段階を結実期とする。小浜温泉の事例では、雲仙市の環境基本計画に温泉エネルギーの活用が盛り込まれたことで、地域において温泉エネルギーを持続的に活用する土壌が確立されたことになる。
このように、地域主体の再生エネ事業を創出するためには、種子期、発芽期、成長期、結実期という過程を経るとともに、各段階で必要な要件を満たしていくことが重要であると考える。
2017年11月14日『厚生福祉』より転載
◆英語版はこちら→ Toward Community Solutions for Renewable Energy: Lessons from Obama Hot Springs