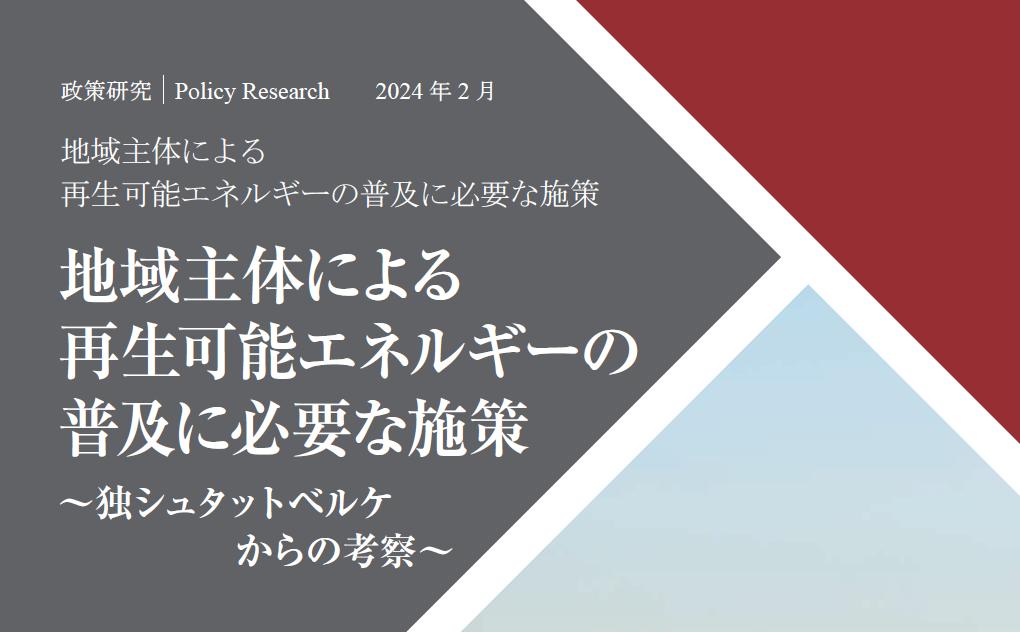C-2022-006
東京財団政策研究所CSR研究プロジェクトは、2022年度の調査テーマを「カーボンニュートラル」に定めてアンケート調査や視察を実施し、そのうち国際・国内動向の整理、先駆的な事例の研究、研究活動をもとにした提言を「CSR白書2022別冊—カーボンニュートラルに向けた地域主体の再エネ普及と企業の貢献」にまとめた。本稿に、白書別冊の調査内容の概要を示す。詳細については、別冊本文を参照されたい。
| 1.カーボンニュートラルに向けた世界の動向 2.カーボンニュートラルに向けた日本の動向 3.企業・自治体による再生可能エネルギー普及・調達の取組事例 |
1.カーボンニュートラルに向けた世界の動向
2015年のCOP21で採択されたパリ協定はわずか1年後に発効され[i]、COP21のサイドイベント「ミッション・イノベーション」で採択された誓約にはパリ協定達成に向けた官民によるクリーンエネルギーのイノベーションの加速が謳われた。民間企業家連合である「ブレイクスルー・エネルギー連合」の発足など民間の動きも活発化しており、世界各国・各地域がパリ協定の達成に向けてエネルギー転換に取り組んでいる。
エネルギー転換の中心である再生可能エネルギーは、気象条件によって変動性があるため電力系統への統合に問題を抱えていたが、ICT技術を活用して変動性を平準化するIoE(Internet of Energy)というエネルギーシステムの標準化・実装化が進められている。政策的な後押しと技術的な開発により再生可能エネルギーの普及が進んだためにそのコストも下がり、2018年時点の均等化発電原価(LCOE)では、再生可能エネルギーが最も安価な電力となっている[ii]。
技術の普及とコストの低下によってクリーンエネルギー市場が形成され、その規模も拡大している。全世界のESG投資額は2020年の35.3兆ドルまで増加しており[iii]、さらに国際エネルギー機関(IEA)はパリ協定の目標達成のため2040年までに世界全体で約58兆7,950億ドル(約6,470兆円)から約71兆3,290億ドル(約7,860兆円)の投資が必要であると試算している[iv]。クリーンエネルギーが巨大な投資分野になりつつある中で、投資を呼び込むために環境に配慮した経営が求められるようになり、2014年には自社が使うエネルギーの100%再生可能エネルギー化を表明するイニシアティブであるRE100(100% Renewable Electricity)が設立された。
上記の動向から、気候変動対策はもはや社会課題であるだけではなく無視できない市場として認識されており、世界がクリーンエネルギーに注視しているとわかる。国際再生可能エネルギー機関(IRENA)によると、2050年までに気温上昇を2°Cより十分下方に抑えるためのコストは19兆ドル、利益は50兆から142兆ドルであるとしており[v]、エネルギー転換は気候変動対策だけでなく、経済政策としても捉えられている。実際に世界の多くの国は経済復興とカーボンニュートラルの達成のためにエネルギー転換を進めるグリーン・ディールを開始し、欧州委員会(EC)は2019年12月に欧州グリーン・ディールを公表して、2050年カーボンニュートラルに向けて10年間で約120兆円を投資する計画を立てた。
カーボンニュートラルに向けた取組を積極的に進める欧州では、日本にも影響を与えうる重要な動向が2つ見られる。1つは2021年4月に公表された「EUタクソノミー」であり、これはESG投資の誘導を見据えた、欧州の価値に基づく事業の基準である。何が「グリーン」かという基準を欧州が先行して決めたインパクトは、域外にも大きく作用する可能性がある。2つ目は2021年7月に世界で初めて作成されたCBAM(炭素国境調整メカニズム)の規則案である。これは、EU域内と比べて気候変動対策が不十分な国の炭素排出に課金する貿易措置であり、EU域外へのインパクトが大きいと考えられる。
こうしてグリーン・ディールを進めるEUにも、逆風がないわけではない。世界的な各種化石燃料の高騰やコロナ禍からの経済活動の再開などの複合的な要因により、2020年秋より欧州の卸電力価格・天然ガス卸売価格が高騰した。また、2022年2月にはウクライナ危機とそれを受けたロシアへの経済制裁によって世界的な資源価格が高騰し、欧州諸国の化石燃料への依存度の高さが問題になった。電力危機の原因の1つとしてエネルギー転換が指摘され、また電力価格が急騰したことで、欧州の化石燃料への回帰が一部で予測された。しかし、2021年10月に、ウルズラ・フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長は「欧州持続可能なエネルギー週間」でのスピーチで、化石燃料の輸入依存に対応するためエネルギー転換を加速するべきであるという立場を明確化した[vi]。また、ウクライナ危機後の2022年5月には、ロシア産化石燃料への依存を低下させる「リパワーEU」が発表された。本計画では、2030年に向けた温室効果ガス排出量削減のための政策パッケージである「Fit for 55」の追加政策として、(1)再生可能エネルギーへの移行加速、(2)省エネ高効率化の促進、(3)エネルギー供給源の多角化、(4)スマートインベストメントの促進、が示された。
以上より、現在のカーボンニュートラルに向けた世界動向は以下の点に要約できよう。(1)パリ協定を皮切りに、世界の政府・企業がカーボンニュートラルへの取組を進めている (2)再生可能エネルギーの普及と技術の発展によってそのコストは大幅に低下し、またクリーンエネルギーが有望な投資市場となっていることで、エネルギー転換は経済政策になっている。(3)特に活発にエネルギー転換を進めているのは欧州であり、日本など他国も欧州主導でのルール形成に影響を受ける可能性がある。(4)電力高騰やウクライナ危機などの逆風はあるものの、欧州はエネルギー転換への歩みを緩めていない。
2.カーボンニュートラルに向けた日本の動向
上記の欧州を始めとするカーボンニュートラルに向けた動きが活発化する中で、日本がカーボンニュートラルを明示的に打ち出すのは、2020年10月の菅首相(当時)の所信表明演説を待つことになる。しかし、2019年度の日本の再生可能エネルギー導入比率は約18%にとどまり、また2015年7月に公表された2030年の導入エネルギー導入目標も22〜24%と、日本は開始時期、導入の現状、目標の全てで世界に遅れをとっていた。また、クリーンエネルギー市場での産業競争力の基盤となる太陽電池モジュール、洋上風力発電、電気自動車、車載用リチウムイオン電池などの技術面でも、その中には日本発の技術やかつては日本がリードしていた領域、特許数では今でも日本が世界のトップである分野があるにもかかわらず、世界シェアでは存在感を示せていない。これらの状況を打破するため、2020年12月に公表された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では、2050年の再生可能エネルギー比率約50〜60%が目標とされ、また野心的な目標として2030年度には2013年度比で温室効果ガス排出量を46%削減するとされた。2021年10月に公表された第6次エネルギー基本計画では再生可能エネルギーを主力電源とするとされ、2030年の再生可能エネルギー導入目標も36〜38%に引き上げられた。
再生可能エネルギーは企業ニーズが高く、日本のRE100の窓口を担当するJCLP(日本気候リーダーズ・パートナーシップ)は2030年の再生可能エネルギー比率50%を求めており、また企業548社(2023年1月5日現在)が参加する気候変動イニシアティブ(JCI)や経済同友会も2030年の再生可能エネルギー比率40〜50%を主張している。この背景には、前述の欧州によるCBAMへの危機感があり[vii]、日本の気候変動対策が進んでいない状況でこの枠組みが拡がれば、日本の輸出商品が課金の対象となるリスクがある。同様に、日本企業はグローバルに普及しつつある脱炭素経営への対応の必要性にも直面しており、例えば2021年6月には東京証券取引所がコーポレートガバナンス・コードを改訂し、プライム市場への上場企業にTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)に基づく情報開示が求められた[viii]。
第6次エネルギー基本計画が目指す2030年の再生可能エネルギー導入目標36〜38%の達成までは、あと数年しか猶予がない。そのためには、以下の各種再生可能エネルギーの特性を考慮する必要がある。
(1)即応力の高い太陽光発電:太陽光発電は技術的に確立されており、設置場所があれば短時間で設置できる。
(2)発展性のある風力発電:再生可能エネルギー導入36〜38%達成のためには、陸上風力340億kWh、及び前目標(22〜24%)のおよそ8倍となる170億kWhの洋上風力導入が求められる。よって、洋上風力のポテンシャルは高く、特に水深が深い日本の海では浮体式洋上風力に期待が集まる。
(3)安定性のある地熱、水力、バイオマス:地熱、水力、バイオマス発電は太陽光、風力発電と比べて気象条件に左右されず、再生可能エネルギーの安定化による電力系統への統合に寄与できる。
上記の各種発電に加えて、電気を消費地に送電するための地域間連系線の整備も課題であり、特に導入が需要を大きく上回ると予想される北海道・東北地内で大きな課題となる。
企業からのニーズが高く、また各地で多様な再生可能エネルギー設備を設置する必要がある中で、地域の主体的な関与が求められる。しかし、大型メガソーラー設置の際には景観や自然環境を破壊してしまう懸念から現地の市民による反対運動が起きており、これらの問題を受けて再生可能エネルギーの設置に抑制的な条例を制定する自治体が増加している。その背景には「外部資本型」のメガソーラーの増加があり、外部資本型ではデメリットを現地が負担する一方で、雇用創出や売電益などのメリットが設置地域にもたらされない傾向がある。
地域の協力を得て再生可能エネルギー設備を設置するためには、欧州で広がる地域主体発電事業の取組である「コミュニティーパワー」が参考となる。世界風力発電協会(WWEA)は、コミュニティーパワーを(1)地域の利害関係者がプロジェクトの大半もしくはすべてを所有している、(2)プロジェクトの意思決定はコミュニティーに基礎をおく組織によって行われる、(3)社会的・経済的便益の多数、もしくはすべては地域に分配される、の3つのうち少なくとも2つを満たすものとしている[ix]。代表例はドイツのシュタットベルケであり、これは現地の自治体、市民、企業などが共同で出資・利用し、再生可能エネルギーだけでなく公益サービス事業も担当する。各公益サービス事業のどれかの業績が悪化しても、黒字部門による内部補助によって全体としての安定性が高められる。主体的な地域の関与を引き出すことは、そもそもの企業価値向上という脱炭素経営の企業側の目的にも貢献する。
また、再生可能エネルギー導入目標達成には、「追加性」のある調達も重要な論点である。すでに再生可能エネルギー100%を達成しているGoogle社は、再生可能エネルギーの調達にあたって「追加性」の指針を掲げており、これは既存の設備ではなく、新設した設備による発電、もしくはそれに繋がる投資や契約によって電力を調達することを意味する。RE100は2022年10月に「技術要件」を改定し、新たな要件として追加性が加えられた。追加性のある調達方法として注目される手法が、コーポレートPPAである。これは、企業や自治体などが発電事業者とおよそ10〜25年の長期契約を結ぶ電力購入を指し、長期契約によって新設設備の初期投資の回収が促され、また次の新設計画の予見性が高まる。
3.企業・自治体による再生可能エネルギー普及・調達の取組事例
以上のように、再生可能エネルギー導入において日本は多くの課題を抱えるが、それらの問題に取り組む先駆的な事例が生まれてきている。以下では、CSR研究プロジェクトとして実施した視察をもとに、3つの先駆的な国内事例を紹介する。
①地域活性化と企業参加を実践する営農型太陽光発電(市民エネルギーちば株式会社、パタゴニア日本支社、株式会社サザビーリーグ)[x]
千葉県匝瑳市では、高齢化による耕作放棄地の増加が深刻な問題となっている。市民エネルギーちば株式会社は、この問題を憂慮した地元の農業生産者を中心に2014年に設立された(設立当初は市民エネルギーちば合同会社)。同社が展開する営農型太陽光発電事業(ソーラーシェアリング)は、約3mの背の高い細型太陽光発電設備を設置する発電形式であり、太陽光パネルの下には光が差し、農地の上に設置できるため、発電と農業を両立できる。太陽光パネルの下では大豆や大麦の有機栽培が行われ、耕作を請け負う農業生産法人(Three Little Birds合同会社)の収入の安定にも寄与している。一般社団法人太陽光発電事業者連盟(ASPEn)は、2021年4月に発表した提言で、国内農地面積(荒廃農地含む)の約2%である10万haに営農型太陽光発電を導入すれば、農作物の生産を損なわずに年間1,000億kWhの電力生産が確保できるとしている[xi]。

2022年9月事務局撮影
市民エネルギーちばは売電利益を基金として「豊和村つくり協議会」を立ち上げ、環境保全や新規営農支援、子どもたちへの教育支援などを展開している。また、株式会社Reを設立し、営農型太陽光発電で生産された農産物を用いた6次産業化も展開しており、地域の雇用創出に貢献している。グループ会社である株式会社TERRAでは、営農型太陽光発電に適した太陽光発電システムの開発に取り組んでおり、一列セルの太陽電池を使用した独自システムの開発による、DC1kW(AC50kW未満時)あたり約13万円台かかる導入コストの、固定買い取り制度(FIT制度)に依存せずに済む10万円台への削減を目指している。同時に、災害時などに電力の地産地消と資金の地域内循環を実現する、農村に特化したマイクログリッドの開発にも着手しており、農地の現状に適したイノベーションを進めている。
市民エネルギーちばはこうした取組によって地域外の支援者を獲得し、環境意識の高い企業として知られるパタゴニア社の日本支社や、「ラグジュアリー」の意味にサステナビリティの視点を組み入れようとしている株式会社サザビーリーグのオフサイトPPAを請け負っている。オフサイトPPAによって生まれた電力は、「みんな電力株式会社」によってパタゴニアや、サザビーリーグが運営するロンハーマンなどのファッションブランドの店舗に供給されている。3社の取組は、地域が主体的に参加し、地域に利益を還元する先駆的なモデルであり、また企業の再生可能エネルギー調達による社会貢献のモデルとして参考にできる。
②世界に先駆けた浮体式洋上風力発電の社会実装(戸田建設株式会社、長崎県五島市)
前述のように、洋上風力発電は再生可能エネルギーの主力電源化において大きなポテンシャルを持つ。しかし、日本近海は水深50m以上の深い海域が多く、世界で普及が進む着床式洋上風力発電の設置が難しい。そのため、深い海域に適した浮体式洋上風力発電が注目を集める。戸田建設株式会社は、世界に先駆け、日本で初めて浮体式洋上風力発電(2MW)の商業運転を長崎県五島市で開始した。
戸田建設株式会社は気候変動対策をビジネスチャンスとして捉え、特に浮体式洋上風力発電事業を有望な分野として、2050年に8,000億円の売り上げを目指している。戸田建設は2007年から京都大学と共に共同研究プロジェクトを始め、2009年には1/10試験機を佐世保港内に設置した。また、FIT制度に依存せずに済むコスト水準を達成するため、タワー部にスチールではなくプレキャスト・コンクリートを使用するハイブリッドスパー構造を取り入れた。環境省による浮体式洋上風力発電実証事業(2010〜2015年度)の受託を受けたことでプロジェクトは大きく進展し、2013年10月には五島市の協力で、長崎県五島市椛島沖で世界初のハイブリッドスパー型の実証機「はえんかぜ」の設置に成功した。また、同時に再生可能エネルギー電力によってグリーン水素を製造するP2G(Power to Gas)の実証にも取り組み、ウクライナ危機後に注目を集めるグリーン水素製造においても世界に先行していた。

2015年7月監修者撮影 浮体式洋上風力発電「はえんかぜ」
本プロジェクトは、五島市をはじめとした地域の理解と主体的な参加によって実現した。五島市は人口減少が著しく、基幹産業である水産業の衰退が憂慮されている。対応策として、五島市は2015年12月に「五島市まち・ひと・しごと創生ビジョン・総合戦略(2015〜2019)」を策定し、方針の1つに「再生可能エネルギーの島づくり」を掲げ、その取組の一つに2010年の浮体式洋上風力発電実証事業が盛り込まれた。事業者と地元の漁業関係者のコミュニケーション円滑化のため、2014年1月には「五島市再生可能エネルギー推進協議会」が設立された。本協議会は、再エネ海域利用法において設置が義務付けられる法定協議会が国、自治体、漁業関係者、学識経験者から構成されるのに対し、町内会連合会や婦人会など「民」までを含めた広範なステークホルダーを含み、それによって法定協議会の前に十分な議論が積み重ねられる点に特徴がある。オール五島市での地域の主体的な関与を実現し、地域活性化の具体的な成果を積み重ねながら、ポテンシャルの高い追加性のある再生可能エネルギーの発電に取り組んでいる事例といえよう。
③北海道の豊富な再生可能エネルギーを活かす取組(北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社
再生可能エネルギーの導入には各地域のポテンシャルを掘り起こす必要があり、特に北海道は多様なエネルギーが豊富に存在し、再生可能エネルギーの活用で全国一の可能性を持つと言われる。北海道は2020年12月の菅首相(当時)によるカーボンニュートラル宣言に先駆け、2020年3月に「2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとする『ゼロカーボン北海道』の実現を目指す」と宣言し、2022年4月には「北海道地球温暖化対策推進計画」を第3次へと改定し、2030年度に温室効果ガスを2013年度比で48%削減するとしている[xii]。
その中で、重要な役割を果たすステークホルダーが北海道電力株式会社である。供給側では、海に囲まれるため日照地域が多く、日本の森林面積の22%を占める森林資源を持ち、畜産業も盛んであるため、各種再生可能エネルギー発電の導入拡大を進めようとしている。需要側では、寒冷地域であるため全国に比べ暖房用エネルギー消費量が多く、スマート電化やルームエアコンの普及による電化を進めており、また業務部門ではZEB(Net Zero Energy Building)の普及拡大、運輸部門ではEV(Electric Vehicle)、FCV(Fuel Cell Vehicle)の導入による電化・水素化の推進に取り組んでいる。
中でも注目されるのは洋上風力発電と水素活用である。洋上風力発電では、豊富なポテンシャルを活かして、株式会社グリーンパワーインベストメントと連携協定を締結し、着床式の設備を建設中である。また、本プロジェクトの取組の1つである「洋上風力発電の余剰電力によるグリーン水素製造および利活用に向けた調査」はNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)からの受託事業であり、洋上風力発電を活用したグリーン水素製造の社会実装を目指す国内初の試みである。
他にも、多様な再生可能エネルギーの受入を拡大するため、電解液中の金属イオンの酸化還元反応を利用したレドックスフロー蓄電池施設の南早来変電所への導入、出力変動を吸収するための可変速式揚水発電の設置などによって、電力の安定化にも貢献している。また、北海道の大きなポテンシャルをさらに活用するため、本州への送電を目的として、「新北海道・本州間電力連系設備」を建設し、より安定的な電力融通の体制を整えた。さらに、茅部郡森町に設置された森地熱発電所は、発電に利用した熱水を地域の園芸ハウス農業のために提供しており、地域の合意をもとにした発電所普及の事例として参考になる。前述した、地域のポテンシャルの掘り起こし、及び再生可能エネルギーの主力電源化のために求められる多様な特徴を持つ電力の組み合わせの貴重な事例である。
以上の分析をもとに「CSR白書2022別冊」では、再生可能エネルギーの普及における企業と地域の社会貢献のあり方と必要となる施策について次の6つの提言を行っている。詳細については「CSR白書2022別冊」本文を参照されたい。
提言1:地域主体の再生可能エネルギーを重視せよ
提言2:地域主体の営農型太陽光発電を促進せよ
提言3:北海道の営農型太陽光発電のポテンシャルを掘り起こせ
提言4:洋上風力発電における地域の合意形成は長崎県五島市の取組を参考にせよ
提言5:洋上風力の事業者選定は地域貢献を重視した評価方法とせよ
提言6:地域発のイノベーションを無駄にするな
CSR白書2022別冊はこちら
[i] 2015年の11月30日から12月13日までパリで開催されたCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)でパリ協定が合意された。本会議では、加盟国に温室効果ガス排出量削減目標の提出が義務づけられ、日本も2030年までの目標を発表した。
[ii] Lazard (2018), “Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis-Version 12.0” (2018年11月)
[iii] GSIA (2020), “Global Sustainable Investment Review 2020”
[iv] IEA (2019), “RE100 Annual Progress and Insights Report 2020”
[v] 国際再生可能エネルギー機関(IRENA)(2020), 『Global Renewables Outlook(国際再生可能エネルギーの展望)』
[vi] European Commission (2021), “Speech by President von der Leyen at the European Sustainable Energy Week”, Brussels, 2021年10月25日
[vii] 日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)(2021), 「炭素税及び排出量取引の制度設計推進に向けた意見書」2021年7月28日
[viii] 日本取引所グループウェブサイト、マーケットニュース「改訂コーポレートガバナンス・コードの公表」
[ix] World Wind Energy Association (WWEA)ウェブサイト, “WWEA defines Community Power”, 23 May 2011
[x] 詳細は2022年3月7日開催「カーボンニュートラルに必須な再生可能エネルギーの普及における企業の社会貢献のあり方:営農型太陽光発電に取り組む企業3社の事例検証」(CSR研究プロジェクト研究会)を参照されたい。
[xi] 一般社団法人太陽光発電事業者連盟(ASPEn)(2021)「2030年の再生可能エネルギー比率+10%に向けた提言〜営農型太陽光発電の大量導入によるエネルギーと食料の自給率向上に向けて〜」2021年4月23日
[xii] 北海道(2022)「北海道地球温暖化対策推進計画(第3次)」令和4年3月