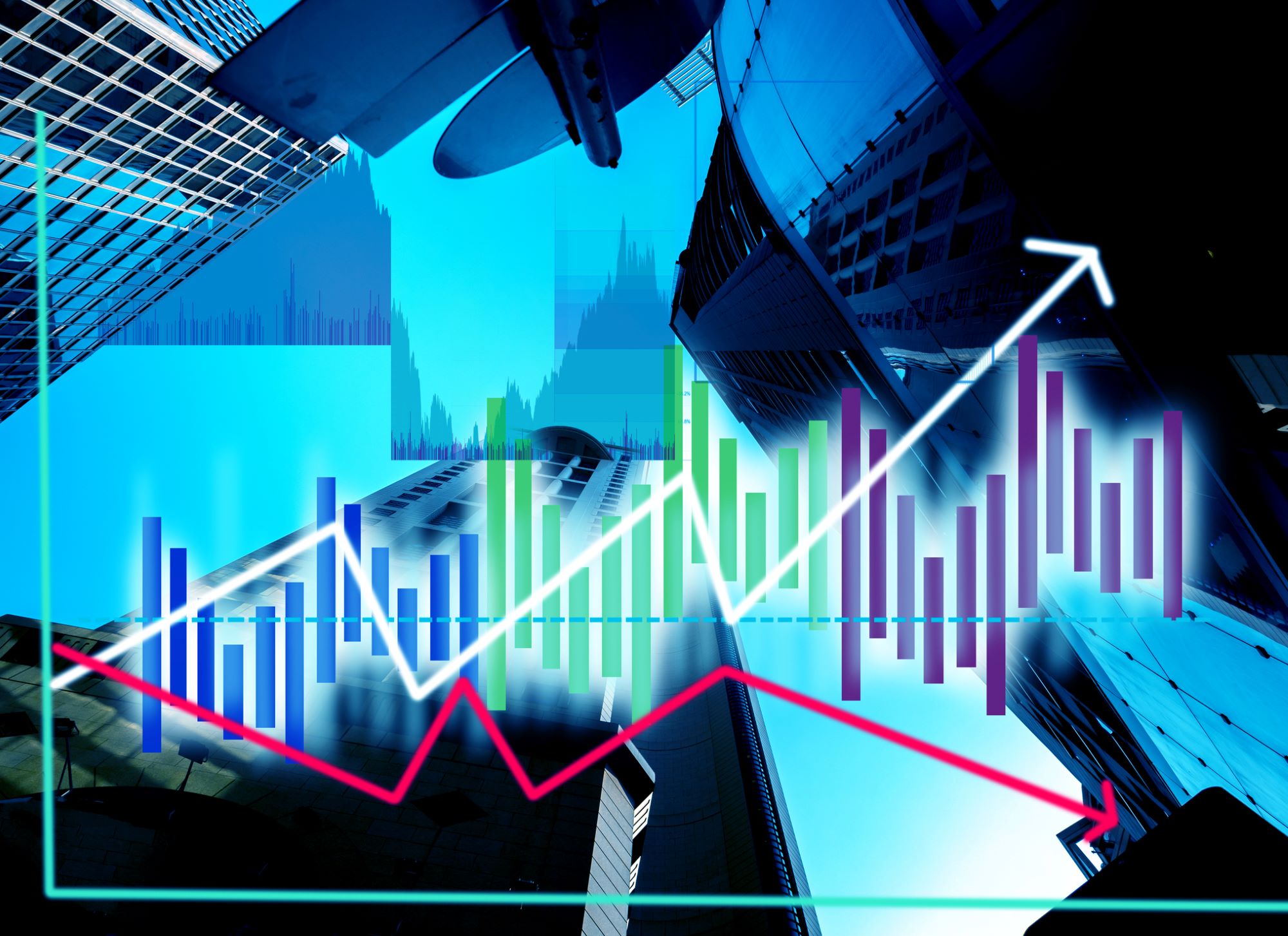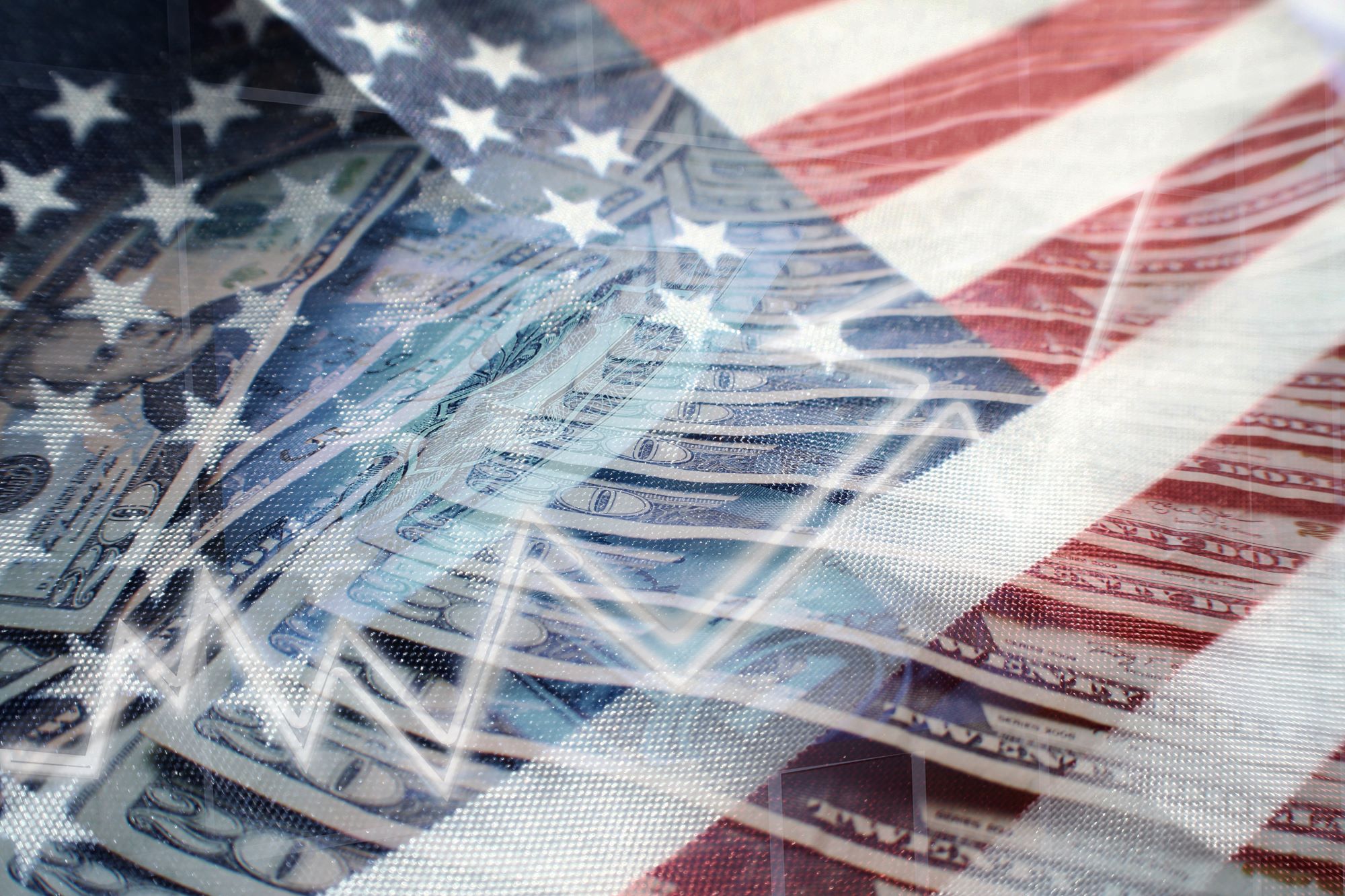人工知能(AI)やビッグデータ・IoTといった第4次産業革命が進み、新たな知識や発想が経済成長の大きな源泉となる中、教育は未来を担う次世代への投資であるが、子どもが置かれた条件の違いを乗り越えて貧困の連鎖を断ち切る鍵でもある。
このような状況の中、安倍首相は先般(6月19日)の記者会見において、「人づくり革命」の推進を打ち出した。高等教育の無償化や大学改革などが柱で、そのエンジンとなる有識者会議(「みんなにチャンス!構想会議」)を今夏に設置し、首相が新たな担当閣僚を任命する予定であるが、「国家百年の計」である教育を単なる「人気取り」の政策に利用してはならない。
そもそも、基本的に政策には「フリー・ランチ」は無く、何らかの財源が必要となる。改革の柱の一つとする高等教育の無償化を実施した場合、どの程度の財源が必要になるのだろうか。そのヒントは、教育再生実行本部の第8次提言(2017年5月18日)の資料から読み取れる。
この資料では、大学・専門学校を含む高等教育の授業料を無償化した場合、約3.7兆円の財源(消費増税1.4%分)が必要で、3.7兆円に所得制限(900万円以下の世帯)を設けた場合でも2.7兆円の財源(同1%分)が必要であるとの試算結果を掲載している。
また、収入が300万円未満の世帯の授業料を全額免除、300万円―500万円の世帯の授業料を半額免除する場合、0.7兆円程度の財源が必要としているが、現下の厳しい財政状況の下で、このような財源を毎年確保するのも容易ではない。
図表:教育再生実行本部・第8次提言 (2017年5月18日、抜粋)

このような状況の中、新たな財源を確保するための「教育国債」構想が政治的な火種として燻っている。教育国債は、大学を含む高等教育の財源拡充を目的とする国債を発行するというものである。いわば子ども世代全体が成人後に自らの税金で返済する教育ローンであり、その社会的収益率が市場利子率を上回る場合、理論的には「教育国債」が正当化できるかもしれない。
しかしながら、現在の財政状況では、教育予算を含む経常的経費を税収で賄えず、財政赤字が恒常化している。すなわち赤字国債の発行は恒常化しており、その一部は既に「教育国債」化しているといっても過言ではなく、「教育」を錦の御旗に、これ以上の国債増発をどの程度許容することができるであろうか。
そこで、一部の有識者が注目しているのが、オーストラリアで新たに実施している「高等教育拠出金制度」(HECS)等であり、政府も「人づくり革命」での検討を明らかにしている。HECSとは、大学卒業後の「出世払い」制度といっても過言でなく、在学中の授業料は無料とし、卒業後に所得に応じて課税方式で授業料を返還する仕組みで、約8割の学生が給付を受けている。具体的には、卒業後の課税所得が約500万円(53345豪ドル)を超えた場合、課税所得に応じて4%~8%の返還率で返還を行い、返還総額が貸与総額に達した時点で返還終了となる。
このHECSは「所得連動型奨学金」(Income Contingent Loan、通称「ICL」)の一種であり、日本でも、海外の仕組みを参考に、(独)学生支援機構がICL型の奨学金を導入している。例えば、(独)学生支援機構が2017年4月から新たに導入した「所得連動返還型奨学金制度」は、最低返済月額2000円が存在するが、所得に応じて9%の返還率で返還し、年収300万円以下の場合は返還を基本的に猶予するものであり、オーストラリアの仕組みと概ね同じで、異なるのは給付率や給付水準等の違いである。
他方、東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策研究センター(2007)「高校生の進路追跡調査第1次報告書」等によると、年収が1000万円超の世帯における4年制大学進学率は62.4%である一方、年収が600万円~800万円の世帯では49.4%に低下し、年収が400万円以下の世代では31.4%にまで低下してしまう。日本国憲法は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」(第26条第1項)と定めており、低所得世帯の子どもで4年制大学に進学したいと思っているにもかかわらず、家庭環境で進学できない実態があるとするならば問題であり、どのような国民も、高等教育を受けることができる機会均等を図ることは極めて重要である。
この問題が発生する主な理由は、いわゆる「流動性制約」に家計が直面してしまうためである。一般的に、大卒と高卒では生涯賃金(平均)で5000万円以上も異なると言われており、4年制大学に進学できれば、大学4年間の授業料の10倍以上の私的な限界便益を得ることができる。このため、大学4年間の授業料や生活費をローンで一時的に借りることができれば、十分な見返りを得ることができ、卒業後の収入でローンの返済もできるはずである。しかしながら、現実には、家計が資金を借り入れようとする場合、貯蓄をするときの利子率よりも高い利子率に直面せざるを得ないことや、一般的に借り入れは貯蓄よりも難しいため、まったく借り入れができないこともある。このような資金繰り制約が存在する状況を「流動性制約」というが、教育分野でこの問題解決に重要な政策手段となるのは「奨学金」であり、(独)学生支援機構の「所得連動返還型奨学金制度」の拡充で積極的に対応するのが望ましい。
もっとも、「所得連動返還型奨学金」(ICL)は、低所得者が多い場合には未返還に伴う損失が発生する可能性があり、その拡充には一定の留意が必要かもしれない。
というのは、オーストラリアのICL(=HECS)は、2013年6月時点で約7000億円(71億豪ドル)の損失が累積しており、2013-2014年の新規貸与者についても、約1000億円(11億豪ドル)の損失が追加で発生する旨の推計があるためである。また、イギリスのICLでは、2012年度末では累計で約3兆円(160~180億ポンド)の損失が存在し、2042年度末には累計で約16兆円(700~800億ポンド)の損失が発生する旨の試算もある。
いずれにせよ、人種差別の撤廃に尽力し、南アフリカ初の黒人大統領となったネルソン・マンデラ氏は、「教育は最強の武器である。教育によって世界を変えることができる」と述べている。資源が少ない日本では人材こそが最大の資源であり、人づくり改革が重要であることは言うまでもないが、このような損失や財政の限界も念頭に、冷静な政策議論を期待したい。