
R-2024-002
2024年3月に日銀がマイナス金利を解除し、イールドカーブ・コントロールも概ね終了したが、円安圧力が再び顕在化している。一般的に、為替レートの決定メカニズムについては、購買力平価説や金利平価説などの諸理論が存在する。このうち、テレビや新聞の報道では、マイナス金利解除の円安の進行につき、金利平価説を利用した説明が多いように思われる。
最も主流の見方は、金利平価説の観点から、「マイナス金利を解除した日銀が追加利上げを急がない姿勢を示唆し、当面は日米金利差が縮まりにくいとの見立てから円売り圧力が続いた」(日本経済新聞社2024年3月20日付)である。この見方は間違っていないが、円安の進行は複合的な要因が絡むものであり、それ以外にも円安圧力が継続する理由がある可能性がある。この複合的な要因のうち、円安と財政との関係について筆者の見方を紹介したい。
この関係の説明には、齊藤(2023)の閉鎖経済モデルを小国開放経済に拡張した簡易なモデルを利用する必要がある。以下ではそのモデルの設定を含め、順番に説明しよう。できる限り簡易に説明するため、2期間のモデルで考える(なお、齊藤(2023)のモデルは実質だが、この場では名目・実質のどちらのケースでも議論が成立するため、特にその区別はしない)。
まず、政府部門の予算制約式だ。2期間のうちの1期目で、その期首時点の国債残高をD0、税収をT1、政府支出(国債の利払費を除く)をG1、金利をrとすると、1期末の国債残高D1は以下となる。
![]()
同様の計算で、政府の2期目の予算制約は以下となる。
![]()
この両式からを消去すると、以下のとおり、政府部門の通時的予算制約式を得る。
![]()
次に、代表的家計の予算制約式を考えよう。2期間のうちの1期目で、その期首時点に保有していた貯蓄(国債を除く)をS0、1期目の所得をY1、1期目の消費をC1とすると、1期目の貯蓄S1は以下となる。
![]()
この式の意味は、次のようなものである。まず、第1項と第2項は、代表的家計が1期目の期首に保有していた貯蓄(国債を除く)と国債から受け取る利子などの収益を表す。第3項は1期目の所得を表すが、この収益にこの所得を加えたものを原資として、消費や貯蓄などを行う。具体的には、まず税金(第4項)を支払い、政府部門が第1期に発行した国債を引き受け(第5項)、消費支出を行い(第3項)、残りを貯蓄(S1)する。
これが(4)式の解釈だが、同様の計算で、代表的家計における2期目の予算制約式は以下となる。
![]()
この式と(4)式からS1を消去すると、以下のとおり、代表的家計の生涯予算制約式(時的予算制約式)を得る。
![]()
この式の右辺は、代表的家計の生涯消費の原資となる「税負担後の生涯所得や資産」を表す。具体的には、右辺の第1項や第2項が1期目の期首に代表的家計が保有していた貯蓄や国債の利子などの収益、第3項が生涯所得、第4項が生涯で支払う税負担に相当する。この生涯所得などを原資として、代表的家計は生涯の消費支出などを行うが、それを表すのが(6)式の左辺の第1項である。第2項(![]() )や第3項(
)や第3項(![]() )は使い残しの貯蓄や、政府部門に貸しっぱなしの国債になる。
)は使い残しの貯蓄や、政府部門に貸しっぱなしの国債になる。
現実は一国に様々な家計が存在するが、代表的家計はその国の家計を一つに集約したものを意味する。経済が2期間で終了するとき、右辺の第2項がS2>0で、貯蓄を使い残すことは非効率である。仮にS2>0なら、この貯蓄を取り崩して消費をすることで、代表的家計の効用を上昇させることができるためである。つまり、S2=0が効率的となる。同様の理由で、右辺の第3項がD2>0となるのも非効率であり、D2=0が効率的となる。この「S2=0」や「D2=0」は「横断性条件」(transversality condition)と呼ばれるもので、この条件を課すと、(3)式と(6)式は以下となる。
<政府部門の通時的予算制約式>
![]()
<代表的家計の生涯予算制約式>
![]()
このうち、(7)式は「国債残高=現在から将来の税収合計-現在から将来の政府支出合計」(※1)を表す。いま、「現在から将来の政府支出合計」が一定の下、財政政策により、国債残高が1単位増加すると、※1を満たすには、※1で「現在から将来の税収合計」が必ず1単位増加する必要があることが理解できるだろうか。
このとき、(8)式では何が起こるのか。まず、(8)式は「生涯消費の合計=貯蓄残高+現在から将来の所得合計+国債残高―現在から将来の税収合計」を表す。「現在から将来の所得合計」は人的資産からの生涯所得に相当するため、「貯蓄残高+現在から将来の所得合計」を「生涯所得を含む資産残高」と記載すると、「生涯消費の合計=生涯所得を含む資産残高+国債残高―現在から将来の税収合計」(※2)となる。
この※2で、国債残高が1単位増加しても、※1を満たすために「現在から将来の税収合計」が必ず1単位増加すると、※2の右辺に存在する「国債残高―現在から将来の税収合計」は増減せず変化すらしない。これは、財政政策で国債残高が増加しても、それは現在や将来の税収増(=増税)で償還されるから、家計の生涯予算制約式に何も影響を及ぼさないことを意味する。この議論は「公債の中立命題」と呼ばれるものだが、※2から読み取れるように、代表的家計の生涯消費の合計などが変化しないことを意味する。なお、これは、国債残高が1単位増加して、それを家計が保有しても、国債が家計にとって純資産とはならないことを示唆するもので、Barro (1974)の議論にも繋がる。
では、S2の横断性条件は課すものの、政府の予算制約上のD2に関する横断性条件を緩めると何が起こるのか。この議論が齊藤(2023)のコアだが、このとき、(3)式と(6)式は以下となる。
<政府部門の通時的予算制約式>
![]()
<代表的家計の生涯予算制約式>
![]()
このうち、(9)式は「国債残高=現在から将来の税収合計-現在から将来の政府支出合計+借りっぱなしの国債」(※3)を表す。※1との違いは、右辺の最終項に「借りっぱなしの国債」が加わっていることである。この項の存在により、国債残高が1単位増加したとき、増税をせず(=「現在から将来の税収合計」を増減せず)とも、※3の等号は成立させられる。例えば、「現在から将来の政府支出合計」を2単位増やし、「借りっぱなしの国債」を3単位増やせばよい。このとき、「国債残高(1単位増)=-現在から将来の政府支出合計(2単位増)+借りっぱなしの国債(3単位増)」となり、※3の右辺と左辺の増減は一致する。
では、(10)式では何が起こるのか。まず、(10)式は「生涯消費の合計+貸しっぱなしの国債=生涯所得を含む資産残高+国債残高―現在から将来の税収合計」(※4)を表す。※2との違いは、左辺の第2項に「借りっぱなしの国債」が加わっていることである。また、※4の「生涯所得を含む資産残高」(貯蓄残高+現在から将来の所得合計)のうちの「貯蓄残高」は現在の貯蓄であり、「現在から将来の所得合計」も供給サイドの生産関数から決まる外生的な変数のため、閉鎖経済モデルの下で、内生的に決まる変数は「生涯消費の合計」しかない。このような状況で、国債残高が1単位増加したとき、政府の予算制約を満たすよう、「現在から将来の政府支出合計」が2単位増加、「借りっぱなしの国債」が3単位増加すると、※4の等号を満たすためには、「生涯消費の合計」が2単位減少するしかない。これは、(公債の中立命題が成立する)※1や※2の議論と異なり、国債残高の累増の帰結として、家計の生涯消費が犠牲となる現象が引き起こされることを意味する。
以上が、齊藤(2023)の概要の一部だが、この閉鎖経済モデルを小国開放経済モデルに修正すると、どうなるだろうか。ここから先のモデルや議論は筆者のオリジナルなものだが、最も簡単な修正は、※4の「生涯所得を含む資産残高」を国内資産残高と対外資産残高に区分することである。対外資産残高はドル建てなどの資産であるため、為替レートを用いて、通貨の単位を円に統一すると、「生涯所得を含む資産残高=国内資産残高+為替レート×対外資産残高」と表せるから、※4は以下の※5に修正できる。
|
<代表的家計の生涯予算制約式> 生涯消費の合計+貸しっぱなしの国債=国内資産残高+為替レート×対外資産残高+国債残高―現在から将来の税収合計 ※5 |
上記の※5では、※4と異なり、内生的に決まる変数が2つ存在する。一つは、家計の「生涯消費の合計」であり、もう一つは「為替レート」である。このため、国債残高が1単位増加したとき、政府の予算制約を満たすよう、「現在から将来の政府支出合計」が2単位増加、「借りっぱなしの国債」が3単位増加しても、「生涯消費の合計」が必ず2単位減少するとは限らない。例えば、「生涯消費の合計」が1単位減少し、「為替レート×対外資産」が1単位増加すれば、※5の右辺と左辺の増減は一致する。
では、「為替レート×対外資産残高」の1単位増加とは何を意味するのか。対外資産残高は外生的に決まっている変数のため、「為替レート」の値が上昇するしかなく、それは円安が進むことを意味する。上記の事例では、国債残高の累増が、家計の生涯消費の一部を犠牲にしながら、円安を引き起こすシナリオを示唆する。「物価水準の財政理論」(Fiscal Theory of the Price Level)という理論が存在するが、この議論はその為替レート版のようなメカニズムかもしれない。為替の動向は複合的な要因が絡むもので断定は難しいが、理論的にはこのようなメカニズムが働いている可能性もあると思われる。
<参考文献>
・齊藤誠(2023)『財政規律とマクロ経済』名古屋大学出版会
・Robert J. Barro (1974) “Are Government Bonds Net Wealth?” Journal of Political Economy Vol. 82, No. 6, pp. 1095-1117














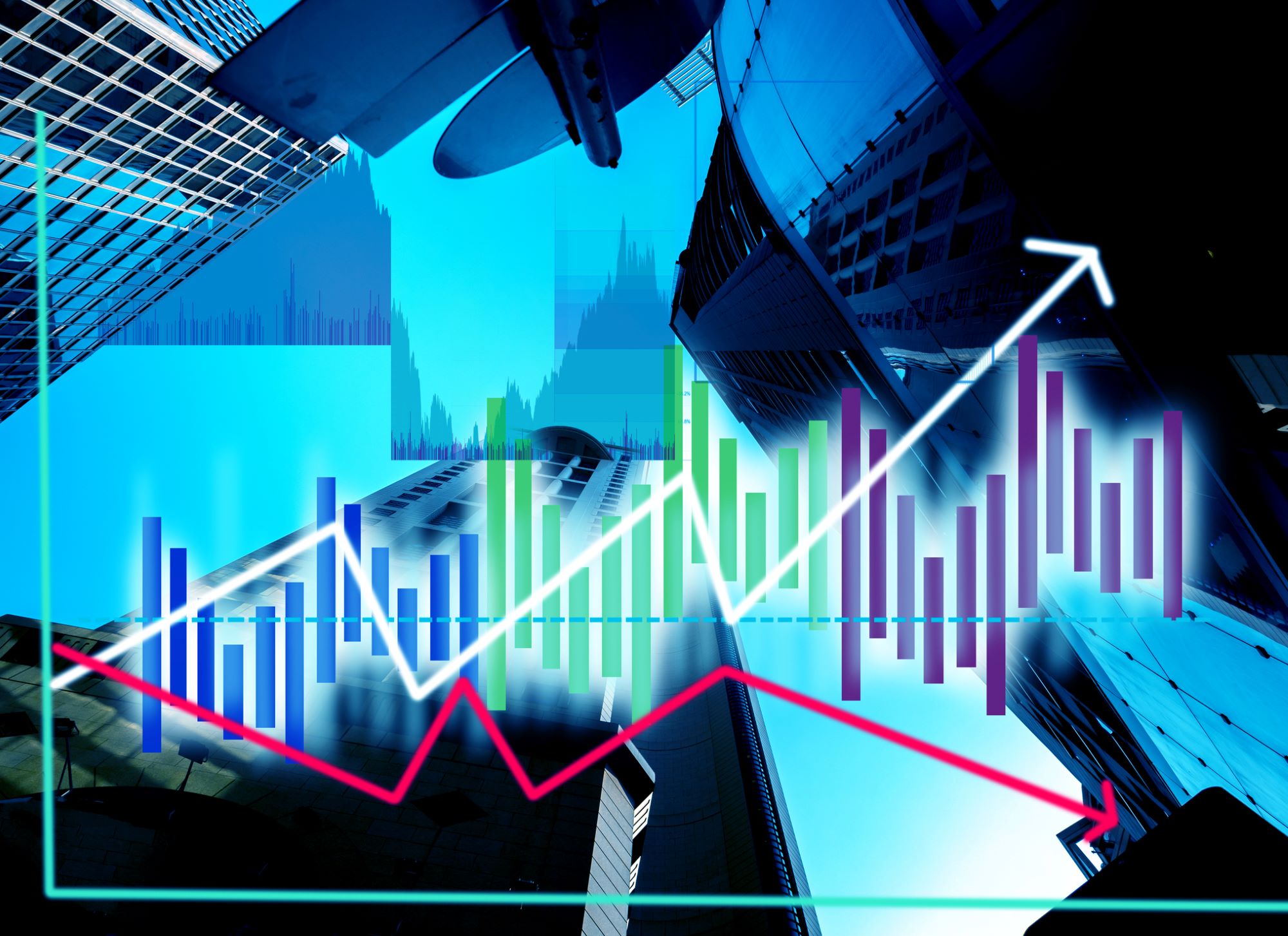






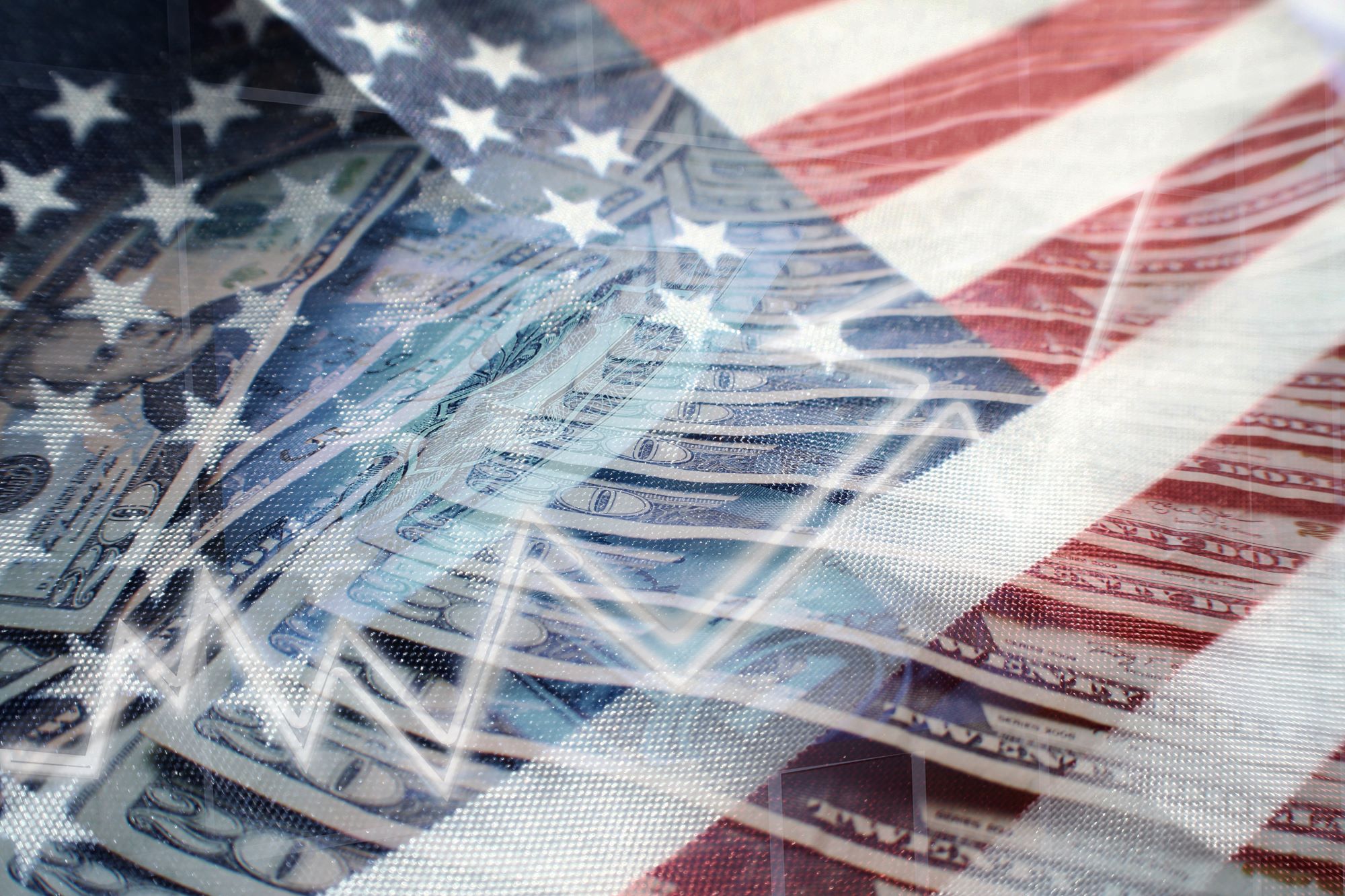





































































































































































































































































_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)





















_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)


































































