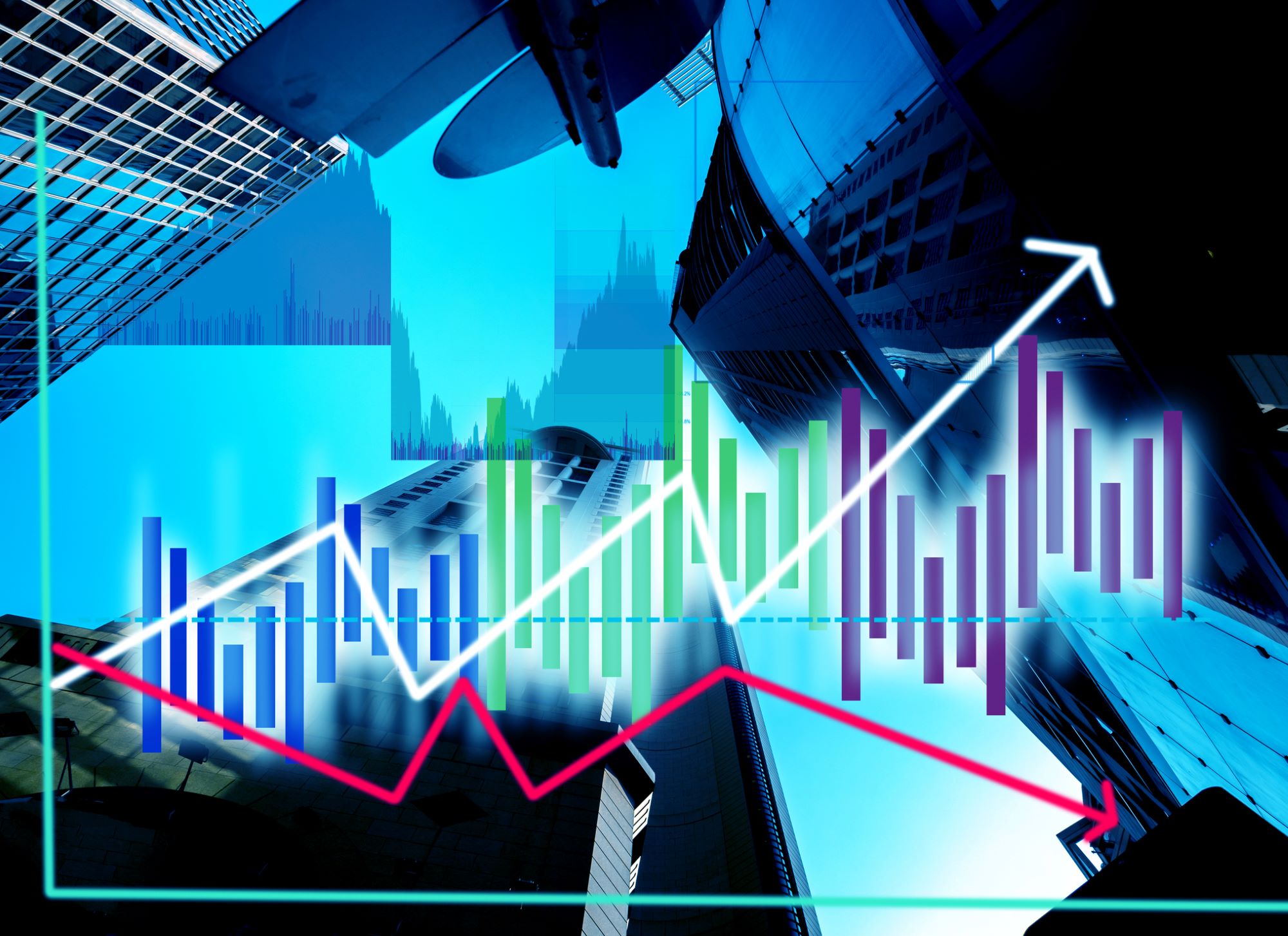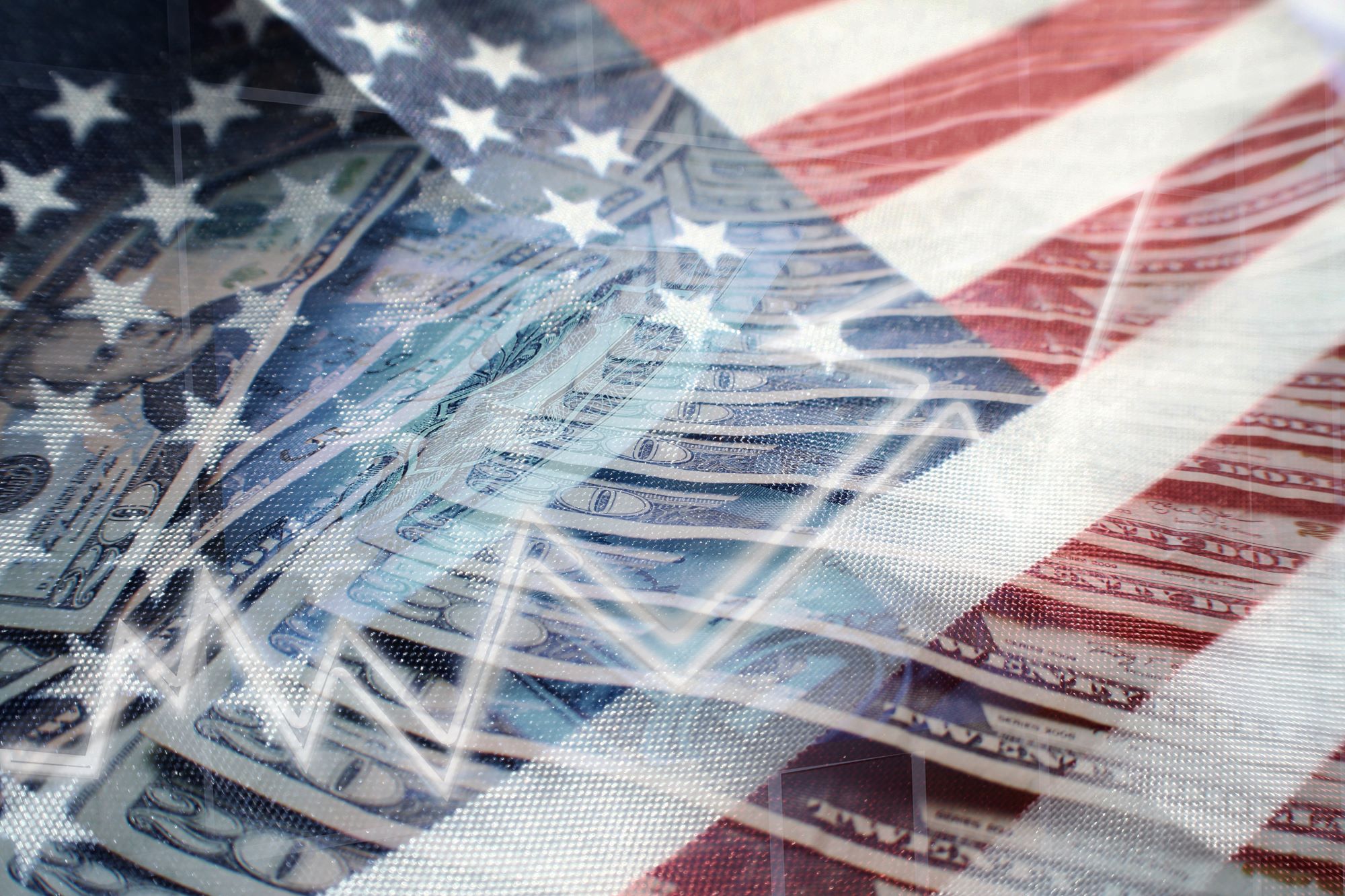R-2024-018
先般(2024年7月3日)、厚生労働省(厚労省)は、公的年金財政の健康診断に相当する「2024年財政検証」の結果を公表した。財政検証は基本的に5年ごとに行っており、経済成長率を含め、シナリオを決める全要素生産性の伸びや賃金上昇率などの前提を置き、年金財政の健康診断を行うものだ。前回の検証は2019年であったが、デフレ脱却前の検証であり、今回はデフレ経済から徐々にインフレ経済に転換し、インフレ率(消費者物価指数の伸び)が継続的に2%を超えるなか、今後の年金がどうなるか、国民やマスコミの関心も高まっていた。この点を含め、本稿では2024年財政検証の内容につき、ポイントを絞って筆者の見方をいくつか紹介したい。
まず一つは、基本的な検証シナリオの数や、前提の妥当性だが、今回の検証では4つのケースを試算している。具体的には、「高成長実現ケース」、「成長型経済移行・継続ケース」、「過去30年投影ケース」、「1人当たりゼロ成長ケース」の4つだ。前回は6ケースだったため、シナリオ(情報量)の数が2つ減少したことを意味する。
では、なぜシナリオの数が2つ減少したのか。この理由は定かではないが、今回の4ケースのうち、3ケース(「高成長実現ケース」「成長型経済移行・継続ケース」「過去30年投影ケース」)は、内閣府が経済財政諮問会議で4月上旬に公表した財政の長期推計(中長期的に持続可能な経済社会の検討に向けて②)の3つのシナリオに沿うように、試算を行っているものと思われる。他方、残りの1ケース(「1人当たりゼロ成長ケース」)は、内閣府の長期推計のシナリオよりも、さらに低い成長率になった場合のシナリオを分析するため、今回の財政検証で追加したものと思われる。
では、上記の4ケースの妥当性はどうか。まず、「高成長実現ケース」が想定する長期的な実質経済成長率(実質GDP成長率)の平均は1.6%、物価上昇率は2%である。GDPデフレーターと消費者物価指数の動きは輸出入の影響などもあり若干異なるが、「名目GDP成長率=実質GDP成長率+GDPデフレーターの伸び」が成立し、GDPデフレーターの伸びを物価上昇率で代用すると、名目GDP成長率の平均は約3.6%となる。
このような考え方に基づき、残りの3ケースの名目GDP成長率を計算すると、「成長型経済移行・継続ケース」は約3.1%(実質経済成長率1.1%)、「過去30年投影ケース」は約0.7%(実質経済成長率▲0.1%)、「1人当たりゼロ成長ケース」は約▲0.3%(実質経済成長率▲0.7%)であることが確認できる。
他方、1995年度から2023年度まで、名目GDP成長率の平均は概ね0.5%であるから、
上記の4ケースのうち、名目GDP成長率が3%を超える「高成長実現ケース」や「成長型経済移行・継続ケース」はやや楽観的であり、保守的に検証するなら、「過去30年投影ケース」で評価するのが妥当と思われる。
では次に、「過去30年投影ケース」で評価したとき、今後の年金の給付水準はどう変化するのか。この変化を確認するため、①「対現役の賃金」(所得代替率)と、②「対物価」の2つの指標で評価してみよう。
まず、「対現役の賃金」だが、この指標は「モデル世帯」の所得代替率の変化から読み取れる。モデル世帯は片働きの専業主婦世帯で、1階の基礎年金部分と2階の報酬比例部分の2つを受け取る高齢世帯を想定しており、所得代替率とはこの世帯が老後に受け取る年金が現役の男性の手取り賃金に対して何パーセントに相当するかを示す値をいう。
つまり、モデル世帯の年金が対現役の賃金で何パーセント分に相当するかを表すが、 2024年度の所得代替率は、基礎年金部分が36.2%、報酬比例部分が25%で、この両方の合計が61.2%になっている。
それが「過去30年投影ケース」では、2057年度以降で所得代替率が50.4%になり、その内訳は、基礎年金部分が25.5%、報酬比例部分が24.9%となっている。これは、1階部分(基礎年金部分)の給付が約29.5%カット(=1-25.5÷36.2)される一方、2階部分(報酬比例部分)の給付が約0.4%カット(1-24.9÷25)されることを意味する。
前回(2019年財政検証)の似たシナリオのケースⅢでは、1階部分(基礎年金部分)のカット率が約28%であったため、基礎年金の刈り込みが1.5%ポイント、より深くなったことを意味し、今後の低年金問題が一層深刻化する可能性を示唆する。
なお、今回の財政検証では、前回と同様、対物価の年金額も掲載している。「対物価」とは、将来の年金額を物価上昇率で2024年の値に割り戻したものをいい、いわゆる年金の実質額を表す。この値は、過去30年投影ケースでは、マクロ経済スライドの調整が終了する2057年において、対物価の基礎年金が月額5.35万円に減少している。2024年の基礎年金が月額6.7万円なので、これは約2割の給付カット(刈り込み)に相当する。前回(2019年財政検証)の似たシナリオのケースⅢでは、2019年で6.5万円であった基礎年金が2046年では6.75万円(対物価)に増加していたので、かなりの違いが発生している。
以上のような問題や懸念があるが、もう一つの重要なポイントは、年金純債務(暗黙の債務)の変化である。年金純債務とは、東京財団政策研究所の論考「膨張する年金純債務-2019年・財政検証から読めるもの-」でも解説したとおり、「完全積立方式であれば存在していた積立金と、実際の積立金との差額」として定義され、この債務が無限に大きくなるのを防ぐため、現役世代や将来世代は、年金の給付調整などの形で一定の追加的な負担を行う必要があるものだ。
2004年の財政再計算のとき、暗黙の債務は690兆円であったが、2009年の財政検証では800兆円、2014年では980兆円、2019年では1110兆円に膨らみ、前回の検証時点では、2004年から2019年という約15年間で、暗黙の債務は1.6倍にも膨張していた。
今回の検証において、筆者が厚労省の公式資料から計算すると、「過去30年投影ケース」の暗黙の債務は980兆円に縮小していた。筆者が知る限り、年金純債務が縮小したのは今回が初めてに思われる。
(表)年金純債務の推移
| 暗黙の債務(国民年金+厚生年金) | |
| 2004年財政再計算 |
690兆円 |
| 2009年財政検証(基本ケース) | 800兆円 |
| 2014年財政検証(ケースE) | 980兆円 |
| 2019年財政検証(ケースⅢ) | 1110兆円 |
| 2024年財政検証(過去30年投影ケース) | 980兆円 |
(出所)厚労省「財政検証」資料等から作成
この主な理由は2つ存在する。まず一つは、マクロ経済スライドの発動だ。マクロ経済スライドは、2004年の年金改革で導入されたが、物価と賃金が下落するデフレ下では発動できないルールになっており、2014年度までは一度も発動できず、その後も、2015年度・2019年度の2回しか発動できなかった。しかしながら、最近は2020年度・2023年度・2024年度と3回も発動できており、それが年金純債務の縮減に寄与した可能性が高い。
また、前回の検証のケースⅢで210兆円しかなかった積立金が今回の検証では300兆円に増えたことも、年金純債務の縮減に寄与している。テレビや新聞報道では、積立金の効果を過大評価する傾向があるが、過去30年投影ケースおいて、完全積立方式なら保有している積立金(過去期間に係る分)は1280兆円必要だが、実際の積立金は300兆円しか存在しない。
積立金の増加などで、年金純債務が前回の検証より若干改善したものの、その影響は限られており、暗黙の債務(980兆円)は2004年時点の690兆円よりも1.4倍に膨張しているため、その膨張を含めて、現役世代や将来世代が追加的に負担することになる現実も忘れてはいけない。
最後に、2024年財政検証が前提とする出生率(合計特殊出生率:TFR)の想定にも言及しておこう。今回の検証で、「高成長実現ケース」「成長型経済移行・継続ケース」「過去30年投影ケース」「1人当たりゼロ成長ケース」が試算の前提とする出生率は、2020年で1.33であったTFRが、2070年に1.36まで上昇していくシナリオを想定している。
しかしながら、先般(2024年6月上旬)、厚労省は、2023年の人口動態統計(概数)の公表を行い、2023年における日本のTFRが過去最低の1.20に低下する可能性を明らかにしている。
財政検証では、出生率が低位のケースの試算も公表しており、2020年で1.33であったTFRが、2070年に1.13まで緩やかに低下していくシナリオの所得代替率も確認してみよう。このシナリオの場合、「過去30年投影ケース」では、2070年度以降で所得代替率が46.8%になり、その内訳は、基礎年金部分が22.9%、報酬比例部分が23.9%となっている。
2024年度の所得代替率61.2%の内訳は、基礎年金部分が36.2%、報酬比例部分が25%であるから、これは、1階部分(基礎年金部分)の給付が約36.7%カット(=1-22.9÷36.2)される一方、2階部分(報酬比例部分)の給付が約4.4%カット(1-23.9÷25)されることを意味する。この事実は、長期的にみて出生率が年金の給付水準に及ぼす影響は大きいということも示唆する。
なお、余談だが、2023年における日本のTFRが過去最低の1.20に低下したとの統計は、東京都のTFRが初めて1を切り、0.99になる可能性を明らかにした。この話は大々的にニュースでも取り上げられ、テレビ等で、「日本のTFRが低いのは、出生率が低い東京に出産可能な女性が集まるためである」というコメントをする識者もいたが、これは誤解である。
確かに、冒頭の統計(2023年)では、47都道府県のうちTFRが最高位なのは沖縄の1.60、最下位なのは東京の0.99で、2020年の人口動態統計(確報)でも、若干数値は異なるものの、東京は最下位の47位だ。
だが、別の指標(データ)で出生率をみると、異なる風景が広がっている。例えば、国勢調査(2020年)のデータを用いて、都道府県別などの平均出生率(出産可能な15歳-49歳の女性人口1000人当たりの出生数)を計算すると、この値が最高位なのは沖縄の48.9、第2位は宮崎の40.7だが、東京の平均出生率も31.5で、最下位でなく42位だ。平均出生率の計算では未婚の女性も含むが、東京の前後では、40位の岩手(32.4)、41位の青森(32.2)、43位の奈良(31.4)、宮城(31.1)、京都(31)、北海道(30.8)が並び、最下位は秋田(29.3)となる。しかも驚くべきことに、東京都心3区(千代田区・港区・中央区)の平均出生率は41.7で、既述の47都道府県の値と比較すると、東京都心3区は沖縄に次ぐ2位になる。この都心3区のうち中央区の値は45.4だ。
人口戦略会議や政府では、地域別TFRや東京ブラックホールという言葉を使い、TFRが低い東京の一極集中の是正を掲げるケースも多いが、平均出生率では都心3区は沖縄県の次に高い。EBPM(エビデンスに基づく政策立案)が流行っているが、データの取り扱いに留意しながら、適切な政策を打つ必要があろう。