
R-2024-130
2023年7月から進めてきた研究プログラム「財政危機時の緊急対応プラン」(以下、財政危機PG)では、財政危機の予兆段階(長期金利4〜5%程度を想定)、初期段階(同7〜10%を想定)における政府・日銀の対応策について検討してきた。研究成果の概要は『政策研究 財政危機時の緊急対応プラン2025』(加藤他 2025)として発表した。
研究の対象としたのはあくまで財政危機の予兆が見られたときの事後対応策であり、いわば「プランB」である。日本社会にとってより望ましいのは、持続可能な財政社会保障を確立し財政危機を未然に回避する「プランA」の策定とその実施だが、最近の政治状況から見て、効果的なプランAの実現は難しい。今まで多くのプランAが財政経済学者やシンクタンクなどから出されてきたが、大幅な消費増税など強力な財政緊縮策を入れ込んだものが大半のため、政治的にほぼ黙殺されてきた。私たちが財政危機PGの検討を始めた動機の一つも、この政治状況にある。
以下では、プランBに特化した財政危機PGを終えるにあたり、今後、プランAが実際に政治的に受け入れられるために有益と考えられる方向性につき、いくつか例示したい。
1.超党派合意の模索
日本政治では、各政党や議員が財政拡張を競い合う状況が続いており、これがプランAが政治的に黙殺されている大きな要因となっている。昨年の自民党総裁選や衆院総選挙を見ても、財政規律の必要性を正面から取り上げた政党や候補者は見当たらなかった。さらに、衆院総選挙後によって成立した少数与党体制下においては、予算案・法案への拒否権という強大な権力を握った主要野党(立憲民主党、日本維新の会、国民民主党)が、互いに競い合うように財政拡張的な政策を提案する状況が見られている。
こうした政治状況において、財政拡張競争が過度にエスカレートすることを防ぐため有益と考えられるのは、財政目標などの方向性について超党派合意を形成することだ。
財政拡張競争が進む中で1つの政党や政治家だけが財政規律を打ち出しても、財政拡張を唱え続ける他の政党や議員に選挙で打ち負かされる可能性が高い(と少なくとも多くの議員は認識している)。最近はSNSでも激しく批判される。よって与野党間でいったん休戦協定を結ばない限り、なかなか財政拡張競争は止まらない。
与野党間で休戦協定を結んだ上で、2.で詳しく述べる第三者を交えた検討を共同して行い、財政社会保障の見通しを共有することができれば、対等な土俵の上での有益な政策論争の展開が期待できる。共有された財政制約の下で、各党が、どの分野に重点投資しどの分野を削るかの知恵比べをすることになるからだ。つまり、財政社会保障の中長期見通しを共有した上での政策論争は、必然的に財源論を組み合わせたものとなる。
こうした財政問題に関する与野党間の「休戦協定」は、決して絵空事ではない。米国議会においては、財政目標などについての超党派合意形成の試みが、レーガン政権下の有名なグラム・ラドマン・ホリングス法をはじめ過去に何度も実施されてきた。日本でも2012年の民主党政権下で成立した「社会保障と税の一体改革に関する三党合意」は、その後の自民党政権下での2度にわたる消費税増税につながった。
少数与党体制下の国会で与野党間の政策論争が活発化し、各種調整が行われることになったこと自体は、国民の代表者が集う国会の本来の機能回復であり、望ましいものだ。今後は、与野党間の合意形成のメカニズムも醸成されていくであろう。現在は7月の参議院選挙に向けた「戦闘モード」にあるが、選挙後などに与野党がいったん休戦し、日本の10年後、20年後まで見据えた財政社会保障のあり方につき一定の合意をしていくことができれば、プランAは実現に向け一歩前に進むはずだ。
2.国民からの信頼確保
ある意味当然のことではあるが、国民の政府に対する信頼は、国民の納税意欲と強く連関していることが知られている。また、各国における国民の政府への信頼は、対GDP比公的債務残高と負に連関している(加藤・小林 2017)。
しかし、日本は他の先進民主主義国家に比べて、国民の政府への信頼が非常に低い傾向にある。OECDが2年ごとに加盟国に対して行っているアンケート調査の最新版では、政府を信頼すると答えた日本国民の割合は最下位(20カ国中20位)となっている(OECD 2021)[1]。また、OECDが別方法で行った2021年調査においても、政府への信頼において日本は37カ国中32位である。最近の「財務省解体デモ」などを見る限り、政府内でも財政当局に対する国民の反発は特に強い印象を受ける。
日本の財政状況は非常に厳しく、今後さらに少子高齢化も進むため、プランAにおいては強力な財政再建策を入れ込むことがおそらく必要になる。現在のように、国民の政府に対する信頼が非常に低い状況では、その実現は極めて困難となるはずだ。
ただ、政府への信頼は時々の政治リーダーによって大きく変動することが、過去に観察されてきた。最近の日本では、小泉政権や第二次安倍政権の際には、国民の政府への信頼の数値が一時的に大きく跳ね上がった。政治リーダーが、20年後、50年後の日本の姿を国民にわかりやすく見せ、そのための応分の負担を国民に直接語りかけていくといったことが重要となる。
また、たとえ政府に対する国民の信頼が低くても、プランAを策定する機関に国民の信頼が集まれば、プランAの実現の可能性も出てくる。たとえば1980年代に土光敏夫氏を会長に据えて行財政改革を進めた第2次臨時行政調査会(土光臨調)は、国民の高い支持を得つつ各種改革を進めた。
東京財団(2013など)では10年以上前から、独立財政機関を国会に設置する提言を行ってきた。1月には立憲民主党の野田代表が、衆議院の代表質問においてその設置を求めた。ただ、今すぐ独立財政機関を設置したとしても、専門家を中心とした機関が国民からの深い信頼を得るには相当な時間がかかる。現状で国民から強い信頼を得てプランAを策定・実現させていくためには、政治家、官僚、専門家といった「いつもの」メンバーだけでなく、より幅広い層の国民やSNS上のインフルエンサーなどが参加する国民会議的機関の設置なども検討されるべきであろう。
3.財政経済政策についての国民の受容度の考慮
過去のプランAの多くは、財政経済学者を中心によって作成されてきたため、財政社会保障の持続性の確保や、各種措置の効率性、公平性といった視点を重視してきた。内容的に優れたものは多い。
ただ、消費税の大幅増税などを含むそれらのプランAは政治的に黙殺されてきており、現状、その政治的な実現可能性は極めて低くなっている。日本が財政民主主義を採る以上、今後のプランAの策定にあたっては、経済財政的な実現可能性だけでなく、政治的実現可能性も考慮していく必要があると考える。
東京財団が国民全般を対象に行った財政社会保障についてのアンケートの調査結果では、国民の多くは日本の今の財政状況について深く懸念しており、将来的に厳しい財政再建が必要となると考えている(加藤 2023)。この点については、ほぼ同時期に行った経済学者へのアンケート調査結果と大きな相違はない。ただ、財政再建の手段として経済学者の多くが消費増税を第一に挙げるのに対し、国民の消費増税に対する反発は非常に厳しいことも判明した。
専門家が世論に過度に迎合するのは適切ではないが、経済財政だけでなく政治的にも実現可能なプランAを考えていく上では、どのような経済財政措置が国民にどの程度受容されるのか、どのようなロジックによって国民の受容度は高まるのかといった点を調査し、プランに反映させていくといった視点も今後は必要になろう。他方で、2.で述べたような政治のリーダーシップを通じ、世論に従うのではなく世論を説得し動かすといった政治の動きも非常に重要となる。
参考文献
加藤創太 2023.『財政問題について経済学者と国民の意識はどう乖離するのか「経済学者及び国民全般を対象とした経済・財政についてのアンケート調査」の紹介』東京財団政策研究所 Review.
加藤創太・小黒一正・愛宕伸康・小林庸平・対木さおり・馬場康郎 2025.『政策研究 財政危機時の緊急対応プラン2025』東京財団政策研究所。
加藤創太・小林慶一郎 2017.『財政と民主主義:ポピュリズムは債務危機への道か』日本経済新聞出版社。
OECD 2021. Government at a Glance. 2021. OECD publishing.
東京財団 2013.『政策提言 財政危機時の政府の対応プラン』東京財団。
東京財団 2013.『政策提言 独立推計機関を国会に』東京財団。
[1] 2021年調査結果。2023年にも同じ調査は実施されているが、日本は含まれていない。

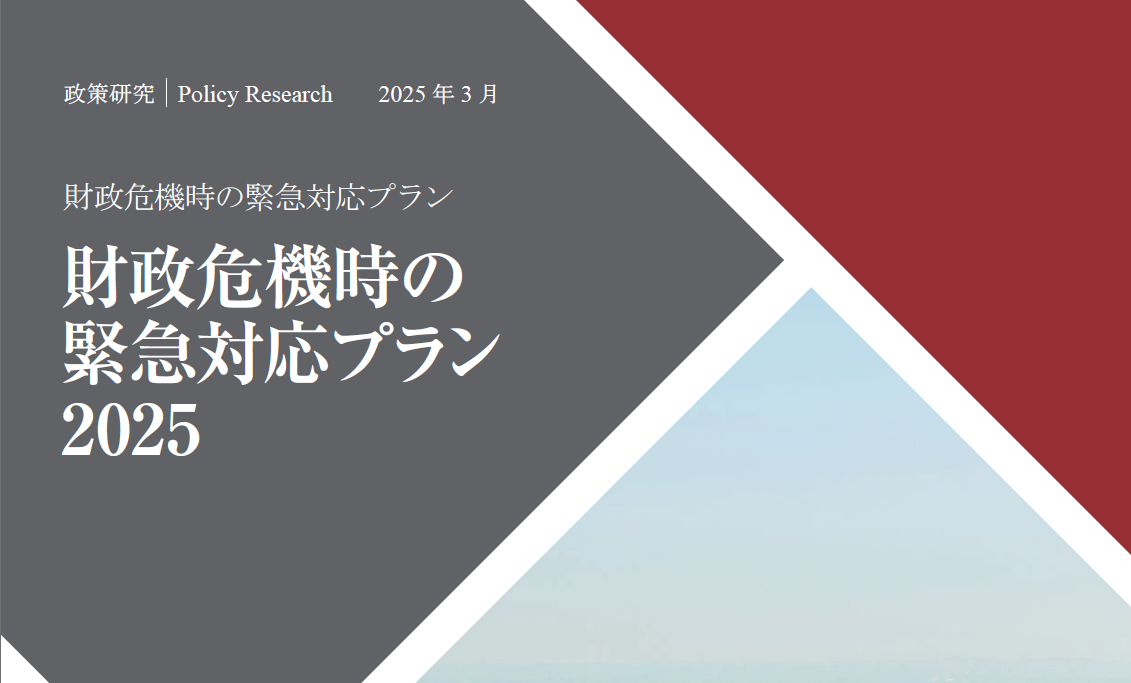














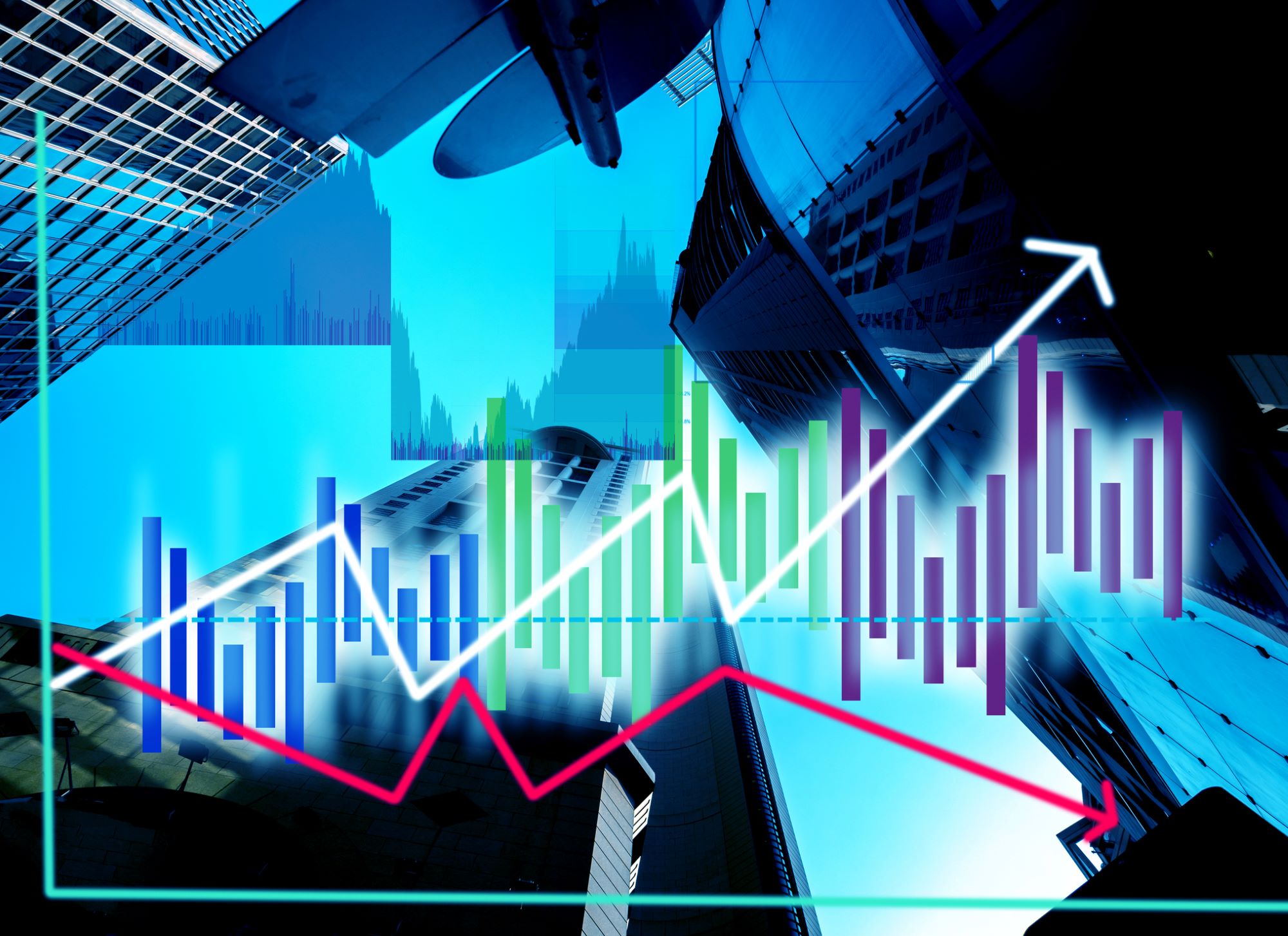











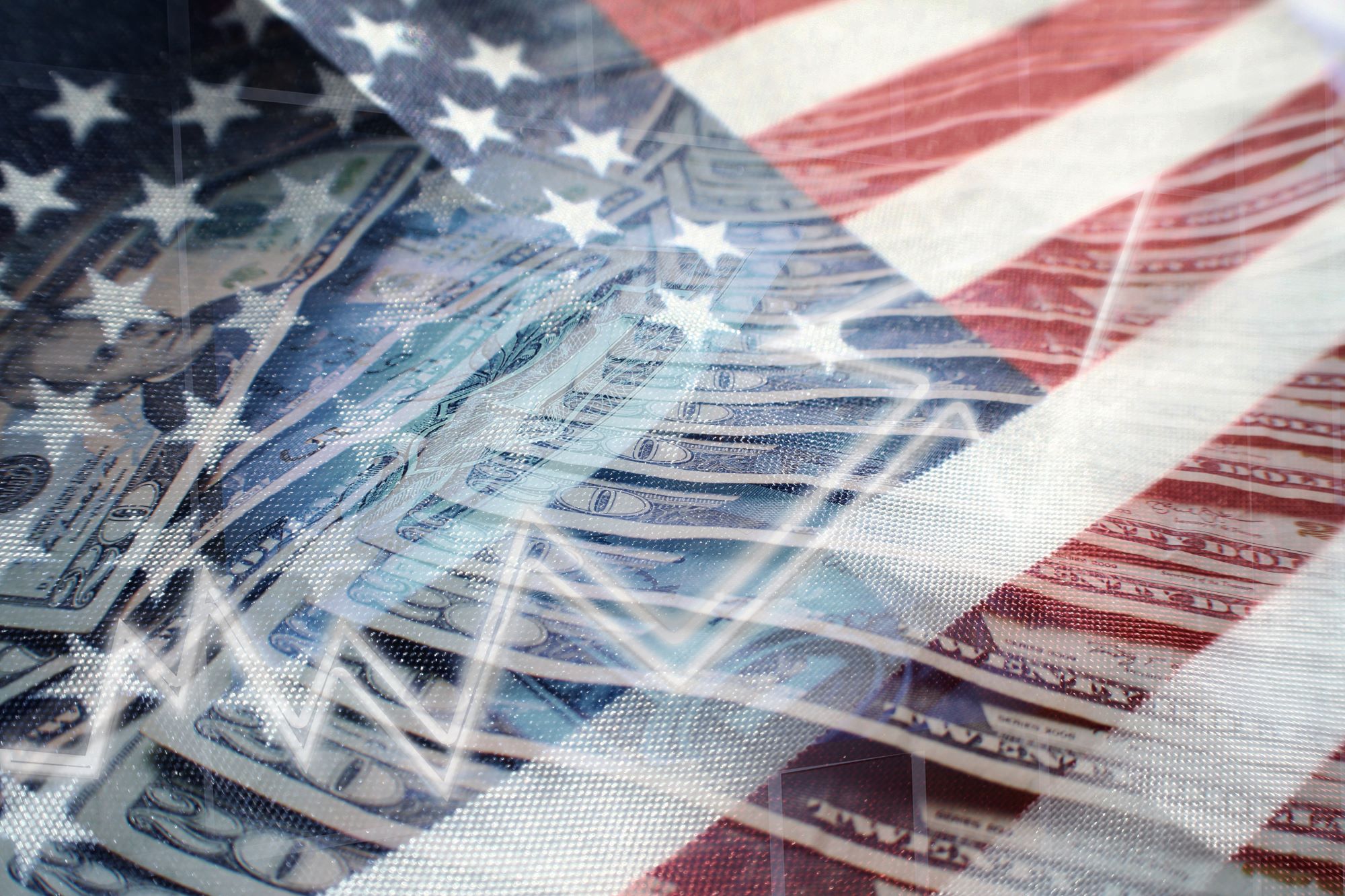




















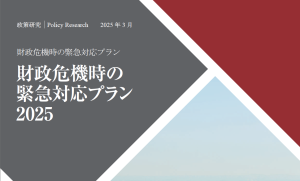




































































































































































































































































_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)





















_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)


































































