
R-2023-055
「未来の水ビジョン」懇話会では、日本の農村風景、環境に配慮した農業を題材に議論を行う。(2023年7月1日 東京財団政策研究所にて)
| Keynote Speech(概要) 1.良好な農村風景とは何か? 2.日本における農業の変化 3.EUの農業政策と日本の現在 さらなる議論 |
Keynote Speech(概要)
真田純子/東京工業大学 環境・社会理工学院 土木・環境工学系

1.良好な農村風景とは何か?
「良好な農村風景」の定義から考えていきたい。2003年、農林水産省が「水とみどりの『美の里』プラン21」を策定し、2005年の景観法制定につながり、それまで都市部中心だった景観行政に農村部も含まれるようになった。だが景観法では、「(自治体が)景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針を定める」(第8条3)とされてはいるものの、「良好な景観」の定義は明らかにされていない。制定時には「主観的な美しさを決めるのは困難であり、それぞれの地域で多様な主体の参画により、透明な手続きの中で決めていくしかない」という議論があった。
次に文化財保護法(2004年改正)における「重要文化的景観」とは、「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国⺠の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」(文化財保護法第二条第1項第五号)とされる。「重要文化的景観」は、世界遺産の「文化的景観」という概念を受けて創設された。世界遺産の「文化的景観」では「持続可能な土地利用に関する技術、伝統的な生活様式が地域の生物多様性を支える」と強調されているが、日本の「重要文化的景観」は、文化庁の「文化的景観」を見る限り、生業と環境の結びつきに関心を示すに止まっている。
日本の景観法では「人が主観的にどう思うか」で良好な農村風景か否かが決まる。「水とみどりの『美の里』プラン21」と「重要文化的景観」は、環境と生業の結びつきに着目しているが、2つは景観法で管理される。つまり、日本における「良好な農村風景」は、人の意識に左右され、理念と運用に差が出る可能性がある。
海外に目を移すと、イタリアは「農村発展のための国家戦略」策定時に「風景ワーキンググループ」をつくり、良好な風景は「環境の多様性、文化の継承、経済の幸せな結合による」と定義し、また、近年では「農業の工業化により風景が失われつつある」と説明している。EUの研究機関Joint Research Centreの報告書には、農地の景観的特徴の分類と定量化が論じられ、農業景観における非生産的な自然や小さな植生が生態系サービスや生物多様性に貢献すると指摘されている。ヨーロッパでは環境と生業の結びつきや、生物多様性への影響に着目している点が日本と違う。
2.日本における農業の変化
農業の変化は農村風景を変える。
まず肥料の利用だ。明治期以降、農地が増え生産性が上がるが、これに大きく寄与したのが無機(化学)肥料の普及だ。明治初期には有機肥料(干鰯、油粕、魚肥、大豆粕など)を利用していたが、「お雇い外国人」の指導で無機肥料が日清戦争以降に広がった。地域ごとに小規模につくられていた肥料は、大企業によって供給されるようになった。
入会地の減少も影響した。地租改正で入会地も課税対象となったが、税金を支払うことができず国有地に編入された。それまで入会地に里山の草や葉をすきこんでいたが、なくなると肥料の自給が難しくなり循環は途絶えた。大量生産が必要な商品作物の需要が増えたことも無機肥料の普及を後押しした。たとえば工場の賄い制度(大正〜昭和前期)で沢庵漬けを出すために大根の規格化が進んだ。
戦後になると、国内でコメを生産する必要があった(戦前は台湾など外地に食料を依存)。工業が復活してくると、工業と農業が連動し無機肥料の生産が増加した。
『作物生産における投入補助エネルギー』(宇田川武俊/1977)によると、1955年から1975年の間に農業における循環型の労働・畜力、自給肥料が減少し、石油由来の補助エネルギー(肥料、農薬、資材・動力、農機具)が増加。それにともない秣場[i](まぐさば)が減少するなど、農村風景や土地利用にも変化が生じた。
とりわけ大きな転換点となったのが1960年の所得倍増計画だ。農業と非農業間に存在する所得格差の是正を行う方針が出され、農業の生産性を高めながら農業者数を減らすことが計画された。機械化、大規模化によって自立できる農業者を増やすというわけだ。
所得倍増計画を受け、1961年に農業基本法が制定され、経済合理的な農政へと転換が図られた。具体的には農業構造改善事業が実施され、基幹作物の選定(効率の悪い多角経営から単一作物に専門化)、経営の合理化(土地の大規模化、協業、機械化)、流通加工の合理化(品種、品質、規格の統一)などが進められた。
野菜生産出荷安定法(1966年)によって指定作物、指定産地も定められた。指定産地には指定野菜の出荷数量の2分の1以上を指定された消費地(主に大都市)に出荷する義務がある一方で、出荷価格が一定以下に下落した場合は、補給交付金が支給される。これにより生産者は参加しやすくなり、大都市周辺を中心に指定産地が増えた。
こうしてみると、日本の農業は消費地(都市)の影響を強く受けている。都市の要請に合わせて農業は変化した。高度経済成長期に農業の効率化が進み、単一栽培、化学肥料やF1種の普及などで、農業構造改善事業が進んだ。「水とみどりの『美の里』プラン21」で言われる「環境に合わせた農業」は現実と乖離している。
3.EUの農業政策と日本の現在
EUは「Common Agricultural Policy(CAP)」として農業政策に10の目標を掲げている。

初期には、農家の適正所得の確保、競争力強化など、主に生産性向上に関する目標が掲げられたが、現在では気候変動対策、環境、生物多様性への配慮などの目標が掲げられている。
EUの共通農業政策は1962年に始まり、当初は自給率の向上を目指し価格支持政策が行われた。しかし効果は限定的で、「余剰食料の山をつくった」、「農業が環境破壊の原因になった」と後日評価されている。余剰食糧が出ると行政が買い取るため莫大な保管費用がかかった。特に酪農を行う地域では冷蔵庫付き倉庫が必要だった。また肥料の大量使用により地下水が硝酸態窒素などに汚染される問題が発生した。例えば、ブルーベビー症候群(乳児が硝酸態窒素を摂取しすぎると酸欠症状を起こす)の事例も報告された。
1985年、EC委員会は「共通農業政策の展望」(グリーン・ペーパー)を発表し、環境破壊の原因の1つが共通農業政策であることを認め、環境配慮の重要性と環境保全型農業の支援が挙げられるなど、思想は大きく転換した。
2003年にはクロス・コンプライアンスの義務化、デカップリングが導入された。前者には法定管理事項(公衆衛生および動植物衛生、環境、動物愛護など13項目)があり、全農業者が守らなければならず、農家は要件を守ることで補助金を受けられる。2017年の時点で、約90%の農家が参加し、効果的に機能していると評価される。
一方の適正農業環境条件は、水、土壌と炭素固定、景観の3分野で定められている。

厳格な取り組みとして、各国は2015年から直接支払いの30%をグリーニングに充てることが義務付けられた。具体的には、永年草地の維持、作物の多様化(農地面積が30ヘクタール以上の場合、3種以上の異なる作物を栽培しなければならない)、環境用地の設置(生態系や景観の維持のための区域。15ヘクタール以上の農地で5%以上)だ。
EUで、農業という私的な経済活動に規制と補助金を通じて公的介入を行うのは、環境によい農業によって得られる環境、風景、文化が公共財であると認識されているからだ。公共財は非排除性と非競合性を持つ。環境保全型農業は経済活動の中で農業者の自由な選択により行われることを期待するのは難しいし、公共財は農業者以外の利益につながる。
適切な農業によりもたらすことのできる公共財には、耕作地や縁の生物多様性、水質保全と利用可能性、土の機能保全、気候変動の抑制、洪水と火事の予防、レジリエンス、農業景観の保全、農村活力の創出、食の安全などが含まれる。
これらの公共財をもたらす農業活動――有機栽培、伝統種の栽培、農地の縁にバッファーゾーンの創出、沼沢地・湿地の維持、水辺を健全な自然状態に保全、湿地を創出など――に補助金が提供されている。
2023年からはさらに環境に貢献する農業を目指し、小規模農家(10ヘクタール程度の農地を所有)へのサポートを行う。
また、EUはFarm to Fork Strategyを推進し、生産から流通・消費までのフードシステム全体を改革し、環境に配慮した良い食品が流通される仕組みを目指す。また、環境破壊をアウトソーシングしない方針を掲げ、EU域外で環境に対して悪影響のある食品を輸入しないとしている。これらの政策が日本にも影響を及ぼす可能性があり、日本でも農業と流通を連携させた環境に配慮したシステムを構築する必要があると考えられている。
日本の農業政策でも環境への影響や持続可能性に対する取り組みが重視されているが、EUに比べると具体性に欠けている。農業政策では食糧供給に力を入れており、環境については具体的な計画が示されていない。中山間地域への直接支払制度では文化の継承や景観の維持につながることが理念として掲げられているが、実際の交付の仕方には理念に沿わない部分もある。多面的機能支払交付金についても、環境保全との一致が問われる内容となっていたり、環境保全型農業直接支払においても、EUのような伝統的な手法や有機肥料の使用などについてはあまり具体的に記載されていない。
日本の農業政策においてはもっと環境配慮が必要だ。特にEUとの貿易関係を考慮すると、日本でも環境保護への取り組みを強化し、農業を持続可能なものとして発展させる必要がある。
さらなる議論


[i] 秣場(まぐさば/共同の草刈場でそのほとんどは入会地)
「未来の水ビジョン」懇話会について
我が国は、これまでの先人たちの不断の努力によって、豊かな水の恵みを享受し、日常生活では水の災いを気にせずにいられるようになった。しかし、近年、グローバルな気候変動による水害や干ばつの激化、高潮リスクの増大、食料需要の増加などが危惧されている。さらには、世界に先駆けて進む少子高齢化によって、森林の荒廃や耕作放棄地の増加、地方における地域コミュニティ衰退や長期的な税収減に伴う公的管理に必要な組織やリソースのひっ迫が顕在化しつつある。
水の恵みや災いに対する備えは、不断の努力によってしか維持できないことは専門家の間では自明であるが、その危機感が政府や地方自治体、政治家、企業、市民といった関係する主体間で共有されているとは言い難い。
そこで「未来の水ビジョン」懇話会を結成し、次世代に対する責務として、水と地方創成、水と持続可能な開発といった広い文脈から懸念される課題を明らかにしたうえで、それらの課題の解決への道筋を示した「水の未来ビジョン」を提示し、それを広く世の中で共有していく。
|
※「未来の水ビジョン」懇話会メンバー(五十音順)2023年7月現在 |

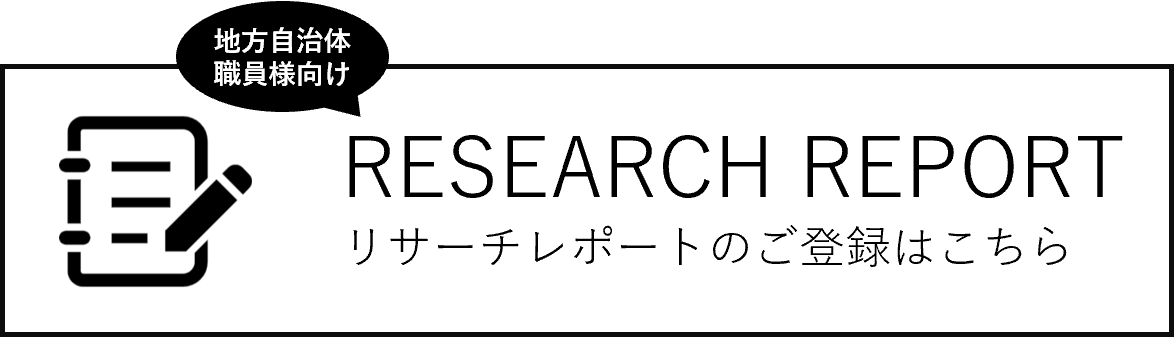


































































































































































































































































_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)





















_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)


































































