
R-2024-098
本Review(1)では、経済政策に関する考え方について、コンセンサスが形成されつつある分野として、マクロ経済政策の実践と格差問題を見据えた経済政策思想の2つを指摘した。ただし、マクロ経済政策に関しては、①金融政策と財政政策の併用、②景気刺激には財政政策、インフレ抑制には金融政策というすみ分けという形で、現実の政策運営でコンセンサスが形成されているのに対し、格差是正については、経済学者ないし知識人の間で考え方の収斂(しゅうれん)が始まったに過ぎず、格差是正に向けて現実の政策が動き始めた訳ではない。さらに、マクロ経済政策のように、実際の運営を主にテクノクラートが担う分野や、知識人内部の思想潮流を別にすると、多くの分野で経済政策を導く理念が失われつつあるように感じられてならない。
| 1.経済格差拡大への対応 ・格差拡大と税制 ・移民への怒り ・国際課税協調の困難化 2.貿易と産業政策:高まる国境の壁 ・収穫逓増、外部性と貿易・産業政策 ・経済安全保障という難題 3.脱炭素:勢いは弱まっても止まることはない ・減速する政府主導の脱炭素 ・それでも脱炭素の動きは止まらない |
1.経済格差拡大への対応
・格差拡大と税制
格差問題については、トマ・ピケティが2013年に刊行した大著『21世紀の資本』で、詳細なデータを用いて、1980年代以降の新自由主義の時代に多くの先進国で経済格差が急拡大したことを明らかにしたことから、世界的に注目が高まったことは周知の通りである。ピケティとそのグループは、その後も格差の実態と原因に関する研究を続けており、その成果はカリフォルニア大学バークレー校のエマニュエル・サエズとガブリエル・ズックマンの著書『つくられた格差』[1]にまとめられている。同書は、とくにアメリカのケースについて、第二次世界大戦後、1960年代頃までは累進度の高い税制が維持されたため、格差の拡大は回避されてきたが、1980年代以降は所得税の累進制が大幅に緩和されて、格差が急拡大したことを明らかにしている[2](法人税率は、それ以前から低下を始めていた)。さらに、タックス・ヘイブンなどを使った富裕層の租税回避が、格差拡大に輪をかけている事実も指摘している[3]。
これに対し経済学者らは、累進度の強い所得税は労働に負のインセンティブを与えることから、経済成長を抑制する効果を持つといった考えをしばしば表明してきた。レーガノミクスの頃に主張された「減税すると、人々が熱心に働くようになるからむしろ税収は増える」といったラッファー曲線の議論がその代表と言えよう。しかし、こうした見方に実証的な根拠がある訳ではなかった[4]。最近の国際通貨基金(IMF)スタッフによる研究では、①不平等の拡大は金融的不均衡を通じて、経済成長の脆弱性を高める、②再分配政策は経済成長にプラスに働くといったことが明らかにされている[5]。
・移民への怒り
このように、合理的に考えれば、所得税の累進性を高めるなどして、経済格差の是正を進めるのが望ましいのだが、現実にそうした動きはあまり広がっていない[6]。典型は米国だ。バイデン政権の頃は、トランプ大統領が第1期に実施した富裕層向けの減税や法人減税は実施期間が終われば終了するとされていたが、昨秋の大統領選にトランプ氏が勝利したことで、トランプ減税は継続される可能性が高まった。
欧州各国での右翼ポピュリスト勢力の伸長や、米国でのトランプ大統領の再登場をみると、欧米の一般国民が怒りを覚えているのは、格差拡大よりも移民に対してだと感じられる。欧州では、ウクライナ戦争以来、ウクライナからの避難民に中東やアフリカからの難民が加わって、EUへの移民が急増したという事実がある。バイデン政権下の米国でも、移民の流入が急増した[7]。本Review(1)ではピケティのバラモン左翼vs商人右翼という図式を引用したが、欧米の中低所得層の多くは、自らの人的資本不足を認めてバラモン(高学歴エリート)から見下されるのは耐え難い。それより、自身の不幸は移民たちのせいだと思いたいのではないか。不適切な表現かもしれないが、そう感じられてならない。
・国際課税協調の困難化
所得税の累進性緩和に先立って法人税減税が進められたのは、他の国に比べて法人税率が高いと、企業が海外に拠点を移してしまうのではないかという恐怖感が働くため、各国の間で「底辺への競争」(race to the bottom)が起こるからだ。実際、米国のビッグテックの多くが重要拠点をアイルランドに置いているのも、アイルランドの法人税率が低いからだ。今でも経済学の教科書には、「法人減税は設備投資増加につながる」と書いてあるが、法人減税で増えるのは「設備投資ではなく自社株買いだ」というのがビジネス界の常識である。それでも、第二次安倍政権が2015年度から法人税減税を実施したように、法人減税のトレンドが止まらないのは、今でも「底辺への競争」が続いているからに他ならない。
だから、「底辺への競争」を止めて、経済格差是正を進めていくには国際的な課税協調が不可欠になる。このため、経済協力開発機構(OECD)は租税委員会にBEPS(base erosion and profit sifting)というプロジェクトを設けて、検討を進めてきた[8]。国際課税協調は大変困難なもので実現は容易でないと考えられていたが、2021年に入って交渉に予想以上の進展がみられ、10月にはOECD各国が法人税の最低税率を15%として、デジタル課税も導入することで合意が成立した。筆者はこれを大歓迎したのだが[9]、残念ながらその後目立った進展は見られていない。それどころか、トランプ大統領は早速デジタル課税に否定的な見解を示しており、課税に関する国際協調は今後ますます難しくなっていく可能性が高い[10]。
2.貿易と産業政策:高まる国境の壁
・収穫逓増、外部性と貿易・産業政策
収穫一定を前提とする伝統的なヘクシャー・オリーン型の貿易理論が支配的だった時代には、経済効率上、自由貿易が最も望ましいと考えられてきた。しかし1980年頃、ポール・クルーグマンらが収穫逓増と不完全競争を前提とした新貿易理論(new trade theory)を引っ提げて登場すると、成長が期待される産業に補助金を与えることで規模を拡大し、他国に先んじて競争力を高めるといった貿易政策が有効という結論になった。同じことは国内の産業についても成り立つため、日米貿易摩擦の時代には、産業政策や戦略的貿易政策の研究も活発化した[11]。
しかし、やや皮肉なことに、1980年頃には中国が改革・開放政策に踏み切り、1990年頃にはソ連崩壊に伴ってかつての東側諸国が一斉に市場経済に参入したため、現実の貿易パターンは要素賦存の違い(資本集約度の高い西側先進国vs労働集約度の高い中国や体制移行国)を反映したヘクシャー・オリーン型に近いものとなった。このことと当時の新自由主義思想の広がりが相まって、欧州統合、北米自由貿易協定(NAFTA)、世界貿易機関(WTO)の発足といった貿易や対外投資の自由化が積極的に進められたのである[12]。また、この頃は特定の産業に補助金を与えて、育成を図るような産業政策は、基本的に望ましくないものと考えられていた。
だが、貿易構造は再度変化している。1980~90年代の世界貿易がヘクシャー・オリーン型になったのは巨大な人口を抱えた中国の参入によるものだったが、今や中国は低賃金財を主に輸出する国ではなく、ハイテク分野で米国としのぎを削る存在になった。今度こそ収穫逓増型の新貿易理論の世界になった訳だが、1980年頃に想定された収穫逓増産業が自動車や家電だったのに対し、現在のデジタル産業の収穫逓増度ははるかに高い。ましてネットワーク外部性が働くため、最初に大きな市場シェアを手にした企業が有利な立場を維持しやすくなる。各国には、補助金を使ってこうした分野の産業育成を進めようとするインセンティブが強く働くだろう。実際、米国ではバイデン政権の下で、インフラ投資・雇用法、インフレ抑制法、CHIPSプラス法など、実質的に産業政策と見なしうる様々な施策が実施に移された。日本でも、多額の補助金を給付して内外の半導体工場を誘致する動きが広がっているが、これは明確な産業政策である。
また近年は、後述する脱炭素に寄与する財の生産、貿易が重要になっているが、この分野は気候変動という巨大な外部性に立ち向かうのだから、補助金政策を用いることが経済学的にも正当化される。もちろん、本来は例えば電気自動車(EV)であれば自国産であっても輸入品であっても同等の補助金を給付すべきだが、輸入品に多額の補助金を支給するのは納税者の納得を得にくいだろう。こうして自由貿易の維持は難しくなっていく。だから、第1次トランプ政権で引き上げられた輸入関税はバイデン時代にも引き下げられなかったのであり、第2次トランプ政権ではさらに事態が悪化する可能性が高いと覚悟しておく必要があろう[13]。
・経済安全保障という難題
さらに、近年は経済安全保障という考え方に注目が集まり、そのことが問題を複雑化している。元はと言えば、コロナ禍において日本では、マスクが不足したり、ワクチンを地力で開発できなかったりといった問題が明らかとなり、国民の安心、安全を守れないことが懸念された。さらに、企業のサプライチェーンが世界中に広がって複雑化する中で、半導体やレアメタル・レアアース、医薬品などの調達も懸念されるに至った。要するに、新自由主義時代のサプライチェーン作りは、コストの最小化に最大の眼目を置いたため、いざという時のレジリエンスを欠くことが明らかになったのだ。このため、日本政府は2022年に経済安全保障推進法を策定し、①サプライチェーンの強化、②先端技術の開発支援、③インフラの安全確保、④特許の非公開化などを進めることとした。世界各国でも同様の取り組みが行われている。
コロナのパンデミックやロシアのウクライナ侵攻を経験したことで、大きなリスクに直面しても国民の暮らしを守る体制を整えたいとする各国の意図はよく理解できる。とくに中国に関しては、周辺国への威圧や国家安全法や反スパイ法の濫用を巡って、他国が脅威を抱いたとしても決して不思議ではない。だが、経済安全保障上の必要は、収穫逓増や外部性と比べても定義が明確でないため、対応措置が歯止めなく広がってしまう危険があることは否定できない。経済安全保障を口実とした恣意的な貿易制限が広がるリスクは十分にあると言えよう。とくに、米国と中国の間で国家の威信を賭けた対立が深まっていることを踏まえると、経済安全保障が両者の対立の火種となる恐れもある。米国のバイデン前政権が「small yard, high fence」と唱えていたように、「競争を守るために最重要なポイントはしっかり守るが、後は企業活動の自由に任せる」という姿勢を堅持することが重要だと思う。
3.脱炭素:勢いは弱まっても止まることはない
・減速する政府主導の脱炭素
地球温暖化はますます深刻化している。日本の夏の気温は2023年、2024年と2年連続で過去最高を記録した[14]。筆者が子どもだった1960年代には、最高気温が30℃を超えると暑いと感じたし、最高気温が35℃を上回る猛暑日など記憶にない。ところが2024年の東京の猛暑日数は20日に達し、福岡県の太宰府市に至っては何と40日連続の猛暑日だったという。スペインやカリフォルニアでは毎夏のように大規模な山火事が発生しているし、ツバルなどの島しょ国では海面上昇による水没のリスクが懸念されている。こうした中で、これ以上の地球温暖化を食い止めるために温室効果ガスの削減を求める脱炭素の動きが世界的に広がってきたのは周知の通りである。
脱炭素の運動は、様々な主体によって担われてきた。まず、かつては少女だったスウェーデンのグレタ・トゥーンベリさんに象徴される民間の市民運動である。こうした草の根の運動が、企業等の脱炭素の取り組みに大きな影響を及ぼしてきたことは間違いない。また、筆者は脱炭素に向けての金融の影響を重視してきた。これは、2006年に国連が責任投資原則PRI(Principles for Responsible Investment)を制定し、世界の主だった機関投資家に署名させたことに端を発するものだったが、その後ESG(Environment, Social, Governance)投資の活発化につながっていく。その結果、脱炭素を目的としたグリーン債が大量に発行されることとなった。さらに、2017年には世界の金融監督当局が2017年に気候変動リスク等に関する金融当局ネットワークNGFS(Network for Greening the Financial System)という国際組織を立ち上げ、脱炭素の運動は金融監督にも影響を与えるようになっている[15]。
これらに加えて、1997年の京都議定書(COP3)、とりわけ産業革命以降の世界の平均気温の上昇幅を2℃以下に保ち、1.5℃以下に抑える努力をするとしたパリ協定(COP21)以降は、政府が先頭に立って脱炭素を進める動きが目立っていた。日本では、2020年の10月に菅元総理が2050年カーボン・ニュートラルを宣言し、翌年グラスゴーで開かれた国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)では、2030年に温室効果ガスを2013年度比で46%削減すると約束するところまで踏み込んだのは記憶に新しい。米国でも、トランプ大統領が第1期政権時にパリ協定離脱を宣言したが、バイデン大統領は当選後直ちに協定に復帰を果たし、2050年カーボン・ニュートラル、2030年に2005年比で温室効果ガスの50~52%削減を約束するとともに、インフレ抑制法(Inflation Reduction Act)にはEVへの補助金をはじめ多くの気候変動対策を盛り込んだ[16]。
しかし、ごく最近は政府主導の脱炭素の動きがやや息切れ気味となっている。2024年11月にアゼルバイジャンの首都バクーで行なわれた国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)では、先進国などが気候変動対策に2035年までに少なくとも年間3000億ドルを拠出することが決まったが、同会議はその金額を巡る議論に終始した感がある。その背景の第1として、ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー危機がある。ウクライナ戦争勃発直後は原油などのエネルギー価格が急騰しただけでなく、ロシアからの液化天然ガス(LNG)輸入に大きく依存してきたEU諸国で、エネルギー不足への不安が大きく高まった。化石エネルギーの価格上昇は長い目で見れば脱炭素の加速要因だが、短期的な供給不安は脱炭素へのブレーキとなる。第2は、人工知能(AI)の急速な普及に伴う電力需要の急増である。こちらも化石エネルギーへの依存を続けざるを得ない要因となる[17]。加えて、トランプ大統領が復帰直後にパリ協定からの離脱を再決定したことは周知の通りである。トランプ氏は、石油や石炭を「掘って掘って掘りまくれ(Drill, baby, drill!)」と叫ぶ。政府主導による脱炭素は当面減速を余儀なくされるに違いない。
・それでも脱炭素の動きは止まらない
このように、政府主導の脱炭素は減速するとしても、それで脱炭素の流れ自体が止まることはないだろう。日本でも欧州でも、気候変動対策が必要なことは有権者に広く認識されている。だから、トランプ第1期政権がパリ協定から離脱した時と同様に、多くの国が協定離脱へとなだれを打つ可能性は低い。また、現在のパリ協定では各国が自ら決めた排出量削減目標(NDC)に沿って脱炭素を進めていく仕組みになっている。ある国が目標達成はできないとしてNDCを引き下げれば、これは政治的敗北と見なされやすい。そう考えれば、従来のように政府が先頭に立って目標を引き上げていくことはなくなるとしても、直ちに目標引き下げ競争になるとは考えにくい[18]。
一方、民間企業の多くは、引き続き脱炭素にコミットし続けるだろう。日本でも多くのビジネスマンがSDGs(Sustainable Development Goals)バッジを身に付け、テレビにもSDGsをうたったCMが多数流れているように、地球環境を意識した経営を行っていると示すことは企業イメージの向上に重要だと考えられているからだ。また、やや長い目でみると、技術進歩と規模の経済によって、再生可能エネルギーのコストが低下していく一方、化石エネルギーのコストは上昇していくだろう。結果、再生可能エネルギーへの財政補助は減っていっても、脱炭素の流れは続くと思われる[19]。
そもそも、トランプ政権がパリ協定から離脱しても、米国全体が反・脱炭素に向かう訳ではない。民主党支持者の多い青い州では、地方政府レベルで引き続き気候変動対策が進められていく可能性が高い。また、インフレ抑制法に基づくEVや蓄電池工場などへの補助金廃止が議会で可決されるとは考えにくい[20]。さらに、EUで準備が進められている国境炭素税[21]が実際に課税されるようになれば、この負担を逃れるためにEU域外の企業も脱炭素を進めざるを得なくなる。結局、地球温暖化という現実がある限り、脱炭素の流れ自体が途絶えることはないと考えられる。
[1] エマニュエル・サエズ、ガブリエル・ズックマン『つくられた格差:不平等税制が生んだ所得の不平等』、光文社、2020年
[2] 日本では、所得が1億円を超えると所得税率が低下する「1億円の壁」が存在するが、サエズ・ズックマンは米国でも最富裕層では税率が逆進的になることを示している。
[3] タックス・ヘイブンについては、志賀櫻『タックス・ヘイブン』、岩波新書、2013年を参照。
[4] 同様の問題として、日本の在職老齢年金制度がある。現状、働く高齢者の収入(賃金+厚生年金)が月額50万円を上回ると、厚生年金の支給額が減額される仕組みになっているが、この上限を月額62万円に引き上げる案が厚生労働省から示されている。この仕組みが高齢者の就労意欲を損なうとの認識からのようだが、管見する限り高所得の元気な高齢者は働くこと自体に効用(生きがいなど)を感じているように見える。同制度の就労削減効果が大きくないのであれば、この改正で必要となる財源は低所得者への年金給付に使った方がよいのではないか。
[5] Jonathan Ostry et. al. “Redistribution, Inequality, and Growth”, IMF Staff Discussion Note, 2014
[6] 例外的に、イギリスでスターマー労働党政権が大型増税を予定しているが、政権への支持率は大幅に低下している。
[7] 過去2年余り、この移民の大量流入=労働供給増加により、高めの成長が維持される一方、人手不足は緩和してインフレ率は低下した。このように、経済状況のみからは民主党に有利な環境にあったはずだが、大量の移民流入は白人労働者層の怒りを招いたため、結果的にバイデン・ハリスの民主党が2024年11月の大統領選、上下院選挙において、トランプ共和党に敗北することとなった。
[8] BEPS委員会の議長は、浅川雅嗣元財務官(前アジア開発銀行総裁)が長年にわたって務めてきた。
[9] 世界金融危機以降の経済政策思想を振り返る(2) コロナ危機下でのコンセンサスの模索 | 研究プログラム | 東京財団政策研究所
[10] デジタル課税とは、インターネットを通じたサービス提供により、特定の拠点なしに事業展開しているGAFA(米国のIT(情報技術)企業大手であるグーグル(Google、現アルファベット傘下)、アップル(Apple)、フェイスブック(Facebook、2021年10月よりメタに社名変更)、アマゾン・ドット・コム(Amazon.com)の頭文字をつないだ造語)などに課税する仕組みである。この制度では、収益力の高い多国籍企業が利益を生み出す場所で公平に税を負担することになる。デジタル課税に対するトランプ大統領の姿勢については、森信茂樹研究主幹の論考トランプ政権とデジタル税制の行方 貿易戦争は関税だけではない—連載コラム「税の交差点」第126回 | 研究プログラム | 東京財団政策研究所を参照。
[11] この頃のクルーグマンの貿易理論は、Paul Krugman, Rethinking International Trade. MIT Press, 1990にまとめられている。当時の産業政策、戦略的貿易政策に関する日本での研究については、伊藤元重・清野一治・奥野正寛・鈴村興太郎『産業政策の経済分析』、東京大学出版会、1988年、冨浦英一『戦略的通商政策の経済学』、日本経済新聞社、1995年などを参照。
[12] この頃、貿易理論においては、少数の大企業が国際的なサプライチェーンを構築して競争するという新新貿易理論(new new trade theory)が登場していた。Mark Melitz, “The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity”. Econometrica, 2003を参照。
[13] トランプ大統領は本年2月初めに、不法移民や不法薬物の取り締まり不足を口実にメキシコとカナダに25%の関税を課し、中国からの輸入関税を10%上乗せすることを決定したが、メキシコ、カナダ向けは直ちに実行を延期した(中国向けは実施)。このようにトランプ大統領は関税を他国との交渉手段に用いる可能性(関税の武器化)が高く、トランプ関税の先行きは予断を許さない。
[14] 6~8月の平均気温は2年連続で過去最高タイ。猛暑日の日数では、2024年が2023年を上回った。
[15] この点については、2021年に筆者が東京財団政策研究所のウェブサイトに寄稿した拙稿コロナ・ショック下の金融と経済(第16回)脱炭素の経済的論理(上)―金融の力と世論・政策の相乗作用― | 研究プログラム | 東京財団政策研究所、コロナ・ショック下の金融と経済(第17回)脱炭素の経済的論理(下) ―日本が直面する2つの困難― | 研究プログラム | 東京財団政策研究所を参照
[16] 脱炭素を巡る国際政治に関しては、上野貴弘『グリーン戦争:気候変動の国際政治』、中央公論新社、2024年が詳しい。
[17] これらは、岸田前総理による原発政策転換(可能な限り低減→最大限活用)の一因となったとみられる。
[18] 今年のCOP30はブラジル北部のベレンで行われる予定だが、パリ協定に沿って脱炭素目標を5年ごとに見直す年になる。日本政府は、既に2035年の温室効果ガスの排出量を2013年度比で60%削減する方針である。ただし、昨年末にこの方針が打ち出された時も、マスコミ等に大きく取り上げられることはなかった。脱炭素への熱が衰えつつあることは否定できない。
[19] これは自動車のEV化も同じである。足もとではアーリー・アダプター(新しい技術や製品、サービスが市場に登場した際に、一般の人々よりも早い段階でそれを取り入れる消費者層)の購入一巡などを背景にEV化の動きが減速しており、HV(ハイブリッド自動車)の販売が好調となっている。しかし、長い目でみれば今後ともEV化が進んでいくとの見方が一般的である。
[20] EVや蓄電池工場は共和党優位の州に多く立地していると言われる。
[21] カーボン・プライシングの一種で、環境規制の緩い国からの輸入品に事実上の関税を課す仕組み。EUでは、2023年から事業者に対する炭素排出量の報告が義務化されており、2026年から実際の課税が始まることになっている。
■Review(1)はこちら→世界インフレ後の経済政策を考える(1)―マクロ経済政策の実践と経済政策思想の現在地―
■続きはこちら→世界インフレ後の経済政策を考える(3)―日本社会の「相対的安定」― 近日公開予定









































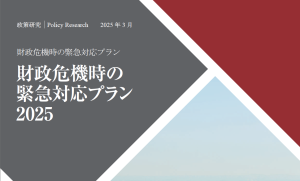



































































































































































































































































_20220805hayakawa_jpg_jpg_w300px_h199px.jpg)





















_20220408hayakawa_jpg_jpg_w300px_h169px.jpg)


































































