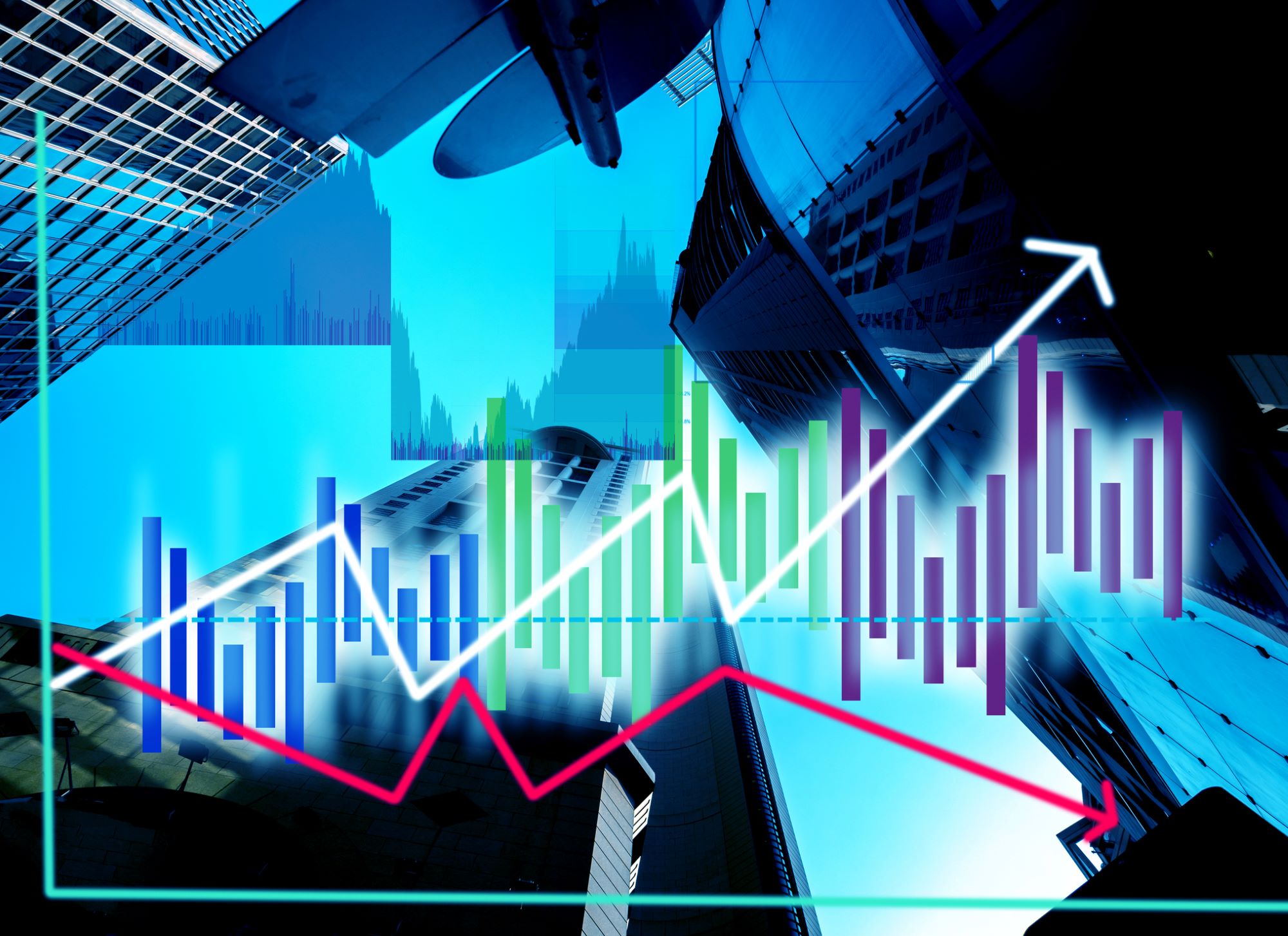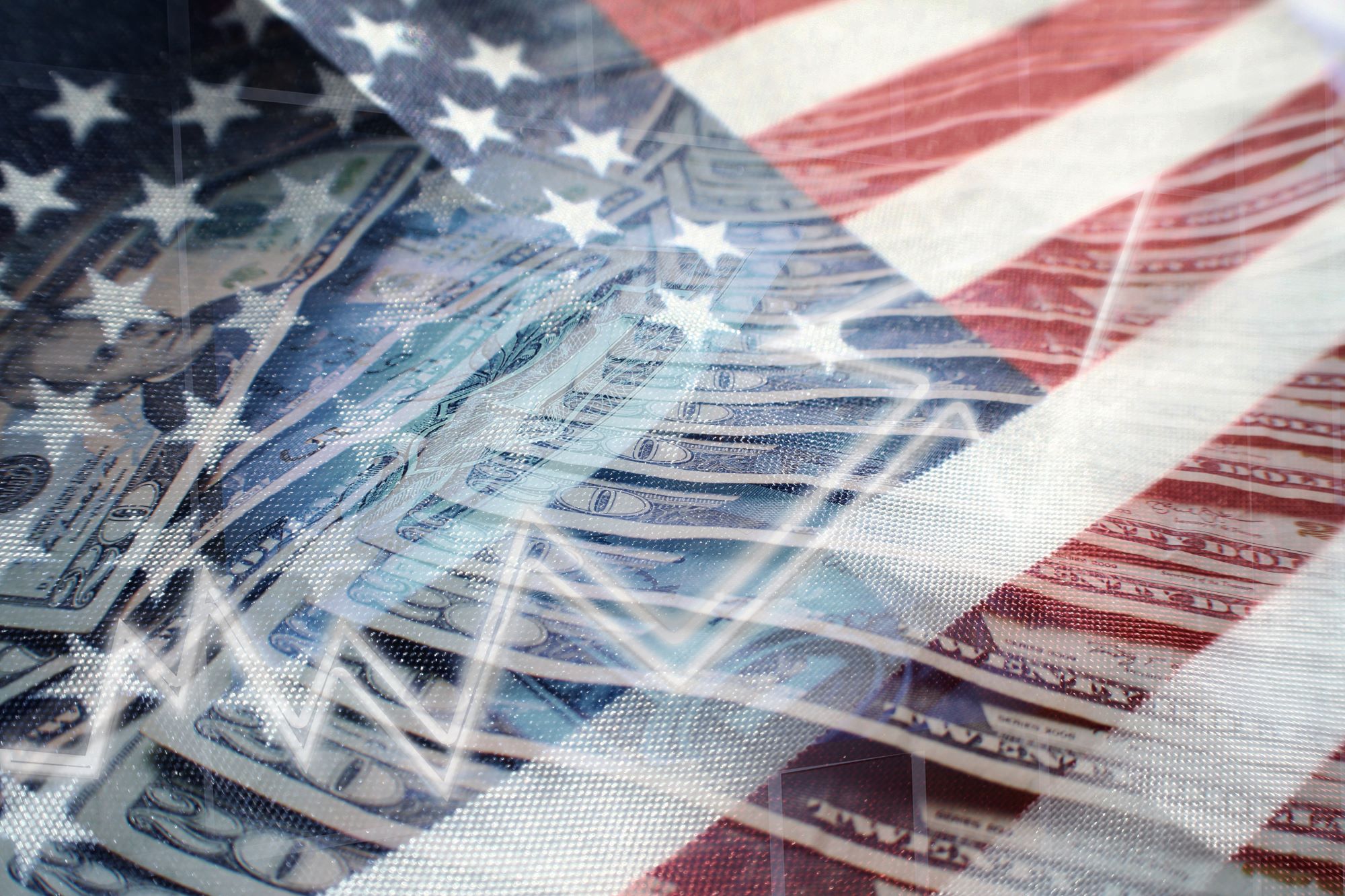加藤 創太
上席研究員
7月の東京都議会議員選挙で、自民党は歴史的な惨敗を喫した。高位安定してきた安倍晋三政権の支持率も急降下した。個別の大臣・国会議員の言動もあったが、学校法人「森友学園」への国有地払い下げ問題、学校法人「加計学園」の獣医学部の新設問題、そして安倍晋三政権の対応のあり方が大きな影響を与えたのは間違いないだろう。
そのうち、加計学園の問題には、1990年代以降に日本が進めてきた政治・行政制度改革の功罪が象徴的に現れている。
* * *
90年代以降の改革熱狂が志向した大きな方向性は、政冶・行政面での政冶主導および官邸主導の実現と、経済面での規制改革だった。今回、岩盤規制のーつとされる獣医学部の新設が官邸主導で認められたことは、見方によってはまさにこうした制度改革の成果であり、ここ20年以上、日本が目指してきた方向性そのものと言える。
戦後日本の政治・行政システムは、政治学者の故・佐藤誠三郎氏らが「仕切られた多元主義」と呼んだように、省庁ごとの仕切りの範囲内で政官財の利害調整を行ってきた。明治期に引かれた省庁間の線引きの枠内で政策を考えるという意識が、霞ヶ関の官僚たちには染みついていた。そうした仕切りを乗り越え、仕切りの中で長年醸成された既得権や利権を打破する政策を実現する手法として、官邸主導は極めて有効である。日本が環太平洋経済連携協定(TPP)への署名にこぎ着けたのも、強力な官邸主導に多くを依っている。
他方で、加計学園問題は、政治主導、官邸主導の問題点も浮き彫りにした。
90年代以降の一連の改革は一貫して、政治家、特に官邸に強い力を与える方向を志向してきた。背景には上記の「縦割り行政」に加え、「官僚主導」「決められない政冶」への強い批判があった。
しかし議院内閣制は本来、大統領制や半大統領制などに比べて行政府の長(首相)とその周辺(官邸)が強い権力を持ちうる制度である。議会(立法府)の第一党党首が首相を務めることが多いため、立法府と行政府が一元化されるからだ。もちろん以前の中選挙区制であれば、自民党が一党優位であっても、自民党内の派閥が「党内党」として首相の権力に強い規律を与えた。多くの欧州国家が採る大選挙区制では、政権の連立政党が首相に強い規律を与えている。
90年代に導入された小選挙区制が議院内閣制と組み合わさったことにより、他の先進民主主義国家と比しても、首相および官邸が政権内で絶大な権力を握ることが制度的に可能となった。さらに先の民主党政権への有権者の強い幻滅が加わり、小選挙区制度の下で政権への最大の規律となるはずの対抗野党が政権批判の受け皿となれない状態が続いている。
 政治から一定の距離を保つはずの各種機関にも官邸の強い力は及んでいる。行政機関については、一連の「政治主導」のスローガンの下、官邸は内閣人事局を通じて幹部人事権を握った。報酬などで差異を設けづらい行政機関において、公務員の最大のインセンティブ(誘因)となるのは人事である。上司の心の内を「忖度」して動ける人間が「できる」と評価されるのは、官僚組織も企業も同じである。かつて各省庁の幹部への「忖度」を競い合っていた官僚たちが、今は官邸への「忖度」を競い合うようになったのは当然の帰結だ。
政治から一定の距離を保つはずの各種機関にも官邸の強い力は及んでいる。行政機関については、一連の「政治主導」のスローガンの下、官邸は内閣人事局を通じて幹部人事権を握った。報酬などで差異を設けづらい行政機関において、公務員の最大のインセンティブ(誘因)となるのは人事である。上司の心の内を「忖度」して動ける人間が「できる」と評価されるのは、官僚組織も企業も同じである。かつて各省庁の幹部への「忖度」を競い合っていた官僚たちが、今は官邸への「忖度」を競い合うようになったのは当然の帰結だ。
行政機関以外でも、政治からの一定の独立性が求められる日銀の審議委員の任命には、「経済または金融に関して高い識見を有する」という日銀法の基準よりも、アベノミクス(安倍首相の経済政策)への賛同の度合いが重視されている印象がある。最高裁判事人事、内閣法制局長官人事、NHK会長人事などにも、従来の慣行を超えた官邸の強い介入があったと報じられている。
加計学園問題で明らかになったのは、官邸への権力集中とその権力の中枢への「忖度」が永田町や霞が関を中心に広がっている姿である。権力集中には大きなリスクが伴う。また、せっかく官邸主導により既存勢力の既得権や利権が打破されたとしても、その既得権や利権が一般には開放されずに、新たな権力の下での新たな利権になるのでは意味がない。
権力集中の弊害を防ぐには、権力へのガバナンス体制の構築が何より重要となる。数年に一度の選挙による政権交代に政治行政のガバナンス(統治)のすべてを託すのではなく、各種の政治行政制度を総合的に見た上で、あるべき日常的なガバナンス体制を判断していかなければならない。
* * *
まずは、権力分立のあり方だ。例えば日本と同様に議院内閣制と小選挙区制を併用する英国では、政治家の官僚への人事権は強く制限されている。二大政党制も根づいている。首相の解散権の行使も強く制限されるようになった。オーストラリア、ニュージーランドなど議院内閣制を採る他の主要先進民主主義国家でも、政治家による官僚の人事権は制約されている。他方、米国では大統領が官公庁幹部を政治任用するが、大統領は議会と独立しており、議会から強い規律を受ける。日本は首相の議会解散権の行使に制約がほとんどない数少ない国でもあり、この面でも首相および官邸の権力が強い。
人事や政策の実施については、透明化、ルール化、第三者の関与などを通じて、政府(特に官邸)の日常的な説明責任を高めることが必要だ。安倍政権は企業に対するコーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)の導入を積極的に推し進めた。決算期ごとの株主総会によるガバナンスだけでなく、企業経営者の日常的な説明責任を高めるためだ。政治や行政においても、数年に一度の選挙だけでなく、政府の日常的な説明責任を促すような仕組みの導入が必要だ。野党が与党批判の受け皿となり得ていない現状ではなおさらである。米国などで一般的となっているエビデンス(証拠)に基づいた政策立案や政策評価の手法を導入することも有益だろう。
森友学園問題、加計学園問題を起点とした今回の政治混乱は、90年代以降の制度改革の功罪を冷静に見直す良い機会となる。制度改革は通常、新たな制度の実際の効果が顕れるまで時間がかかる。今回の件により、90年度以降に「政治主導」「官邸主導」を志向して進められてきた一連の制度改革が、いかに官邸周辺に強大な権力を集中させたかが、国民の前に明らかになった。それに戸惑いを感じている者も多いだろう。しかしあらゆる改革がそうであるように、改革の成否を決めるのは、改革そのものよりも改革後の地道な試行錯誤と微調整である。権力の集中と分散のバランスのあり方が問われている。
◆英語版はこちら "The Kake Gakuen Scandal in Context: The Perils of Concentrating Political Power"
2017年7月9日付『日経ヴェリタス』掲載記事をタイトル他、一部加筆修正