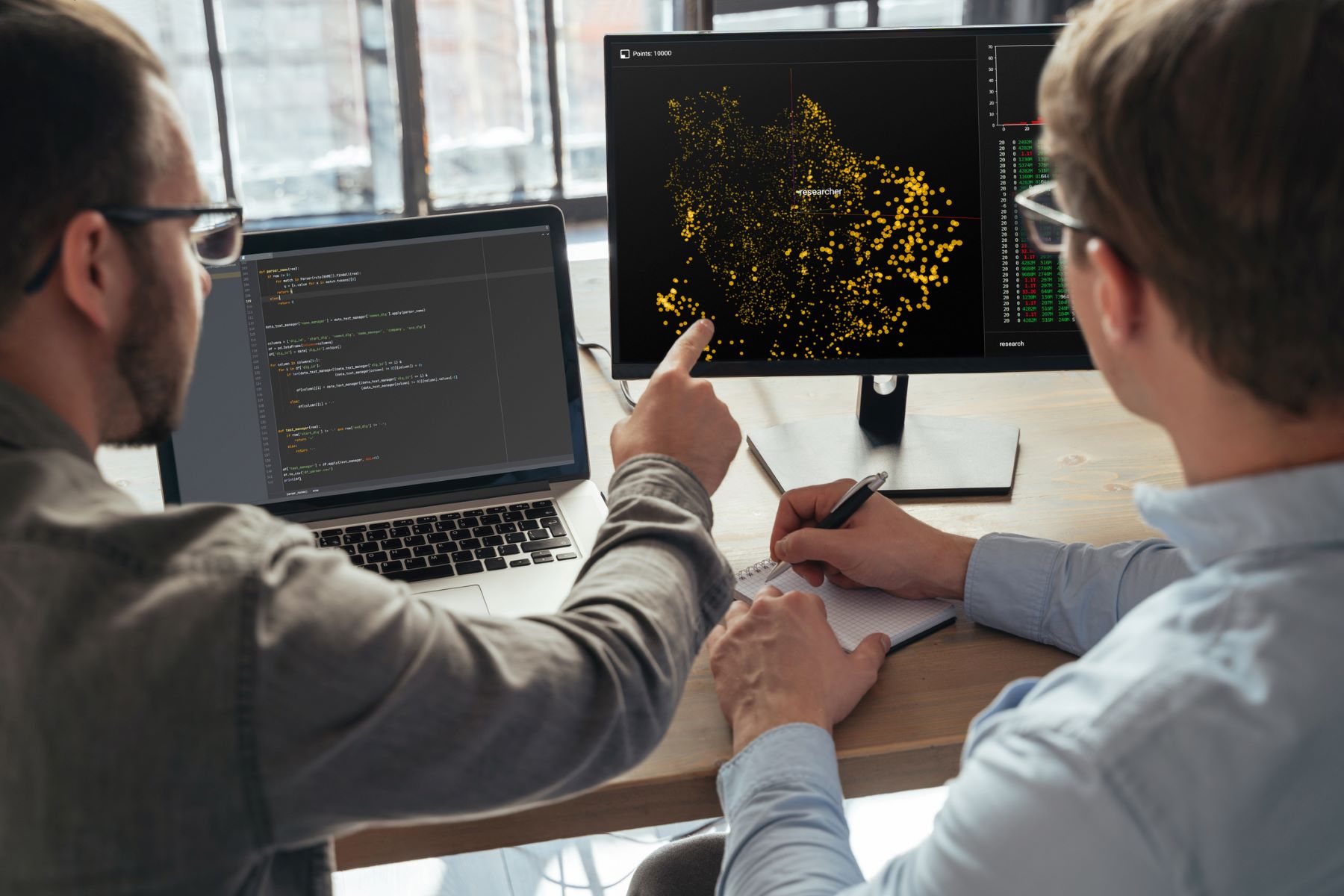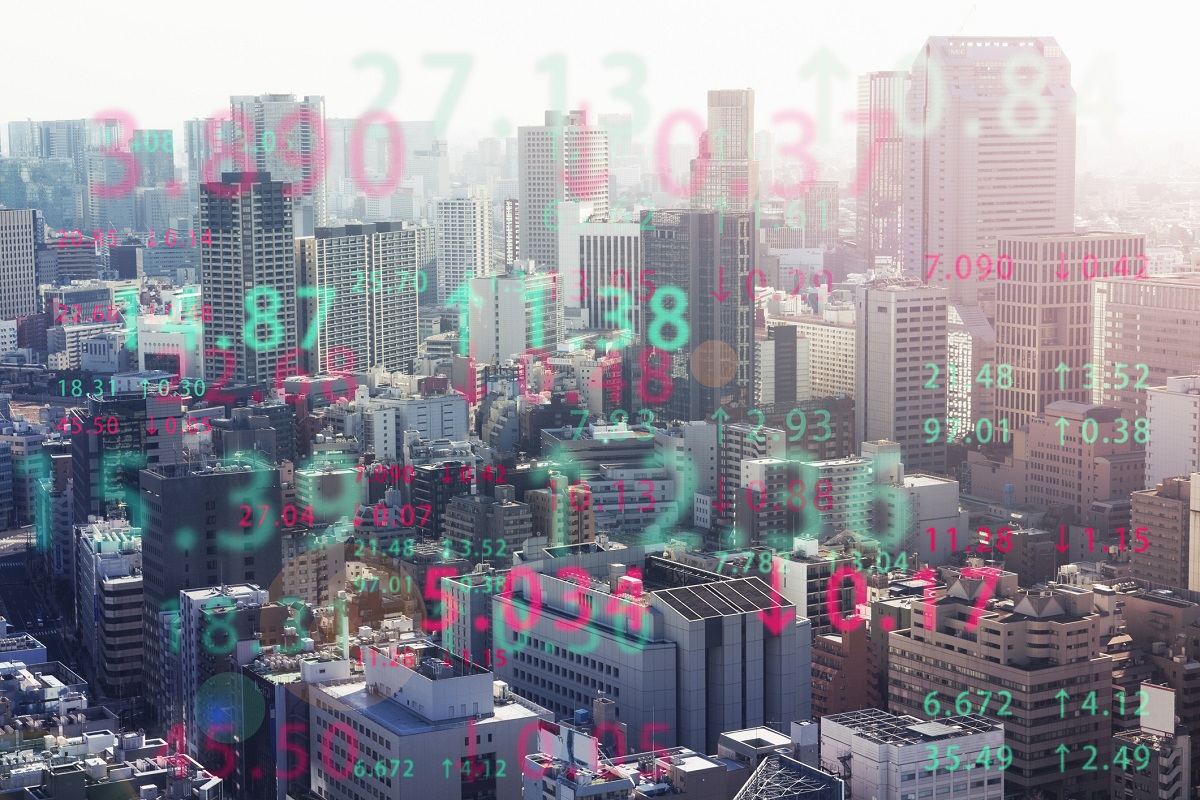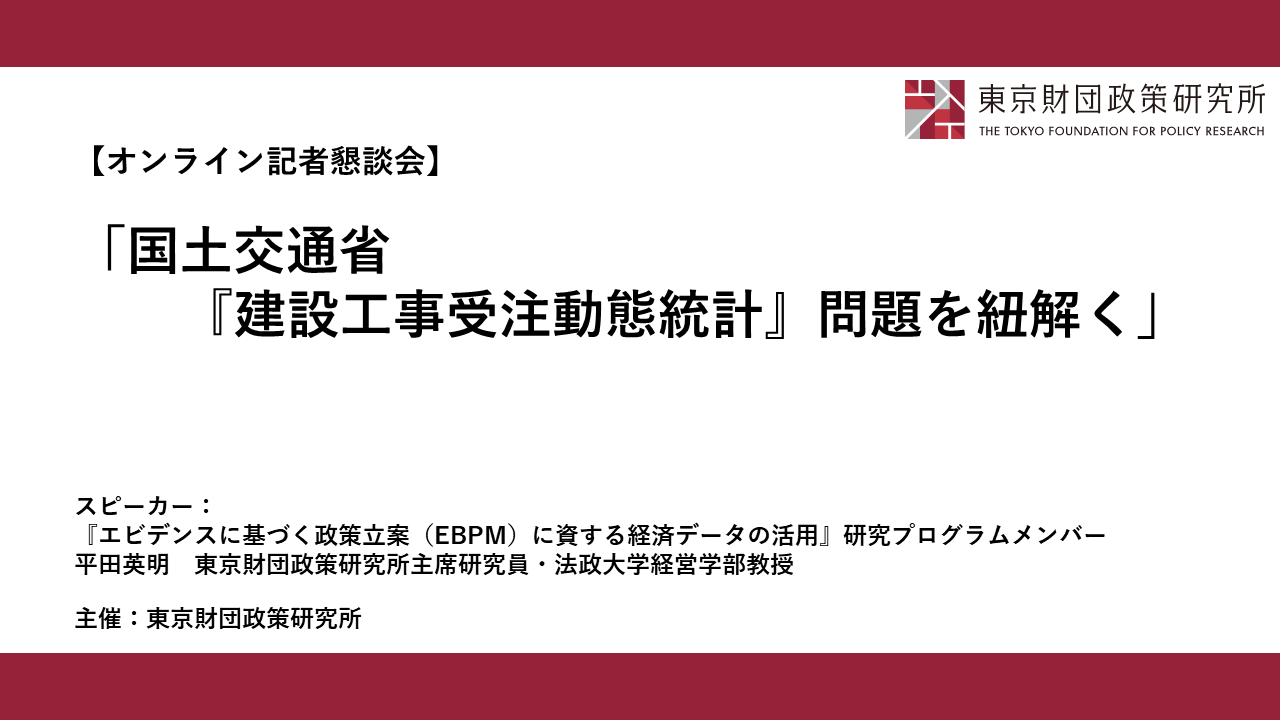東京財団政策研究所「リアルタイムデータ等研究会」メンバー
東北学院大学経済学部准教授
1.はじめに(前回のおさらいと今回の問題意識)
前回は、内閣府経済社会総合研究所(Economic and Social Research Institute、以下、ESRIと略称)が景気動向指数(一致指数)を作成する際に使用するデータセットを用いて、ダイナミックファクターモデルという手法を拡張した小規模モデルにより景気後退確率を推計した。さらに、ESRIが定める景気基準日付(景気の山と谷を定める転換点)に対して、ESRIよりも小規模なデータセットによる再現を試みた。具体的には、一致指数で採用している9系列(鉱工業生産指数、鉱工業用生産財出荷指数、耐久消費財出荷指数、所定外労働時間指数、投資財出荷指数、小売業商業販売額、卸売業商業販売額、全産業営業利益、有効求人倍率)から主成分分析によって、5系列(鉱工業生産指数、鉱工業用生産財出荷指数、耐久消費財出荷指数、所定外労働時間指数、投資財出荷指数)にデータセットの縮小を行なった。分析の結果として、2000年以降の景気基準日付をESRI と同程度の精度によって推定することが可能であることを示した。
しかしながら、この選択結果は、製造業の生産と需要、各財の需要、労働状況に偏ってしまっている。公的な転換点をうまく捉えられているといえども、これを日本経済の景気状況を表すというには、語弊がある。昨今の「いざなぎ越え」という景気評価に対して、実態や実感がないという批判が散見されるのも、選択または観察している統計の差異から生じるものであろう。今回は、前回の縮小したデータセットに、新たな系列を追加することで、より実際の経済状況を考慮した指標の提案及び検証をしていきたい。
2.採用系列の追加
ここでの目標は、日本経済の状況を捉える景気指標の構築である。そのためには、バランス良く統計データを選択する必要がある。それでは、どのような経済活動に注目すれば良いのか。アメリカの景気循環を判定する全米経済研究所(National Bureau of Economic Research、以下、NBERと略称)では、個人所得、雇用、製造、商業販売など4領域の経済統計の変動に注目している。このNBERのアプローチと前回の採用系列を比較すると、不足しているのは、個人動向と商業販売に関する情報である。こうした点も勘案しながら追加系列を検討する。
まず、今回は個人動向を表す指標として家計消費に着目し、内閣府が公表する消費総合指数と総務省が公表する家計消費支出を新規採用系列とする[1]。前者は、家計調査、鉱工業出荷指数、特定サービス産業動態統計より加工された指数であり、消費に関して需給両面から合成された指数である。後者は家計調査の系列である。2018年実質暦年GDPの支出側では、約55.5%が家計(最終)消費支出で占められることから、家計消費の動きは、日本全体を左右させる主要なドライバーと考えられる。
次に、商業販売関連の統計について取り上げる。商業販売に関して、ESRIの景気動向指数では、小売販売額と卸売販売額が既に一致指数の採用系列として利用されている。しかし、これらの指標は前年同月比に加工したものを採用しており、実質変換はされていない。これにより、ESRIの採用系列には、実質値と名目値が混在しており、この問題は未だ改善されていない。ここでは、この小売販売額と卸売販売額に代わる統計指標を考える。商業は日本においては、第3次産業に分類されている。このことから、経済産業省が作成している第3次産業活動指数(以下「第3次活動指数」という。)を候補とする。第3次産業は、2017年暦年の経済活動別GDPでは72%の構成比を占めることから、同産業と製造業を合わせることで、日本の産業の90%近くをカバーできるものと考えられる。
最後に、前述のNBERのアプローチでは触れられていないが、原材料価格と物価動向について考える。主にコモディティなどの原材料市況は、輸入依存度の高い日本の供給サイドと密接な関係を持っているからである。例えば、非鉄は建材や自動車などの幅広い分野で利用されているほか、食品や繊維の原材料も輸入割合が非常に高い。こうした原材料市況の変動は、各財に価格転嫁され、我々の日常生活にも大きな影響を与える。本研究と同様にダイナミックファクターモデルを用いたHenzel and Rengel(2017)でも生産サイドの重要な経済統計として、石油などの原材料市況の情報を挙げている。ここでは、日本銀行作成の企業物価指数における需要段階別素原材料を候補とする。この統計は、農林水産物や燃料などの価格動向について指数化されたものであり、後述する日経商品先物指数(42種)よりも幅広い原材料価格の情報を含むものと考えられる。
以上のことから、家計消費、第3次産業、原材料価格に関連した統計の追加を検討する。家計消費支出と第 3次活動指数は、景気動向指数の遅行系列に分類されており、日経商品先物指数(42種)など商品市況の統計指標は先行系列に分類されている。今回のように、遅行や先行系列を一致系列と混在させることの影響についての検証はこれまで行われていない。また、先行系列の先行性は近年低下していることから[2]、経済動態を捉える景気指標構築を目的として、こうした経済指標を用いることは検討に値する。
3.採用系列の追加と景気後退確率
ここでは、上記で追加候補として挙げた経済統計と、前回絞り込んだ5系列を組み合わせて、景気後退確率を推定する。推定には、前回と同様に拡張したダイナミックファクターモデルを用いる。基本となるデータセットは、前回絞り込んだ5系列(鉱工業生産指数、鉱工業用生産財出荷指数、耐久消費財出荷指数、所定外労働時間指数、投資財出荷指数)であり、この組み合わせをM0とする。次に、追加を考える経済統計は、消費総合指数(季節調整済)、家計消費支出(2015年基準・2人以上・季節調整済)、第3次活動指数(2010年度基準・季節調整済)、企業物価指数の需要段階別素原材料(2015年基準・季節調整済)(以下「素原材料」という。)を用いる。追加データの組み合わせは表1の通りである。

表の ⃝と×は、その統計データの追加有無を意味する。消費総合指数と家計消費支出はどちらも家計消費を示すものであることから、いずれかを選択することにする。標本期間として2000年1月から2018年11月までの月次データを用いて、推定を行う。
推定された景気後退確率を図1から図3にまとめている。値が0.5(50%)を超えるときに、日本経済は景気後退期に入っていると判断する。各図には、ベンチマークとしてM0の景気後退確率を加え、従来指標とどれほど変化するかの目安とする[3]。また、各図における影の部分は、ESRIが景気基準日付で景気後退期と判断した期間を示している。
1系列追加の場合
まず、M0に1系列だけ追加したパターン(M1、M2、M3、M11)についてまとめた図1についてみていく。いずれのパターンも、M0に比べて低い確率で推移している。また、M1とM2においては、動態に大きな差異は見られないことから、消費総合指数と家計消費支出の単体での追加は、どちらを選択しても近い結果になることを示唆している。

2系列追加の場合
次に、2系列追加したパターン(M4からM8の5パターン)のデータによって推定された景気後退確率が図2に描かれている。図2より、以下の特徴がみられる。まず、素原材料を含める場合には景気後退確率が M0の結果に近くなる、またはM0より大きくなっている。また、M6(消費総合指数と素原材料)と M7(家計消費支出と素原材料)では、2014年3月から8月にかけて、景気後退確率が50%から60%に推移する局面、つまり、準景気後退期のような期間が観測される。

3系列追加の場合
続いて、3系列を追加したパターンの結果(図3)について概観する。図3では、M0の結果に比べて、M9とM10ともに概ね同様の結果となっている。図1および図2との違いは、2012年4月から2012年11月までの景気後退期において、M0よりも高い確率で景気後退を示していることである。また、2015年6月から2016年2月までの9ヵ月は、景気後退確率が50%を超えていることから、確率として高くはないが、小さな景気後退期が発生していることになる。

パターン間の景気の転換点の比較
最後に、推定された各パターンの景気後退確率と景気の転換点について考察をする。表2は、ESRIが公表する景気の山と谷及び各パターンの景気判断の結果についてまとめられている。山と谷の定義は、ESRIの定義に従い、山(谷)であれば、景気後退確率が50%を上回る(下回る)直前の月である。表の値は、2であればESRIの判断と比べて、2ヵ月遅れて、転換点と判断したことを意味する。一方で、負の値は、ESRIの判断に比べ、その値の分だけ先行していることを意味する。表2より、どのパターンもESRIの転換点と比較すると、±3ヵ月の範囲内となっている。そして、M0と比べて、転換点の誤差が最も小さいパターンは、M6、M7、M9およびM10である。これら4つの特徴は、第3次活動指数を含めていることである。しかし、図2と図3の結果とを見比べると、2012年3月を山とする第15循環の景気後退期(2012年4月から11月)では、M9とM10の方が、高い景気後退確率となっており、この期間が不景気であることをより明確に指し示している。このことから、今回の追加候補の中では、家計消費、第3次活動指数、素原材料の追加が最適なものと考えられる。第3次活動指数は景気動向指数の採用系列の中では、遅行系列に分類される。しかし、景気の後退確率の推計および転換点の評価をする上では、一致指数への採用も検討していく必要があると考えられる。

4.まとめ
今回は、前回で減量化させた景気動向指数に対して、より実態経済の動きが捉えられるよう家計消費、第3次産業および原材料物価の経済統計を新たに加え、景気後退確率の推定を行った。これにより、前回よりも景気の転換点をうまく捉える景気指標の構築を提案した。しかし、景気動態そのものは未知であることから、この分析結果が最適であるという保証はない。どの統計を追加ないし差し引くことで、どのような影響が出るかについて、試行錯誤を重ね、実証結果を積み重ねていくことがより良いEBPMにつながることから、今後も指標の精微化に努めていきたい。
近年では情報化社会の進展により、ビッグデータを用いた経済分析に注目が集まっている。ビッグデータ分析では、「情報の量が質を凌駕する」と言われることもあり、この景気を測るという研究領域でも有効なのか。次回は、大規模データを用いた景気循環分析について取り上げる予定である。
-
日本銀行が公表する消費活動指数、総務省が公表する消費動向指数は、2000年1月からの月次の数値が公表されていないため採用系列候補から外している。
-
時変型遷移確率に拡張し、先行系列の変動を導入したモデルについては、現在、筆者が研究成果をまとめている。
-
データ系列の延長等により景気後退確率の推計結果は随時更新されている。
参考文献
- Henzel, S. R. and M. Rengel (2017), “Dimensions of macroeconomic uncertainty: A common factor analysis,”Economic Inquiry, 55(2), pp.843–877.
 大塚 芳宏 東北学院大学経済学部准教授
大塚 芳宏 東北学院大学経済学部准教授
1979年東京都生まれ。06年千葉大学修士(経済学)、金融機関の営業・調査部に勤務。12年一橋大学経済学研究科で博士号取得後、北海道大学大学院経済学研究院助教、長崎県立大学経済学部講師を経て、15年から現職。