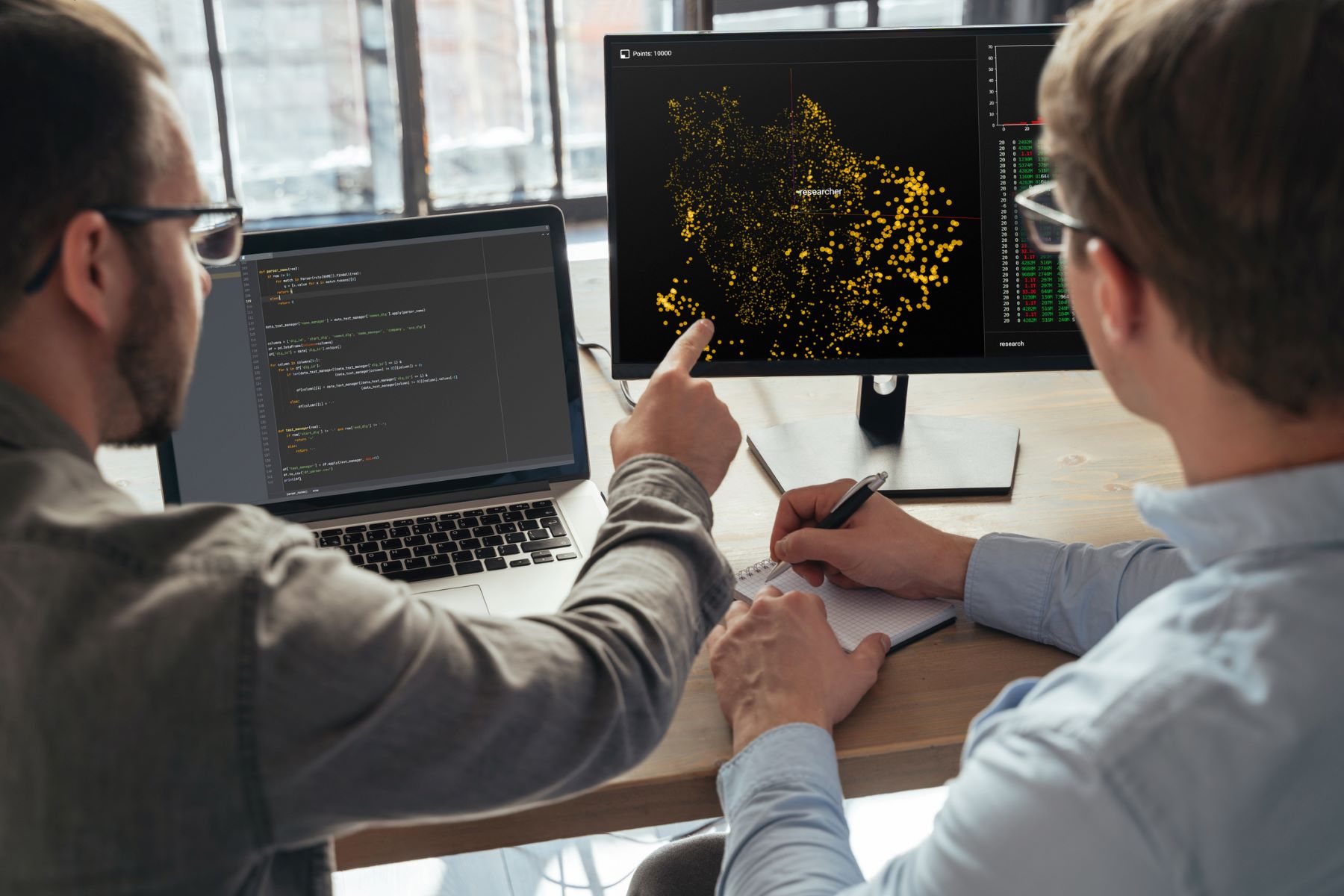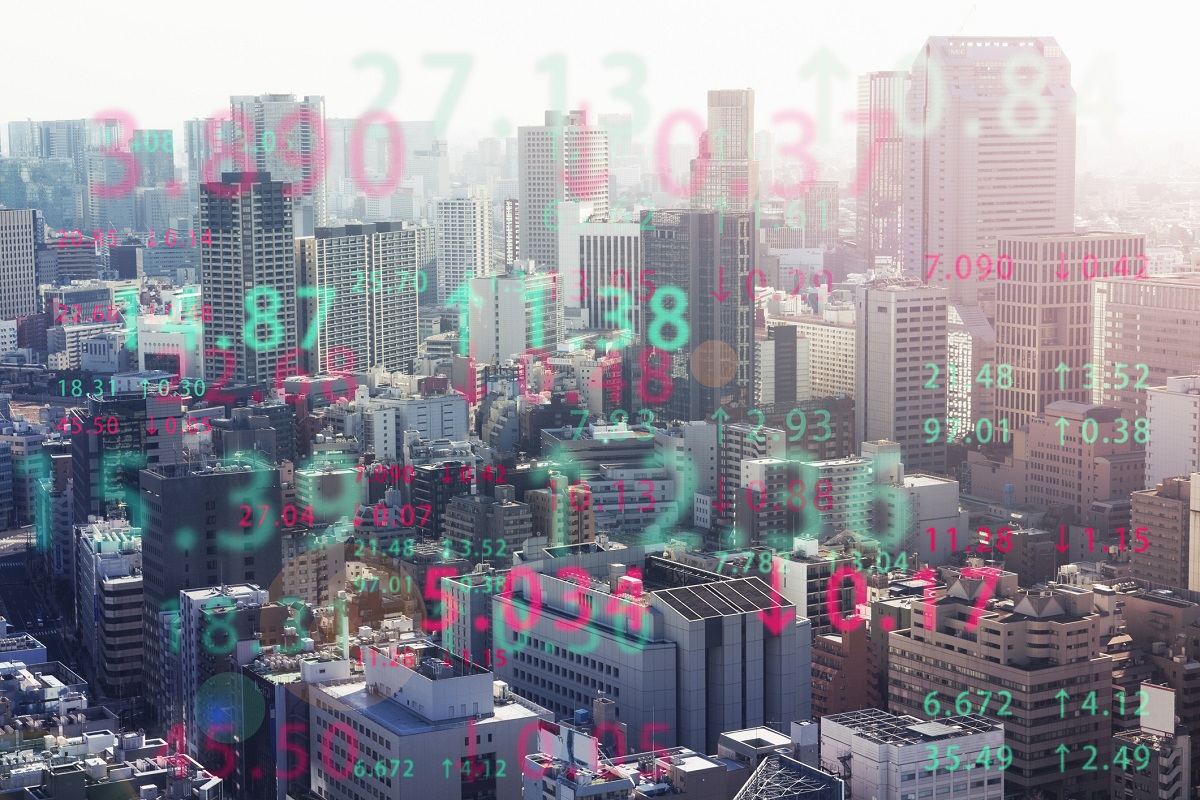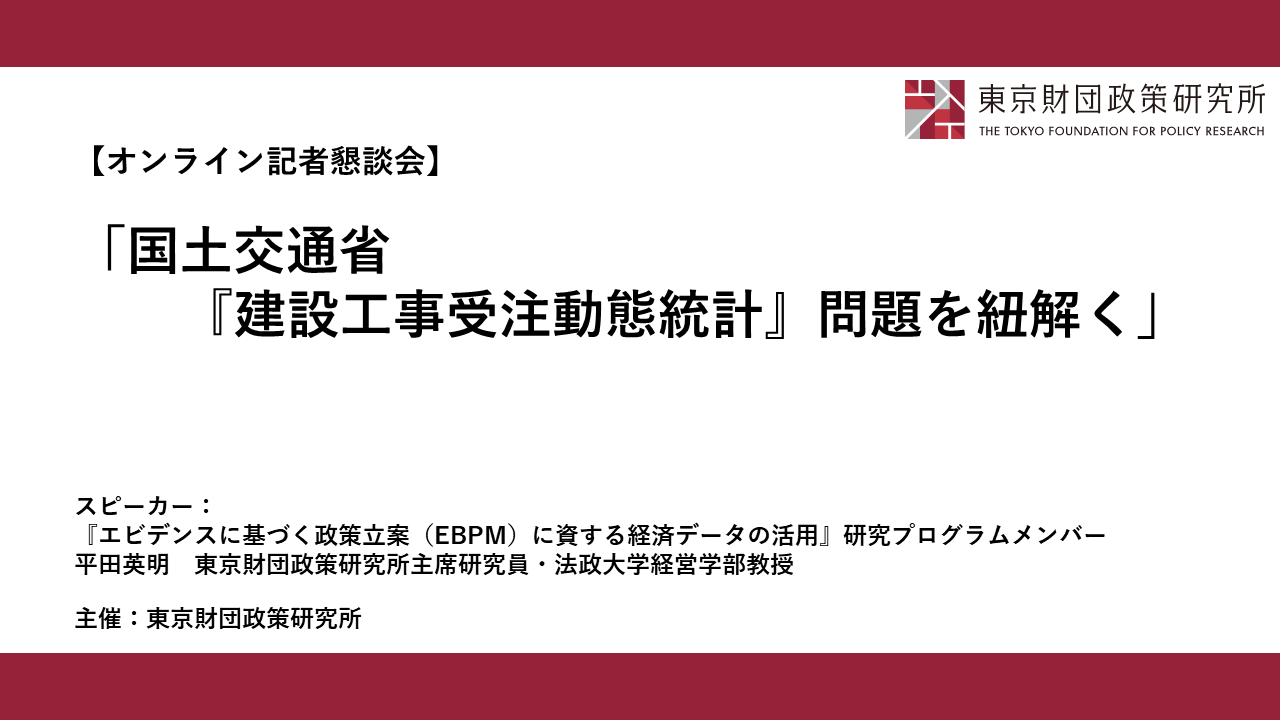東京財団政策研究所「リアルタイムデータ等研究会」メンバー
大阪経済大学経済学部教授
1.はじめに
今秋の消費税率引上げ(2019年10月1日)で、政府が最も懸念するのは2つである。過去2回の税率引上げ(1997年、2014年)と同様に、①大規模な異時点間の代替効果(いわゆる駆け込み需要とその反動減)から大きな景気変動が生じること、また、②所得効果により消費低迷及び景気悪化が生じることである。ただし、今次は、税率引上げに伴う増収分に匹敵する大規模な財政政策が実施される見込みであること、食料品等に軽減税率が導入されることが、過去2回と大きく異なる。
他方、欧州のEU加盟国では付加価値税(Value-added Tax、以下「VAT」という。)は加盟国の共通税制と位置づけられ、すべての加盟国に導入が義務付けられている。VATの運用については2006年のVAT指令(Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax)により定められ、標準税率は15%以上と定められている。また、軽減税率の導入については加盟国に委ねられているが、2019年3月時点ではデンマークを除く全ての国で軽減税率が導入されており、VATの税率変更と同時に軽減税率の変更も実施される場合が多い。
しかしながら、欧州でのVATの税率変更では、森信(2014)の指摘通り、ドイツ(2007年、16%から19%へ引上げ)及びイギリス(2010年に15%から17.5%、及び2011年に20%へ引上げ)では増税の前後で駆け込み需要や反動減は見られず、欧州ではVATの変更で大きく騒がれることはない。本論では、欧州諸国におけるVAT引上げの状況との比較を通じて、日本における消費税率引上げの影響が大きくなる要因について検討する。
以下では、 欧州及び日本におけるVAT変更前後の消費動向について概観した後、
- 価格転嫁行動
- 税率の変更幅
- 軽減税率利用度合
- VAT税率変更と同時に行う税制変更パッケージの内容
の観点から欧州と日本の違いを整理・検証する。なお、次回のコラムで、これからの要因の効果について実証分析の結果を示す予定である。
2.欧州及び日本におけるVAT変更前後の消費動向
2000年以降の欧州のVATの変更例について、8カ国12事例における国民経済計算(System of National Accounts: SNA)・四半期ベースの民間最終消費の動きを、税率変更幅の違いを考慮して示したのが図表1である。図表1-1は1%以下の変更時、図表1-2は2%以上の変更時を示している。所得効果とみられる消費の落ち込みが確認できるのは2011年のイタリア(1%引上げ)及び2012年のオランダ、スペイン(2%引上げ)である。一方、異時点間の代替効果とみられる動きは、2007年のドイツ、2010年のイギリスで駆け込み需要とその後の反動減の動きがみられるが、多くの地域では確認できない。ドイツ、イギリスともその後の所得効果による消費の落ち込みについては確認できない。
さらに詳細にみるために、月次ベースのデータを用いる。欧州では月次ベースで日本の家計調査のような需要側統計データは作成されていない。そこで、小売業販売額を基に、食料品と非食料品に区分して、月次ベースで確認する。食料品と非食料品で区分するのは、軽減税率の対象品の多くが食料品であるからである(付表1、付表は文末にまとめて掲載)。月次ベースで利用可能なイギリス、イタリア、アイルランド及びギリシャの4カ国についてみる(図表2-1から2-4)。概ねどの国においても、食料品は税率引上げの影響を受けていない。他方、非食料品について駆け込み需要は確認できないものの、税率引上げ直後に減少し、比較的短期間で元の消費水準まで戻っていることが確認できる。
日本についても同様に、家計調査を基に月次ベースでみると、欧州と大きく異なり、過去3回とも食料品及び非食料品の両方において異時点間の代替行動及び所得効果による消費のレベルシフトが確認できる[1]。特に、2014年は他の時期と異なり、消費のレベルが下がったままとなっており、同期間の所得の伸びが低迷していたことを裏付けるものといえる(図表3-1から3-3)。
3.欧州及び日本の比較①:価格転嫁行動の違い
先行研究によれば、欧州では税率変更分の価格転嫁の方法が異なること、また税率変更幅に比較して価格転嫁が低いことから、VAT税率の変更の影響が小さいと指摘されている。
イギリスについては(五十嵐, 2012)、国内の小売業者の財務担当者や大手会計事務所へのヒアリングによれば、事業者は、①全ての商品について、税率が上がった分だけ一律に価格を引き上げるのではなく、商品の性質に応じて価格の引上げ幅を変え、売上全体で見て税率引上げに伴うコストアップ分をカバーする方法を採用し、②税率が引き上げられたのは2010年、2011年ともに1月であるのに対して、クリスマスに向けた商戦が開始する前年の秋ごろと、翌年1月との2回に分けて価格を引き上げたとのことである。
また、フランスについては(森信, 2014)、税制当局者へのヒアリングによれば、イギリスと同様に、事業者は、税率引上げが決まると、実施前から商売を取り巻く様々な状況を考慮に入れ、徐々に価格(税込みの総額表示)を改定していくとのことである。また、税率分を一律に引き上げるのではなく、売れ筋の商品は多めに価格を引き上げ、そうでないものは価格を据え置くなど、全体としての売り上げとマージンの確保を念頭にVATの負担増を消費者に求めているとのことである。
事実、価格転嫁率についてイギリス統計局(ONS, 2011)の調べでは、2010、2011年の2.5%の税率引上げによる価格転嫁はそれぞれ0.4%、0.76%と指摘している。つまり、イギリスにおいては、付加価値税率の引上げに伴う価格転嫁の度合いについては、それぞれの企業の価格戦略に基づき、商品の性質に応じてその在り方が異なっている上、価格転嫁の時期もまちまちとなっており、この方法によりイギリスの消費者は付加価値税の負担の増減について、それほど敏感なわけではないと指摘している[2]。ドイツでは、2007年増税時の駆け込み需要期に耐久財の価格が上昇し、価格転嫁率の73%の内24%が増税前、49%が増税のあった2007年に転嫁されていたと指摘している(Carare and Danninger, 2008)。
これに対し、日本は欧州とは全く異なる価格設定がなされている。高野他(2015)によれば、日本の場合には駆け込み需要期にスーパーなどのセールにより、価格下落が確認できるとしている。日経・東大日次物価指数[3]で前年比の消費税抜き価格の動向をみると、1997年と2014年の消費税率引上げ前の駆け込み需要が生じている税率変更の1か月前には、販売価格が下落している様子が確認できる(図表4-1および4-2)。また、税率変更後については、日本銀行(2014)は、2014年度の消費税率引上げに関し、CPIの総合(除く生鮮食品)でみた場合、課税品目にフル転嫁されると仮定して機械的に試算すると2.0%ポイント程度押上げられるとしている。また、電気代やガス代等、料金計算で税率引上げ前の3月を含む場合などの経過措置の影響を含むベースでみれば1.7%程度価格転嫁が可能としている。このような試算によるCPIの税抜き価格の指数は増税前後でほとんど変化していないことから、増税による価格上昇の大半部分を一律に、消費者に価格転嫁しているとみられる。
このように、欧州では税率変更前から企業の裁量的な価格設定により徐々に増税分の影響を吸収しようとしているのに対して、日本では増税前に価格が下落していることから逆に増税後の価格上昇幅が大きくなり、税率変更後の影響を過大にさせている可能性がある。
4.欧州及び日本の比較②:税率の変更幅の違い
EU諸国のVATの税率は、1968年の導入以降、標準税率の変更が107回実施されている(2019年1月末時点)。引上げ幅の最小はフランス0.4%(2014年1月)であり、最大はイギリス7.0%(1979年6月)となっている(図表5)。1%以下の変更は42回、2%は31回、3%は10回となっており、それを超える引上げは多くない。特に、1%の引上げは37回と最も多い。2%未満でみれば、46回とほぼ半分程度を占めている。また、短期間で数次の引上げを行う場合には、引上げ幅を1%ずつ段階的に実施している地域もみられる(チェコの2010年、2013年、イタリアの2011年、2013年、フィンランドの2010年、2013年)。

しかし、日本では2%(1997年)、3%(1989年、2014年)と欧州の平均的な引上げ幅より大きなものとなっている。また、税率10%引上げの当初計画は2014年4月、2015年10月と短期間・段階的に実施する計画であった。日本経済研究センター(2014)では、税率を1%ずつ段階的に引き上げた方が経済に与える影響は小さいとの試算結果を示し、1%ずつの段階的な引上げを提言している。2019年10月の引上げは1997年4月と同様、2%の引上げである。税率引上げ幅の小幅・段階的に引き上げる方法を定量的に検討する必要があるのではなかろうか。
5.欧州及び日本の比較③:軽減税率利用度合の違い
EU諸国のVATでは軽減税率の導入が認められている。VATを最初に導入したフランス(1968年1月)では、VAT導入と同時に軽減税率を採用している。その他の国についてもVAT導入時に軽減税率を導入し、現在まで続けられている場合がほとんどである。2017年4月現在で軽減税税率を導入していないのはデンマークのみである。また、2000年以降の47回のVATの変更のうち、軽減税率を同時に税率と軽減税率の適用対象を拡張しているのは20回、VATのみの変更は27回となっている(付表2)。
欧州では図表1のとおり、非食料品では税率変更の消費への影響がみられるが、軽減税率の対象品である食料品では税率変更の消費への影響を受けていないとみられる。軽減税率の効果と考えられる。この点は、ある意味で、軽減税率の導入に対する反対意見である「税制が消費者の行動を誘導する」ものと言えるが、経済活動にショックを与えていないかの観点からの軽減税率の効果検証を行うべきであると考える。
6.欧州及び日本の比較④:VAT税率変更と同時に行う税制変更パッケージの違い
日本での消費税率の変更に限らず、欧州における税制の変更時には他の税制も同時に変更される場合が多い。所得税の税率及び税率の刻み数の変更と、VAT変更との同時期実施について、OECDのTAX data baseから把握可能な24カ国[4]及び日本をみると、2000年以降、対象地域では35回のVATの変更が実施されている。
所得税率の刻みについては、ドイツ(2007年、2→3段階)、イギリス(2010年、2→3段階)、ギリシャ(2010年、4→9段階)等、35回中7回、刻み数が拡大されている(付表3)。
所得税率の変更では、最低税率の引下げの場合はオランダ(2001年4.50%→2.95%)等、4回の事例がある。他方、最低税率の引上げはポルトガル(2010年、10.50%→11.08%)等4回となっており、引下げも引上げもさほど事例は多くない(付表4)。
最高税率の場合、最高税率引上げはドイツ(2007年、42.0%→45.0%)の他、9事例と多い。最高税率の引下げはオランダ(2001年、60.0%→52.0%)の他、4事例と多くない。最高税率の引上げは、VAT税率の引上げと合わせ、高所得者層への増税効果が強まることを意味し、これがドイツの2007年VAT税率上げ時に駆け込みが強くなった要因かもしれない[5]。(付表5)
日本の場合、1989年の消費税導入時は物品税が廃止され、自動車等では実質的な減税となり消費が拡大したものも見られた。1997年においては、1996年度までの所得税減税の廃止や健康保険制度の改定などから消費税率引上げ分と合わせて約9兆円の負担増とされている[6]。 2014年の場合には相続税や復興特別法人税などで改定がみられたものの、大きな税制変更はない。
7.日本へのインプリケーションと課題
以上、欧州の状況を日本と対比しながら述べたが、欧州での経験は、日本における今後の消費税増税の影響緩和策の検討に生かすべきものではなかろうか。日本においては、欧州と比較して消費税率の変更前後で大きな生活環境の変化が生じるような状況を作りだしていると考える。もちろん、消費税の導入は実質的な所得の減少であるものの、それを感じさせにくくするような取り組みができるのではなかろうか。まず、欧州においては、販売側について、日本のように消費税率の引上げと同時に一律に価格転嫁する状況にはなく、各事業者が価格転嫁を行う時期や、消費財毎の価格転嫁率の大きさなどに企業側の裁量的な判断が可能である。また、税率の変更幅について、経済に与える影響が小さいとの分析がある1%ずつの小幅な改定を段階的に実施している。今後の消費税増税では検討すべき課題は多いと考える。
次回のコラムでは、今回整理した、所得税の同時変更、VATの税率変更幅及び軽減税率の変更等、事例毎の違いを考慮しつつ、欧州におけるVAT税率変更の効果について実証的な分析を行い検討する。
付表
脚注
[1]SNA・四半期ベースでは確認しづらいが、図表4-1の通り、月次の家計調査ベースでみると1989年の消費税導入時においても異時点間の代替行動が生じていた可能性が確認できる。
[2]イギリスの民間調査機関のCentre for Retail Researchの調査(2011)では、小売店の64%が税率変更の最初の月に税率変更のほとんどもしくはフルに価格転嫁する予定としている。したがって、税率変更前の価格転嫁については定量的な分析が必要といえる。
[3]CPIでは品質一定のものを定点観測しており、セール等短期間の特売の価格の情報が反映されない。日経・東大物価指数では特売も対象としており、特売の場合、品質の異なる廉価品なども対象となる。
[4]対象国は、オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリスの24カ国。
[5]この点についてはUnconventional Fiscal Policy(非伝統的財政政策)として指摘されている(D’Acunto, Hoang and Weber(2018))。
[6]さらに、歳出削減(公共事業費等で約4兆円)も同時に実施されている。
参考文献
- 五十嵐文彦(2012)「イギリス税制視察の報告~付加価値税制の現状と改革への挑戦」、ファイナンス、2012年11月号.
- 小巻泰之(2015)『経済データと政策決定』、日本経済新聞出版社.
- 鎌倉治子(2008)、「諸外国の付加価値税(2008年版)」、国立国会図書館調査及び立法調査局『基本情報シリーズ①』.
- 高橋哲彰、菊池紘平、井上里菜(2015)「欧州諸国に学ぶ駆け込み・反動の抑え方-消費増税の価格転嫁に日欧の差-」、日本経済研究センター「経済百葉箱」第81号、2015年4月8日.
- 日本銀行(2014)「金融経済月報」、2014年3月12日.
- 日本総研(2013)「欧州の事例から読み解く消費増税の影響」、Research Eye、No.2013-018、2013年9月24日.
- 日本経済研究センター(2014)「消費再増税「1%ずつ」検討を」、2014年10月.
- 森信茂樹(2014)「価格の一斉改定、日本特有」、日本経済新聞「経済教室」、2014年2月24日.
- Alm、 James and Asmaa El-Ganainy, “Value-added Taxation and Consumption,” Tulane University Economics Working Paper 1203, July 2012
- Carare,A. and Danninger, S. (2008), “Inflation Smoothing and the Modest Effect of VAT in Germany,” IMF Working Paper, WP/08/175.
- Cashin, D. and Unayama, T.(2011), “The Intertemporal Substitution and Income Effects of a VAT Rate Increase: Evidence from Japan,” RIETI Discussion Paper Series 11-E-045, April 2011.
- Centre for Retail Research(2011), “VAT HIKE TO 20%: Effects on Retailers and Consumers”, http://www.retailresearch.org/vatincrease.php
- Francesco D’Acunto, Daniel Hoang, Michael Weber (2018), “Unconventional Fiscal Policy,” NBER Working Paper No. 24244
- European Commission (2017), "VAT ratee applied in the member states of the European union", Situation at 1st January 2017.
- Office for National Statistics (2011), “Impact of the VAT increase on the CPI”
 小巻 泰之 大阪経済大学 経済学部教授
小巻 泰之 大阪経済大学 経済学部教授
1962年生まれ。2001年筑波大学大学院博士課程単位取得退学。ニッセイ基礎研究所、大蔵省財政金融研究所客員研究員、日本大学経済学部教授などを経て、2018年より大阪経済大学経済学部教授。専門は経済統計、経済政策、地域経済。
著書:『経済データと政策決定――速報値と確定値の間の不確実性を読み解く』(日本経済新聞出版社、2015年)、『世界金融危機と欧米主要中央銀行――リアルタイム・データと公表文書による分析』(共著、晃洋書房、2012年)など。