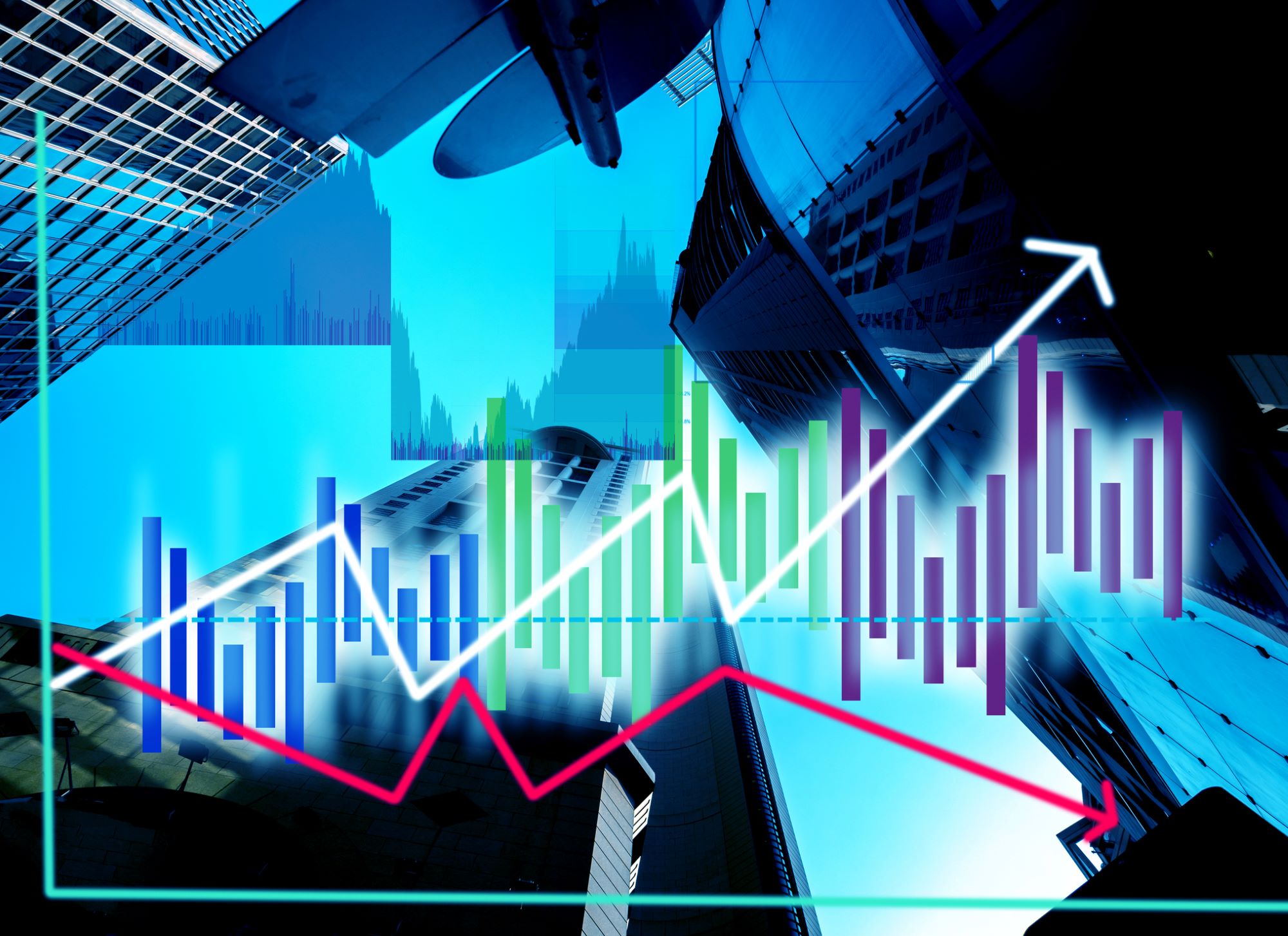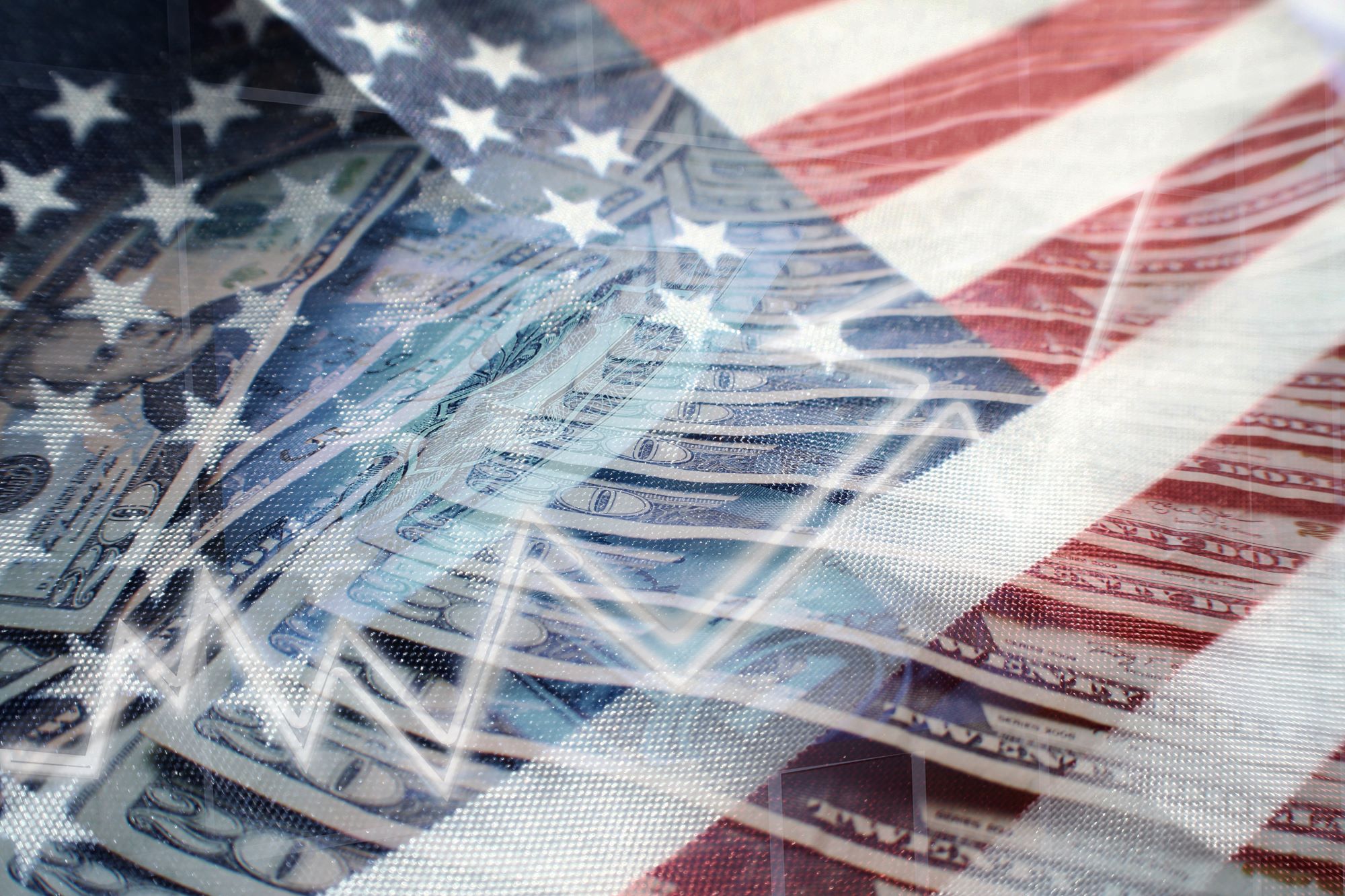3.「政治主導」時代の世襲議員――「官主導」との関係
「官主導」から「政治主導」への転換の必要性が唱えられるようになってすでにだいぶ経つ 7 。理由としてよく挙げられるのは、民主主義の審査を受けていない官僚が国を実質的に動かすのはおかしい、前例踏襲主義の官僚では変動の時代に対応できない、などである。そもそも本当に官主導なのか、という点については政治学者の間でも意見が分かれており検討の余地があるが、いずれも正当な指摘である。
政策面における「政治主導」の実現のため何より必要なのは、指導力や知見に富み、有権者の多様な支持を集め、高い政策形成能力を持った人材が政治のリーダーシップを握ることである。議院内閣制においては、政治の行政に対する強い統制権が与えられており、官僚組織に授権しつつもうまくコントロールする最低限の手段は、政治に与えられているはずである。もちろん法制度的に足りないものがあれば補っていく必要があるが、そうした法的手段を創る権能自体も政治が有している。
すでに見てきたように、議員、特に政府および与党幹部に世襲議員が占める割合が極めて高くなっている。本稿後半では、こうした状況が、官主導に代わるべき政治主導の時代にどういう意味を持つかについて見ていきたい。
(1) 民主主義的正統性をどう考えるか
「官主導」の最大の問題として指摘されているのは、民主主義的な正統性を持たない官僚が国家運営の実質的な主導権を握ることである。そうだとすれば、「政治主導」の時代に求められるのは、民主主義的プロセスを経て選ばれた議員が、内閣などを通じ官僚組織をガバナンスしつつ、政策形成を主導していくこととなる。行政府に入った議員たちには、民主主義過程を通じて吸収される多元的な価値観や利益を代弁し、政策に反映していくことが求められる。
他方、世襲議員批判に対する反論の最大の論拠となっているのも、世襲議員は選挙を経て選ばれている、という点である。つまり民主主義的正統性である。有権者が真に世襲議員を望まないのならば世襲議員は選挙で選ばれないはず、だから第三者が口を挟むべきではない、というわけだ。特定郵便局長の世襲制に批判的だった小泉元首相が息子を世襲候補として立てた件にも、議員の場合は民主的な選挙によって選ばれるから特定郵便局長とは話が違う、という反論は可能である。
つまり、政治主導にとっても、世襲議員にとっても、議員が持つ民主主義的な正統性が最大の支えとなっているのである。だが、異様とも言える世襲議員の突出は、議員の民主主義的正統性に対し重大な問題を投げかける。果たして議員が十全に民主主義的プロセスを経て選ばれたのか、という点に疑義を生じさせるからだ。
たしかに日本の選挙制度は十分に民主的であり、その選挙で有権者の投票を得て勝利したという意味で、世襲議員も厳しい民主主義的プロセスを経たとは言える。しかし、強固な「三バン」を持つ世襲議員などが実際の選挙で非常に優位に立つことは、過去の世襲議員の当選率の高さなどから見て否めないだろう。候補者同士が対等な立場に立って競い合うという、民主主義的競争が十分に行われていない可能性がある。
さらに、すでに述べたように憲法上保障される参政権には「選ぶ権利」だけでなく「選ばれる権利」も含まれる。「選ばれる権利」が十全に保障されない国では、「選ぶ権利」も形骸化する。極端な例を挙げれば、昨年話題になったジンバブエの大統領選では立候補者がムガベ大統領1人であり、投票の85.5%の得票率で圧勝した。しかしこの選挙がいかに公明正大に行われていたとしても、ムガベ大統領に民主主義的な正統性を認める者はいないだろう。
現行の小選挙区制では政党の公認なしに候補者が当選することはほぼ不可能である。逆に、自民党か民主党の公認を受けさえすれば、当選確率は極めて高くなる。その公認の過程が民主主義的でなく、密室(党内)の血液検査(血筋検査)であったとすれば、「選ばれる権利」が十全に保障されたとは言えない。もちろん、民主党は結党以来公募制を盛んに用いており、自民党も最近ではよく公募を行っているが、実際に検証してみればわかるように、「出来レース」となっているものも多い。
「選ばれる権利」が制限されている状況では、「選ぶ権利」も、現実的に当選可能性のある候補者が2人に絞られた後に、非常に限定的に行使されるに過ぎない。世襲議員に反発を感じる有権者であっても、支持する政党の唯一の候補者が世襲候補であれば、その世襲候補に票を投じることも多いはずだ。
単純化した例で見てみよう。たとえば、次回選挙の際の最大の争点が、仮に消費税導入の可否だったとしよう。小選挙区制の下では2大政党制になるのが通常なので 8 、A党の候補Xが消費税導入を支持し、非世襲議員だったとする。B党の候補Yが消費税導入に反対し、世襲候補だったとする。そうなると、たとえ世襲議員に批判的な有権者であっても、消費税という最大争点で導入に反対していれば、いやいやながら世襲候補Yに投票せざるをえないだろう。
このように「国民が自ら代表を選ぶ」という民主主義の建前は、現行の選挙制度、政党制度の下ではその多くがフィクションと化している。小選挙区制度の下で有権者の多くは、二大政党内部において選ばれた2人の候補者のうちいずれを選ぶかの選択権しか与えられない。政党という憲法にも現れない組織の内部手続きが、非常に重要な影響力を与えているのである。政党内で世襲候補が選ばれやすいという状況があるとすれば、世襲議員の民主主義的正統性に大きな留保が付くことになる。
政治主導にとっても、世襲議員にとっても、民主主義的正統性は決定的な重要性を持つ。そうだとすれば今後は、政党内などにもオープンな民主主義過程を埋め込むことが重要となるであろう。また、民主主義的競争が公平かつ熾烈に行われるために、候補者間の競争条件などをなるべく均質化していく努力も必要となる。
(2) 官僚制との関係
政策形成の過程で、議員と共に重要な役割を担うのが官僚である。その主導権を官僚から議員(特に内閣)へというのが、官主導から政治主導へ、という議論の中心である。したがって、政治主導への途を考えるには、また、現時点で政治の中枢を担っている世襲議員の政策形成能力を考えるには、官僚制との新たな役割分担のあり方を常にセットで考えていかなければならない。
繰り返しになるが、官僚は民主主義的な過程を経て選ばれていない。国民に官僚を「選ぶ権利」は与えられていない。しかし、「選ばれる権利」を「(官僚に)なる権利」と読み替えれば、現時点では実は官僚の方が、議員よりも幅広い人材に門戸を開放していると考えることすら可能である。
大学を卒業し、国家公務員試験に通りさえすれば、誰でも官僚にはなれる。実際、省庁幹部の経歴を見てみれば、試験中心の採用であるため一部の大学の出身者に偏っているものの、生まれ育った家庭環境などは、世襲議員が突出する内閣閣僚や与党幹部より多様である。世襲官僚も、独自に特殊な試験を課していた外務省を除けば非常に少ない。省庁の中には所属職員の子弟の採用を内規で禁じているところもある。
宮崎市定氏の『科挙』(中公新書)によると、6世紀の隋で科挙が導入された背景には、世襲貴族が天子の周囲を固めて、天子が実権を握れない状態があったという。天子が世襲貴族と戦い、今でいう官邸主導の政策立案を進めるためには、幅広い階層から優秀な人材を募る必要があると考えられた。そういう意味では、今の日本の政策形成システムは、世襲議員中心の内閣や与党と、より幅広い人材のプールの中から試験で選ばれた官僚とが、微妙なバランスを保って相互に補完し合っているという見方すら可能である。
また、「官主導」の時代の議員は、政策形成については、官僚の書いたメモを読み上げていれば済んだ。しかし、政治主導の時代の議員は、官僚を逆に使いこなすことで政策を形成していく高い能力が求められる。政治主導の時代にふさわしい議員を増やすには、世襲経営者の分析が示唆するように、現職議員の子弟という狭い社会から選んでいるだけでは足りないだろう。官僚よりもはるかに幅広い人材のプールの中から激しく多面的な競争を経て、優秀な議員が選ばれるような仕組みが必要になる。
こうした実態をきちんと考慮せずに、やみくもに政治主導を推し進めたり、官僚に幅広い人材が集まるシステムを廃棄してしまうと、科挙制度導入以前の隋のように世襲議員ばかりが実権を握り、首相がリーダーシップを発揮しようとしてもそれをサポートする人材を確保できないという状況が生まれかねない。そういう意味では、官僚制に批判的な与党議員の中に世襲議員が目立つことは、単なる偶然ではないのかもしれない。
官主導から政治主導への転換が、隋での科挙官僚から世襲貴族への権限移転とならないようにするためには、官僚制と世襲議員の突出とをセットで改革していくことが必要である。その際に重要となる要素は、すでに述べてきたような、民主主義的正統性と多元性の確保、既得権益からの開放、そして激しい人材間競争の実現である。これらの要素の実現抜きに世襲議員が突出し続け、官僚に人材が集まらなくなれば、科挙制度が導入される以前の隋の状況に追いやられかねない。
次回は、こうした方向性を基に、あるべき改革の姿について、憲法論も含めて見ていくこととする。
7 私がここで言う「政治主導」とは「内閣(官邸)主導」のことであって、「与党主導」でも「政治家主導」でもないが、この点についての詳細な議論はここでは省く。
8 正確には、政治学において現実との整合性が強く実証されてきた「デゥヴェルジェの法則」は、小選挙区は2人の有力候補で争われると予見するだけで、必ずしも小選挙区での二大政党制の定着は予見していない。これは郵政民営化選挙の際の自民党の造反議員と「刺客」との対決などを見れば明らかであろう。