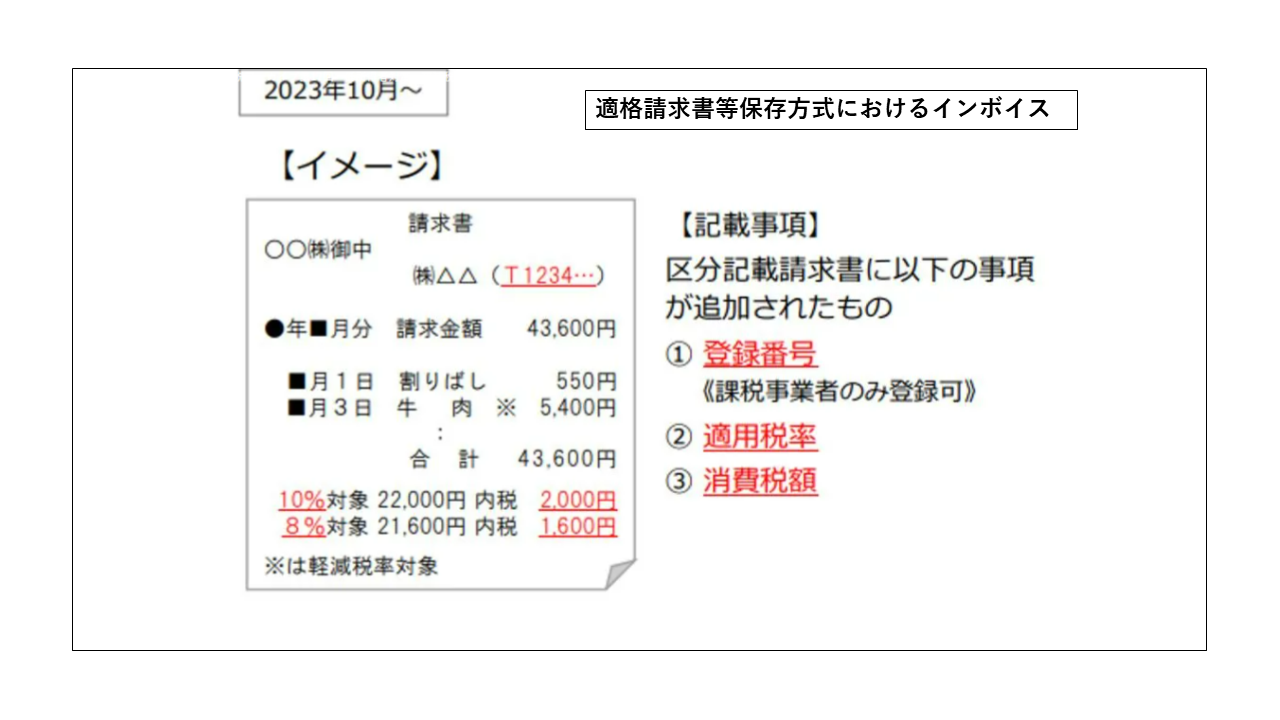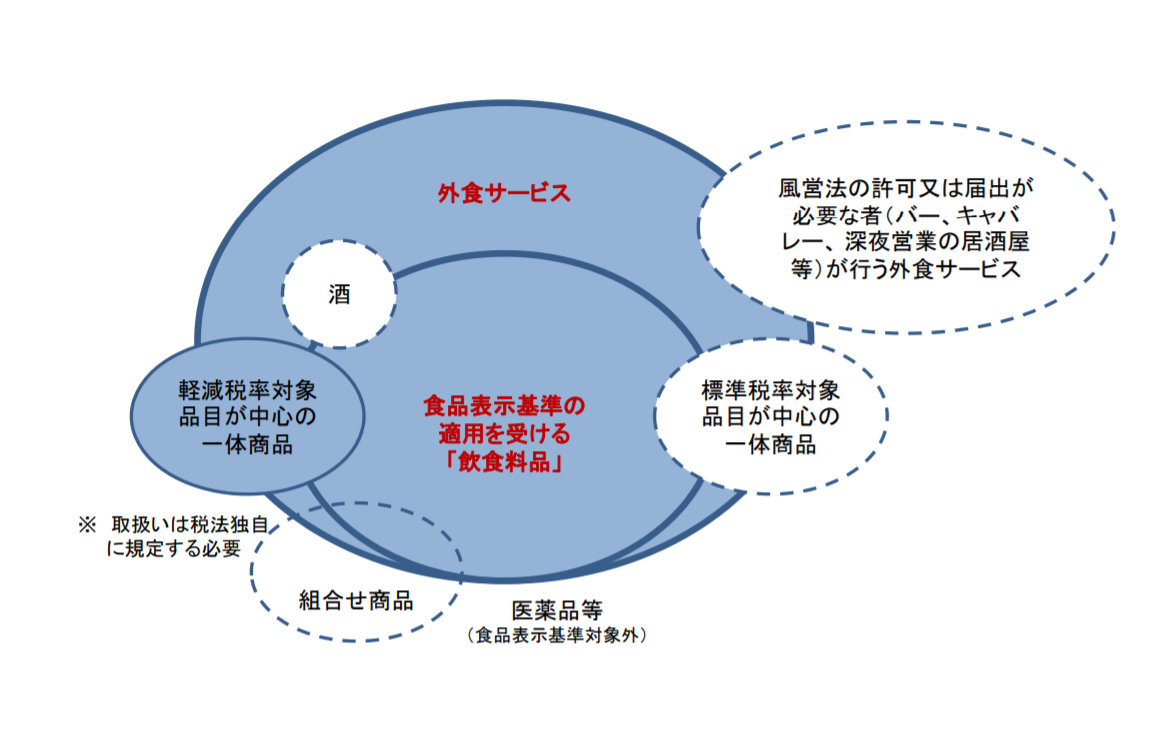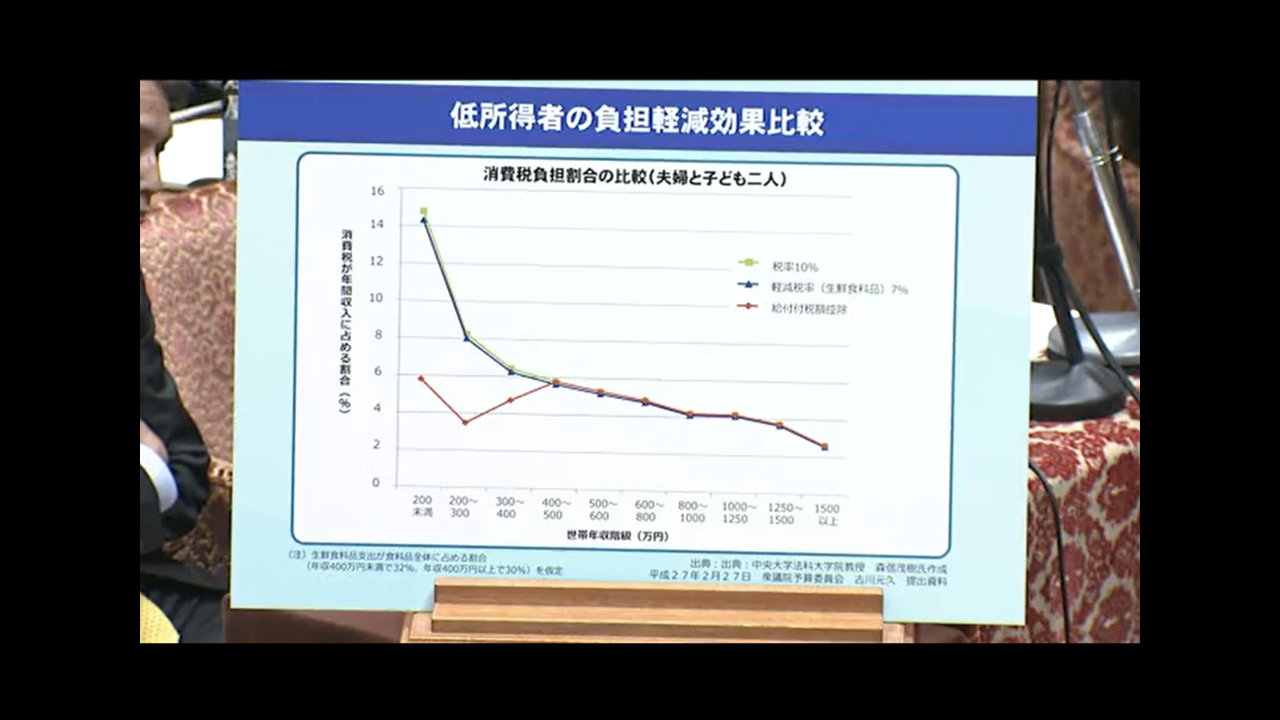7月16日、ニューヨーク州立大のステファニー・ケルトン教授が来日し、「現代貨幣理論(Modern Monetary Theory、以下MMT)について講演した。
MMT では、政府と中央銀行の統合勘定を前提とするので、政府の国債発行残高のうち日銀保有分は帳消しと観念する。その上で政府の借金は国民の資産の拡大ということで、政府は緊縮財政を行う必要はなく、民間経済に貯蓄の余剰(カネ余り)があるかぎり、赤字を出すような経済政策が望ましい、というものである。金融政策の有効性を否定し、すべては財政政策だといっている。
米国製の目新しい経済理論には目がない日本のマスコミは、ここぞとばかりに報道した。便乗する国土強靭化を主張する安倍政権元ブレーンも参加していた。消費増税が選挙の争点となる中、「増税は必要ない」という彼女の主張は大きな注目を浴びた。
彼女は、「日本で実験済み、これだけ財政赤字を拡大してもインフレが起きないのは、MMTが正しいことを証明している」「インフレになりそうになったら増税すればよい」とも発言していた。
筆者の印象は、フリーランチはないと批判されたラッファーカーブや、減税すれば人々の勤労意欲が上がり税収も増えるといったブードウーエコノミクス、最近では、ヘリコプターマネー、シムズ論の類だ、というものである。
積極的財政政策をうたう点は、ケインズ主義と似ているが、財政赤字は継続可能で赤字は貨幣の発行で埋めれば良いという点で異なっている。また、継続的な政策という点で、ヘリコプターマネーともニュアンスが異なる。
筆者の感じた違和感、問題点は次のとおりである。
まず、「インフレが生じ始めたら増税すればいい」というが、インフレはいったん始まると容易には沈静化できない。わが国のリフレ派を代表する日銀審議委員ですら「インフレが制御できなくなる」として反対している。
「『インフレが深刻になった場合には増税する』というトリガー条項を決めておけばよい」とも発言している(7月18日付日経朝刊)が、わが国憲法がとる租税法律主義を知らないたわごとだ(米国には租税法律主義はない)。
土地バブル時代に土地神話の根絶を狙った地価税が導入されたのは、土地基本法が制定された89年からなんと3年後の92年である。税制調査会での議論、法律の策定、衆参両院での国会審議などで時間がかかり、土地バブルが崩壊してからの導入となった結果、急激なバブル崩壊につながった。
財政政策として彼女が主張するのは、公共事業である。これも90年代のわが国の経験を知らない空想的な議論だ。バブル崩壊後に120兆円規模の減税と公共事業の拡大が、景気対策という名目で行われたが、いまだデフレ脱却すらできていない。効果や効率を考えずに行われた公共事業は、景気浮揚効果を持たず、維持・補修に四苦八苦しているというのが現状だ。
図表は、わが国一般会計の歳出・歳入の推移を描いたものだが、そのギャップ(いわゆるワニの口)は、バブル崩壊後とリーマンショック後に大きく開いている。これは景気対策としての公共事業の追加(歳出の拡大)と減税(歳入の減少)が行われたためで、結果として景気は回復せず、ワニの口はますます拡大した。

いずれにしてもMMTは、米国特有の状況下での話で、わが国とは事情や背景の異なるものだ。実験するのなら、以下の理由から、米国で行うべきだ。
第1に、米国では大統領選挙が始まっており、民主党の候補者の多くは、大きな政府を標榜している。彼らの公約である学生ローンの債務棒引き、完備されていない医療保険制度の構築などに必要な財源を正当化するためには、目新しい理論が必要だ。それをMMTに求めている。医療制度が、曲がりなりにも完備されているわが国とは、おおきく事情が異なる。
第2に、トランプ側にも事情がある。公約だったラストベルトへのインフラ投資は財源不足からとん挫している。さらに大規模な減税を行ったことから、大幅な財政赤字の懸念が生じている。「財政赤字はそれほど大きな問題ではない」といいたい事情がある。
いずれにしても、金融政策より財政政策・公共事業を優先させる「遅れてきたケインズ政策」は、人手が足りなくてボトルネックとなっているわが国には全くあてはまらない。打ち出の小づちからばらまかれる財源で公共事業を行なえば、一時的には潤っても、すぐさまその維持コストが便益を上回るという状況が生じ、公共投資の乗数効果はマイナスになってしまう。
わが国のリフレ派ですら反対しているので、議論の価値はない、ともいえるが、実験を行うなら、米国で行ってほしい。
(サムネイル:Stephanie Kelton, Professor of Economics and Public Policy, College of Arts and Sciences at Stony Brook University (May 2019))