
このレビューのポイント
医療人材育成のあり方について、研修医の患者有害事象とかかりつけ医の健康影響に焦点を当て、その課題を調査研究しました。今年度の総括として本Reviewにて以下について報告いたします。初期臨床研修制度の導入により、研修医の労働環境と教育体制が改善されましたが、過剰な労働負荷や心理的ストレスと患者有害事象が関連することが示されました。女性医師は男性医師に比べて有害事象が少ないことも明らかになりました。また、全国の人々を対象とした国民対象調査の結果、かかりつけ医を持つ人は健康的な生活習慣を持つ傾向があり、喫煙率が低く、定期的に運動し、適度な飲酒を心がけることがわかりました。がん検診受診率や新型コロナウイルスワクチン接種率も高く、メンタルヘルスにおける問題も少ないことが示されました。かかりつけ医制度の重要性が再確認されたことにより、今後はかかりつけ医体制を充実させることと、医療安全を改善させるための医療人への介入が急務となります。
R-2024-112
【全文PDFはこちら】
1.初期臨床研修制度導入の背景
日本に初期臨床研修制度が導入された背景には、医師免許取得後の医師が十分な研修を受けないまま医療現場に医師として自由に勤務することによる問題がありました[1]。研修制度が整っていなかった頃、医師国家試験合格者は、卒後に入職した病院での教育を十分に受けることができず、多くの医学部卒業生が選択した大学病院でのストレート研修システムでは、単一診療科目を集中的に研修することが強調され、高度専門医療に偏り、初期研修に必要な幅広い疾患への対応能力を学ぶ機会が不足していました。同時に、何十年もの間、研修医の無給・低賃金の環境が改善されることもなく、研修医の生活基盤が脆弱であったことも問題でした[2][3]。その結果、多くの新人医師が生活費を補うため所属内外問わず一般病院でアルバイト診療を行っていました。
このような環境下でのアルバイト診療では、患者安全の視点が欠如しており、若手医師が経験や技能に乏しいまま患者を診ることになり、医療事故や患者とのコミュニケーション不全が頻発しました[3]。当時の研修医による誤診や医療事故は社会問題となり、研修医の過労や教育体制の不備が背景にあり、それが医療事故や訴訟の増加につながっていたと考えられています。特に1999年は「医療安全元年」と呼ばれ、医療事故が社会的に大きく取り上げられるようになりました。
2.研修に専念させる制度の導入
こうした背景から、2004年に新しい初期臨床研修制度が導入されました。この制度では、医師免許取得後の2年間の研修を事実上必修化し、内科や外科、救急など複数の診療科をスーパーローテーションで学ぶ仕組みを採用しました。また、研修医には給与を支給し、アルバイト診療を禁止することで研修に専念できる環境を整備しました。具体的なスーパーローテーションでは、内科で最低24週間、救急医学で12週間、外科、産婦人科、小児科、精神科、地域医療でそれぞれ4週間の研修が必要とされています[4]。
この制度改革により、若手医師は適切な指導体制の下でプライマリ・ケアを中心とした基本的診療能力を身につけることが可能となり、質の高い医療提供につながっていると評価されていました[4][5][6]。この制度導入によって研修医の教育環境が改善され、指導体制も整備されました。また、その頃に並行して、病院の医療安全管理体制も強化され、誤診や医療事故を防ぐための取り組みが進められました。
3.研修医の医療過誤リスク
しかし、患者の権利意識の高まりもあり、医療訴訟件数そのものは2004年時点で10年前の約2.3倍に増加しており、単純に「減少した」とは言い切れない状況でした[7][8]。全体として見ると、研修制度導入後は教育や安全管理の面で一定の改善が見られるものの、訴訟件数への影響は複雑な要因が絡んでおり、一概に評価することは困難となっています。このような背景から、初期研修において、研修医による医療行為に関連する患者安全の実態はあまり評価されませんでした。患者安全での有害事象に関連した研修医の状況やそのリスクを増加させる要因についても、調査研究が不足していました。
一方、欧米での先行研究では、研修医は医療過誤の最大約80%に関与していることが示唆され[9]、過度の業務負担と監督の不足が研修医の医療過誤のリスクを増加させることが指摘されています[10]。その他、研修医以外の医療従事者を含む中ではバーンアウトや頻繁なハラスメントなどの心理的要因が医療過誤のリスクを増加させることが示唆されました[11]。
4.臨床研修医の刑事責任が問われた医療事故ケース
代表的な判例として、2018年に発生した医療事故で、臨床研修医が刑事責任を問われたケースがあります。この事件は、心臓手術を受けた患者が集中治療室(ICU)で低酸素脳症を引き起こし、重い後遺症を負ったことが発端です。患者は手術後、ICUで経過観察を受けていた際、研修医が患者の容体を観察していましたが、約13分間にわたり脳に酸素が供給されない状態が続きました。この結果、患者は脳に深刻なダメージを受け、回復の見込みがほとんどない重度の後遺症を負いました[12]。
この事故に対し、研修医は「業務上過失傷害」の罪で起訴されました。検察側は禁錮1年を求刑しましたが、裁判所は最終的に研修医に対し罰金20万円の有罪判決を下しました。裁判所は判決理由として、「研修医であっても医師として患者の診療に携わる以上、一定の注意義務を負う」と述べました。しかし一方で、この事故には他の要因も関与していたことも考慮されました。例えば、ICU内で使用されていたモニターのアラームが切られていたことや、ICU全体の管理体制に不備があったことなどです。また、この事故ではICUを管理していた麻酔科部長も責任を問われ、別途罰金30万円の略式命令を受けています。
この事件は、研修医個人だけでなく、医療チーム全体の責任や体制の問題についても議論を呼ぶ結果となりました。特に、研修医として経験が浅い段階でも法的責任が問われる可能性があることや、医療現場全体での安全管理体制の重要性について、多くの示唆を与える事例となっています。
5.女性医師の増加がもたらす患者安全への影響
近年注目されてきている患者安全に関連する要因として、医師の性別があります。欧米の研究によれば、女性医師は男性医師と比較して患者の死亡率や再入院率が低いことが示されています[13][14]。女性医師は予防医療(カウンセリングやフォローアップの手配)を提供する可能性が高く、患者中心のコミュニケーション(積極的なパートナーシップ行動、感情に焦点を当てた患者対応、長い患者訪問時間)を行う傾向があると示唆されています。これらの要素が、性別による医療の質・安全の差異を説明する一因となっている可能性があります。
しかし、2022年における日本の医師に占める女性の割合は24%であり、他のOECD諸国と比較して低い水準となっています[15]。2018年には、医学部入学試験における女性受験者への差別が顕在化し、教育機会の不平等が問題視されました。この非倫理的な措置の背景には、妊娠・出産・育児・家庭活動に伴う女性医師の職場離脱による医師不足を招く懸念が存在していましたが[16]、この組織的な女性差別が明るみに出た後、該当する大学では合格した医学生の男女比率が逆転しました[17]。この新しい時代の医学生がまだ医師として活動を開始していないため、キャリアの初期段階における女性医師の能力を支援するための体制が求められます。さらに、日本の研修医においても性別と有害事象リスクとの関連性を明らかにすることが重要です。
6.重大な有害事象を経験した研修医は全体の約1割
これらの状況を鑑み筆者らは、患者有害事象を経験した研修医の背景を精査しました。2023年1月17日から30日にかけて実施された基本的診療能力評価試験[i]と連動して行われた調査データを解析対象とし、全国の662の病院から研修医が参加し、インフォームドコンセントを取得の上で合計9,011人が試験に臨みました。そのうち、全国の612の病院から6,063人の研修医が調査に参加しました。
ここでの有害事象とは、研修医が行った医療過誤に起因する患者の死亡または重大な後遺症として定義され、二値変数(0または1)として分析されました。データ解析には混合効果ロジスティック回帰モデルを適用し、個別の要因および病院の要因を調整しました。
内訳としては、6,063人の研修医のうち、1,934人(32%)が女性で、4,129人(68%)が男性でした。3,142人(52%)が初年度の研修医であり、2,921人(48%)が2年目の研修医でした。月に6回以上の救急外来夜勤(n=564、9%)、週に80時間以上の勤務(n=796、13%)、平均して1日あたり15人以上の入院患者を担当する(n=128、2%)などの労働負荷が報告されました。また、燃え尽き症候群(n=1,042、17%)、看護師による研修医への行動(n=1,945、32%)、指導医による行動(n=1,986、33%)などの精神的負担も報告されました。
合計752名(全体の12%)の被験者が、過去1年間に医療ミスによる重大な有害事象を1件以上報告しました。これに関連して、研修医の性別が女性であることが有害事象リスクの低減と関連していることが示されました(調整オッズ比 0.74, 95%信頼区間: 0.62, 0.89)。
また、月6回以上の救急外来夜勤という労働負荷は、有害事象のリスクを増大させることが示されました(調整オッズ比1.31,95%信頼区間:1.09,1.57)。一方で、週45~79時間の勤務は、週45時間未満の勤務と比較して有害事象の発生が少ないとする結果も認めました(調整オッズ比0.59,95%信頼区間:0.41,0.85)。
すべての心理的ストレス要因は有害な出来事のリスク増加と関連していました。具体的には、看護師によるハラスメントの調整オッズ比は1.23(95%信頼区間:1.01,1.49)、指導医によるハラスメントの調整オッズ比は1.36(95%信頼区間:1.12,1.64)、燃え尽き症候群の調整オッズ比は1.34(95%信頼区間:1.10,1.64) でした。
病院要因と有害事象の関連性についての解析では、病床あたりの入院患者数が100人増加することがリスクの0.95%増加に寄与していることが示されました。その他の要素、すなわちベッド数あたりの救急車受け入れ数、外来受診患者数、救急受診患者数、医師数、および看護師数と有害事象との間には、有意な統計的関連は認められませんでした。
7.医師の性別と患者安全の関係
この研究では、上記と併せて女性研修医は有害事象との関連が少ないことが確認されました。日本での我々の発見は、女性医師は男性医師と比較して患者の有害事象発生率が低いことと関連しているという、欧米での知見と一致しています。
米国の大規模データによると、入院した約158万人の高齢患者のうち、女性医師によって治療された患者の30日死亡率は11.07%であり、男性医師によって治療された場合の11.49%よりも0.42%低いことが示されました[18]。また、治療後に再入院した約154万人の患者の治療担当医を調べた研究では、当該患者の15.02%が女性医師によって治療され、男性医師によって治療された患者の15.57%よりも低い結果となっていました。
同様に、外科医の性別が患者の術後転帰に影響を与える可能性も示されています。2023年に発表された米国医師研究では、65歳以上の約300万人を対象に、女性外科医が執刀した患者の術後30日死亡率が男性外科医より低く、特に女性患者と女性外科医の組み合わせで最も低い死亡率(1.3%)を示しました[19]。同じ研究者が同年に発表したカナダの医師研究でも、女性外科医が治療を行った患者では、術後90日および1年後の死亡や有害事象の発生率において男性外科医が治療した場合より低いことが確認されました[20]。
8.医師の性別による患者対応の違いについての先行研究
患者への対応が医師の性別でどう異なるかについて、さまざまな研究が実施されています。例えば女性医師は、患者中心のコミュニケーション(例:積極的なパートナーシップ行動、感情面への配慮、長時間の患者訪問)を主体的に行う傾向があることが示唆されています[21]。また、女性医師は日本の研修医の立場をより深く考慮する傾向があることや、多職種連携を円滑に行っている(看護師とのコミュニケーションが上手で情報を得やすい)事も考えられ、この点はさらなる研究が必要です。
また、女性と男性の医療倫理的価値観の相違も示唆されています[22]。女性は比較的強いケア志向を持ち、男性は比較的強い公正志向を持つと言われています[23]。ケア志向とは、関係性を重視し、他者への損害を回避することに基づく道徳的推論の一種であり、公正志向は公平性を重視することを含みます[24]。医療の場面において、ケア志向は患者やスタッフとの対人関係の重要性に焦点を当て、患者のニーズに耳を傾け、迅速に対応することで患者の病態を改善し、他の医療従事者と協力して働くことができます。一方、公正志向は、患者の診察や治療の機会の公平性を重視し、科学的エビデンスや原理原則に従う行動を優先しますが、患者や他の医療従事者との間でコミュニケーションの不一致を引き起こすことがあります。
9.研修医の労働負荷と有害事象の関連
著者らの研究では夜勤回数、1日の入院患者数などの労働負荷の量的側面と、ベッドサイド時間に費やす時間などの質的側面も考慮しました。ベッド数当たりの指導医数や看護師数を調整した多変量モデルにおいて、夜勤休日救急外来勤務が月6回以上の場合、月0〜2回の場合と比較すると、前者の方で有害事象が多いことが認められました。これは救急対応を要する重症患者を多く経験することまたは長い労働時間による影響の可能性があります。同様に、1日あたり患者のベッドサイドで労働する時間が平均70〜90分の研修医のほうが、平均10〜30分の研修医と比較した場合に、より有害事象が多いことが認められました。これはベッドサイドでの医療管理を要する重症患者を受け持つことに関連する可能性があります。一方で、1日あたり患者のベッドサイドで労働する時間が平均10〜30分の研修医は、患者ケアのチームメンバーとして十分な役割を与えられていない可能性もあります。
一方、週45〜79時間の労働時間の研修医と比べて、45時間未満の労働時間の研修医では有害事象が多いことが示されました。この結果には議論の余地がありますが、労働が極端に少ない研修医では不十分な労働時間による研修不足が関連している事が推測されます。近年の働き方改革によって研修医の労働条件も改善されつつありますが、単に労働時間を短くする事だけでは不十分であり、研修内容について更なるブラッシュアップが必要です[25]。
10.ハラスメントおよび燃え尽き症候群と患者安全リスク
看護師や指導医によるハラスメントおよび燃え尽き症候群など、様々な心理的ストレスが有害事象のリスクを増加させることが示されました。厚生労働省は、燃え尽き症候群を「仕事や活動に対する快適な認知と態度が失われた状態」と定義しています[25]。中国で実施された医師および看護師を対象とした先行研究では、参加者の26%に燃え尽き症候群が見られ、これは医療ミスと有意に関連していました[26]。我々の研究では、男性のほうが燃え尽き症候群を経験する可能性が高くなっていましたが、全体的な燃え尽き症候群の割合は先行研究よりも低くなっていました。その理由は、我々の研究が医師に限定されている点と、日本の研修医は2019年に導入された労働基準法改正の主要な対象となっており、この改正が労働環境改善をもたらしている可能性が挙げられます。
我々の研究結果は、ハラスメント等の心理的負担が望ましくない医療結果のリスクを増大させるという過去の研究と一致しています[11]。その研究では、職務関連のハラスメント、個人関連のハラスメント、身体的威圧によるハラスメントが有意な因子として示唆されています。また、我々の研究では、研修医が受けるハラスメントの割合は約30%であり、これは前述の先行研究との類似の割合を示しています。特に男性研修医は、看護師(男性36.5%、女性33.2%)および指導医(男性40.0%、女性28.4%)からのハラスメントに直面する頻度が、女性研修医より高いことが明らかになりました。医療現場以外でも、研修医の採用面接では、女性受験者は点数が高くなる傾向があるともいわれており、受験者の印象、身だしなみ、言葉遣い、コミュニケーション力などが関連しているかもしれません。
日本においては、医師は患者治療における責務やリーダーシップ役割への期待から、医療ケアの階層で最上位に位置付けられていると指摘されています[27]。そのため、医師が他の医療従事者からハラスメントを受ける可能性は低いかもしれません。しかし、女性研修医と比べて、なぜ男性研修医が看護師や指導医からハラスメントを受ける頻度が高いのかは、明確ではありません。先行研究によれば、男性は女性の多い職場環境ではハラスメントのリスクが高まる一方で、男性の多い環境ではそのリスクが増加しないとされています。一方、女性はいずれの環境でもハラスメントのリスクが高くならないことが示されています[28]。同環境下での女性研修医の行動や言動などに、男性研修医のハラスメントリスクを減らす鍵があるかもしれません。今後の医療安全のためにも、なぜ男性研修医は職場でハラスメントのリスクが高いのかについて、更なる研究が必要です。
11.かかりつけ医の機能
かかりつけ医は「健康に関することをなんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師」と定義されています[ii]。また、プライマリ・ケアは「患者の抱える問題の大部分に対処でき、かつ継続的なパートナーシップを築き、家族及び地域という枠組みの中で責任を持って診療する臨床医によって提供される、総合性と受診のしやすさを特徴とするヘルスケアサービス」と定義されています[iii]。
著者らは、かかりつけ医を持つことが健康に関連する生活習慣や受療行動とどのような関連があるかを調べました。特に喫煙、飲酒、運動の生活習慣、睡眠、がん検診受診、新型コロナウイルスワクチン接種、新型コロナウイルス感染における入院、メンタルヘルスとの関連について定量的に評価しました。全国の人々を対象にしたJACSIS調査[iv]を実施しました。その調査票から関連する質問データを抽出し、その回答を適切な交絡因子で調節し、ロジスティック回帰分析を行いました。
調査結果として、かかりつけ医を持つことが健康に与える影響が明らかになりました。かかりつけ医を持つ人は、持たない人に比べて健康的な生活習慣を持つ傾向にあります。特に、喫煙率が低く、定期的な運動を行う割合が高いことが示されました。飲酒に関しては、かかりつけ医を持つ人の方が適度な飲酒を心がける傾向が見られました。
併せて、かかりつけ医を持つ人は、がん検診を受ける割合が高いことがわかりました。特に、乳がんや大腸がんの検診受診率が顕著に高く、新型コロナウイルスワクチン接種率も高いことが示されました。メンタルヘルスに関しては、かかりつけ医を持つ人はメンタルヘルスに関する問題を抱える割合が低く、特に、うつ病や不安障害の発症率が低い結果となり、新型コロナウイルス感染における入院率も低くなっていました。
これらの結果から、かかりつけ医を持つことが健康に与えるポジティブな影響が明らかになりました。かかりつけ医制度の重要性が再確認されるとともに、今後の医療政策においても重要な役割を果たすことが期待されます。この調査により、かかりつけ医を持つことが健康に与える影響の詳細が提示され、かかりつけ医制度の促進を促すべきエビデンスとなっています。
12.まとめ
医療人材育成のあり方について、研修医の患者有害事象とかかりつけ医の健康影響に焦点を当てました。病院診療の現場では初期臨床研修制度が導入され、医師養成の基軸となりました。その制度導入の背景には、研修医の過酷な労働環境と不十分な教育体制がありましたが、2004年の制度改革により、研修医は給与を受け取りながら複数の診療科で研修を受けることが可能となり、学習環境が向上したとされます。しかし、患者有害事象を経験する研修医の背景要因についての研究はなかったので、今回我々は初期臨床研修を対象にアンケートによる調査研究を実施しました。そのデータ分析結果によると、女性医師は男性医師に比べて有害事象が少ないことが示されました。また、研修医の過剰な労働負荷や心理的ストレスが有害事象のリスクを高めることも示唆されました。一方で、週45時間未満の勤務時間や不十分なベッドサイド勤務時間などの研修時間不足も関連していました。これらについては早急な改善が求められ、今後は、研修医の労働環境と教育体制をさらに改善し、労働負荷や心理的ストレスを軽減させることで、患者有害事象を減らすことを目指すべきです。一方、プライマリ・ケアの現場では、かかりつけ医を持つことで、健康的な生活習慣が促進され、がん検診やワクチン接種率も高まります。また、メンタルヘルスの問題や新型コロナ感染による入院リスクも低減されることが明らかになりました。かかりつけ医制度の重要性が再確認された事で、かかりつけ医体制の整備や予防医療の推進により、更なる地域社会全体の健康水準の向上と、医療費の負担軽減に寄与するものと考えます。
参照
[i] https://jamep.or.jp/gm-ite/
[ii] https://kakarikata.mhlw.go.jp/kakaritsuke/motou.html
[iii] https://www.primarycare-japan.com/nursing.htm
[iv] https://jacsis-study.jp/dug/index.html
参考文献
[1] 日本医師会. 医師養成についての日本医師会の提案 -医学部教育と初期臨床研修制度の見直し- 2011; Available from:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/043/siryo/__icsFiles/afieldfile/2011/03/08/1301894_9.pdf
[2] 植山直人. 無給医問題に関する考察 ~歴史と背景および求められる対応~ 2019; Available from: https://doctor-work.com/wp-content/uploads/2019/08/451b2725c20abb7e4ec8c62d7c4fc3f8.pdf
[3] 厚生労働省. 医師臨床研修制度の変遷.2025;Available from: https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/rinsyo/hensen/
[4] 医師臨床研修必修化 日本の医療はどう変わる?.2004;Available from: https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/old/old_article/n2004dir/n2566dir/n2566_04.htm
[5] 研修医とは?制度や期間、給料、研修先の選び方について詳しく解説.2024;Available from: https://doctor.mynavi.jp/column/medical_intern_period/
[6] 厚生労働省. 医師臨床研修指導ガイドライン2023 年度版.2023;Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001173603.pdf
[7] Tokuda Y, Kishida N, Konishi R, Koizumi S. Cognitive error as the most frequent contributory factor in cases of medical injury: a study on verdict's judgment among closed claims in Japan. J Hosp Med. 2011;6(3):109-14.Epub 20100817
[8] 日本臨床麻酔学会. 医療事故の法と事故調査のあり方.2016; Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsca/36/7/36_710/_pdf
[9] Kirkman MA, Sevdalis N, Arora S, Baker P, Vincent C, Ahmed M. The outcomes of recent patient safety education interventions for trainee physicians and medical students: a systematic review. BMJ open. 2015;5(5):e007705.
[10] Singh H, Thomas EJ, Petersen LA, Studdert DM. Medical errors involving trainees: a study of closed malpractice claims from 5 insurers. Archives of internal medicine. 2007;167(19):2030-6.
[11] Al Balushi AA, Alameddine M, Chan MF, Al Saadoon M, Bou-Karroum K, Al-Adawi S. Factors associated with self-reported medical errors among healthcare workers: a cross-sectional study from Oman. Int J Qual Health Care. 2021;33(3).
[12] 医療安全推進者ネットワーク. 医療判決紹介. 2005; Available from: https://www.medsafe.net/precedent/hanketsu_0_50-1.html
[13] Tsugawa Y, Jena AB, Figueroa JF, Orav EJ, Blumenthal DM, Jha AK. Comparison of Hospital Mortality and Readmission Rates for Medicare Patients Treated by Male vs Female Physicians. JAMA Intern Med. 2017;177(2):206-13.
[14] Saka N, Yamamoto N, Watanabe J, Wallis C, Jerath A, Someko H, et al. Comparison of Postoperative Outcomes Among Patients Treated by Male Versus Female Surgeons: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Surg. 2024;280(6):945-53. Epub 20240510.
[15] OECD. Health Statistics 2023. 2023; Available from: https://web-archive.oecd.org/temp/2024-02-21/78817-health-data.htm
[16] Kinoshita S, Kishimoto T. Increase in the number of female doctors and the challenges that Japan's medical system must face. Glob Health Med. 2024;6(6):433-5.
[17] Watari T, Mizuno K, Sakaguchi K, Shimada Y, Tanimoto Y, Nakano Y, et al. Gender Inequality Improvement in Medical School Admissions in Japan. J Womens Health (Larchmt). 2024;33(3):339-44. Epub 20231109.
[18] Miyawaki A, Jena AB, Rotenstein LS, Tsugawa Y. Comparison of hospital mortality and readmission rates by physician and patient sex. Annals of Internal Medicine. 2024;177(5):598-608.
[19] Wallis CJ, Jerath A, Ikesu R, Satkunasivam R, Dimick JB, Orav EJ, et al. Association between patient-surgeon gender concordance and mortality after surgery in the United States: retrospective observational study. BMJ. 2023;383.
[20] Wallis CJD, Jerath A, Aminoltejari K, Kaneshwaran K, Salles A, Coburn N, et al. Surgeon Sex and Long-Term Postoperative Outcomes Among Patients Undergoing Common Surgeries. JAMA Surg. 2023;158(11):1185-94.
[21] Roter DL, Hall JA. Physician gender and patient-centered communication: a critical review of empirical research. Annu Rev Public Health. 2004;25:497-519.
[22] Krupat E, Rosenkranz SL, Yeager CM, Barnard K, Putnam SM, Inui TS. The practice orientations of physicians and patients: the effect of doctor-patient congruence on satisfaction. Patient Educ Couns. 2000;39(1):49-59.
[23] Jaffee S, Hyde JS. Gender differences in moral orientation: a meta-analysis. Psychological bulletin. 2000;126(5):703.
[24] Gilligan C, Attanucci J. Two moral orientations: Gender differences and similarities. Merrill-Palmer Quarterly (1982-). 1988:223-37.
[25] 厚生労働省. 長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル. 2021; Available from: https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000693032.pdf
[26] Li Z, Liu L, Zhang X, Yan K, Wang X, Wu M, et al. Occurrence and associated factors of self-reported medical errors among Chinese physicians and nurses: a cross-sectional survey. Ann Med. 2025;57(1):2445187. Epub 20241226.
[27] 藤本学, 島村美香, 稲葉一人. 日本の医療現場における破壊的行動が医療者の適応状態および患者の安全に及ぼす影響. 臨床倫理. 2021;9:29-40.
[28] Salin D. Risk factors of workplace bullying for men and women: the role of the psychosocial and physical work environment. Scand J Psychol. 2015;56(1):69-77. Epub 20141020.





















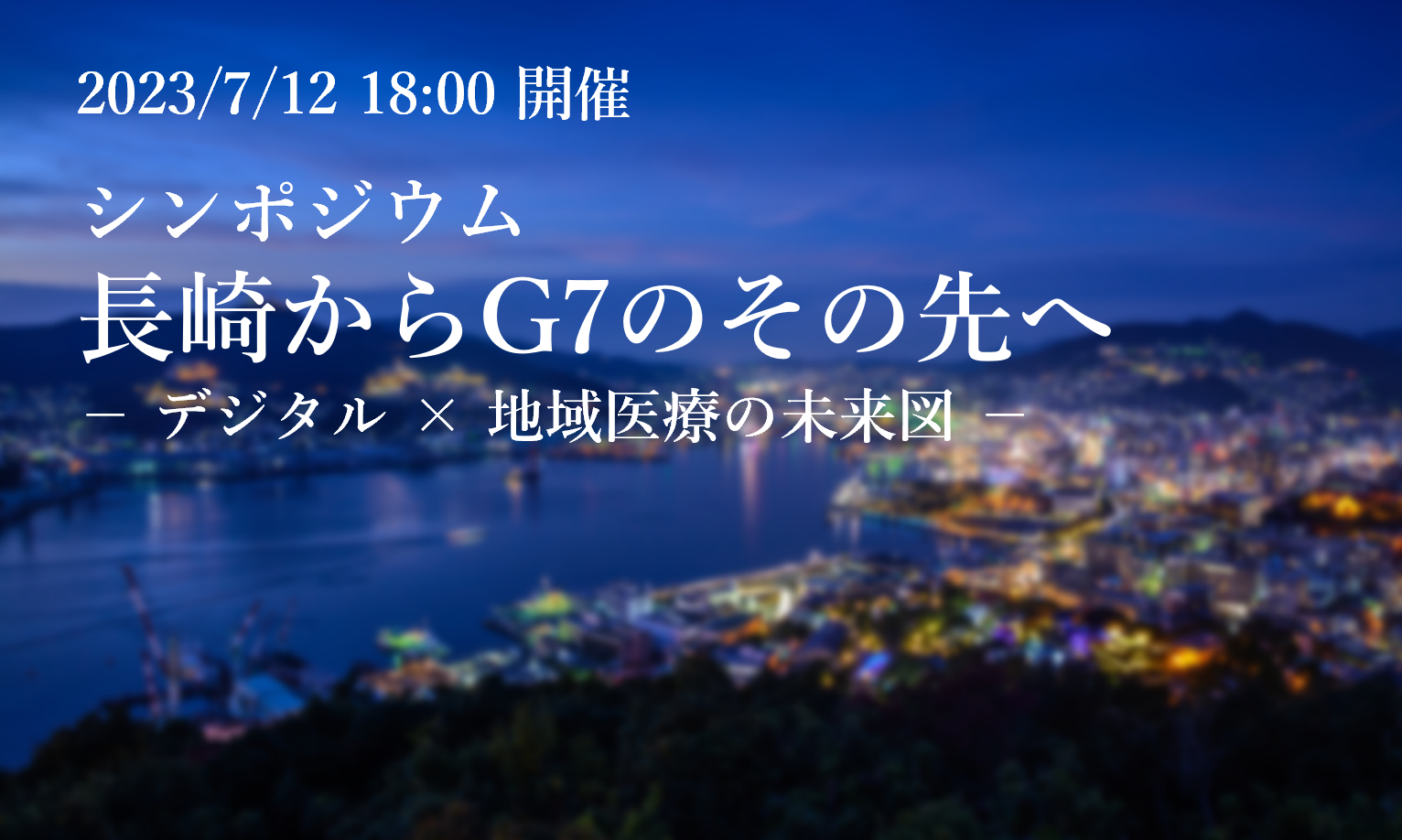





















































_jpg_w300px_h200px.jpg)












































