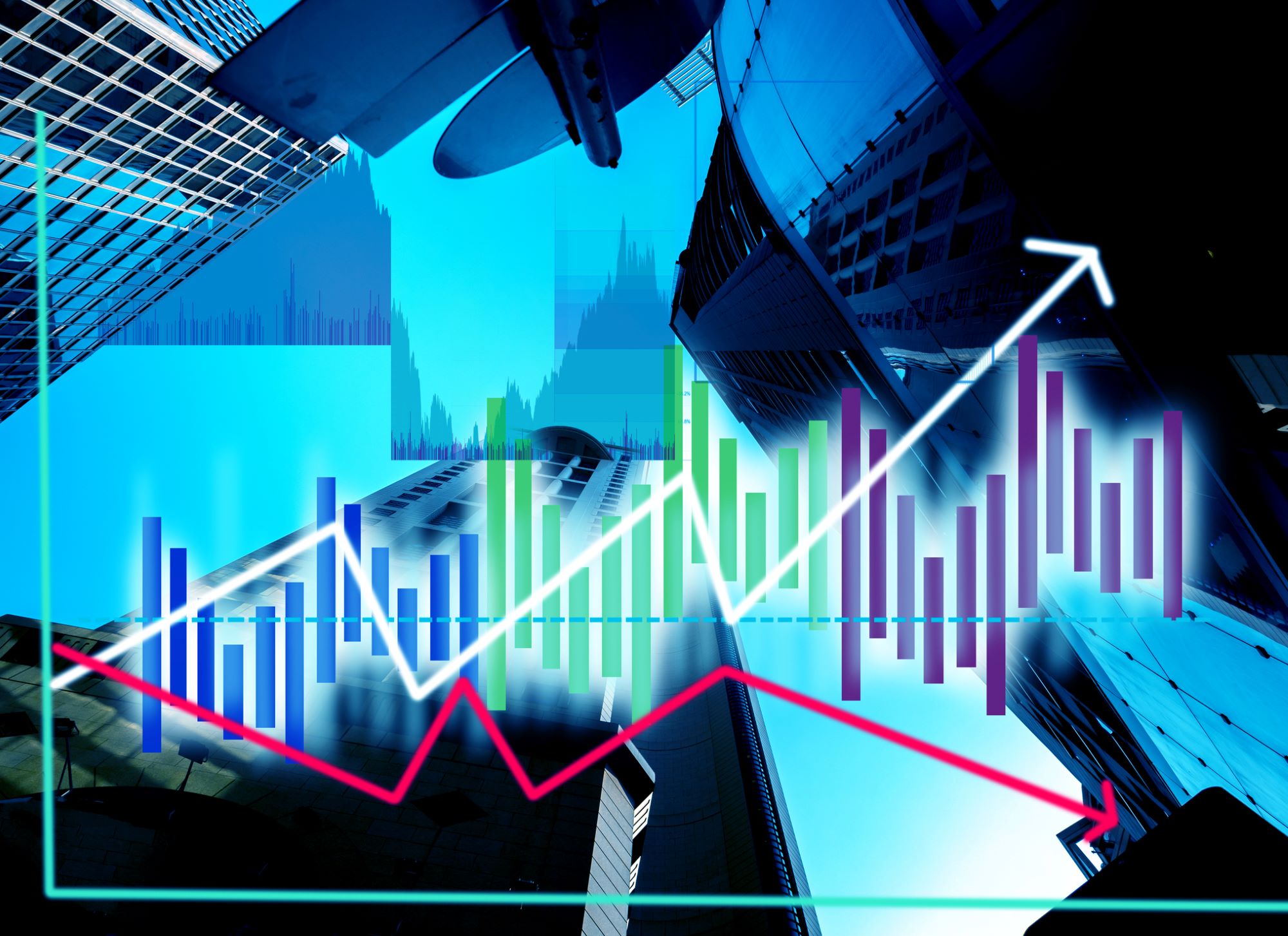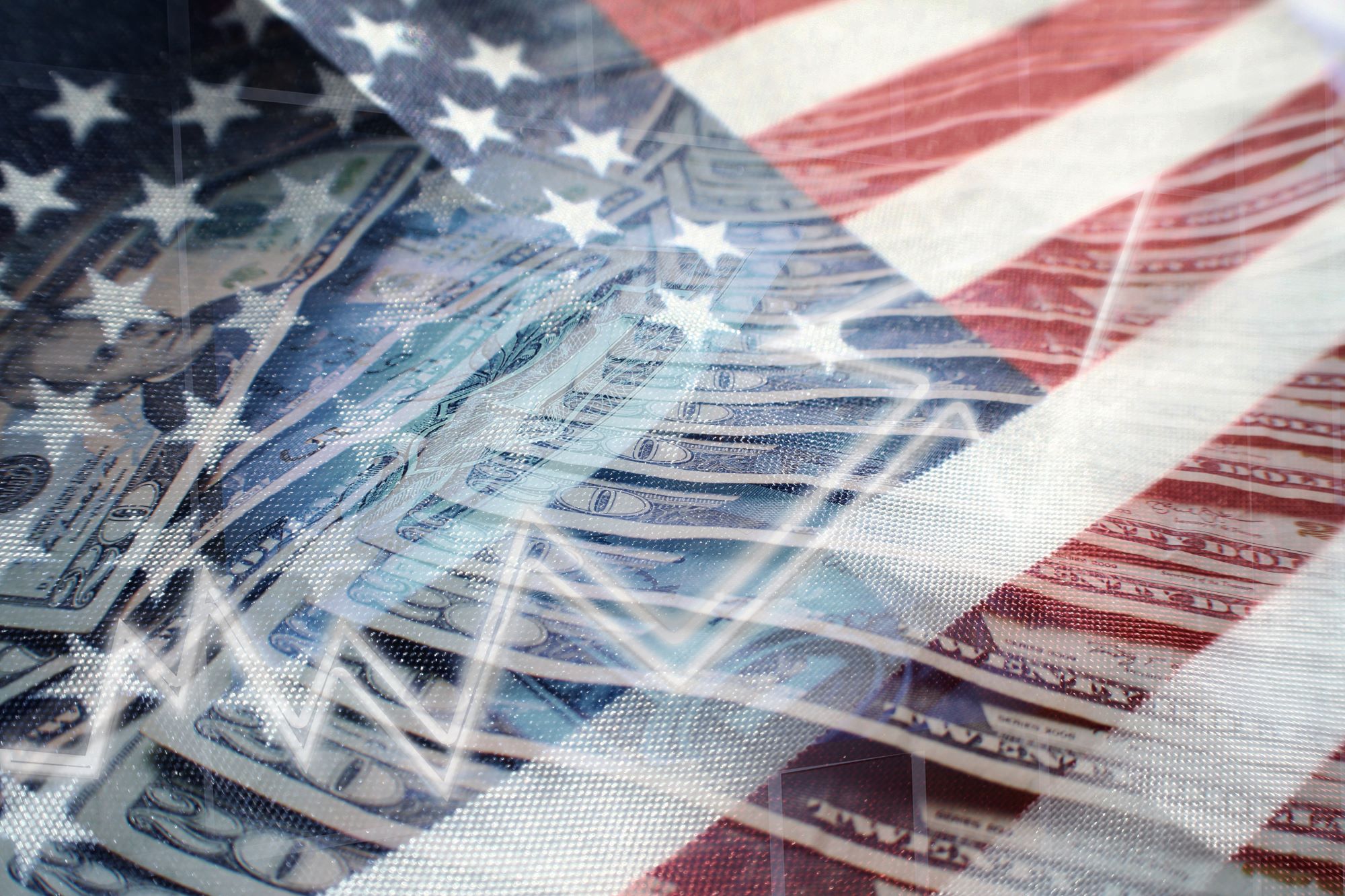![日本における二院制はどうあるべきか−−「カーボンコピー」論と「強すぎる参議院」論を超えて/[第2部]日本の二院制をどう考えるか:分析の視点](/files/research/Politics_and_Economy/20210329kato_2.jpg)
| 第1部:世界の中で見た日本の二院制(加藤創太、茨木瞬) I. 根強い二院制批判――「参議院無用論」から「強すぎる参議院」へ II.各国との比較で見た日本の二院制の位置づけ 第2部:日本の二院制をどう考えるか:分析の視点(加藤創太) Ⅲ.制度改革を行う上で考慮すべき視点 第3部:日本の二院制をどう変えていくべきか:政策提言(加藤創太) Ⅳ.日本の両院制のあり方――制度改革の方向性 Ⅴ.結び |
Ⅲ.制度改革を行う上で考慮すべき視点
それでは、日本の二院制はどう変えていくべきか? 維持すべきか?
従来の日本では二院制か一院制か、という議論が多かったが、上記で見てきたように、二院制の中にも様々な類型があり、政治過程で果たす役割も大きく異なってくる。二院制を維持する場合でも、法改正や運用を通じて、どのような二院制にしていくのか、という議論も非常に重要である。
一院制も二院制も、二院制の中の各類型も、民主主義の長い歴史の中で生き延びてきた制度であり、それぞれに長短があり、多面的な検討が必要だ。あるべき二院制あるいは一院制の姿を考える上で考慮すべき主要な視点を以下にまず整理した上で、今後のあり方を考えていく。
1.法的な視点――憲法、法律、規則、慣行 [1]
日本の二院制は憲法42条で規定されており、一院制に転換するためには当然、憲法改正が必要となる。衆議院の参議院に対する優越事項なども憲法で規定されているため、それらを変えるにも憲法改正が必要だ。他方、衆参両院の議員の選出方法、各院の運営方法などについては国会法や公職選挙法など法律レベルで多くが規定されており、法律改正によって制度改革できる範囲も大きい。さらに国会規則や国会運営上の慣行などによっても両院の運営は規律されており、そのレベルにおいても、両院の運営は大きく変化しうる。
憲法レベルの変更
日本における二院制のあり方につき提言するためには、したがって、法的にどのレベルまで踏み込むかについて意識的でなければならない。とりわけ憲法レベルまで踏み込むかは、大きな判断事項である。なぜなら、二院制の問題だけで憲法改正を行うのは、現実的に考えれば非常に難しいからだ。憲法改正の発議には両院の議員の三分の二以上の賛同が必要だが、衆議院はともかく参議院でそれが通るとは考えられない。
一院制への移行はわかりやすく歯切れが良いため、「改革派」を自称する政治リーダーがメディアなどで大きく打ち上げることは少なくない。しかし実際に一院制導入を目指して政治生命を賭ける政治リーダーの姿はいっこうに見られない。それどころか水面下では、一院制の導入に向けた超党派の動きや、自民党憲法調査会での参議院の機能の大幅な見直しの動きなどは、過去に徹底的に政治的に潰されてきた。
こうした中、二院制に関する憲法規定の修正が今後実施されるとすれば、包括的な憲法改正が検討されるような場面でその一部として取り込まれるようなケースくらいである。本稿ではそういった場合に備え、憲法レベルでの改正については、改正の方向性を提案するに止める。
法律・規則・慣行レベルの変更
法律・規則・慣行レベルでは、日本の二院制を一院制に移行することはできない。しかしリップハルトの類型からもわかるように、同じ二院制の中でも様々な類型があり、それぞれ政治過程に果たす機能は異なってくる。一院制に近い機能を果たしている二院制もある。日本のあるべき二院制の機能を考えた上、その実現に向けて、法律や慣行レベルで調整できる範囲は小さくない。
さらに慣行になると法律に比べて拘束力が弱いため制度改革の実効性が乏しいという見方があるかもしれない。しかし比較制度研究では(Aoki 2001など)、法律と慣行を連続的に取り扱っており、法律より実効性が強い慣行も多い。特に立法府の場合は法律を自ら改廃する権能を有しているため、法律だからといって強い拘束力を持つわけではなく、立法府内における合意に基づく慣行と法律とでは、その拘束力の差は他のケースと比べ小さい[2]。
本稿では法律や慣行や与野党合意を主なツールとして、二院制のあり方を変えていく途を考えていく。
2.実質的な視点――権力の集中と分散のバランスのあり方
二院制と一院制の長短については表1に主なものをまとめてある。根幹にあるのは、権力の集中と分散のトレードオフだ。このトレードオフは、同じ二院制でも「弱い二院制」(権力集中)と「強い二院制」(権力分散)との間にも当てはまる。
表1:二院制と一院制の長短

田中喜彦 2003「二院制をめぐる論点」『調査と情報』第429号を基に、著者が他文献から一部を追加
一院制や「弱い二院制」のように第一院(下院)に権力が集中すれば、迅速な判断や果敢な改革は容易になる。市場経済のスピードに民主主義の意思決定のスピードが追いつかない近年の状況の中、より断固とした判断を短時間で実施しうる権威主義国家の、民主主義国家に対する優位も唱えられるようになった。また新型コロナ感染症対策でも、権威主義国家の方が果断な対策を素早く発動できるという指摘もされている。現代においても、権力集中の要請は大きい。
他方、民主主義政体の下での権力の集中は、「多数者の専制」など、歴史的にさまざまな悲劇を引き起こしてきた。冒頭に引用したフランス革命時のシェイエスらの影響で設立された一院制の国民公会は、多数派による「恐怖政治」を引き起こし、フランスはすぐに二院制へと移行している。近年でも、欧米の先進民主主義国家ではポピュリズムが拡がり、少数派の人権を侵害するような過激な発言を、政治リーダーが平然と口にするような事態が生じている。現代においても、権力分散の要請も大きい。
一院制と二院制――簡易なシミュレーションからの示唆
東京財団政策研究所の「政治のリスク分析」プロジェクトは、政治権力の集中と分散が政策にどのような影響を与えるかなどにつき、分析を行ってきた。プロジェクトでは(Kato 2018)、確率微分方程式にウィナー過程を採り入れて不確実性から生まれるノイズを模した上で、一院制と二院制とで国民全体の厚生がどのように変動するかについての簡易なシミュレーションを行った。
二院制を採用すると、第一院の極端な判断を監視し是正する機能を第二院が果たす反面、意志決定のスピードが遅くなり、ときに第二院の拒否権行使により膠着する。模式的なシミュレーションでは、たとえば以下のような結果が得られた。国民の厚生が全体のトレンド(傾向)から5%以上プラス・マイナス双方向に乖離する確率は、一院制では4.7%、二院制では0.62%となった。つまり一院制は二院制に比べ、国民全体の厚生を大きく改善できる可能性がある一方、大きく損なう危険性もある。
シミュレーション結果が示唆するのは、確率的には低い極端なケースが発生すると、一院制のパフォーマンスが一気に落ちうるということである。そういった極端なケースでは「多数者の専制」や「民主主義の悲劇」にもつながりかねない。たとえば周辺国から不当な攻撃を受けた直後に衆院選が行われれば、衆議院の構成は極端に右派に偏る可能性があり、政策も極端に右寄りに偏りかねない。二院制であれば、そういう時には参議院が衆議院の抑制役として機能する。
他方、二院制のパフォーマンスが大きく落ちるのは、衆参両院が拮抗し、政策形成が膠着状態(stalemate)になる場合である。金融危機やパンデミックなど緊急の対応が必要な状況で政治が膠着すれば、危機的な状態に陥りかねない。他方、二院間の構成の差異が小さくなると、膠着状態の可能性は低くなるものの、二院制のうちの第二院は第一院の冗長なカーボンコピーとなり、「無用の長物」化する。
一院制と二院制――既存の理論・実証研究からの示唆
政治学の研究においても、二院制と一院制とが立法に与える影響などについて理論・実証研究が進められてきた。すでにその一部は表1の中で紹介してあるが、本稿で今まで紹介してきた指摘とも概ね整合的である。
権力の抑制と均衡の観点からは、第二院(上院)の存在が、第一院(下院)での拙速で軽率な立法に対するチェック機能を果たすことが示されてきた(例 Cox & Tutt 1984; Tsebelis 1995, 1999,2002など)。また、議院内閣制の下では、内閣に対しては第一院より第二院の方が独立的な立場に立つため、内閣(行政府)に対するチェック機能も果たしうることが示されている。この点は、日本の文脈において竹中(2010)も指摘している。
二院制は政策の安定性や予見可能性を増すという理論・実証分析もなされている(Alt & Lowry 1994; Buttom et al. 2000など)。これは反面、革新的な政策の実施には一院制の方が向いているということにもつながりうる。他には、両院が政策形成でお互いに妥協するため、より効率的な政策が可能となるという分析結果(Tsebelis & Money1997)もあれば、両院での討議過程などを通じてより多くの情報が政策当局者に提供されるため、二院制の方がより良い政策につながるという分析結果(Lupia & McCubbins 1994; Rugers 1998)もある。
このように、拒否権プレーヤーの研究で有名なミシガン大学のジョージ・ツェベリス教授をはじめ、政治学の理論・実証分析は全般的には二院制(あるいは二院制の中での「強い二院制」)のプラス面を示唆するものが多い。
ただ、こうした二院制のプラス面は、両院の構成が十分に異なる場合のみ生まれるという分析もなされており(Krehbiel 1996; McCarty & Cutrone 2008)、これは先ほどのシミュレーション結果とも整合的だ。福元(2007)はこの点に関し、日本の衆参両院の議員構成や法案審議が異なっているかにつき、精緻な実証分析を行った。その結果は両者に違いはほとんどないというもので、そうであれば日本の二院制は無意味だという厳しいが説得力のある判断を福元は下している。
「第3部:日本の二院制をどう変えていくべきか:政策提言」に続く
<参考文献>
Alt, J. E. and R. C. Lowry. 1994. "Divided Government, Fiscal Institutions, and Budget Deficits: Evidence from the States." The American Political Science Review 88(4), 811-828
Aoki, M. 2001. Towards Comparative Institutional Analysis. Cambridge: MIT Press.
Bottom, W. P., C. L. Eavey, G. J. Miller, and J. N. Victor. 2000. “The Institutional Effect on Majority Rule Instability: Bicameralism in Spatial Policy Decision.” American Journal of Political Science 44(3): 523-540.
Cox, G. W., and T. N. Tutt. 1984. “Universalism and allocative decision-making in the Los Angeles County Board of Supervisors.” Journal of Politics, 46 (2) :546-55.
福元健太郎 2007.『立法の制度と過程』。木鐸社。
Kato, S. and M. Inui 2018. "Risk Analysis of Bicameralism.” A paper accepted and presented at the annual meeting of the Midwest Political Science Association.
Krehbiel, K. 1998. Pivotal Politics: A Theory of US Lawmaking. Chicago: University of Chicago Press.
Lupia, A., and M. D. McCubbins. 1994. “Who Controls? Information and the Structure of Legislative Decision Making.” Legislative Studies Quarterly 19(3): 361-384.
McCarty, Nolan, and Michael Cutrone. 2008. “Does Bicameralism Matter?” In B. R. Weingast, and D. Wittman (eds). The Oxford Handbook of Political Economy. Oxford UK: Oxford University Press.
竹中治堅 2010.『参議院とは何か 1946〜2010』。中央公論新社。
Tsebelis, G. 1995. “Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism, and Multipartyism.” British Journal of Political Science 25(3): 289-325.
Tsebelis, G. 1999. “Veto Players and Law Production in Parliamentary Democracies: An Empirical Analysis.” The American Political Science Review 93(3): 591-608.
Tsebelis, G. 2002. Veto Players: How Political Institutions Work. Princeton NJ: Princeton University Press.
Tsebelis, G. and J. Money. 1997. Bicameralism. Cambridge: Cambridge University Press.
[1] 竹中(2010)も、参議院改革は、憲法改正、法律改正、慣行の3つのレベルで考えるべきだと指摘している。
[2] たとえば1997年に橋本内閣の下で成立した財政構造改革法は、翌年には小渕内閣によって停止された。法律を改廃する権力を持つ与党政権では、自らを拘束する法律が作れない(「自らの手を縛れない」)ことを示した一例である。