
このレビューのポイント
少子高齢化が加速する中、特に地方における医療資源の効率的活用と医療アクセスの確保が喫緊の課題となっている。その中で、岡山県吉備中央町の産婦人科領域を含めたオンライン診療や遠隔的な分娩サポート対応事例を視察した。米国のバーチャル病院やProject ECHO、フランスの遠隔診療ブースなど海外の先進事例や失敗事例からの示唆を踏まえ、日本の状況に適応可能な政策提言として、オンライン診療の恒久的拡充、デジタルインフラへの投資、医療データ連携基盤の整備、地域医療人材の支援強化、ガイドライン策定とモデル事業の全国展開の5つの政策を提言する。これらを総合的に実施することで、人口減少下でも全国どこでも必要な医療が受けられる持続可能な体制の構築を目指すべきである。
|
はじめに |
はじめに
日本では少子高齢化が加速し、人口減少に伴う地域社会の維持が大きな課題となっている。2024年の出生数は外国人を含めて約72万人と9年連続で過去最小を更新し続けている[1]。総人口も既に減少局面に入り、2060~2070年には現在の3分の2程度(約8,700万人)まで縮小し、高齢者(65歳以上)が人口の4割前後を占めると見込まれている[2]。こうした人口減少社会において、限られた医療資源で地域住民に持続的な医療サービスを提供するには、テクノロジーの活用による効率化と地域医療体制の強化が不可欠である。
本稿は、まず国内外の事例から得られる示唆を検討し、日本の地域医療への応用可能性を探る。その上で、政策立案に資する具体的な政策提言を示す。
人口減少社会における地域医療の現状と課題
人口減少と高齢化は、特に地方で深刻である。また、若年層の都市部流出により地方の医師数は不足し、「医療過疎地」が生まれている。産科・小児科・耳鼻科など特定分野では地域の病院・診療所の閉鎖や医師不在が相次ぎ、住民は遠方の医療機関に頼らざるを得ない状況である。例えば、岡山県北部では、COVID-19下で出生数が自治体ごとに2~4割減少し、加えて医師の働き方改革により、大学病院から地方への医師派遣が難しくなると見込まれている。このため周産期医療(産科・新生児医療)を地域で維持するには、従来以上に効率化・集約化を図る必要性が指摘されている[3]。
また、高齢化の進行により慢性疾患の患者や要介護高齢者が増加する一方、現役世代の減少で、医療・介護を担う人材確保が困難になると予想されている。地域住民の移動手段も限られ、高齢者は通院自体が負担となる。このような状況下で、オンライン診療を含めたデジタル技術を活用した医療提供は、(1) 少ない医療従事者でより多くの患者を診る効率化、(2) 地理的障壁を超えた医療アクセス向上、(3) データ活用による予防・早期介入の強化、といった効果が期待されている。
岡山県吉備中央町における産婦人科デジタル化の取り組み
岡山県吉備中央町は中山間地域に位置し、岡山市内の岡山大学病院まで車で往復2時間以上を要する医療過疎地である。同町では「デジタル田園健康特区」[4]に指定されたことを契機に、著者の牧は同町のアーキテクト(構想全体を企画する人材)として、産婦人科や小児心身医療科、整形外科等のオンライン診療や、耳鼻科や睡眠時無呼吸症候群のデジタルスクリーニングによる受診勧奨を含む地域医療のデジタル化を進めており、妊産婦支援や遠隔医療など約10の施策からなる計画が推進中である。
デジタル技術による周産期医療の効率化
岡山県では大学発のベンチャー企業と協働し、周産期医療にデジタルシステムを導入した。その一例が妊産婦の緊急搬送補助システムである。2018年より、地域医療介護総合確保基金事業を用いた施策として開発。従来、産科救急で地方から基幹病院に妊産婦を搬送する際、搬送元施設での情報共有や受入病院での手術準備に時間を要していた。そこで妊産婦のカルテ情報やバイタルデータ等をリアルタイムで共有できるシステムを県内全域に展開した結果、救急搬送時の連携が円滑化し、救命救急士の対応時間短縮と受入側の準備迅速化につながった。その効果として、妊産婦が搬送されてから緊急手術に至るまでの時間が、平均7分30秒短縮されたと報告されている[5]。2024年より群馬県全域でも導入がスタートした。わずか数分とはいえ、周産期医療では母子の生死を左右し得る重要な改善であり、デジタル技術による効率化の実例といえる。
さらに吉備中央町では、働く女性へのデジタルサポートとして、妊産婦の健康情報を日常的に把握する取り組みも行われている。紙媒体の「母子健康手帳」をスマートフォンで簡便にデジタル化できる仕組みを備える子育て支援アプリ(「ウィラバ(WeLoveBaby)」)[6]を導入し、妊婦健診結果や生活習慣情報をデータとして蓄積・共有している。この仕組みによりオンライン診療中に母子手帳データをカルテ内で閲覧可能となり、出産前後の母子ケア支援に役立てている。デジタル化された母子健康情報は緊急時にも迅速に参照でき、適切な処置に繋げられるため、地域全体の周産期医療の質と連携体制が強化されている。
オンライン診療・遠隔ケアの実践
医師が常駐しない診療科については、オンライン診療等の遠隔ケアでカバーする仕組みづくりが進められている。町の診療所には防音個室ブース「テレキューブ」が特別仕様で設置され、岡山大学病院の医師によるオンライン診療が受けられる環境が整備された[7]。テレキューブ内にはディスプレイと各種機器が備えられ、患者は画面越しに医師と対面する形で診察を受ける。プライバシーが確保された防音空間で対面に近い感覚の診療が可能となり、遠隔地でも安心感を持って受診できている。岡山大学病院側でも特区の枠組みを活かし、遠隔診療が院内業務に過度な負担をかけず円滑に運用できていると報告されている 。オンライン診療では、検査データを共有しながら診断・フォローアップを行う仕組みづくりも検討されており、特に遠隔地で課題となる採血検査等については規制緩和を見据えた実証が進められている。耳鼻科のオンライン難聴スクリーニングでは、マイナンバーと紐づけされたポータルアプリのQRを読み取ることで個人情報を簡単に自動登録ができて検査が可能である。このしくみは2025年2月から開始となり、137名が検査に参加し、50名以上に対して受診勧奨の情報提供がなされた。
このように、吉備中央町ではデジタル技術を駆使して「いつでも・どこでも」質の高い医療を届ける挑戦が行われている。住民のニーズに即した形でオンライン診療や見守りシステムを導入し、高齢者や妊産婦への継続支援も強化されている。吉備中央町ではそれまでに1件もなかった町内での出産が、2024年に開院した助産院と岡山大学病院がデジタル連携を行ったことで安心して実施できるようになり、2024年度は7名の出産が認められた[8]。国も年間200億円規模でデジタル田園都市国家構想を推進しているが、吉備中央町はその健康領域における医療モデルケースの一つとして、少子高齢化・人口減少に対応する先駆的役割を期待されている。
海外の先進事例と示唆
海外においても人口減少や医療資源不足に直面する地域で、テクノロジーを活用した様々な先進的取り組みが行われており、日本の地域医療への示唆となる。以下に主な事例を紹介する。
(1) 米国:バーチャル病院による遠隔モニタリング(Mercy Virtual)
米国ミズーリ州のMercy Virtual Care Center[9]は実際の入院病床を持たない「バーチャル病院」として、遠隔医療と在宅患者モニタリングを大規模に展開している。集中治療室(ICU)の専門医が遠隔で各地の提携病院ICU患者を24時間監視し支援するしくみにより、リモートICUプログラムにおいて患者死亡率を35%も低下させ、ICU在院日数も30%短縮する成果が報告されている[10]。また、慢性疾患患者への遠隔モニタリングでは入院率を約50%減少させ、患者当たりの月間医療コストを従来の750ドルから300ドル未満に削減するなど、医療の質と効率が飛躍的に向上した。遠隔ケアによって担当患者数を倍増しても追加人員を要さない体制を構築し、患者満足度も極めて高い水準(NPSスコア+86)を維持している[11] 。この事例は高度な専門医療を地域間でシェアすることで、医療資源の有効活用と患者転院の減少を両立できることを示している。
(2) フランス:医療過疎地への遠隔診療ブース導入
フランスでは、国民の13%(約900万人)が医師不足の「医療砂漠(無医地区)」に居住しており、高齢化や慢性疾患増加で状況は悪化している 。そこでH4D社製の遠隔診療ブース(複数のセンサー・医療機器を内蔵した個室)を市役所や薬局などに設置し、遠隔地からでも対面に近い診察を受けられる体制を整えた[12]。パンデミック時にはフランス全土で100台以上のブースが展開され、ブース内の15種類のセンサーにより聴診・血圧測定など一通りの診察が可能なため、初診の98%で遠隔医が適切な診断・治療を完結できたと報告されている。ブース設置と同時に、患者を支援するスタッフ配置や住民向けデジタル教育にも取り組んだ結果、高齢者などデジタル機器に不慣れな層でも遠隔診療を利用しやすくなった。フランスでは規制緩和により遠隔診療の地域制限や対面受診要件を撤廃したこともあって、全国のオンライン診療件数は、2019年の12.7万件から2020年には1,850万件へと150倍に急増し、その後も一定水準で定着している。このように、公的な制度整備と技術導入により地方の医療アクセス格差是正に成果を上げた例と言える。
(3) 米国:Project ECHOによる地域医療者支援
米国発の「Project ECHO」は、大学病院などの専門医が遠隔地のプライマリケア医等を継続的に指導・メンタリングする仕組み(テレメンタリング)で、地域医療水準の向上に寄与している[13]。例えばニューメキシコ州で始まった肝炎治療のECHOプログラムでは、週次の遠隔カンファレンスを通じて地方医師が専門知識と最新治療法を学び、結果として地域の患者の治療成績が専門医と遜色ないレベルに向上した。最近の研究では、糖尿病領域のECHOに参加した地方医療提供者約300名の患者群(約900人)は、専門医がいる都市部病院の患者群と比べて平均HbA1c値の低下幅が同等であったことが確認されている 。具体的には、ECHO参加医の患者は平均で1.2%のHbA1c低下を達成し、これは合併症リスクを大幅に減少させる有意な改善である。このモデルは「知識を移転し、患者を移動させない」ことを理念とし、専門医のいない地域でも慢性疾患や特殊疾患のケアを向上させられることを示している。日本でもへき地医療支援や地域医師のスキル向上策として応用が期待できる。
以上の海外事例から導かれる示唆は、(吉備中央町の事例と同様に)テクノロジーの活用によって「専門医療へのアクセス向上」「予防的なケア強化」「医療従事者の能力開発」が可能になるという点である。これらを実現するためには、単に機器を導入するだけでなく制度面・人材面の整備が重要であることも各国の経験が示唆している。日本の地域医療においても、これら事例を踏まえた包括的な政策アプローチが求められる。
オンライン診療の導入に向けた課題
日本では1997年にオンライン診療(遠隔診療)が解禁され、2020年以来の新型コロナ(COVID-19)パンデミックに際してオンライン診療が利用されたことも含めて、現在いくつかの事例が厚生労働省からも紹介されてはいるが[14]、2017年時点で導入していた病院は全体の0.2%、診療所も0.4%に過ぎず普及しているとは言い難い状況であった[15]。この低迷の背景には制度設計上の制約があり、オンライン診療の対象患者が慢性疾患で特定の医学管理料を算定されている者に限定されるうえ、初診から少なくとも3か月間は対面診療を継続する必要があるなど患者条件が厳しかったことが挙げられる。医師側にとっても対面診療に比べ診療報酬が低く、オンライン診療と対面診療を並行する負担や緊急時対応の難しさも指摘され、結果的にオンライン診療を利用する患者数が限定的となりコストを回収できないケースも報告されている。東京都内の医療機関からは「オンライン診療の準備や待機に時間を割けず、1人あたりの診察時間も長くなる」「カメラ越しでは視診に限界があり触診や聴診ができない」といった運用上の問題点が挙げられており[16]、こうした制度面・実務面の課題が導入効果を減殺したと考えられる。
利用者側の受容性にもギャップが見られる。ある国内調査では、回答者の約9割がオンライン診療を「利用したことがない」と答えている[17]。COVID-19流行期には一時的な初診解禁措置もあってオンライン診療の利用は増え、認知度も向上したものの多くの患者にとって依然なじみの薄いサービスであり、感染流行終了後は医療機関の参入も限定的で(2021年時点で提供医療機関は全体の1割以下)、患者側では「利用方法がわからない」「診療の質が不安」といった心理的ハードルが残存している。医師側でも「画面越しでは症状を十分評価できない」「対面診療より診療報酬が低い」など慎重・消極的な意見が根強く、日本医師会もオンライン診療の安全性や報酬体系の課題を度々指摘してきた経緯がある15。このように患者・医療者双方の受容性と運用実態との乖離が大きいことが、オンライン診療の持続的な定着を阻む一因となっている。
国際的にも、オンライン診療は必ずしも期待通りの効果を上げていない。例えば医療資源の乏しいアフリカでは、遠隔医療への期待が以前から語られてきたが、現実には持続的に成功した事例は少ない[18]。その要因として、医師不足という構造問題に加え、貧困やインフラ未整備、通信回線の不安定さ、停電の多さなど複合的な障壁が遠隔医療の定着を妨げている 。また制度設計の問題も大きく、南アフリカではCOVID-19以前、遠隔診療に対する保険償還(報酬)が認められず医師会ガイドラインも厳格であったため、医師-患者間のオンライン診療はごく限定的にしか行われなかった。このように技術そのものよりも制度・環境面の未整備によって、オンライン診療は各国で当初期待されたほどの効果を発揮できずにいる。
地域医療情報連携の不十分さによる課題
医療効率化と地域包括ケア推進のためには、地域の医療機関同士が患者情報を円滑に共有することが重要である。情報連携が不十分な場合、患者の紹介・転院時に必要情報が伝わらず医療機関連携が断絶し、重複検査や投薬ミスなどの非効率・リスクが生じる[19]。ある研究では、電子カルテ非連携下で転院した患者の32%に重複検査が見られ、うち20%の検査は臨床上不要な重複だったと報告されている[20]。実際、紙の診療情報が共有されない場合に重複検査が頻発することは以前から知られており、不十分な電子連携でも同様の問題が起こり得る。このため各地域で医療情報連携ネットワークの構築が図られてきたが、その運用は必ずしも順調ではない。
日本においては、2012年以降に各地で立ち上げられた地域医療情報連携ネットワークの40%以上が、開始から5〜6年以内に中止・終了もしくは他地域との統合に至っており、継続運用されていない状況にある[21]。現存するネットワークについても、当初の目的を「達成できた」と満足している地域は全体の41.1%に留まる[22]。言い換えれば半数以上の地域で、情報連携ネットワークが期待された効果を十分には発揮できていない。実際、画期的な仕組みとされたネットワークも現場での活用状況は低調で、参加医療機関が少なく「形骸化」してしまっている地域が多数報告されている[23]。背景には財政・人的リソースの問題があり、国の補助金(地域医療介護総合確保基金)で初期構築したネットワークほど運用費用の捻出に苦慮し、結果として短期間で運営停止に追い込まれる傾向が指摘されている。持続可能な運営のためには、初期補助に頼らず地域内で維持費を確保する仕組みや参加促進策を講じる必要があるという教訓が得られる。
海外でも地域HIE(Health Information Exchange)の持続には共通の課題がある。米国では地域ごとにHIE組織を設立し電子情報連携を促進する試みが繰り返されてきたが、その多くは財政難や十分な参加医療機関を集められないまま頓挫し、歴史的に見るとHIE促進団体の失敗率は成功率を大きく上回るとされる[24]。技術的なインフラ以上にビジネスモデル(採算性)の欠如や関係者の合意形成の難しさが障壁となり、政府や保険者が明確なメリットを示せない場合、現場の医師が参加に消極的となってしまう。また、せっかくHIEを導入しても現場の医療従事者に使われなければ意味がないが、システム設計が不十分で必要な情報をすぐ見つけられないといった場合、医療者の利用頻度は低下しがちである。実際、HIE上で必要な患者情報を発見できない場面があると利用が敬遠され、HIEの価値が発揮されないと報告されている。このように導入プロセス上の課題(運用資金や制度設計の不備)やユーザーである医療者・患者側の受容性の低さが相まって、せっかくのテクノロジーが期待された医療効率化の効果を十分に生み出せないケースが国内外で散見されるのである。各事例の教訓として、技術導入の際には制度的支援策や運用設計を周到に整え、利用者への周知・教育やインセンティブ付けを通じて受容性を高めること、さらに長期的な財政計画と経営陣のコミットメントによって持続可能性を確保することが不可欠である[25]。
政策提言
以上を踏まえ、人口減少社会の地域医療を維持・強化するために政府が講じるべき具体的政策を提言する。読者である政策立案者の視点に立ち、予算措置・制度改正・ガイドライン策定等の観点から整理した。
- オンライン診療の恒久的拡充と制度整備
COVID-19下で特例的に拡大したオンライン診療の定着に向けた法整備を進める。2025年の医療法改正案においてオンライン診療の法定化・基準の明示、オンライン診療受診施設の設置者による届出などが含まれているが[26]、さらに安心して初診からのオンライン診療も地域医療連携の一環として実施されるような法的基盤を確立することが望まれる。またオンライン診療の診療報酬上の評価を引き上げ、医療機関が導入しやすいインセンティブを与える。離島や山間部など医師不足地域では対面診療と同等に保険適用し、患者側の自己負担軽減措置(通信費補助等)も講じる。さらに遠隔診療後の薬の受け取りまでシームレスに完結できるように、オンライン服薬指導等に関しても適切に実施されるように推進する。
- デジタルインフラへの投資と地域への設備支援
遠隔医療を支える通信ネットワークや機器整備に対する公的支援を拡充する。ブロードバンド未整備地域へのインフラ投資を加速し、高速インターネット網を全国隅々まで行き渡らせる。また、医療過疎地の住民が身近に遠隔診療を利用できるよう、公共施設や調剤薬局等へのテレキューブ型診療ブースの設置やオンライン診療実施可能な車両等の配置を補助する。高齢者など機器操作に不安がある層には、地域包括支援センター等と連携してデジタル機器の使い方支援や予約手配を行う体制を整備する。併せて遠隔モニタリング機器(例:在宅心電図・血圧・血糖測定デバイス)の導入補助や貸与事業により、慢性疾患管理や在宅ケアを促進する。政府による補助金に加え、自治体にも裁量を持たせ地域の実情に合った設備投資を可能にする。
- 医療データ連携基盤とAI活用推進
地域医療を効率化するため、医療・健診・介護データを連携・共有できる基盤を整備する。例えば妊産婦の電子母子手帳や診療情報をクラウド上で管理し、救急搬送時に搬送先病院へ自動共有する仕組みを全国に拡大する。また地域の診療所と中核病院との間で電子カルテや検査結果を相互参照できるよう標準化を推進し、重複検査や情報伝達ロスを減らす。地域医療連携ネットワークの基盤を活かしながら、政府主導で進めている全国統一の医療情報プラットフォームの構築とともに、セキュリティとプライバシー保護の指針を示して運用定着を図る。さらに蓄積されたビッグデータを活用しAIによる診断支援や重症化予測モデルの開発を促進する。過疎地医療で有用なAIツール(例:皮膚疾患や眼疾患の画像診断支援、チャットボットによるトリアージ)を承認・保険償還する仕組みを整え、医師の負担軽減と見落とし防止に役立てる。政府は産学官連携の実証事業の支援を行い、地方からAI医療の恩恵を享受できるようにする。
- 地域医療人材の支援とネットワーク強化
テクノロジーと並行して、人材面での地域医療強化策を講じる。まず、都市部の専門医と地域の医療従事者を結ぶ遠隔教育・相談ネットワークの構築を支援する。国立病院や大学に地域支援専任のポジションを設け、定期的なオンライン症例検討会や研修を開催してへき地の若手医師をサポートする。参加する専門医側には報酬加算や業務評価上のインセンティブを与え、継続的な指導を促す。次に、地域で不足しがちな産科・小児科・救急科などの領域で、非常勤医やリタイア医師がオンラインで診療協力できる制度を作る。医師免許の地域的偏在是正のため、オンライン診療に限り、都道府県をまたいだ広域での医師活動を認める規制緩和も検討する。さらには、救急救命士や看護師の役割拡大も推進する。特に救急搬送時に遠隔医の指示の下で超音波検査や一部処置を行えるよう消防法・医師法の規制を見直し、必要な研修を施した上で地方でも迅速な救命措置が取れる体制を作る。こうした人材面の強化策により、テクノロジーの効果を最大限に引き出すことができる。
- ガイドライン策定とモデル事業の全国展開
新たな遠隔医療やデジタル技術を安全かつ効果的に普及させるため、国としてガイドラインを改定・策定する。オンライン診療の適応疾患・頻度・緊急時対応等に関する指針を明確化し、医療者と患者双方が安心して利用できる基盤を整える。また遠隔モニタリング機器の品質基準やデータ管理の標準を定め、機器間の互換性確保と情報漏えい防止を図る。さらに、吉備中央町を含む「デジタル田園健康特区」のようなモデル事業で得られた成果と課題を分析し、ベストプラクティスを他地域へ横展開する。国は自治体向けにガイドブック・ツールキットを作成し、テクノロジー活用による地域医療改革の成功事例(遠隔診療ブースの運用方法や住民説明のポイント等)を共有する。加えて、各地の取り組み状況や医療アクセス指標をモニタリングし、PDCAサイクルで政策を改善していく仕組みも構築する。こうしたトップダウンの標準策定とボトムアップの現場知見活用を組み合わせることで、全国的に均てん化された地域医療の底上げを実現する[27]。
おわりに
人口減少社会における地域医療の維持は待ったなしの課題である。テクノロジーの活用は万能ではないが、適切な政策支援の下で実装すれば医療の効率化とカバレッジ拡大に大きく寄与する。岡山県吉備中央町は、デジタル技術により周産期医療や在宅ケアの新たなモデルを提示している。その知見と、海外の先進事例から得られた示唆を組み合わせ、我が国の実情に即した改革を進めることが重要である。政策担当者には、予算・制度・人材育成の各面から大胆かつ迅速な手立てを講じることが求められる。テクノロジーを味方につけた地域医療改革によって、全国どこに住んでいても「必要な時に必要な医療」が受けられる持続可能な体制を築くことが、本稿の提言する目標である。その実現に向け、産官学の協働と長期的視点に立った政策推進が期待される。
参考文献
[1] 厚生労働層 人口動態統計速報https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2024/12.html
[2] 国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口(令和5年推計)https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp_zenkoku2023.asp
[3] coFFee doctors「子どもを産んでもいいな」と思える日本に https://coffeedoctors.jp/doctors/4717/
[4] 内閣府 スーパーシティ・デジタル田園健康特区https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/supercity/openlabo/supercitycontents.html
[5] 牧尉太・増山寿「⾰新的事業連携型国家戦略特区指定を受けて〜産婦⼈科を軸としたデジタル化と規制改⾰〜」(2022年4月16日)
[6] 母子健康手帳のデータ化サービス「ウィラバ」 https://sonae.ltd/welovebaby.html
[7] PR TIMES デジタル田園健康特区のオンライン診療をテレキューブで実現(株式会社ブイキューブ)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000192.000047162.html
[8] 広報きびちゅうおう 2024年9月号 Vol.239「町内の助産院第1号の赤ちゃんが誕生しました」https://mykoho.jp/article/%E5%B2%A1%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E5%90%89%E5%82%99%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%94%BA/%e5%ba%83%e5%a0%b1%e3%81%8d%e3%81%b3%e3%81%a1%e3%82%85%e3%81%86%e3%81%8a%e3%81%86-2024%e5%b9%b49%e6%9c%88%e5%8f%b7-vol-239/%e7%94%ba%e5%86%85%e3%81%ae%e5%8a%a9%e7%94%a3%e9%99%a2%e7%ac%ac1%e5%8f%b7%e3%81%ae%e8%b5%a4%e3%81%a1%e3%82%83%e3%82%93%e3%81%8c%e8%aa%95%e7%94%9f%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/
[9] Mercy Virtual Care Center https://www.mercy.net/
[10] Tiger Buford ’The hospital of the future is here today.’ https://orthostreams.com/2024/12/the-hospital-of-the-future-is-here-today/#:~:text=Reduction%20in%20Hospital%20Utilization%3A%20The,effectively%20outside%20traditional%20hospital%20settings
[11] Bill Siwicki ‘Mercy Virtual Care Center: A deep dive into a virtual hospital’ https://www.healthcareitnews.com/news/mercy-virtual-care-center-deep-dive-virtual-hospital#:~:text=,month%20to%20less%20than%20%24300
[12] Julien Gamon ‘Remote consultations in France: an answer to medical deserts?’ https://www.credit-agricole.com/en/news-channels/the-channels/economic-trends/remote-consultations-in-france-an-answer-to-medical-deserts#:~:text=Thirteen%20percent%20of%20France%E2%80%99s%20population,to%20deteriorate%20despite%20regionalisation%20efforts
[13] The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust ‘New Study Shows Project ECHO Improves Diabetes Care in Rural Settings’ https://helmsleytrust.org/news-and-insights/new-study-shows-project-echo-improves-diabetes-care-in-rural-settings/#:~:text=%E2%80%9CThe%20ECHO%20Model%20provides%20a,of%20the%20Endocrinology%20ECHO%20program
[14] 厚生労働省 – オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001233108.pdf
[15] 飛田英子「オンライン診療の現状と展望」日本総研 Research Focus https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/11704.pdf
[16] 東京医師会 – 「オンライン診療に関するアンケート調査」結果報告 https://www.tokyo.med.or.jp/29014
[17] ドクターズ・ファイル – オンライン診療の利用状況に関する調査 (オンライン診療で患者が抱く不安と期待とは?患者調査レポート〖前編〗 | クリニック未来ラボ)
[18] Omboni et al., The worldwide impact of telemedicine during COVID-19 (The worldwide impact of telemedicine during COVID-19: current evidence and recommendations for the future) (The worldwide impact of telemedicine during COVID-19: current evidence and recommendations for the future)
[19] Vest et al., Health information exchange: persistent challenges (Health information exchange: persistent challenges and new strategies - PMC)
[20] Stewart et al., A preliminary look at duplicate testing associated with lack of electronic health record interoperability for transferred patients (A preliminary look at duplicate testing associated with lack of electronic health record interoperability for transferred patients - PMC)
[21] 令和3年度第5回宗谷保健医療福祉圏域連携推進会議 【資料6】ICT活用事例集 https://www.souya.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hgc/kikaku/106295.html
[22] 日本医師会総研 –ICTを利用した全国地域医療情報連携ネットワークの概況(2023) https://www.jmari.med.or.jp/result/working/post-4511/
[23] 厚生労働省 – 地域医療情報連携ネットワークの現状https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000683765.pdf
[24] Kierkegaard et al., How could Health Information Exchange better meet needs of care practitioners? https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4287667
[25] Hosseini, S.M., Boushehri, S.A. & Alimohammadzadeh, K. Challenges and solutions for implementing telemedicine in Iran from health policymakers’ perspective. BMC Health Serv Res 24, 50 (2024). https://doi.org/10.1186/s12913-023-10488-6 https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-023-10488-6#:~:text=This%20challenge%20is%20influenced%20by,P%202
[26] 厚生労働省 医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について(報告)https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001421848.pdf
[27] 藤田卓仙 「日本の医療DXのための共同規制:ボトムアップとトップダウンの融合」東京財団政策研究所レビュー https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4677
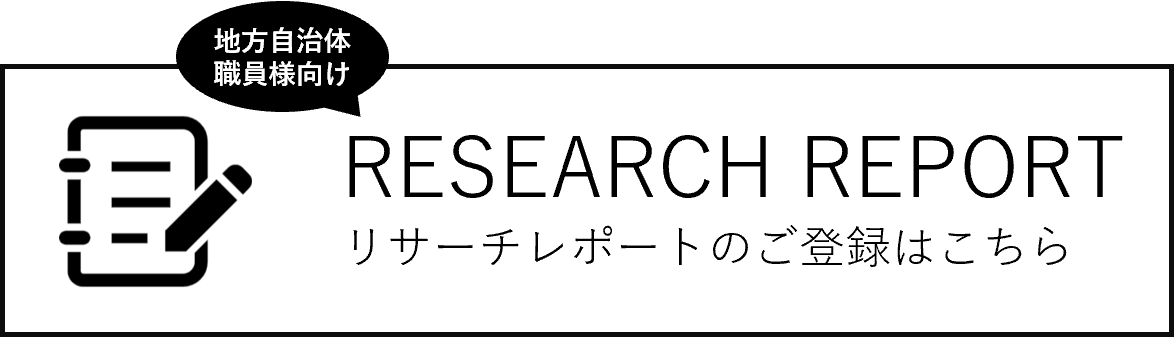












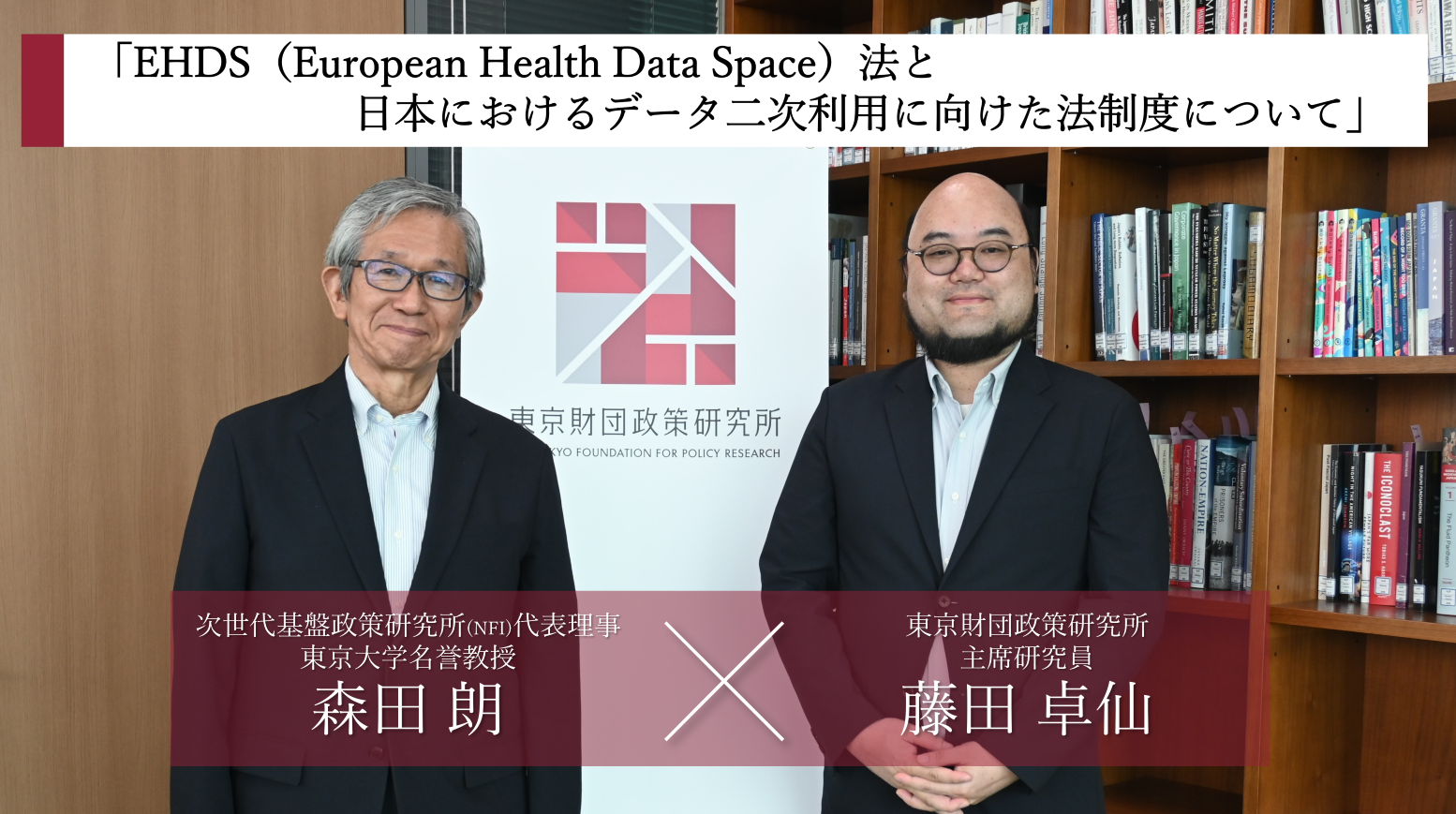


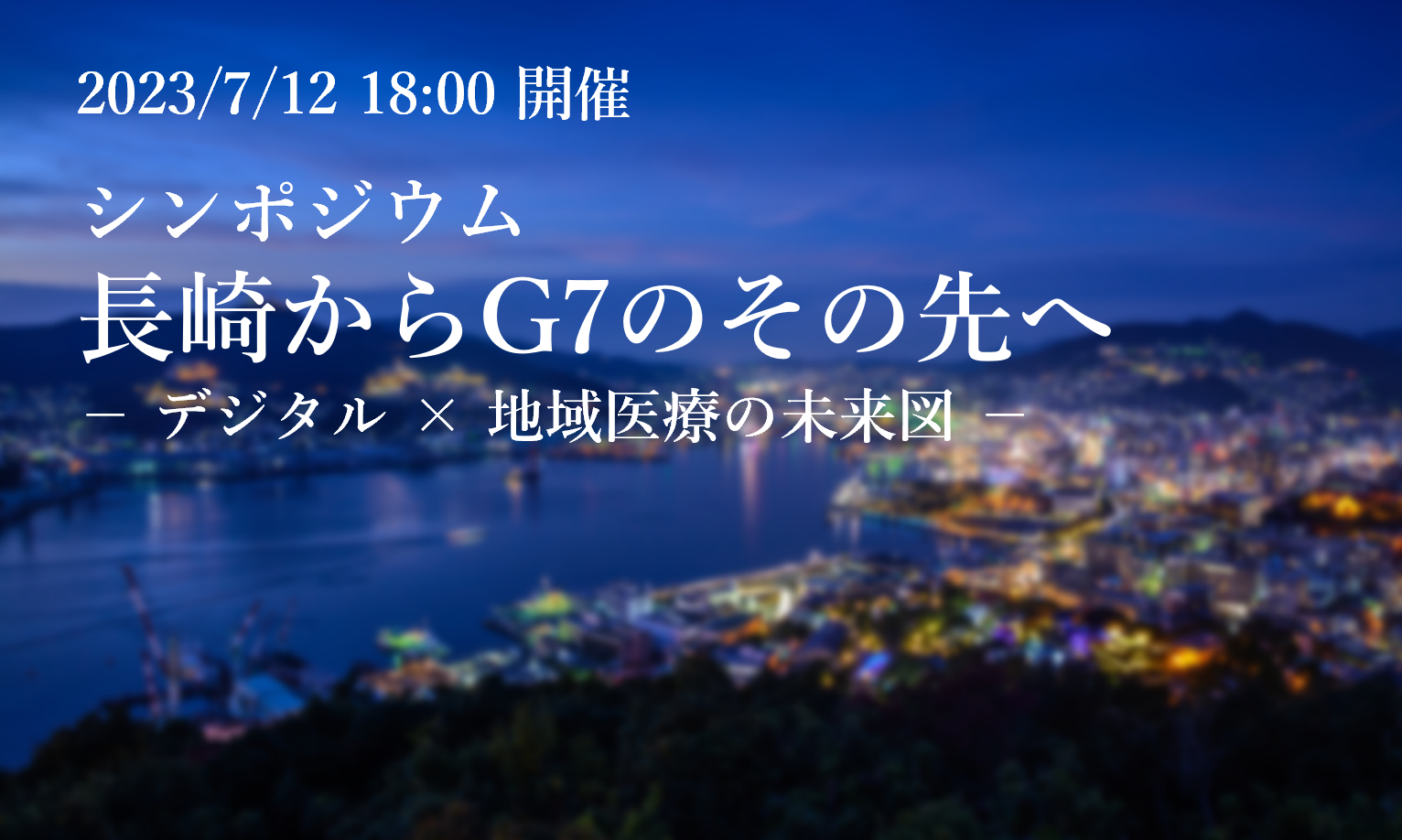





































_jpg_w300px_h200px.jpg)












































