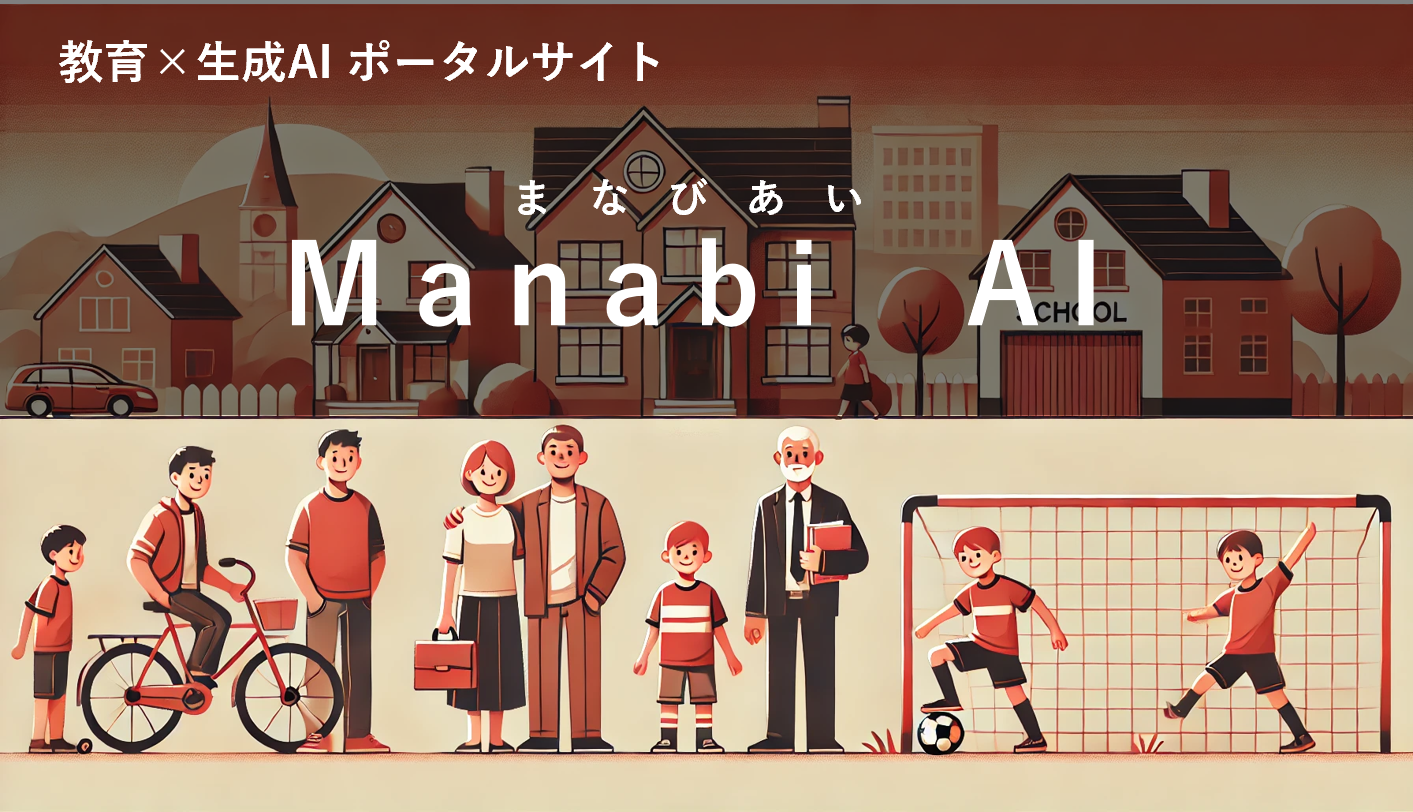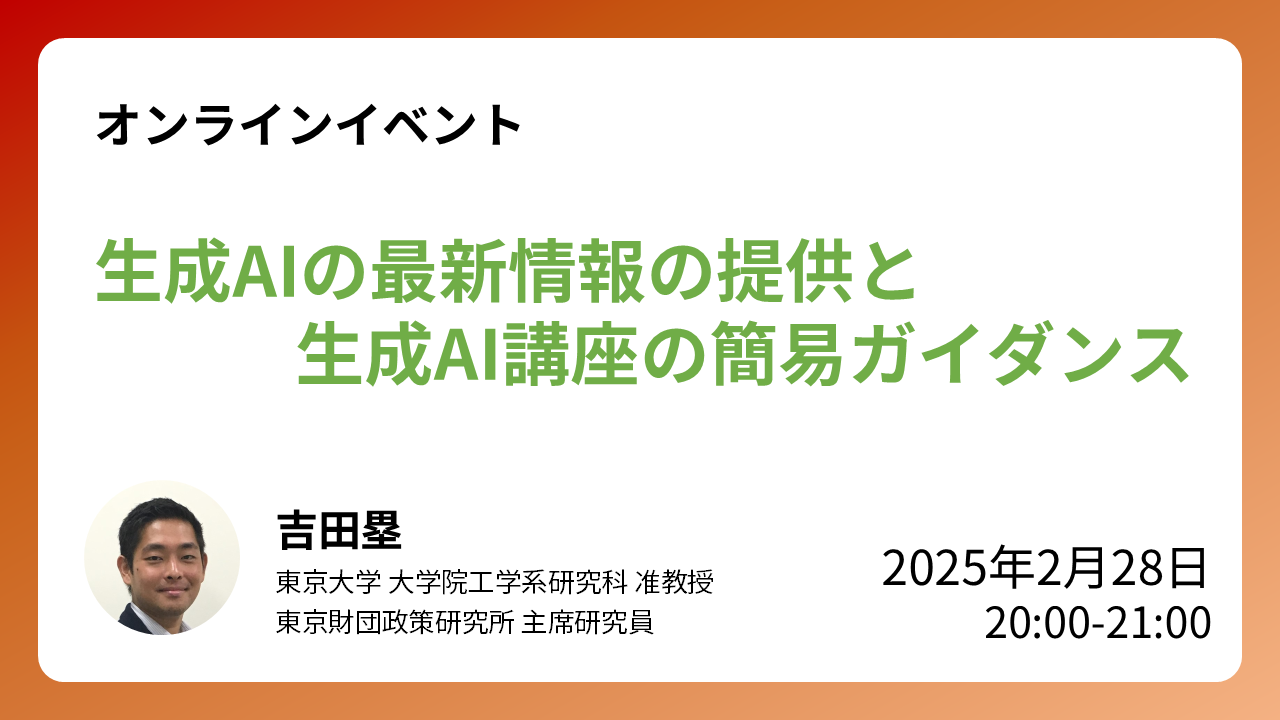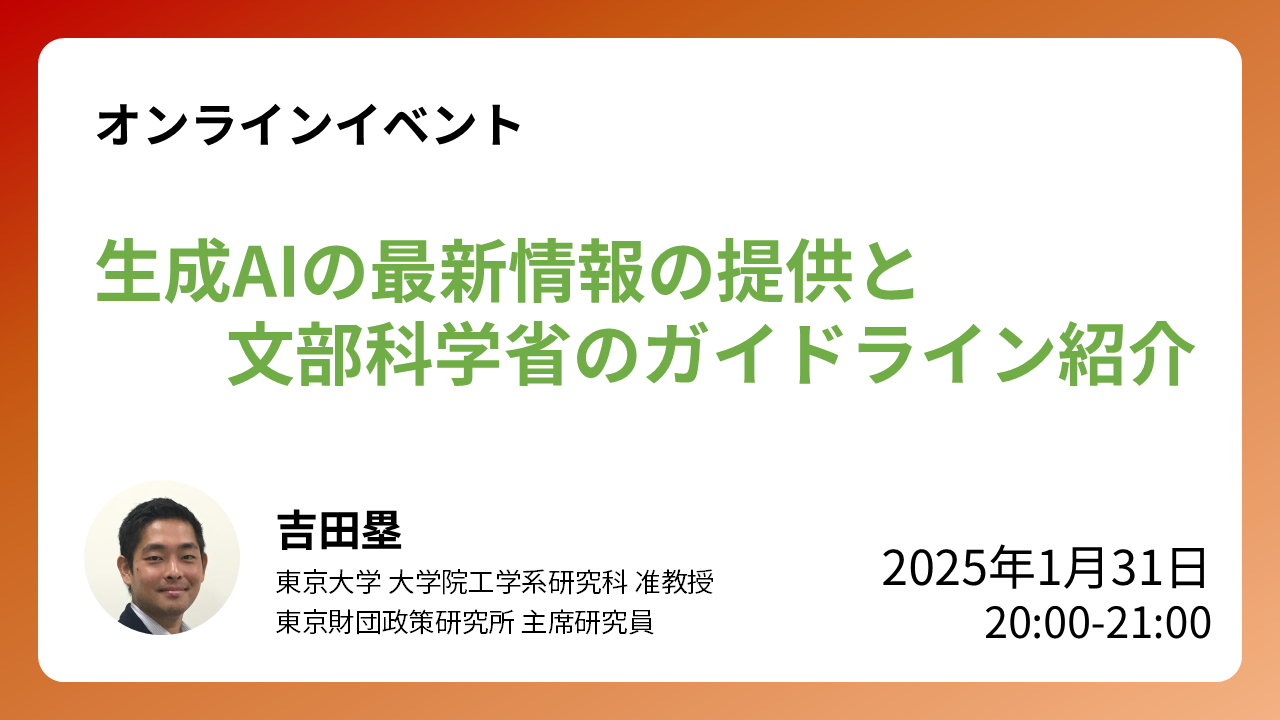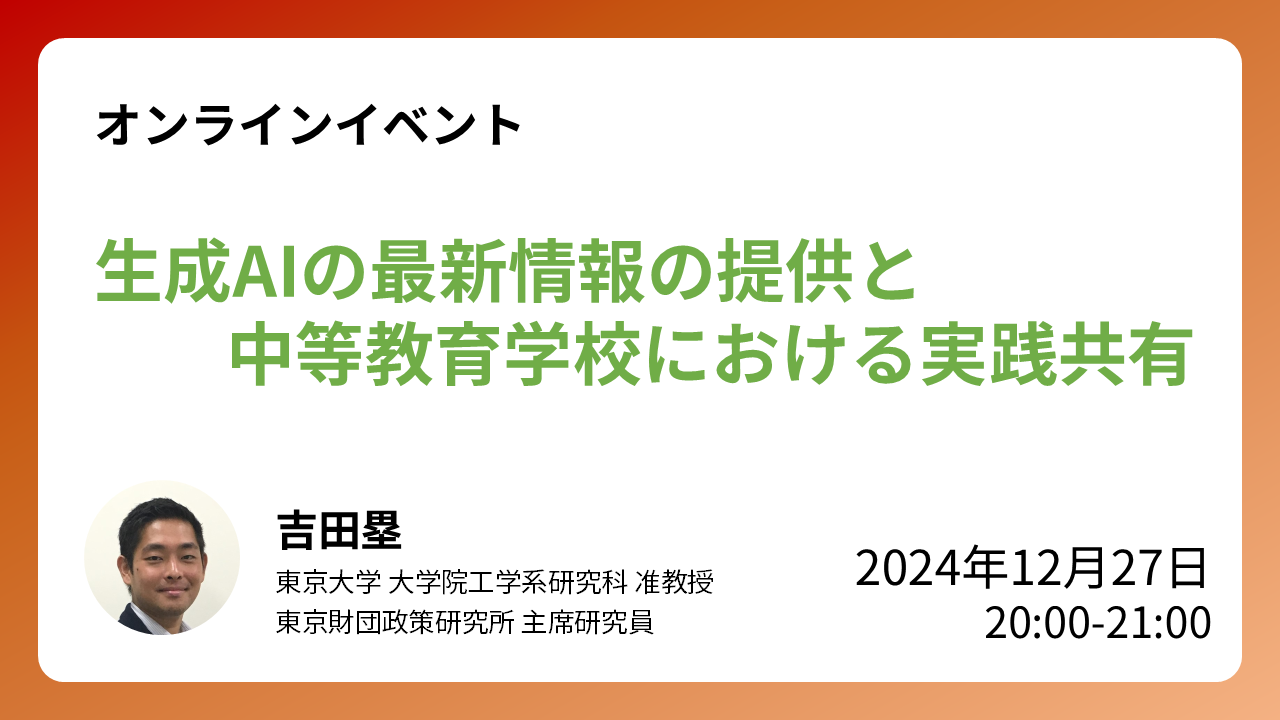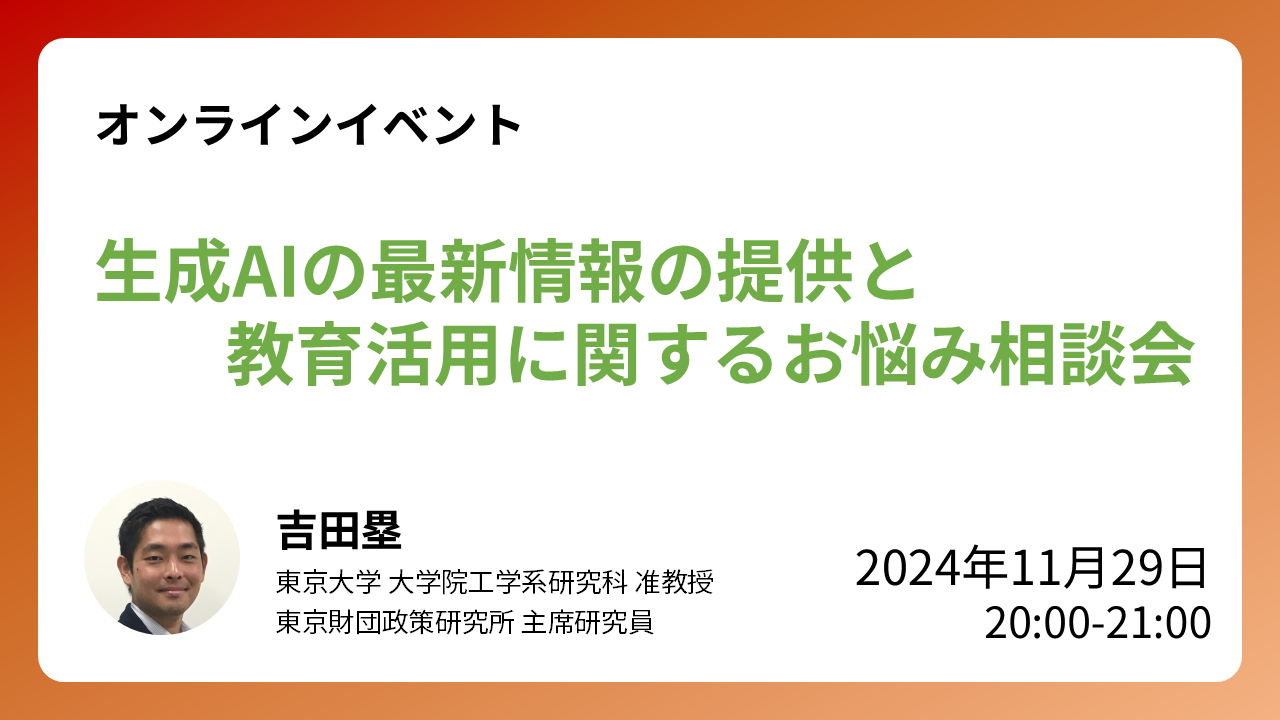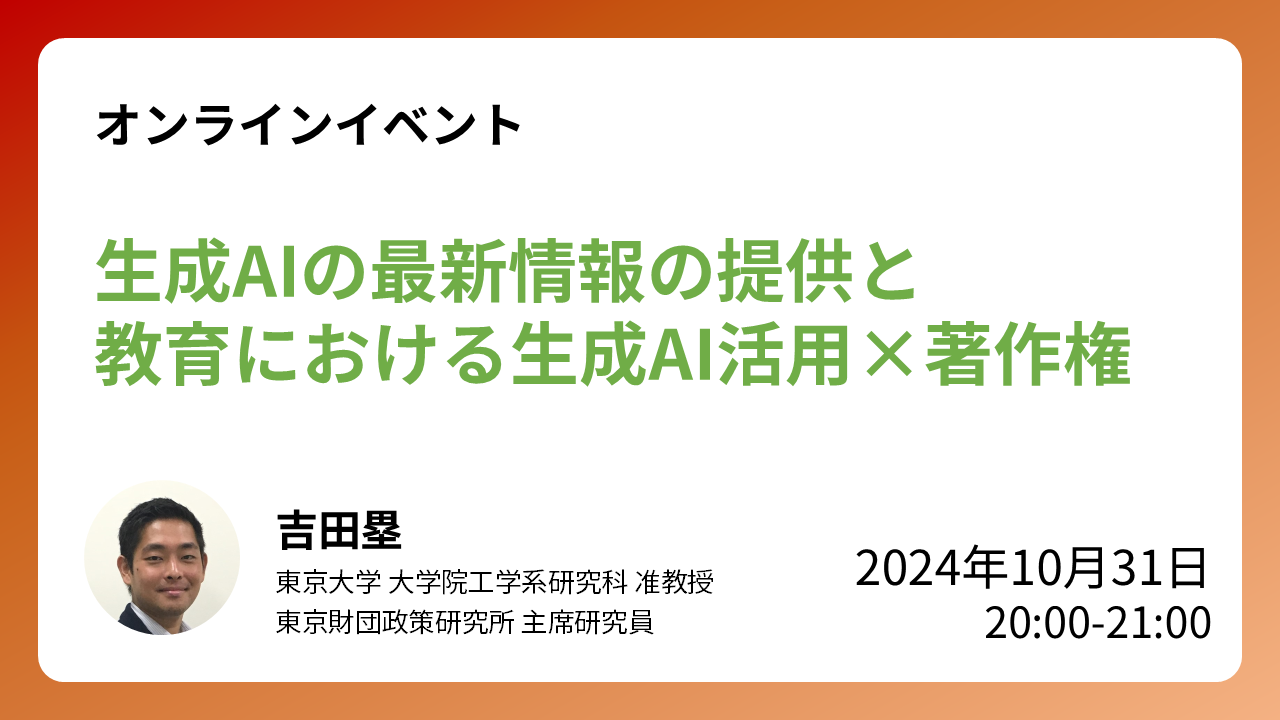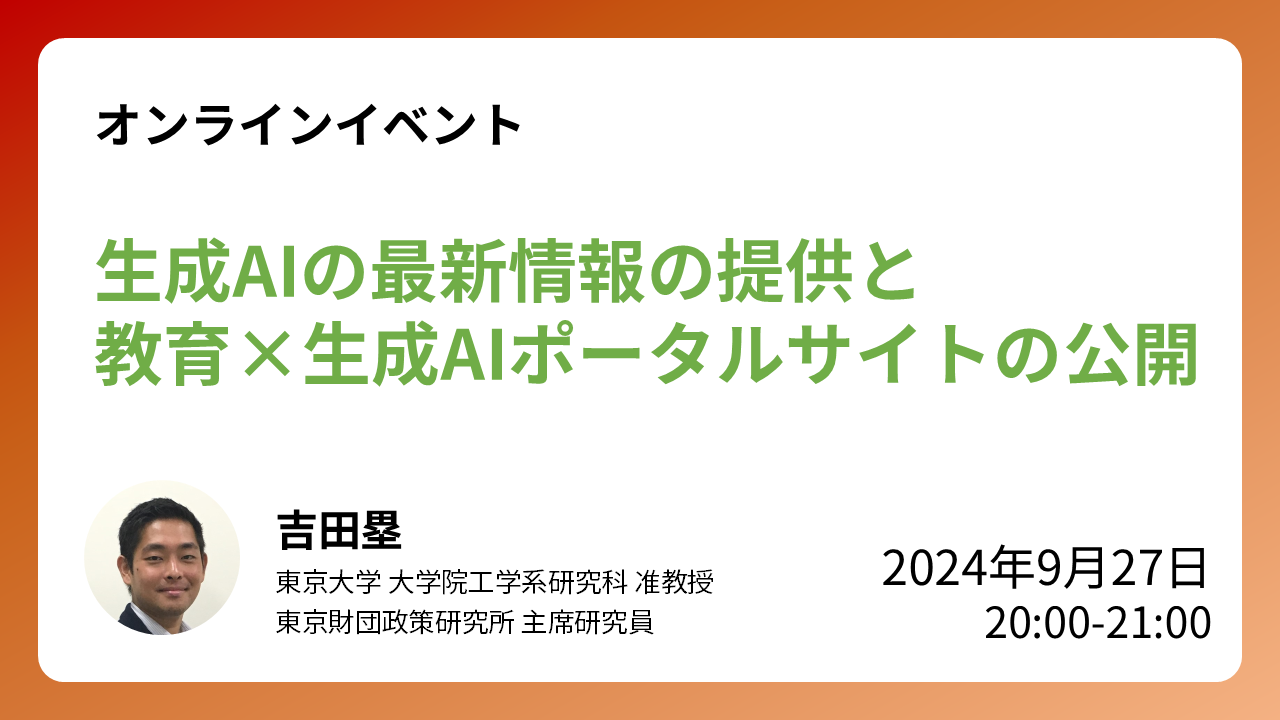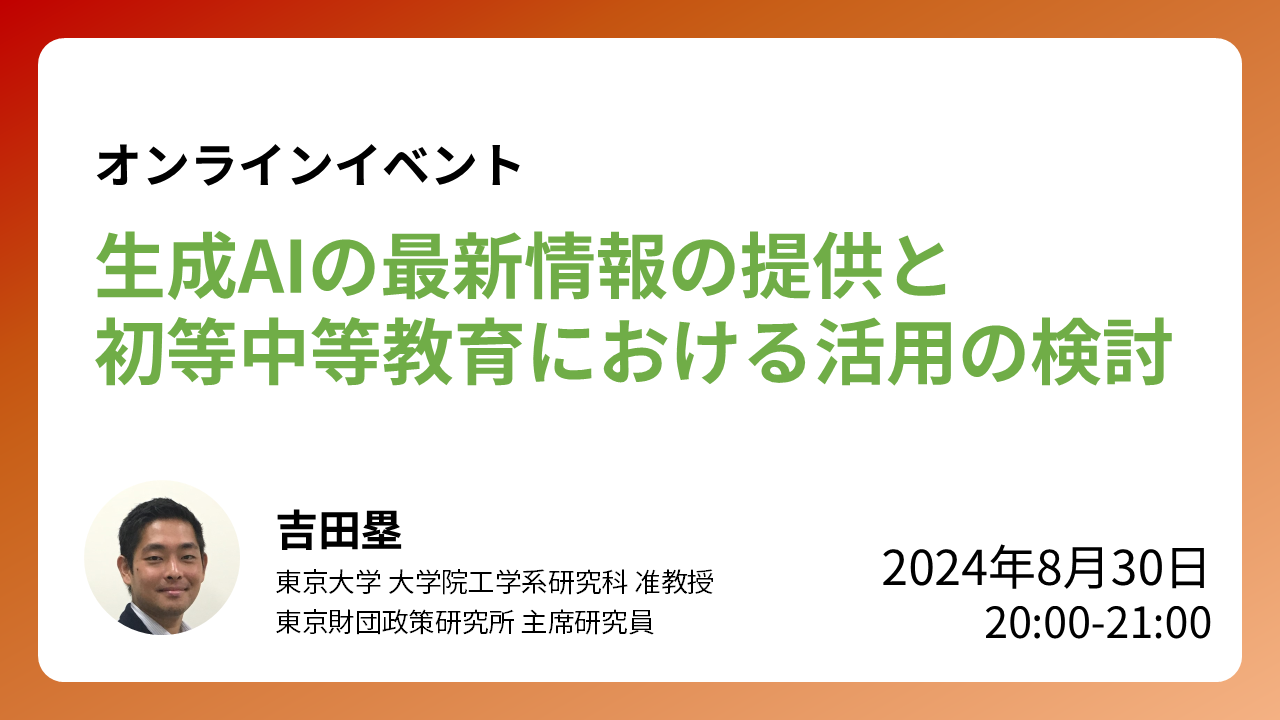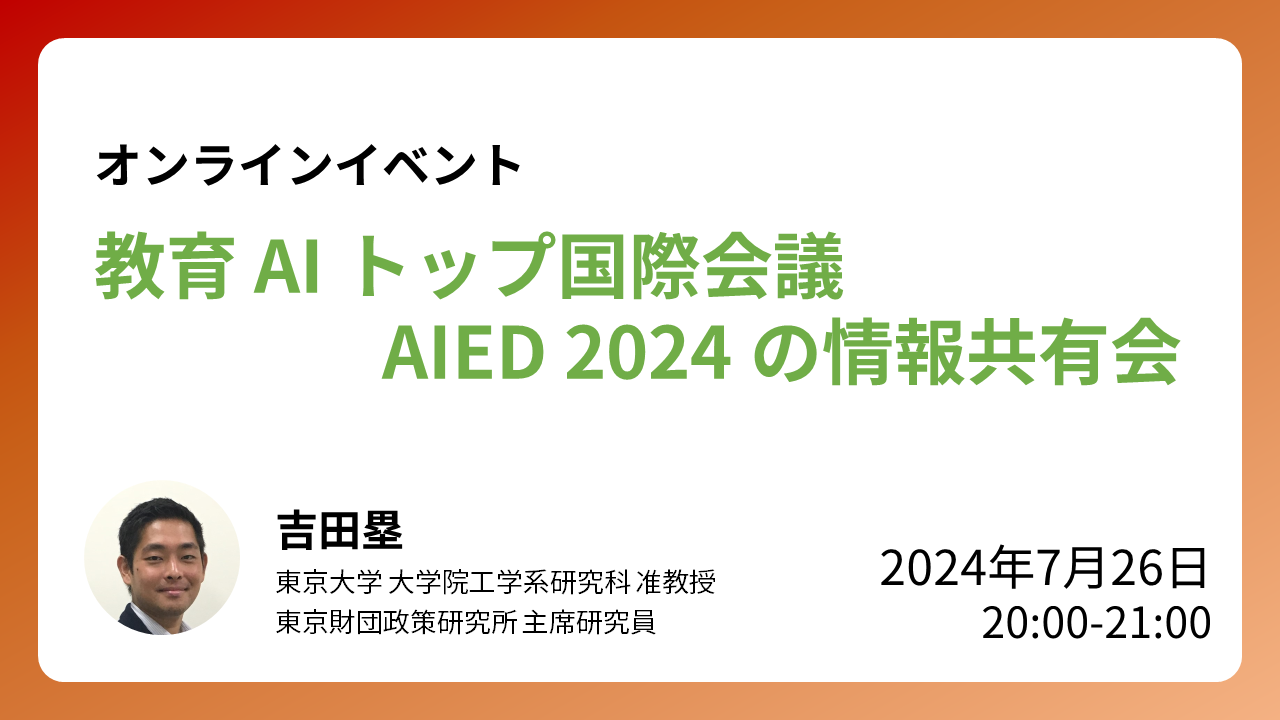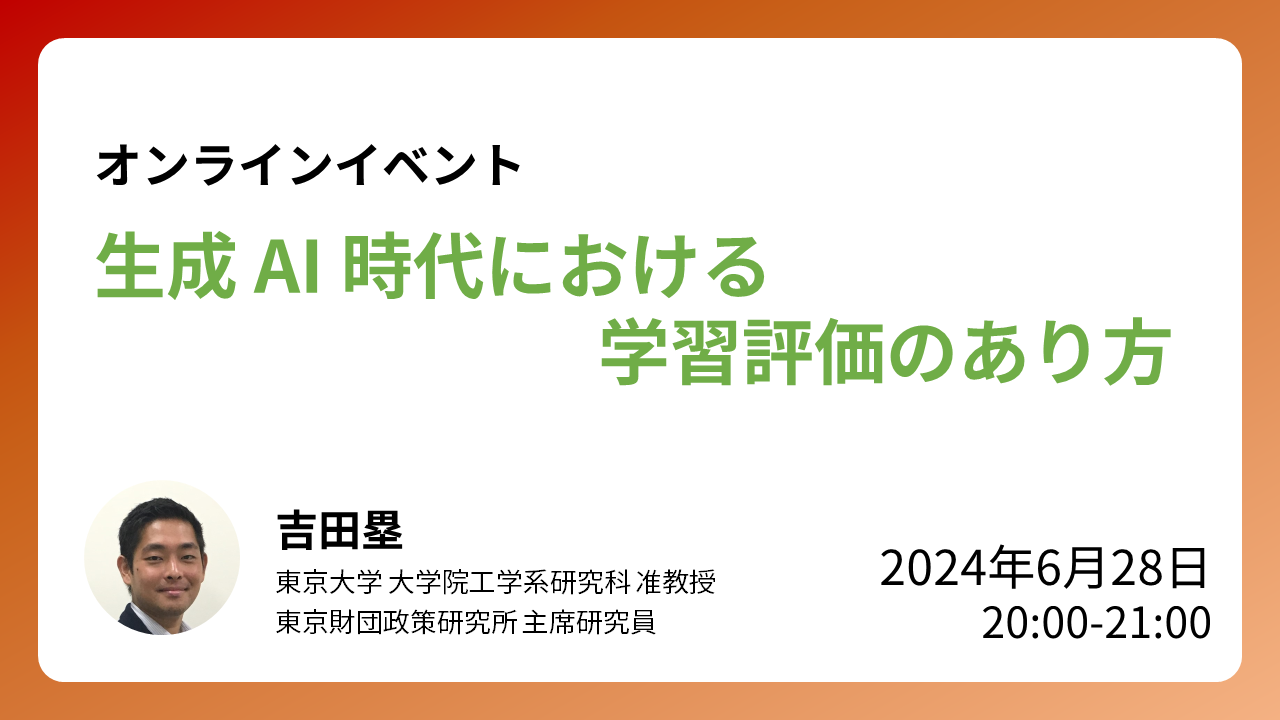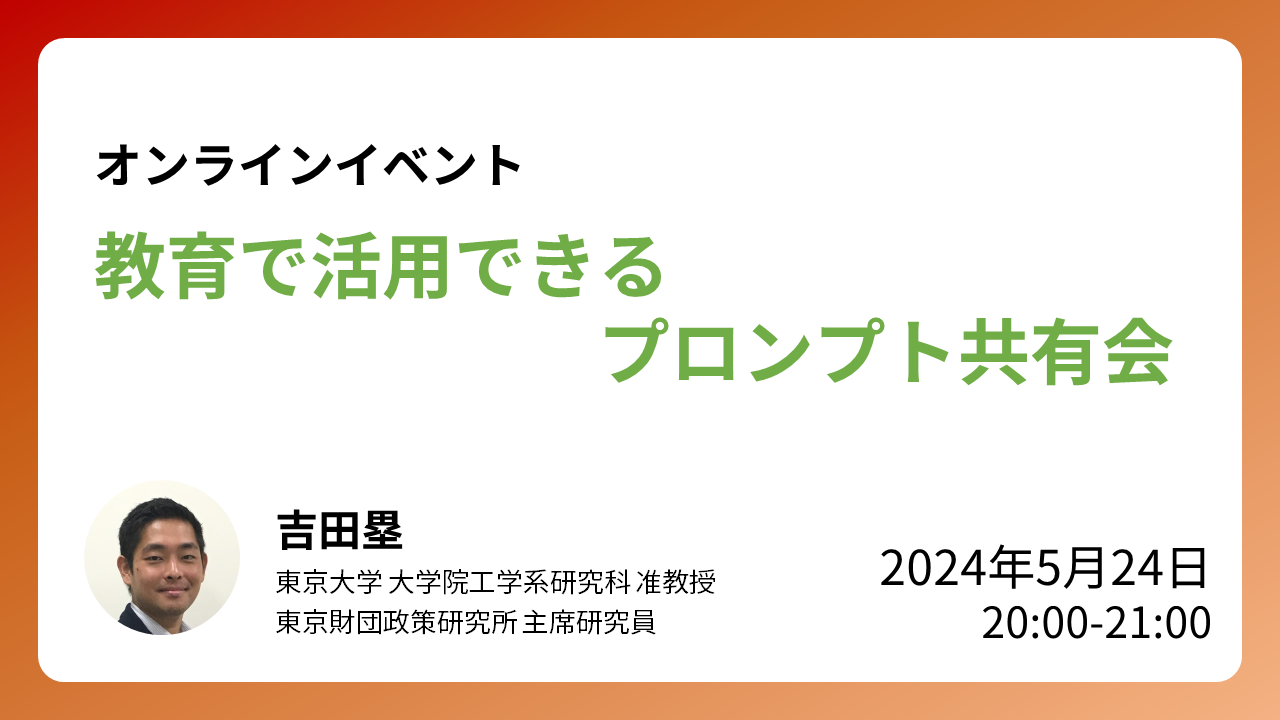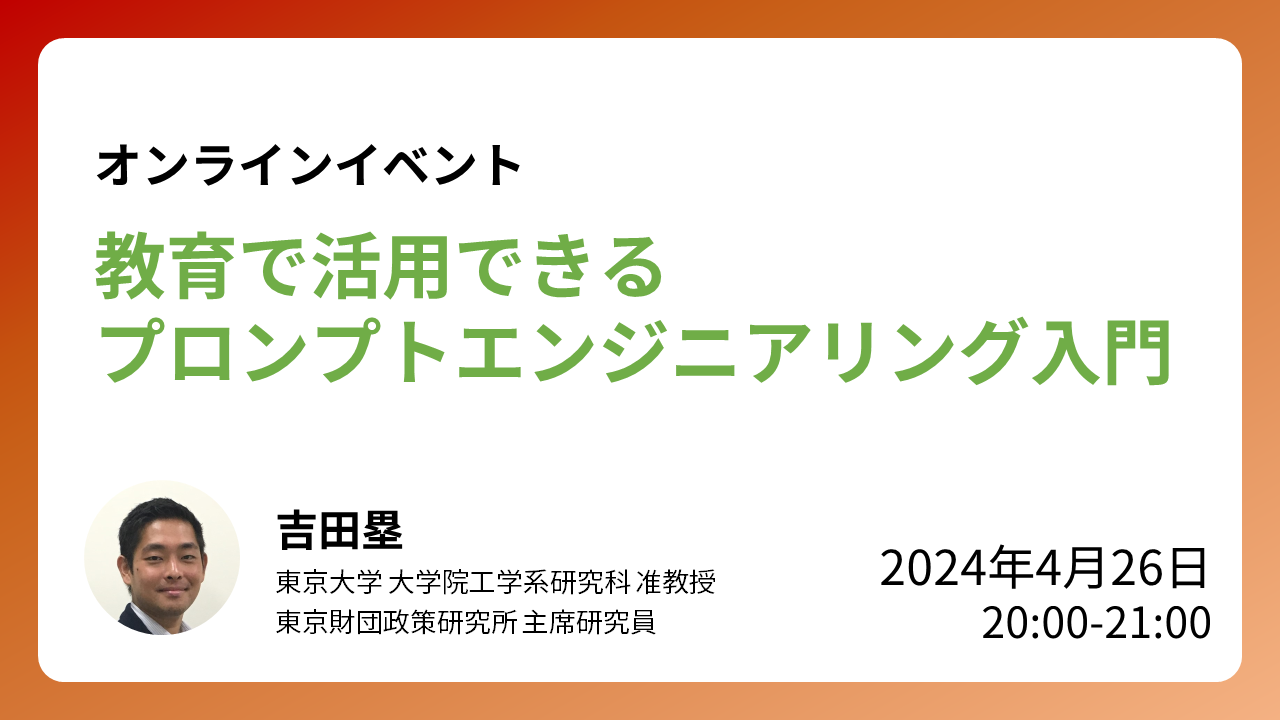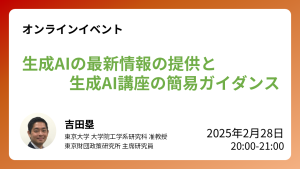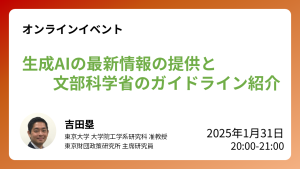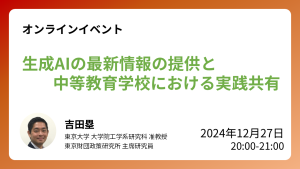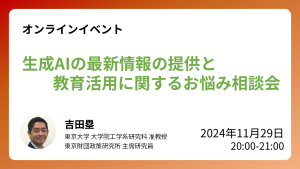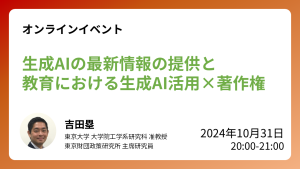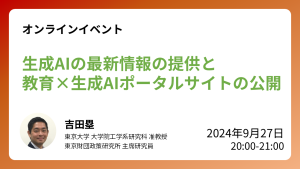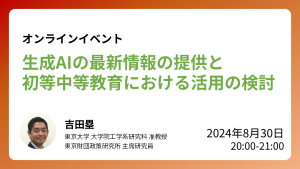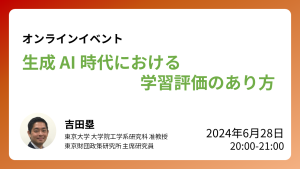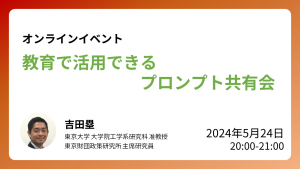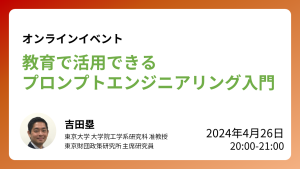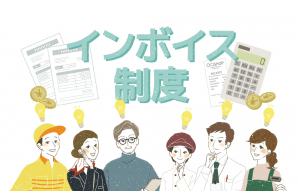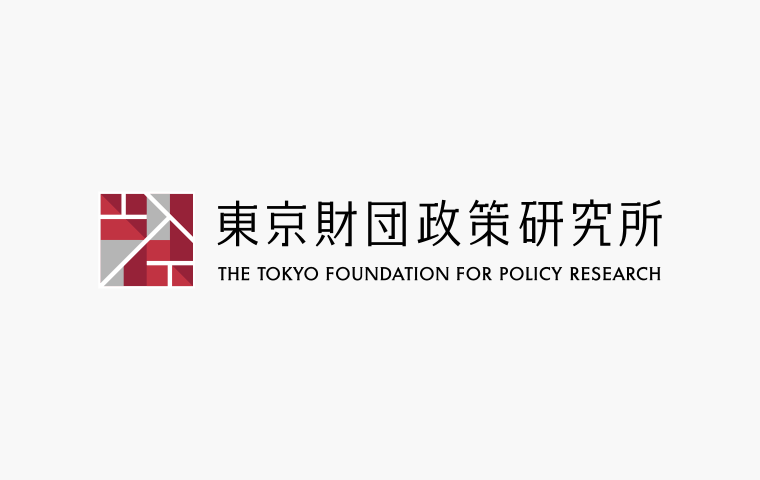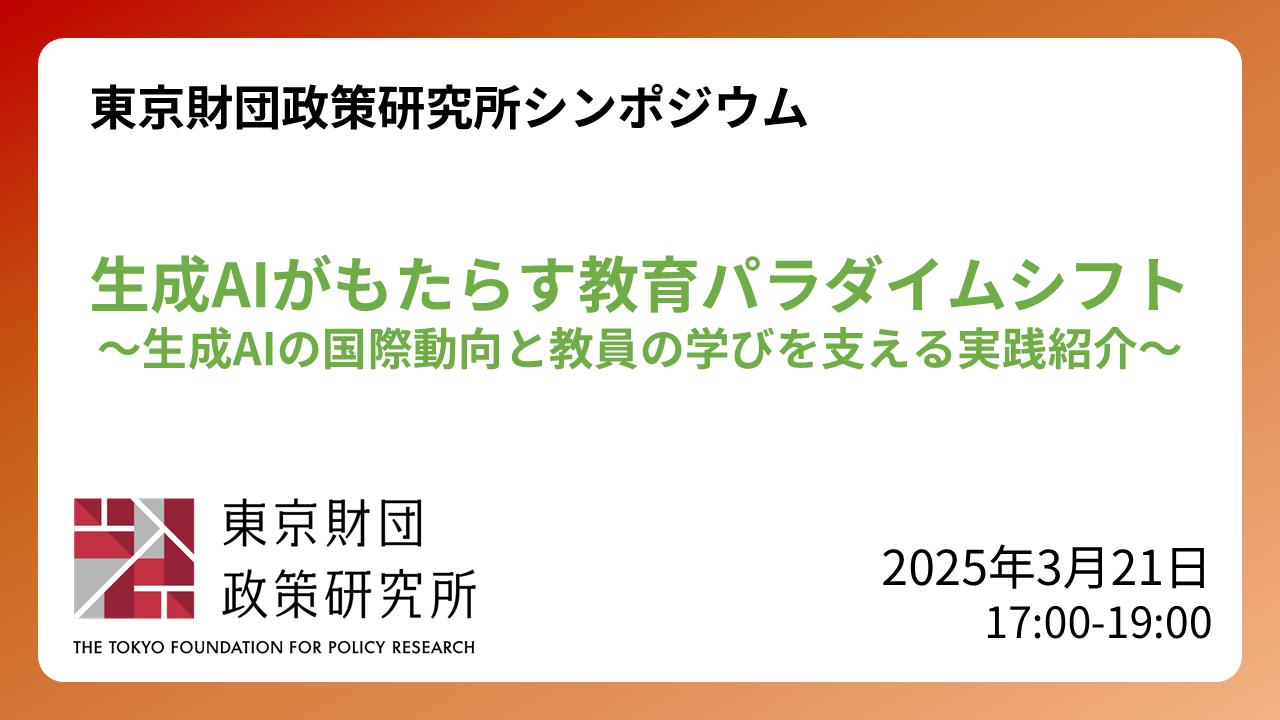
E-2024-031
2022年11月以来、ChatGPTをはじめとする生成AIの急速な発展は社会に大きな影響を及ぼし、教育現場での活用可能性も広がっています。ところが、教員の負担は年々増加しており、学びを支える教員への支援が十分と言える状況ではありません。
そこで、研究プログラム「学び続ける教員を支える生成AI に関する学びの場づくり」(研究代表者: 吉田塁)では、教育現場における生成AIへの理解の深化と活用の促進を目的とし、教員が最新の情報を含む形で生成AIの理解を深め、実践知を効率的に共有し合える環境の構築に取り組んでまいりました。
本シンポジウムでは、冒頭において、内閣府「人間中心のAI社会原則会議」の座長や総務省「AIネットワーク社会推進会議」の議長を長年務めている須藤修研究主幹が生成AIに関する国際的な動向の解説も含めた基調講演を行い、実際に出席してきた国際会議等の場で得られた各国の生成AIに関する実情や様々な研究データを踏まえ、マクロな視点で日本の現状や目指す方向性などについて提言しました。
また吉田塁主席研究員は、本研究プログラムで取り組んできた教員の学びを支える実践内容を含む活動報告に加え、それらの取り組みや自身の研究から得られた知見をもとに、立場ごとの生成AIに対する向き合い方や捉え方について提言しました。
最後に、吉田塁主席研究員をファシリテーターとしたパネルディスカッションを行い、須藤修研究主幹と本研究プログラムのリサーチアシスタントである学生2名を交え、初めて生成AIを使った際の印象、生成AIの使い方、生成AIによって数年後の未来がどう変わるかなど示唆に富んだディスカッションが活発に行われました。
世間では、まだまだ生成AIに対してネガティブな捉え方がなされる場面も少なくありません。しかし、生成AIの無い未来を考えるほうが難しく、人間が中心となって生成AIを活用していくことが重要です。本シンポジウムが教育現場や各家庭における生成AIとの向き合い方、活用の方法を考えるきっかけになりましたら幸いです。
■講演資料
須藤 修 東京財団政策研究所 研究主幹/中央大学 国際情報学部 教授
吉田 塁 東京財団政策研究所 主席研究員/東京大学 大学院工学系研究科 准教授
■参加者アンケート
本シンポジウムに参加くださった皆様からのアンケートをご覧いただけます。
開催概要
■テーマ:「生成AIがもたらす教育パラダイムシフト:生成AIの国際動向と教員の学びを支える実践紹介」
■日 時:2025年3月21日(金)17:00~19:00
■会 場:YouTube Live
■登壇者:
須藤 修 東京財団政策研究所 研究主幹/中央大学 国際情報学部 教授
吉田 塁 東京財団政策研究所 主席研究員/東京大学 大学院工学系研究科 准教授
梶 花音 「学び続ける教員を支える生成AI に関する学びの場づくり」リサーチアシスタント/東京大学 教養学部 2年生
山本 笙太 「学び続ける教員を支える生成AI に関する学びの場づくり」リサーチアシスタント/東京大学 教養学部 2年生
■プログラム:
・開会挨拶
吉田 塁 東京財団政策研究所 主席研究員/東京大学 大学院工学系研究科 准教授
・基調講演
須藤 修 東京財団政策研究所 研究主幹/中央大学 国際情報学部 教授
・活動報告
吉田 塁 東京財団政策研究所 主席研究員/東京大学 大学院工学系研究科 准教授
・パネルディスカッション
須藤 修 東京財団政策研究所 研究主幹/中央大学 国際情報学部 教授
吉田 塁 東京財団政策研究所 主席研究員/東京大学 大学院工学系研究科 准教授
梶 花音 「学び続ける教員を支える生成AI に関する学びの場づくり」リサーチアシスタント/東京大学 教養学部 2年生
山本 笙太 「学び続ける教員を支える生成AI に関する学びの場づくり」リサーチアシスタント/東京大学 教養学部 2年生
・閉会挨拶
吉田塁 東京財団政策研究所 主席研究員/東京大学 大学院工学系研究科 准教授
■研究プログラムについて
「学び続ける教員を支える生成AI に関する学びの場づくり」研究プログラム
◆ 教育×生成AI ポータルサイト Manabi AI(まなびあい)
教育における生成 AI の利活用に関する基本的な情報や最新情報をまとめることを目的にしたポータルサイトです。(吉田塁主席研究員: 監修・記事作成)