
R-2024-128
本プログラムでは、ウェルビーイングを育む教育のひとつの視点として、「問いを立てる力」に着目している。自己決定理論では、自律性・有能感・関係性という3つの基本的心理欲求が満たされると内発的動機づけにつながるとされており、また、この基本的心理欲求は、主体的に学び続けることやウェルビーイングにも重要な要素である。これらの基本的心理欲求も踏まえると、問いを育み、問いを立て、実現するサイクルを意識することが、生徒の主体的な学びとウェルビーイングにつながると考えられる。
現在、問いを育むための教育実践の一つとして、対話型鑑賞の実践型研究に取り組んでいる。本稿では、対話型鑑賞の概要やその教育的意義、また問いを立てる力やウェルビーイングにどのように寄与しうるかについて、解説する。
対話型鑑賞とは何か
対話型鑑賞とは、単に美術作品を理解するための手法ではなく、美術・芸術作品を介し他者と対話を重ねながらその理解や気づきを深める鑑賞方法である。この方法は、鑑賞者が作品を主体的に意味づけし、その過程で他者との対話や自己内省を通じて思考を深めることを目的としている。特に「意味生成的な美術鑑賞」という概念は、鑑賞者が主体的に作品の意味を生成し、その生成プロセスが教育的価値を持つことを強調している。
対話型鑑賞の原型は、ニューヨーク近代美術館(MoMA)による「Visual Thinking Strategies(VTS)」に端を発している。この手法は、観察、議論、解釈、そして日常生活や社会との関連付けという4段階を通じて、参加者の多角的な視点を引き出す構造を持つ。鑑賞の中で参加者は自ら問いを立て、他者との意見交換を通じて作品に新たな解釈を見出す。これにより、芸術鑑賞が単なる知識の獲得ではなく、創造的な学びの場となる。
歴史的背景と教育的意義
対話型鑑賞の起源は戦後の日本にさかのぼる。その発展には、1952年(昭和27年)に翻訳出版された教育哲学者ジョン・デューイの「経験としての芸術」が与えた影響が大きい。この作品は、教育を生徒の生活経験に根ざしたものとし、知識を押し付けるのではなく、生徒自身が経験から学ぶべきだと説いた。この思想は戦後の日本教育の基盤を形成し、美術教育にも多大な影響を与えた。
例えば、1973年に静岡県浜松市で行われた「モナ・リザ」の鑑賞授業では、生徒が自由に意見を述べ、それに対して教師が肯定的なフィードバックを行うことで、生徒の主体性を引き出した。この授業は、今日の対話型鑑賞の基盤を形成するものであった。そのような授業が50年以上前に行われていた事実は、対話型鑑賞が単なる近年の流行ではなく、教育現場で長らく培われてきた伝統に根ざしていることを示している。
対話型鑑賞の教育的効果
対話型鑑賞には以下の教育的効果があるとされる:
- 自己理解の深化:生徒が自身の考えを表現し、他者との意見交換を通じて自己を再認識する。
- 表現力と粘り強さの向上:議論を通じて自分の考えを伝える力が養われ、粘り強く意見を形成する力も向上する。
- 他者理解の促進:異なる視点に触れることで共感力が育まれ、多様な文化や価値観を受け入れる態度が醸成される。
これらの力は、変化が激しく不確実性の高い現代社会を生き抜くための「生きる力」として重要である。
このように、対話型鑑賞は、子どもたちが自由に作品を解釈し、自らの疑問や気づきを共有する場を提供する。この過程で生徒は、自分が見たものに対する解釈や感想を言語化し、他者の視点を取り入れることで、より深い洞察を得る。このような体験は、生徒が主体的に学ぶ力を育み、自己決定に基づく学びの姿勢を強化する可能性がある。
実践方法と課題
対話型鑑賞を実践する際には、以下の要素が重要である:
- 作品選定:多様な解釈が可能な作品を選ぶことで、参加者の想像力を引き出す。
- 問いの設定:オープンエンドな問いを設定し、生徒の自由な発言を促す。
- ファシリテーターの役割:中立的な立場から、生徒の発言を肯定し、さらに深い思考を促す。
しかし、対話型鑑賞が表面的な模倣にとどまる場合、参加者の主体性が損なわれる危険性がある。そのため、ファシリテーターや教師は生徒の発達段階や学習課題を十分に考慮した授業設計を行う必要がある。
対話型鑑賞の可能性
対話型鑑賞は、教育現場にとどまらず、社会全体のウェルビーイングを向上させる可能性を持つ。美術作品を通じた気づきや発見は、個人の自己理解を深めるだけでなく、他者理解や多文化共生を促進する。その結果、対話型鑑賞は、人と人、文化と文化をつなぎ、豊かな社会を形成する手段となる。
このように対話型鑑賞は、学びを「知識の蓄積」から「意味の生成」へと転換させる新しい教育の形を示している。この手法がさらに広がり、教育現場や社会で持続可能な形で活用されることが期待される。
参考文献
上野 行一
『風神雷神はなぜ笑っているのか―対話による鑑賞完全講座』光村図書,2014年,ISBN 978-4-89528-894-1.

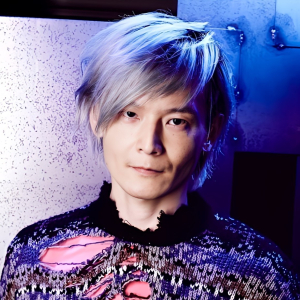


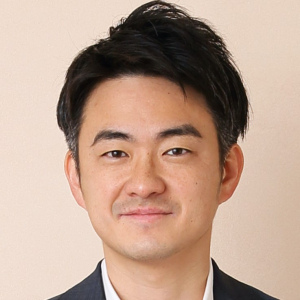



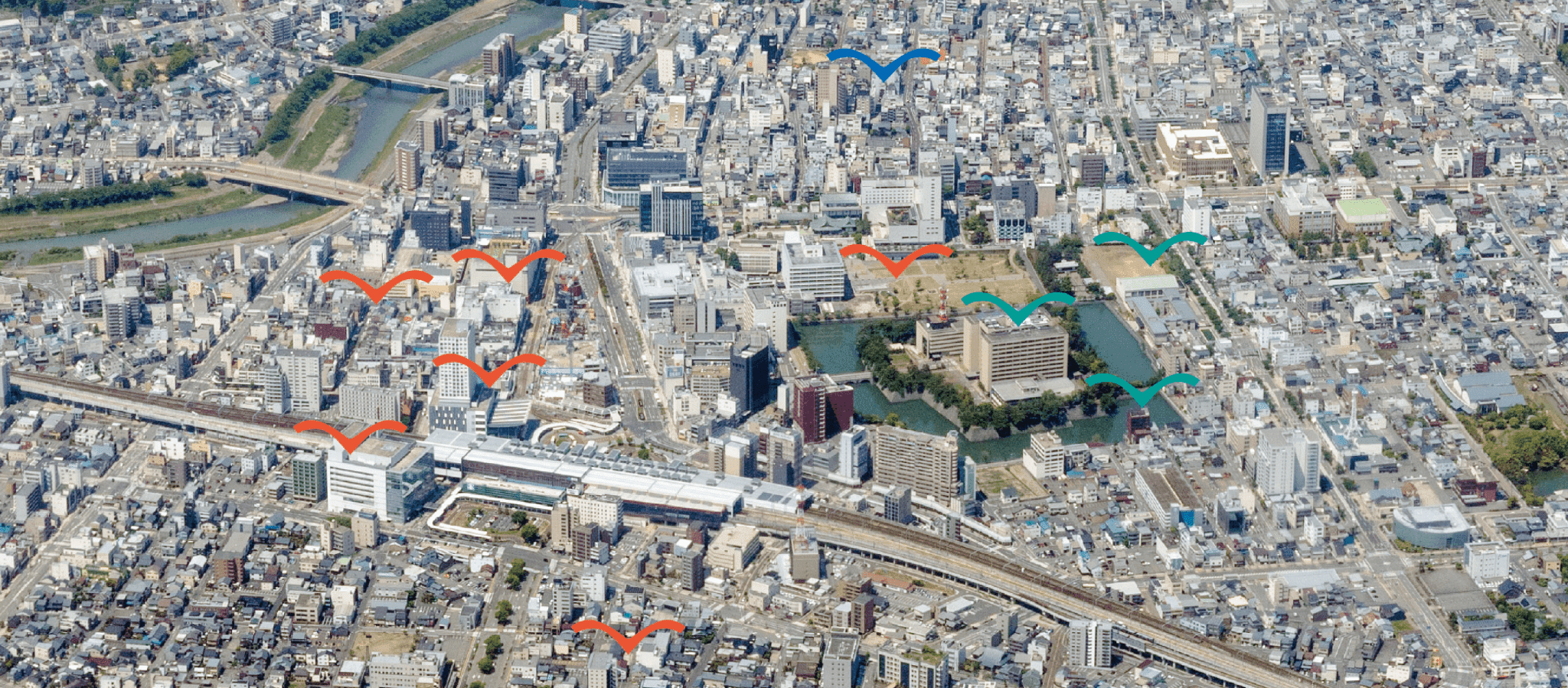










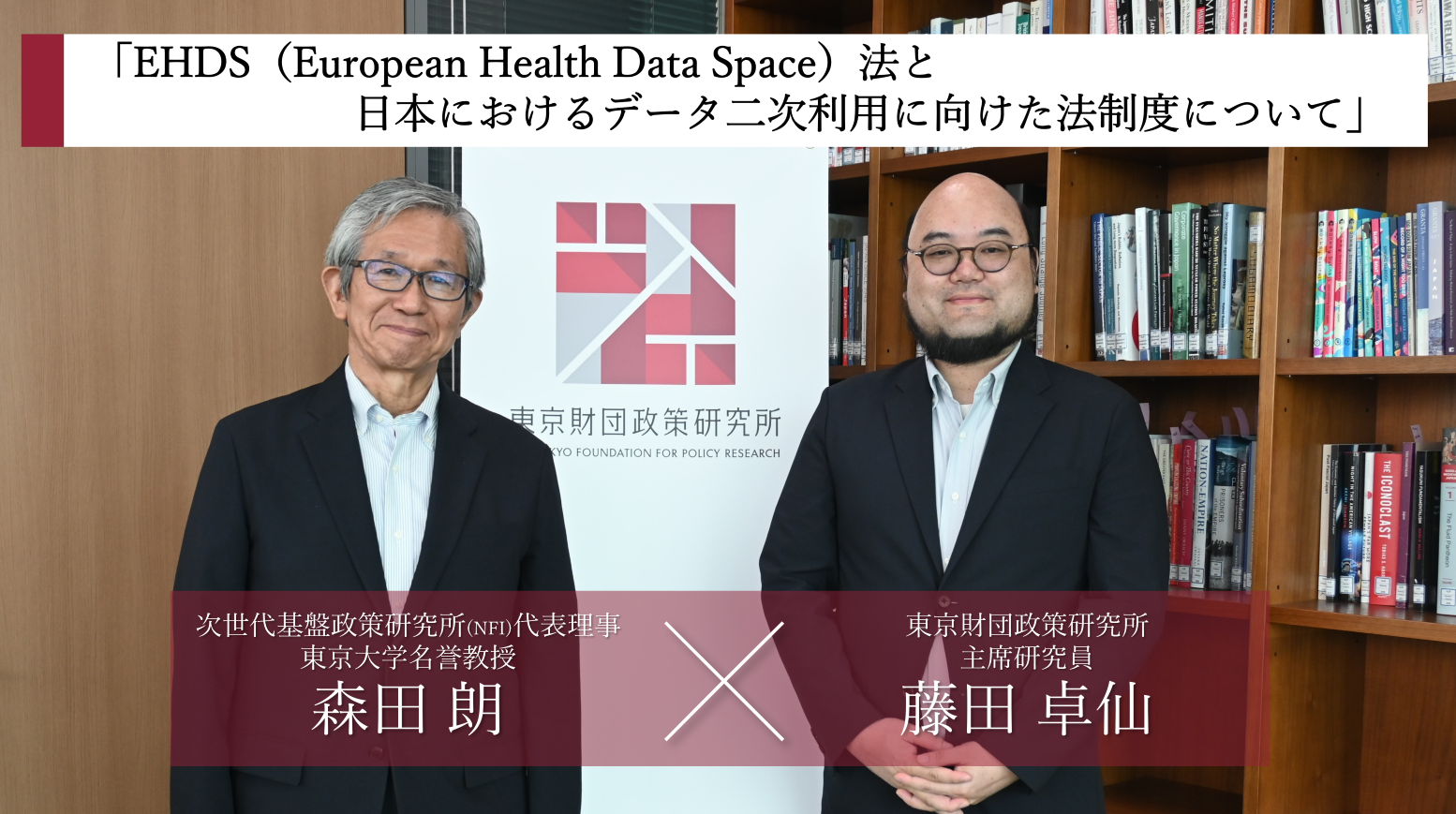







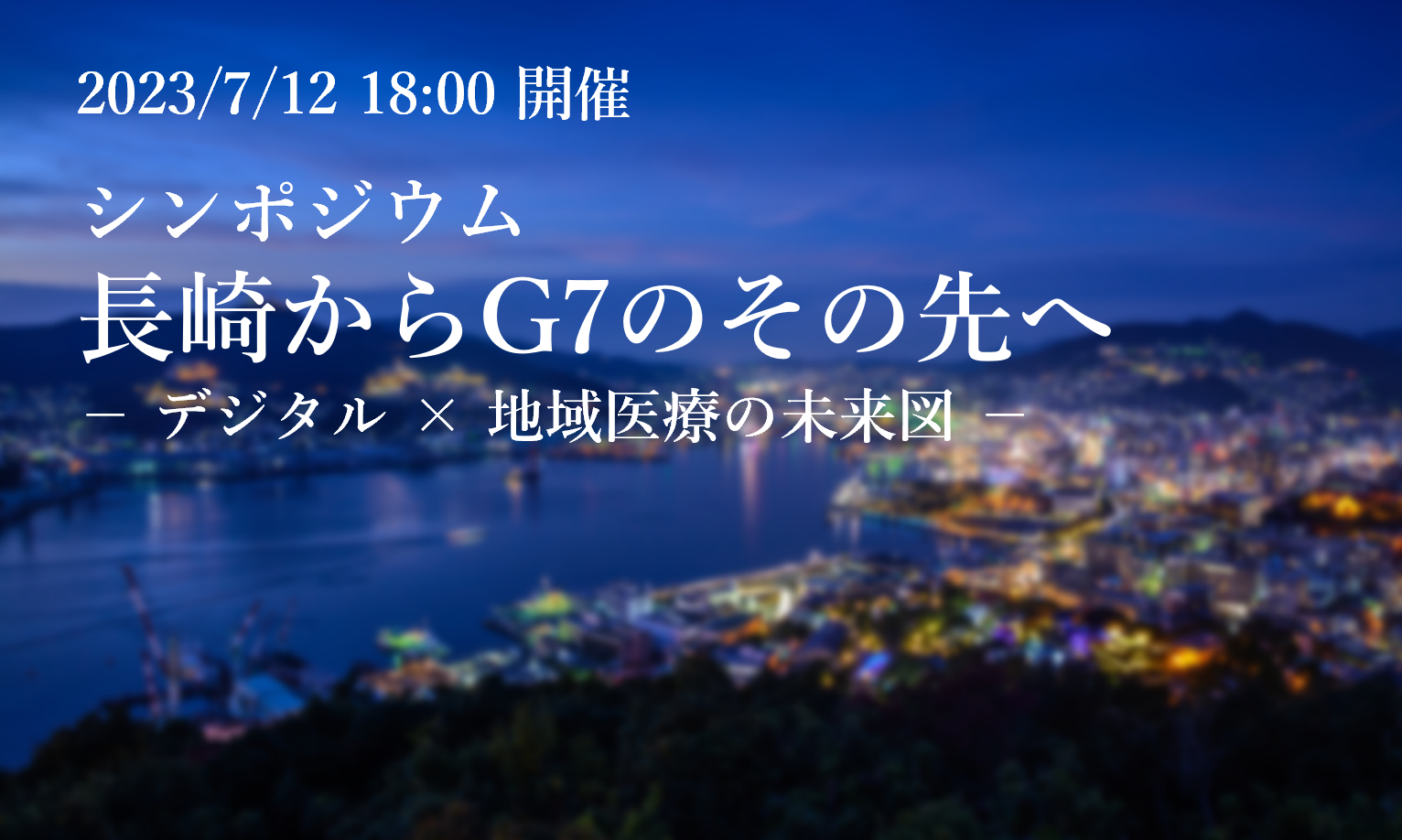









































_jpg_w300px_h200px.jpg)












































