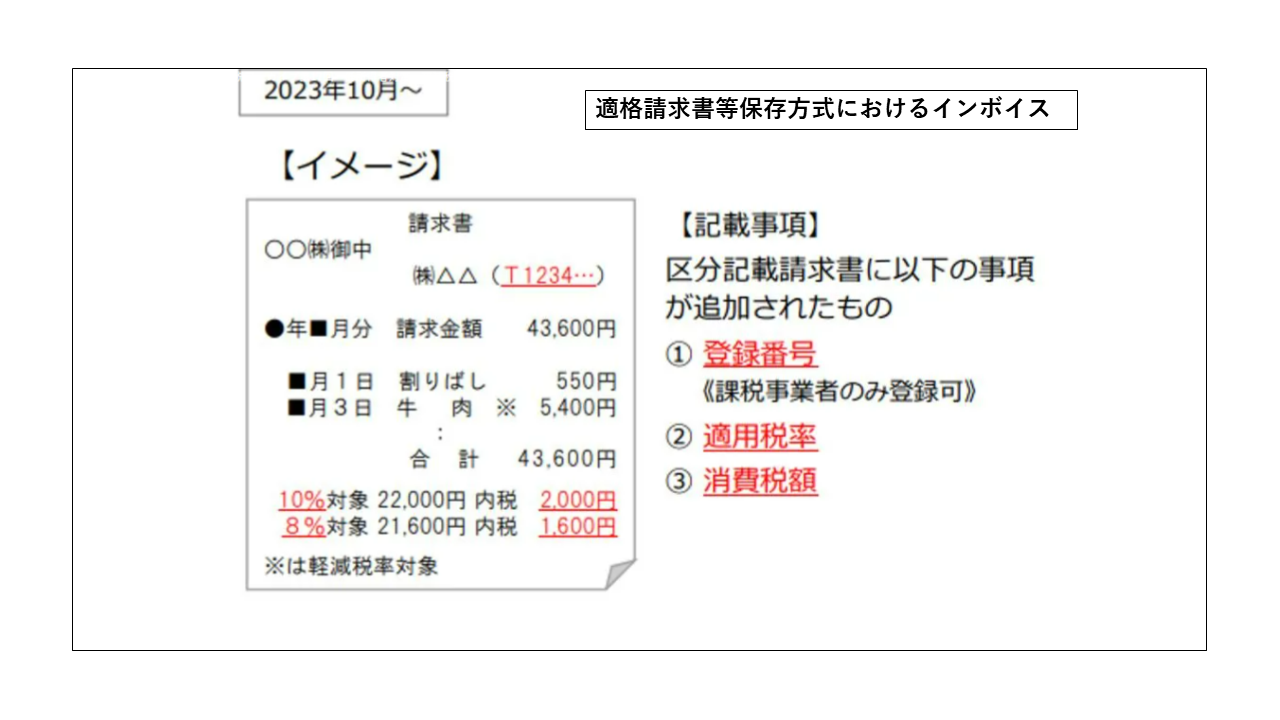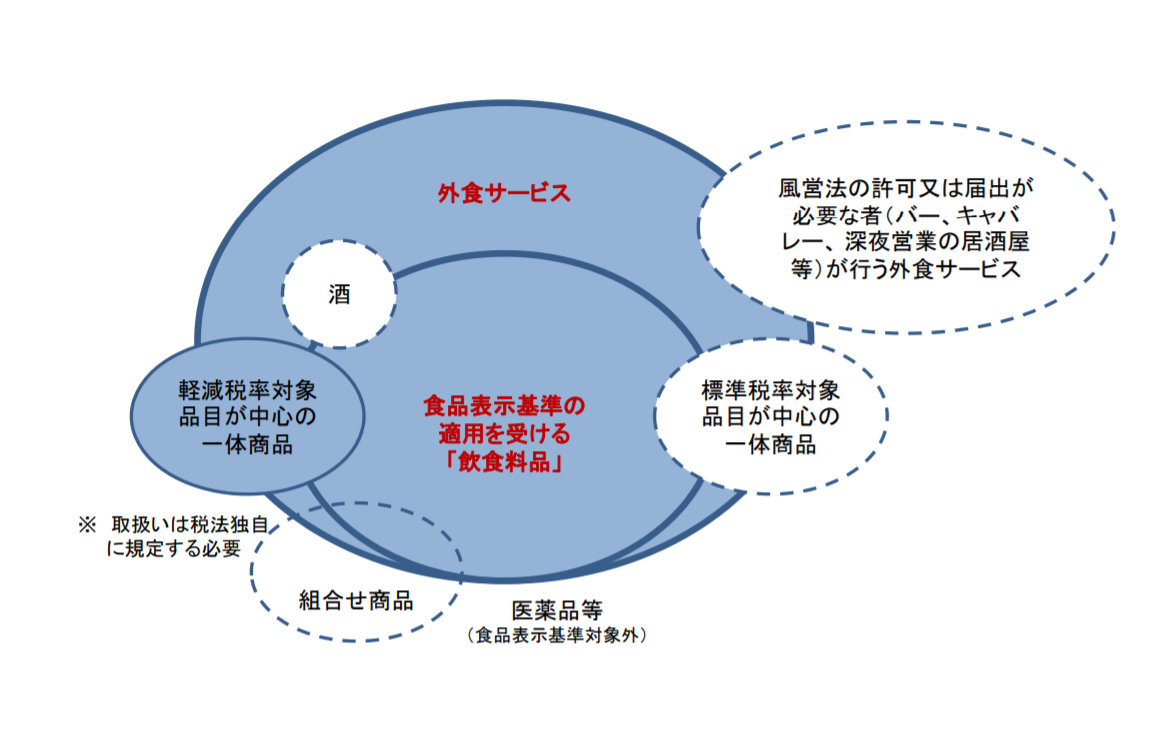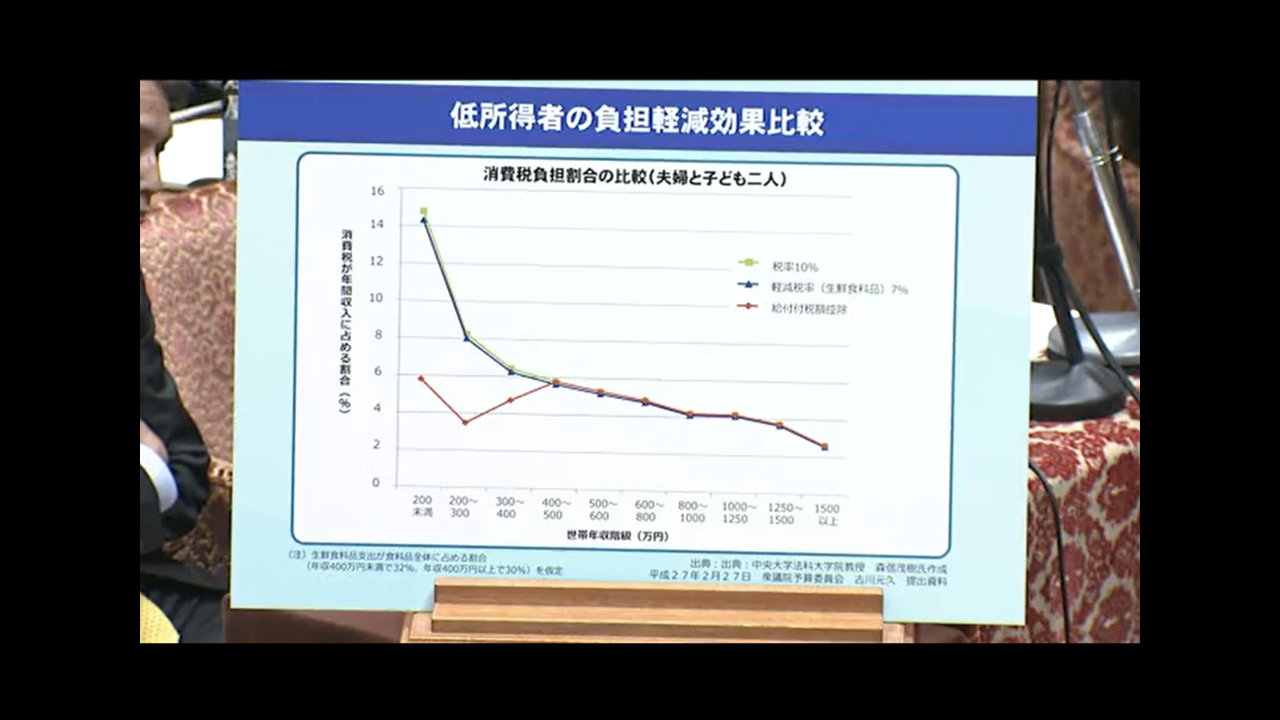森信 茂樹
私は東京財団で、 「税と社会保障の一体化の研究」プロジェクト を担当し議論を重ねてきた。本年1月にまとまった「社会保障・税の一体改革素案」については、さまざまな論点は残されてはいるものの、われわれが07年以降提言してきた、社会保障・税番号や、それを活用した「給付付き税額控除」が素案の中に入っており、基本的に賛成という立場である。24日から国会が始まり、社会保障・税一体改革についての議論が焦点となるが、消費税をめぐり論点となりそうな点を以下、取り上げて、自らの考え方を述べてみたい。
第1の論点:経済成長をすれば増税は必要ない
これは、最も多く見受けられる議論である。
この議論は、「500兆円のGDPが名目4%成長して、その際40兆円の税収が12%(5兆円弱)伸びる」というような計算が前提となっている。これは、税収の伸び率と名目成長率の比である税収弾性値を3(12÷4)という前提を置いている、ということである。しかし80年代、90年代のわが国の平均的弾性値の実績を見ると、おおかた1.2から1.3となっている。2000年代は、経済がマイナス成長なので、弾性値の意味がない。つまり、弾性値が3などと言うことは、起こり得ないことで、空想的なことを前提にしているということである。
また、名目成長率が4%になった場合には、金利はおそらくそれに近い水準であろう。そうであるなら、国の歳出の方も、国債費を大幅に増やす必要がある。さらに、物価も上昇しているので、物価連動となっている社会保障費などは歳出を増やす必要がある。つまり、歳入が増加しても、歳出も合わせて増加するので、財政再建にはならないということである。
重要なポイントは、金利が上昇すれば、金融機関の抱える大量の国債に含み損が生じる。これが、貸し渋りを通じて、中小企業の倒産をもたらす可能性があり、まさにパニックの引き金となる。
レーガン政権1期の時、「経済成長すれば財政再建ができる」という経済理論がラッファーカーブと並んで主張された。これは、後に「ブードゥーエコノミクス(呪術経済学)」とからかわれた理論である。さすがに、わが国でも、まともな経済学者でこの論を唱える人は少なくなった。
誤解なきよう述べれば、規制緩和などによる民間主導型の経済成長が必要なことは、いうまでもない。医療や介護、農業などの分野にも、もっと規制緩和を進め、成長の種をまいていく必要がある。つまり、政府は経済成長の加速と税負担の増加策、さらには歳出削減を3つの柱として政策を進めていく必要がある。
一方で、金融政策により無理やり経済成長率を4%、5%に持っていくという考え方には、実現可能性が限りなく低いということだけでなく、上述したようなさまざまな副作用のほうが大きいので行うべきではないという立場でもある。
第2の論点:デフレ経済下では消費税率を引き上げると、中小企業は転嫁できないので倒産ラッシュが起きる
消費税は、物価の引き上げを通じて取引の相手方、最終的には消費者に負担を求める税なので、取引の相手方への転嫁が行いにくいデフレ経済下では、自らのマージンを削って納税する必要が生じる。これが行き過ぎると、倒産を招くという批判である。
確かに、経済が継続的な物価の下落状態に陥るようなデフレスパイラル時には、消費税引き上げ分の転嫁ができず注意する必要がある。しかし、現在のように、物価が横ばいで、わずかながらでも経済成長が続いているような状況では、このような極端なことは起きないであろう。
自由経済の下では、価格は需要と供給によってきまる。コストによって決まるわけではない。事業者は、為替レートや国際市況の変化により日々変わる原油価格や1次産品価格応じて、製品価格をその都度変えているわけではない。消費者への価格転嫁が容易でない場合には、節約や生産性の向上などあらゆる努力を行ない、それを吸収しようとする。 日々変動するコストを全体として織り込んで、マージンを確保しつつ商売を行うのであって、消費税率の引き上げはコスト変動のワンノブゼムにすぎない。大企業や競争相手も同じ条件である。倒産が続発するという議論はまやかしであろう。
関連して、外税方式でなければ、相手方に転嫁できない、という議論もある。平成16(2004)年以後、消費者に価格を示す場合には、「外税表示」(税抜き価格表示)から、消費税額を含む価格の表示(「総額表示」)を事業者に義務付ける法律改正が行われたが、その理由は、「消費者」にとっては、店頭で余分な計算をする必要もないので、総額表示の方が明快で便利、というものである。消費税の議論をする際に、「事業者」の利便や利益だけでなく、「消費者」の利便も考えることが必要ではないか。
VAT(付加価値税)を発明したフランスでは、近い将来、消費税率が引き上げられるような場合、事業者は、価格転嫁のしやすい売れ筋商品から、次第に値段(総額表示)を引き上げていくそうである。
第3の論点:経済の成長率が伸び悩む場合には、消費税率の引き上げを停止すべきである
素案には、以下のような「弾力条項」がついている。経済への配慮として、「消費税率引上げ実施前に「経済状況の好転」について、名目・実質成長率、物価動向など、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案した上で、引上げの停止を含め所要の措置を講ずるものとする規定を法案に盛り込む」ことである。
リーマンショック並みの経済変動が生じればともかく、名目経済成長が少々低くても、粛々と進めていくべきではないか。生産労働人口が年率1%程度減少する中では、4%や5%の名目成長率など当分考えられない。また、そうなればなったで、冒頭のような問題が生じる。
重要なことは、消費税率の引き上げにより、社会保障財源が確保されることで国民に安心効果(「非ケインズ効果」の裏返し)が生じ、中期的にはわが国経済にプラスの影響を与えるという視点を持つことだ。
スウェーデンの例を紹介してみよう。1990年代初頭のバブル経済崩壊により、GDP比12%という大幅な財政赤字に陥ったスェーデン政府は、景気回復のための大減税を93年に行った。ところが、国民の多くは、「今日の減税は、明日の悪いニュース」と受け取り、政権は選挙で議席を失った。新しい社会党政権が財政再建にコミットする政策に転換し、経済回復が始まり、経済成長と財政再建の両立が可能となったという。このあたりのことは、富田俊基氏の「日本国債の研究」に詳細に書かれている。
今わが国には、安心効果とは逆の「非ケインズ効果」が生じているという有力な説がある。「非ケインズ効果」とは、人々が財政赤字からくる将来の社会保障に安心できず、財布のひもを締めるので、経済が落ち込むという現象である。
わが国で、90年代に、大量の国債を発行して減税や公共事業の追加を行ったが、景気回復しなかった原因の一つも、国民が、将来の国債の償還や利払いに不安を感じ、近い将来増税があるのではないかと考え始め、所得の増えた分を追加的な消費に振り向けず貯蓄に回した結果であるという実証研究もある。
パリバ証券の河野龍太郎氏は、次のような分析をしている。「高齢化要因を取り除いた貯蓄率の推移を見ると、2000 年代に入ってむしろ上昇傾向さえ見られる。」その原因は、「2000年以降、年金制度を始め社会保障制度の不備が顕わになると同時に、公的債務の大幅な膨張も加わり、人々は不安の高まりから貯蓄を行った。とりわけ負担を強いられる現役世代が、将来の負担増懸念から、消費を抑制し貯蓄を増やしたのだと思われる。・・公的債務が未曾有の水準まで膨張した日本で、それ(非ケインズ効果)が始まっているのである。」というのである。
このような状況の下で、政権が、財政再建に向けての政権の強いコミットメントをすると、民間経済主体の経済政策に対する信認は回復し、将来不安が解消され、消費をはじめとした経済活動は活発化する。これが、先述のスウェーデンの例で、そのほかイタリアにも見られたという研究がある。
このことは、「増税すれば経済が良くなる」ということではなく、増税と併せて、国民の安心できる社会保障制度の整備(さらには歳出削減)を行うことによって、国民が財政再建に納得すれば、安心効果が期待できるということである。ここでも、成長戦略がセットである。
第4の論点:消費税は、輸出企業に還付するので、大企業優遇税制ではないか
企業が国内で生産されたモノを外国に輸出する場合には、輸出代金には消費税はかからない(免税)。さらに、モノをつくるための仕入れにかかる消費税は、輸出者に還付される。これが、輸出企業優遇であると、問題にされることがある。
国境を超えるモノの取引に付加価値税(消費税)をどのように課税するかについては、生産地で課税すべきという考え方と、消費地(仕向け地)で課税すべきという2つの考え方がある。それぞれメリット、デメリットがあるが、EUは、自国の競争条件を勘案して、消費地課税を原則としている。つまり、国境を越えた取引には、生産地ではなく消費地で課税する、ということが国際的に確立したルールとなっており、わが国もそのルールを採用している(せざるを得ない)のである。
そこで、わが国からモノを輸出する場合には、消費税はわが国では課税されず、わが国へ輸入されるモノには、国内で生産されたモノと同様に輸入時に課税することとなっている。
具体例として、輸出企業Aが、取引先Bから80(税抜き価格)で部品を購入し、自ら製品に仕上げて100で売るという場合を考えてみよう。
国内取引では、A社は、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を控除(仕入れ税額控除)して、税務署に消費税を納入する。つまり、100×5%=5から、80×5%=4の消費税を控除し、1(5-4)を納税する。
これが、輸出取引になると、100にかかる消費税額は免税(ゼロ税率)となり5の分の課税がなくなる(免除される)ので、A社は、4(0-4)の消費税還付を受け取ることになる。
では、輸出企業は還付分だけ得をしたのだろうか。そうではない。A社はすでに仕入れ先であるB社に4の消費税分を代金の一部として負担しており(B社は80に対して課税されるのでA社に84の代金を請求する)、A社は4を還付してもらってもB社に払ったその4が戻ってくるだけ、つまり、プラスマイナスゼロである。B社も、自らの付加価値にかかる分はA社に価格転嫁しているので、負担はない。
課税されない5という消費税の免除額は、Aの生み出した付加価値20(100-80)にかかる消費税(1=20×5%)だけでなく、仕入れ先であるB社や、その前段階の業者(たとえば原料・材料を供給した者)が作り出した付加価値(利益)である80にかかる消費税(4=80×5%)を含む合計である。この5の課税を免除することにより輸出企業は消費税抜きの価格で輸出価格を設定することができ、輸出先の国の消費者に日本の消費税負担が及ばないようにしているのである。
つまり、輸出企業は、輸出の際に、仕入れ代金としてすでに支払った(負担した)消費税分(4)を還付してもらい、自らの付加価値に対する消費税分(1)を納税しなくてよいので、輸出価格に5を上乗せして回収しなくてよい(日本の消費税を転嫁しなくてよい)というだけの話である。輸出企業が得をしているわけでも損をしているわけでもない。
第5の論点:今後の地方分権を踏まえて、消費税は全額地方税とすべきだ
これは、道州制論者に多く見受けられる主張である。社会保障・税一体改革では、消費税収は全額社会保障に充てられることになっている。例えば、基礎年金国庫負担の半分である7-8兆円は、消費税収でまかなうことになる。そこで、消費税が地方に回れば、その分(国庫負担の半分)を所得税などで調達する必要がある。このことだけを考えただけでも、消費税を全額地方に回すことは不可能である。
また、政策論としては、実現可能性がない提言である。「道州制の下で、たとえば関東州は15%、北海道は10%と、道州ごとに異なる税率決定が可能になるので、分権に対応できる」という意見である。しかし、消費税は仕向け地課税が原則で、道州間で異なる消費税率を施行するには、関所による州境調整が必要となる。これは非現実的である。
これに対して、一部に、カナダの行っている商業統計によるマクロ的な調整モデルを使えば、異なる税率も理論的には可能であるという議論がある。しかし、例えマクロ的に清算ができたとしても、道州により異なる消費税率が実現すれば、我が国経済が混乱することは目に見えている。通販やネット販売など事業者が直接消費者に販売するような取引(B to C取引)は、他州の消費者に販売しても、事業者の存在している州の消費税率しか課税できない。また、全国展開する事業者は、売上げ・仕入れの管理を、販売店のある州ごとに、適用税率を管理する巨額の事務コストが生じる。さらに、売上げを低い税率州で行ったと仮装する帳簿操作・脱税の監視は誰がどのように取り締まるのか、という問題もある。
道州ごとに異なる消費税率は、「理論的には可能」であるかもしれないが、それは「机上の空論」である。
分権後の地方は増加する公共サービスに必要な自前の財源をどう確保すべきか。これには2つの考え方がある。1つは住民税の拡充である。スウェーデンでは、地方の基幹税として、基礎控除等を最小限に限定して32%程度の均一税率を課す応益税な所得税を採用している。わが国もこれに習い、住民税を課税最低限を絞った応益的なものに変え充実していくことが考えられる。
もう一つは、地方消費税の独立・拡充である。消費税を、国●●%、地方●●%と分離・独立させる。対国民では税率は一本とする。分権後の地方政府は、自らの財源拡充の必要性を、徹底的な行財政改革を進めつつ、国と切り離して住民に直接訴え、みずから拡充努力を行い、消費税率を引き上げる。私は、後者の方法が現実的ではないかと考えている。