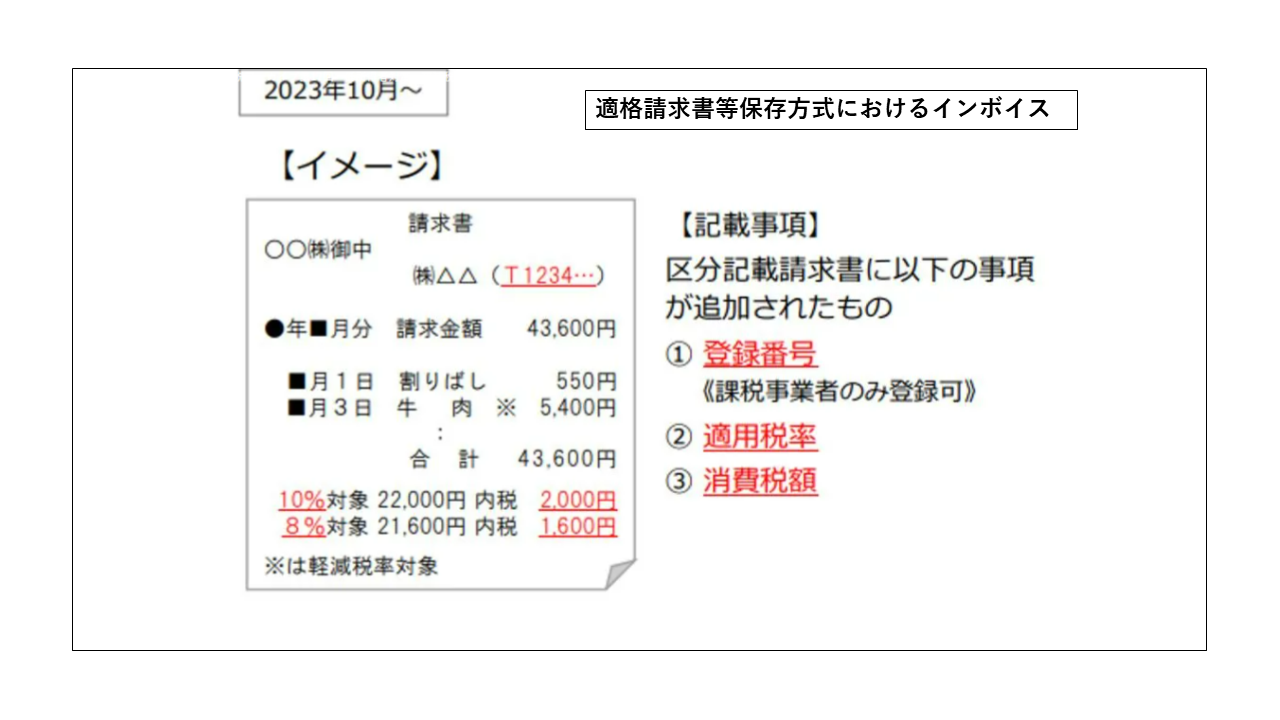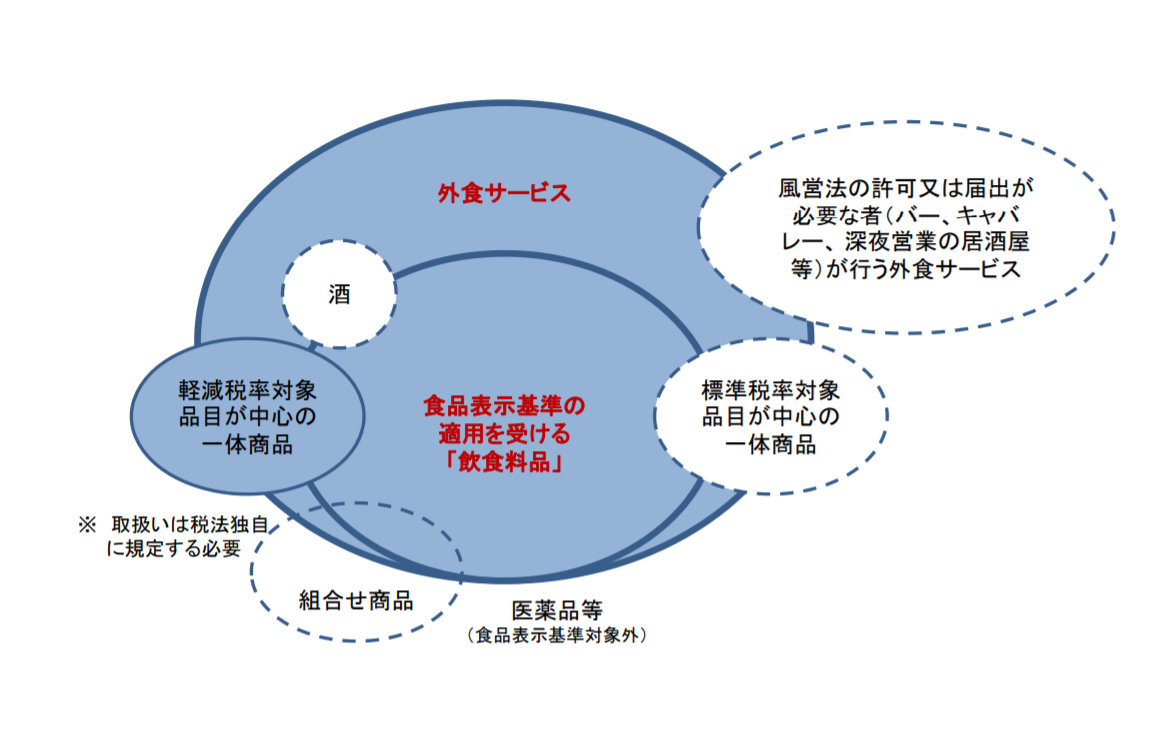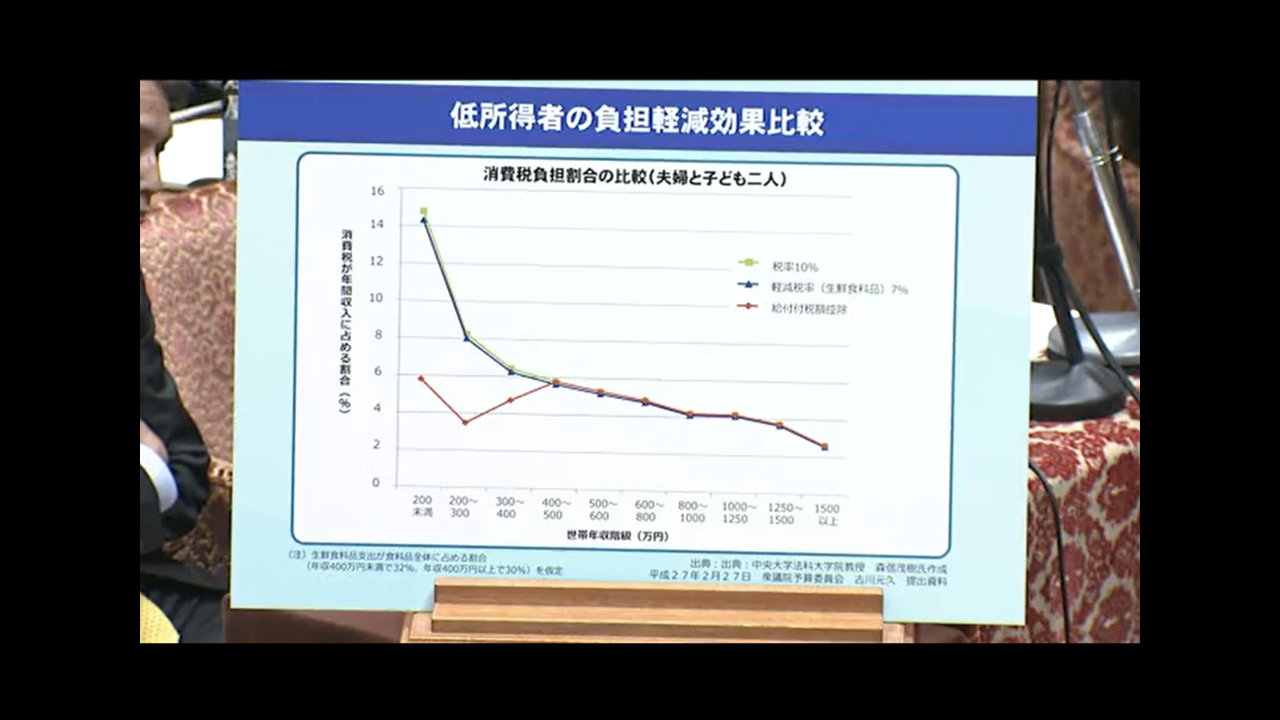ここ数年、わが国の法人税の世界では、「課税ベースを拡大して税率を引き下げる改革」が継続的に行われてきた。その結果わが国の法人税率(地方税の損金算入を調整したいわゆる実効税率)は、安倍総理の公約通りの20%台(16年度、29.74%)となった。国税の法人税率を見ると23.4%と、米国トランプ税制改革で予想される25%前後の税率と比べても、遜色のない水準である。
このような税率引下げの反面、課税ベースが拡大されてきた。とりわけ、資本金1億円超の企業に適用される地方法人税である外形標準課税の外形割合(付加価値割の割合)は、04年度導入時の4分の1から16年度の8分の5へと拡大された。この結果、労働集約的な企業、あるいはROEの比較的低い企業の中には、一連の法人税改革の結果、負担が増加する企業も出始めている。
また、外形標準課税のような、所得を課税標準としない税制は、他の先進諸国でも縮小傾向にあり、わが国だけが拡大することは、グローバル経済の中でわが国法人税制のガラパゴス化(国際標準からのかい離)を進めることとなった。そこで経済団体は、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」法人税改革を、平成29年度税制改正要望から落とすところとなった。
このことは、税務当局に、じっくり法人税本法を見直す時間的な余裕を与えることになった。これが、これから取り上げるスピンオフ税制が実現した背景だ、と筆者は考えている。
米国では、税法で多様な組織再編税制が規定されている。会社分割の方法も、親会社が財産出資を行うことによって子会社を設立し、その取得した株式を親会社の株主に分配する方法(スピン・オフ)、親会社が財産出資を行うことによって子会社を設立し、その取得した株式を親会社の株主が保有する親会社株式と交換する方法(スプリット・オフ)など3つの類型がある。この規定を活用し、事業や資産を売買して莫大な利益を上げるのがウォール街のビジネスの一つである。そのようなグリーディー資本主義を横目でにらみつつ、わが国でも変化が生じてきた。
わが国の組織再編税制は、「企業グループ内再編成」と「共同事業再編成」の2つしか認めておらず、支配株主がいない分割型分割や子会社株式の分配については税制適格とならない(課税が生じる)。しかし今回の税制改革によって、分割型分割と現物分配によるスピンオフが、課税の心配なく(課税繰り延べ)できるようになる。企業の機動的な事業再編成を促進することによって、デフレ脱却を目指す攻めの経営を促すことの重要性が認識されたといえよう。
これにより、ノンコア事業の切り出し・他社との統合が可能になり、親会社の経営者は本来の中核事業に専念することができるし、スピンオフされた子会社の方も、迅速で柔軟な意思決定が可能になり、経営者や従業員のモチベーションが高まるという効果も期待される。
これによりコングロマリットディスカウントの解消も期待される。よく取りあげられるのは、米国のイーベイである。イーべイの子会社であるペイパルがスピンオフにより独立し、自由に活動できるようになった結果、双方を合算した企業価値はスピンオフ前の企業価値を上回り、コングロマリットディスカウントが解消されたという事例である。埋没していた会社の価値が、スピンオフによって新たに見いだされたのである。
米国型の、事業切り売り・グリーディー資本主義には、注意をする必要があるが、そこはわが国の税法でしっかりと条件が付されている。
長いデフレでアニマルスピリッツが萎えているわが国に、攻めの経営を促すツールの一つとしてスピンオフの導入は必要な税制改正だ。
(2017年4月号『月刊資本市場』連載「明日へのかけ橋」(85話)より転載)