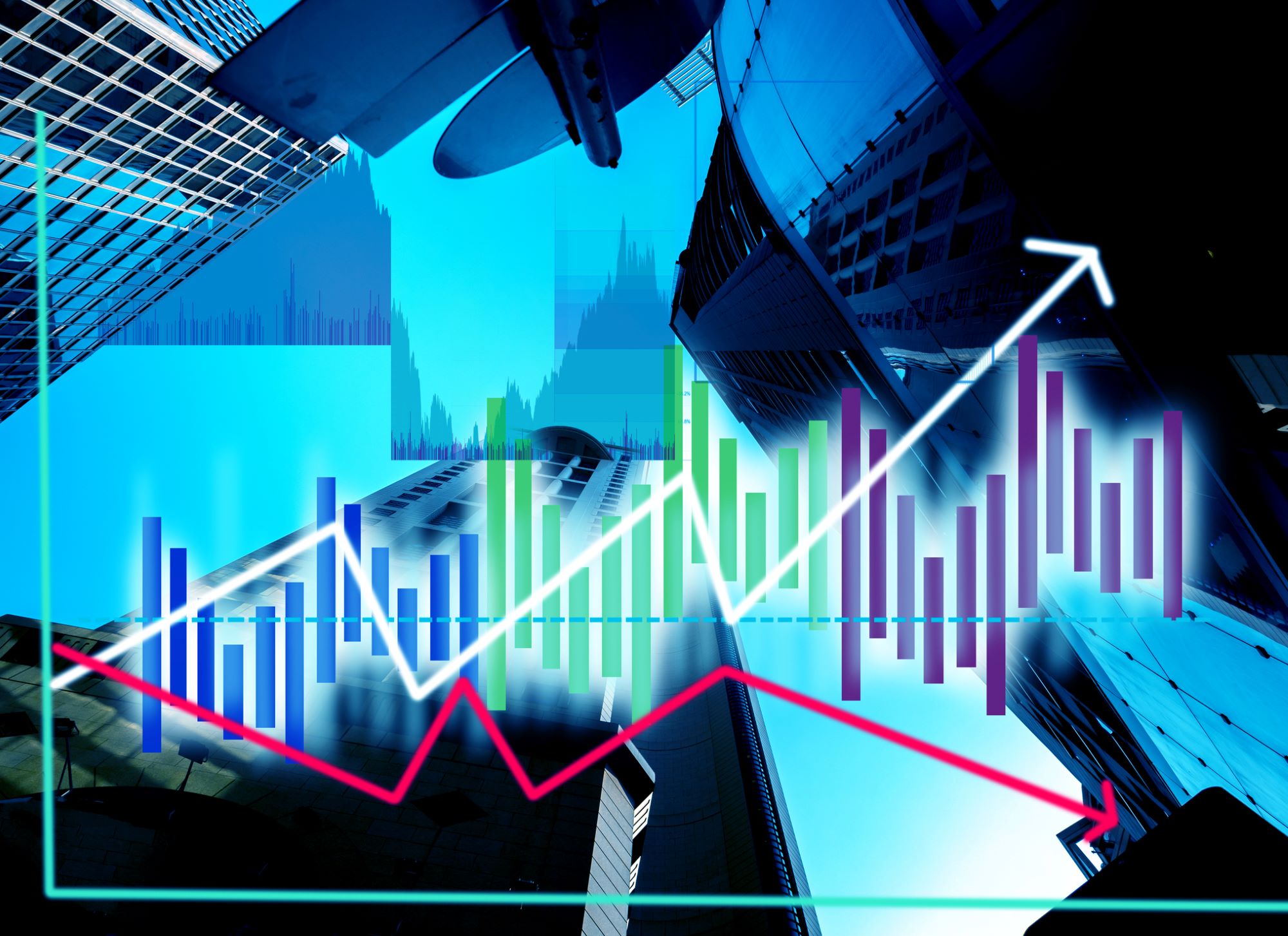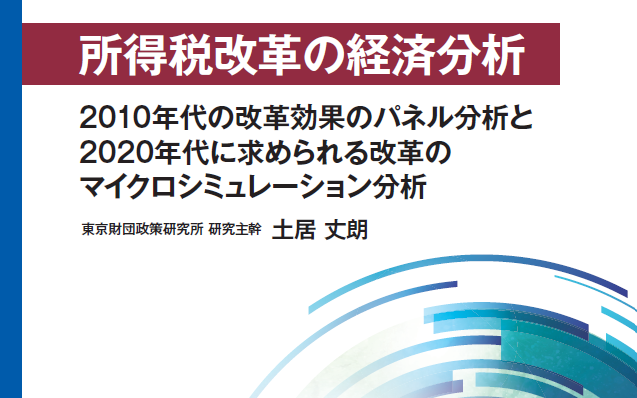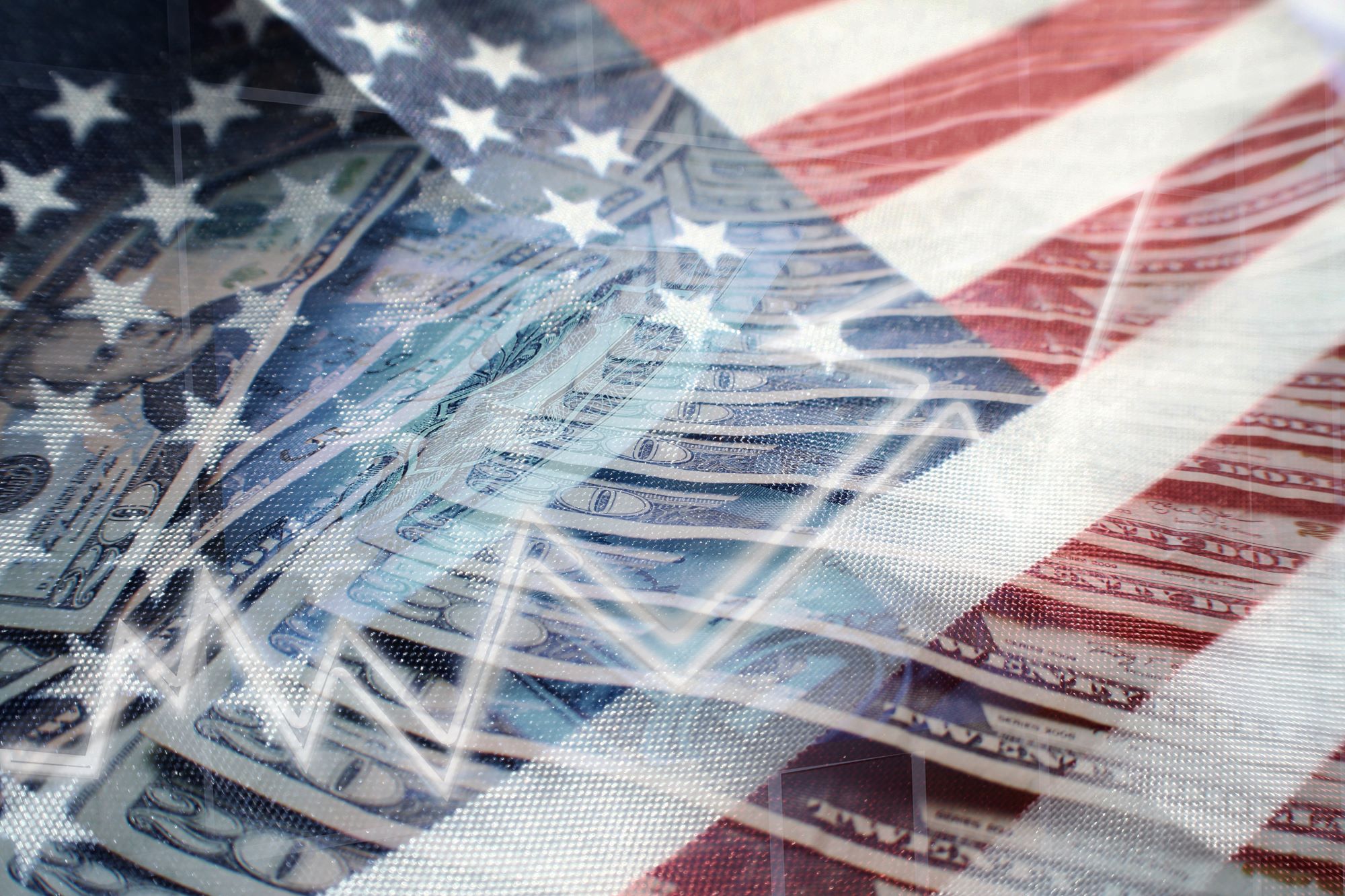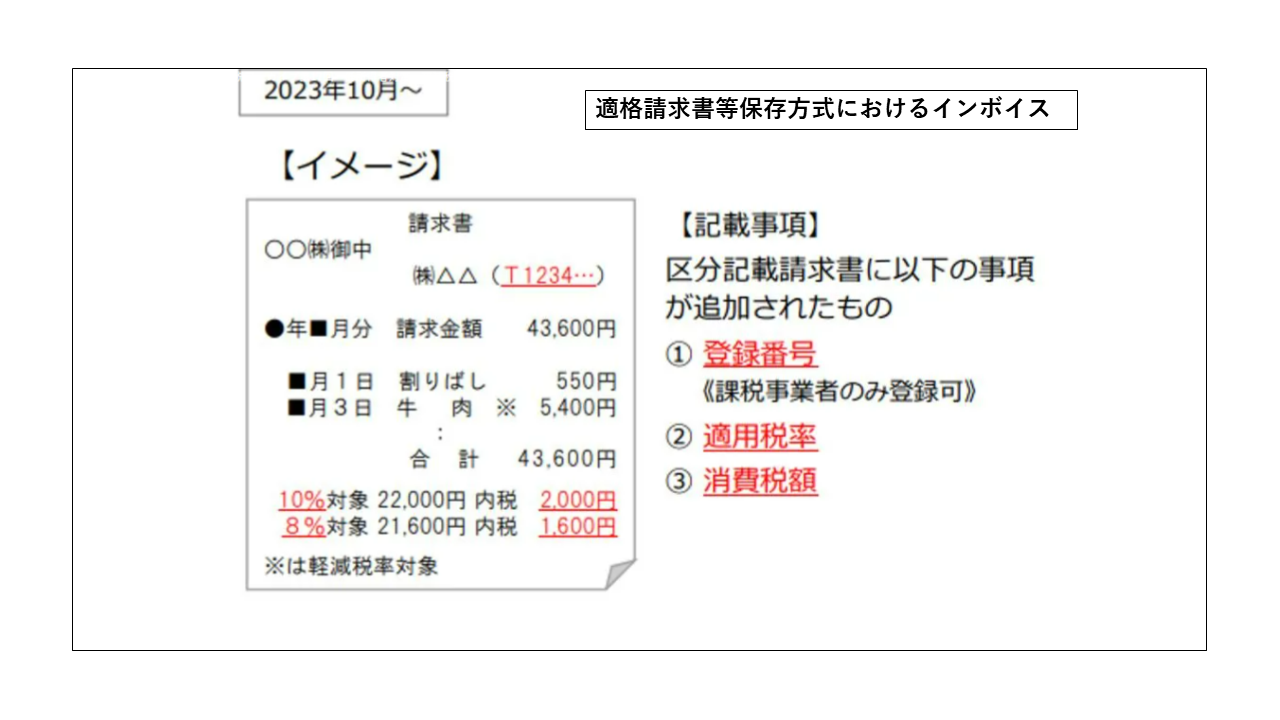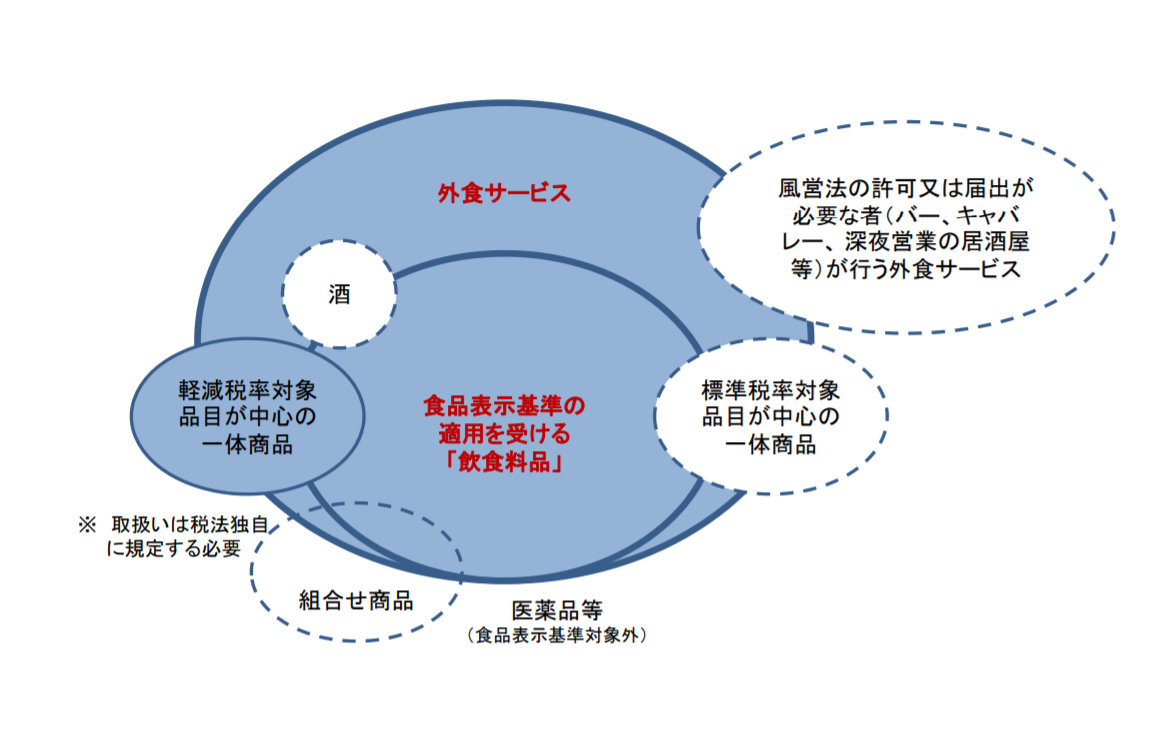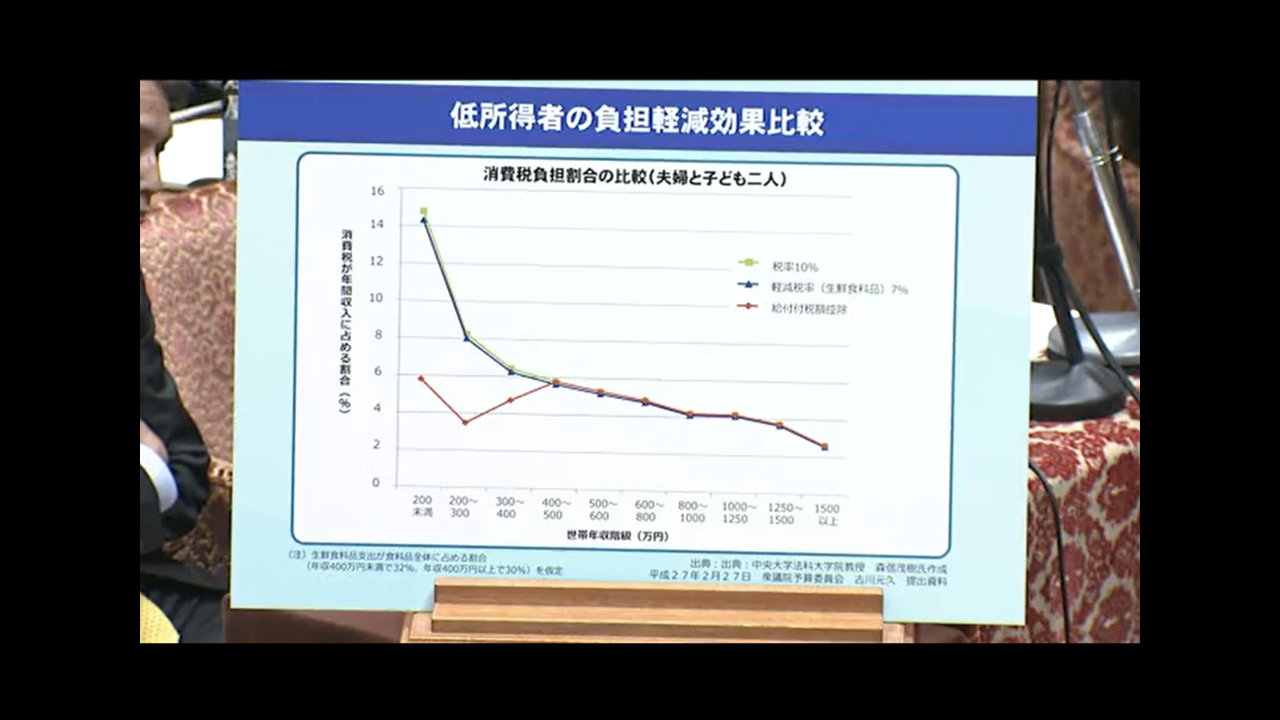| 前書き なぜ今、緊急提言が必要か 1. 非常時と平時の財政を分ける:新型コロナ対策特別会計創設の提言 2. 財政依存からの脱却:「低金利のわな」を打開する政策 3. 医療版マクロ経済スライド 4. 社会保障の「支え手」をどう増やすか 5. 給与情報を迅速かつ正確に把握する行政インフラ整備 6. マイナポータルを活用しフリーランスのセーフティネットを |
3. 医療版マクロ経済スライド
医療財源の構造問題
新型コロナウイルスのパンデミックは、日本や世界において、創薬としてのワクチン開発や医療基盤の重要性を改めて認識させたが、日本の公的債務残高(対GDP)は200%超で累増が続いており、医療財政を含め、日本の財政状況は厳しい状況に直面している。このような状況の中、いま医療財政は2つの課題を抱えている。1つは「公的医療保険財政の持続可能性をいかに高めるか」という課題であり、もう1つは「新型コロナウイルスの感染拡大という危機にいかに対応するか」という課題である。
この問題にわれわれはどう対処すればよいか。まず、一つ目の課題に対しては、後期高齢者医療制度(75歳以上が加入)の診療報酬に自動調整メカニズム(いわゆる「医療版マクロ経済スライド」)を導入することが考えられる。
そもそも、後期高齢者医療制度の財源(給付費)の9割は現役世代の保険料からの支援金と公費で賄われ、残りの1割が75歳以上の保険料で賄われているだけで、賦課方式である年金と似た財政構造を有する。このため、「医療版マクロ経済スライド」も、2004年の年金改革で導入した「マクロ経済スライド」を参考に構成できるはずだ。
すなわち、公的年金のマクロ経済スライドと同様、例えば、現役世代の人口減や平均余命の伸び等を勘案した調整率を定めて、その分だけ、後期高齢者医療制度にかかる総額の伸びを抑制することにしてはどうか。この調整のために最も管理しやすい方法は、75歳以上の診療報酬において、ある診療行為を行った場合に前年度Z点と定めている全ての診療報酬項目の点数を、今年度では「Z×(1 −調整率)点」と改定することである。
自己負担は診療報酬に比例するため、診療報酬を抑制しても75歳以上の自己負担(窓口負担)が基本的に増加することはない。また、過去の趨勢的に医療費の約半分は医療従事者の人件費だが、このメカニズムの下では医療費(対GDP)は一定水準に落ち着き、人件費も成長率に連動して伸びる。
では、調整率はどの程度か。財務省の「我が国の財政に関する長期推計(改訂版)」によると、40年間で対GDP比の医療費等は約5%ポイントの上昇で、1年間の上昇は平均で0.125%であるため、その増加を抑制する調整率は年間0.125%に過ぎない。診療報酬を年間平均で0.125%だけ下方に調整するだけで、医療財政を安定化できる可能性があるのは「驚き」ではないか。
しかも、この自動調整メカニズムは、医療費の「伸び」を抑制するのが目的であり、医療費の「総額」をカットするものではない。例えば、20年度における診療報酬本体の改定率は0.55%増であったが、医療版マクロ経済スライドを導入すると、改定率は(0.55−β)%増となる。例えば、β=0.15%であれば、診療報酬本体の改定率は0.4%となる。
以上は平時の対応だが、危機時の対応も喫緊の課題だ。そのうち最も重要なのは、冒頭で掲げた、もう1つの課題である「新型コロナウイルスの感染拡大という危機」への対応である。
日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会の「新型コロナウイルス感染拡大による病院経営状況緊急調査(最終報告)」(2020年5月27日)によると、いま病院の中には、コロナ危機で大幅な赤字に陥っているものも多い。このような状況において、「コロナ危機で不要不急の過剰な診療が浮き彫りになり、これで医療財政の適正化が進む」という意見もあるが、筆者はこの意見は間違っていると思う。なぜならば、本当は必要な医療を受けたかったにもかかわらず、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、病院での感染を恐れ、受診を回避した患者が相当数いた場合は、誤った解釈となってしまうからである。
また、2020年11月以降、再び新型コロナウイルスの感染が東京都を中心に拡大しており、現状のままでは、医療機関の財務が耐えられるとは限らず、今後の状況次第では深刻な状態に陥る病院が出てくる可能性も否定できない。
医療費「予算枠」の効用
では、この問題にどう対処すればよいのか。1つの発想として、医療費の「予算枠」で余った財源の一部を、医療機関の赤字の補填に活用する方法があると考える。例えば、政府が行う公共事業では計画で一定の予算枠が組まれているが、その予算の枠内で財源に余りが出れば、追加の公共事業で予算を消化することが許される場合がある。公的医療保険は原則出来高払い制であり、現行制度では、医療財政においてこのような予算枠は存在しないが、もし後期高齢者医療制度の医療費全体に予算枠が存在していれば話が変わってくる。
この点で重要となるのは、「医療版マクロ経済スライド」が持つ本当の役割である。既述のとおり、医療版マクロ経済スライドは、現役世代の人口減や平均余命の伸び等を勘案した調整率を定めて、その分だけ、全体の総額の伸びを抑制する仕組みである。しかしながら、後期高齢者医療制度の診療報酬に医療版マクロ経済スライドを導入するということは、後期高齢者医療制度の医療費全体に予算枠に相当するものを新たに設けることを意味する。
すなわち、医療版マクロ経済スライドとは、後期高齢者医療制度の医療費が予算枠を上回る分を診療報酬の自動調整により予算の枠内におさめる方式であり、コロナ危機などの影響により、診療報酬の自動調整を発動せずとも、後期高齢者医療制度の医療費が予算の枠内を下回る際には、危機時の対応として、その余った財源を後期高齢者医療制度の追加予算として利用しても構わない可能性が出てくる。
例えば、2017年度における後期高齢者医療制度の予算は約15.4兆円であるが、このうち公費と支援金の合計で約13.7兆円もある。いま、2020年度の後期高齢者医療制度の予算が2017年度とあまり変わらず、コロナ危機などの影響で医療機関への受診が全体で年間15%減(75歳以上の受診も同様に年間15%減)となったケースを考えてみる。この場合、大雑把な試算では、後期高齢者医療制度の医療費全体で約2.3兆円(=15.4兆円×15%)の財源が余ることになる。公費と支援金の合計(約13.7兆円)に限っても、約2兆円(=13.7兆円×15%)の財源が余ることになり、この財源はコロナ危機に伴う病院の赤字補填の一部に活用できる可能性がある。
もっとも、注意が必要なのは、このような対応が可能なのは「医療版マクロ経済スライド」が導入され、後期高齢者医療制度の医療費全体に予算枠が存在するケースに限られる。すなわち、現行制度上、医療機関に対する報酬は出来高払い制であり、コロナ危機で医療機関への受診が大幅に落ち込めば、その分だけ、医療機関の収支は悪化する仕組みになっているが、予算枠に余剰があれば、危機時の対応として配分しても構わないことにする。だが、このような対応を可能するため、「医療版マクロ経済スライド」を必ずセットで導入する政策的な条件を付与するわけだ。
なお、コロナ危機などの影響で国内総生産(GDP)が急速に落ち込んだときに、「医療版マクロ経済スライド」や「予算枠」の扱いがどうなるのかということに関する疑問もあろう。結論から述べる限り、GDPに対するショックが一時的なケースでは、「医療版マクロ経済スライド」や「予算枠」はショックが発生する前と変わらない。理由は単純で、公的年金の「マクロ経済スライド」もショックが発生する前と変わらないためである。公的年金は5年に一度、年金財政の健康診断と言える「財政検証」を行っており、今後100年間の年金給付と財源が長期で一致するよう、「マクロ経済スライド」で微調整する。その結果、中長期的に対GDP比の年金給付は安定的に推移する。また、GDPが一時的に落ち込んだとき、年金給付をカットしたという報道を耳にしたことがあるだろうか。年金ではそのようなルールは存在しない。
以上のとおり、いま医療財政は、公的医療保険の持続可能性の他、喫緊の課題として、コロナ危機への対応を求められている。コロナ危機への規制改革としてはオンライン診療の恒久化に注目が集まるが、それで医療財政の持続可能性やコロナ危機で悪化する医療機関の収益を改善することはできない。しかしながら、「医療版マクロ経済スライド」や「予算枠」の導入は、この問題を同時に解決できる可能性を秘めている。

(出所)小黒一正「日本経済の再構築」(日本経済新聞社)第5章
4. 社会保障の「支え手」をどう増やすか
「支え手」増加と高齢者就業にかかるブレーキ
社会の「支え手」拡大のためには、高齢者の就業機会のさらなる拡大が求められる。政府はこの点に関して、定年廃止や70歳までの定年延長など「雇用による措置」と、業務委託契約などを通じた「雇用以外の措置」という2本柱の方針を打ち立てている。しかし、残された問題は少なくない。「雇用による措置」については、65歳以上が対象の在職老齢年金(高在老)を撤廃しておく必要がある。「雇用以外の措置」が促す働き方の多様化に対しては、社会保険料の拠出を賃金ではなく所得をベースにしたものに改めるべきだ。
菅新政権は、新型コロナウイルスの感染拡大という最悪の状況下でスタートした。社会保障改革の方針としては、前政権から継承した全世代型社会保障の実現を目指している。その第1の方針は、「人生100年時代」を視野に置いて、高齢者の就労促進などによって社会保障の「支え手」を増やすことだ。第2の方針は、経済力があれば年齢を問わず相応の負担をしてもらう、応能負担を強めることである。
この2つの方針は、基本的に正しい。高齢化が進む中で社会保障を持続可能にするためには、その支え手を増やすことが最も有効である。それと同時に、支え手が少なくなっているのだから、支える必要がない人には、これまで以上に負担をお願いするしかない。
実は、全体の支え手はここ数年、増加傾向を見せている。図は、バブル崩壊が始まった1990年以降において、まさしく社会の支え手である就業者が総人口に占める比率がどのように変化したかを調べたものである。社会全体の就業率は、2000年代初めから半ばにかけて1990年の水準を下回って推移したが、その後はアベノミクスが奏功したこともあって回復している(現在の比率は53.2%)。一方、65歳以上の高齢就業者数/総人口比率は一貫して上昇しており、社会全体の就業率の上昇を牽引してきたことも分かる(現在の水準は7.1%)。もちろん、そのかなりの部分は短時間労働者など非正規雇用者であり、その効果は割り引いて考える必要がある。しかし、社会の支え手としての高齢者の役割が高まってきたこと自体は歓迎すべきである。
高齢者の就業機会のさらなる拡大に関しては、60歳台後半の就業機会の確保が最重要の政策課題となる。政府はこの点に関して、二本立ての方針を示している。第1の柱は、「雇用による措置」である。定年廃止や70歳までの定年延長などがその中身になっている。要するに、従来型の雇用形態を想定し、それを70歳まで伸ばすという方針だ。第2の柱は、「雇用以外の措置」である。事業者に対して、定年後に創業する者と継続的に業務委託契約を結んだり、事業主が実施するあるいは委託・助成する事業に継続的に従事させたりことを要請する。ここでは、高齢者による、雇用者以外の新しい働き方が想定されている。
しかし、それぞれの方針に対して残された課題は少なくない。まず、第1の柱については、65歳以上が対象の在職老齢年金(高在老)が手つかずのままに終わっていることが問題である。高在老は、給与と年金(2階部分)の合計が月額47万円以上になると年金が削減される仕組みであり、就業にブレーキをかけることになる。確かに、同制度によって年金が削減されるのは、会社の重役などかなり少数派である。賃金と年金の合計額は高在老に引っかからない20万円前半の人が最も多い。定年を超えれば、労働時間や賃金を抑え、年金も削減されずに満額受け取りたい。企業も人件費を抑えられるので、その方がありがたい。労使間で均衡が成り立っている。こうした低賃金・短時間労働の均衡状態の下では、高在老を廃止しても就業促進効果は発生しない、という見方が成り立つ。
だが、こうした議論の進め方はおかしい。全世代型社会保障は、65歳を過ぎても雇用者としてバリバリ働き、保険料をたくさん拠出してくれる人々の増加を目指している。こうした「雇用による措置」が奏功すれば、給与と年金の合計の分布も上方シフトする。そうなると、現状では就業に対するブレーキとなっていない高在老が、強力なブレーキとして機能し始める可能性が出てくる。「雇用による措置」によって70歳までの就業機会確保を目指すのであれば、将来ブレーキになるものは早めに撤廃しておく必要がある。
多様な働き方に対応した社会保障負担を
しかし、高齢者の就業機会は従来型の雇用だけではあまり増えない可能性もある。企業にとっては、政府から定年を延長せよ、雇用を続けろと言われても、保険料負担や人件費の増加はやはり避けたいはずである。労働者にとっても、とりわけ高在老が維持されるのであれば、わざわざ年金を減額され、さらに保険料を支払ってまでフルタイムで働きたくない。だとすれば、自営業・フリーランスになったほうがよい。年金も満額受給できる。企業にとっても、保険料負担から解放される。欧米でも高齢者の就業率は回復過程にあるが、その背景には自営業・フリーランスの拡大もある。
多様な働き方という点では、雇用以外の働き方は魅力的だし、それを推進しようとしている発想は悪くない。しかし、最大の問題は、このタイプの働き方を選択した人たちが、どのような形で社会の支え手になってくれるかだ。確かに労働供給は増加し、その意味では社会の支え手は増えるし、税収も増えるだろう。しかし、社会保険料を通じた社会保障財源の直接的な支え手増加にはつながらないかもしれない。
社会保障の財源を、雇用以外の働き方を選択した高齢就業者にどのように負担してもらうかという問題は、まだ十分検討されていない。働き方の多様化が進むと社会保険料の拠出は賃金ではなく、金融所得などを含めた幅広い所得をベースにしたほうがよいという判断もあり得る。フランスの一般化社会拠出金(CSG)とのように、社会保障財源の一部を税で徴収するというアイデアも有力な選択肢となる。この一般社会拠出金の課税対象は、賃金だけでなく金融所得や投資収益などを含む幅広いものとなっており、応能負担や所得再分配の観点からも理に適った形になっている。日本においても、マイナンバーに基づいて全国民を対象に改称されたマイナポータルに所得情報を集約させ、社会保障財源を(給与だけではなく)得られたすべての所得に基づいて拠出させる仕組みを導入すべきである。
新型コロナウイルスの感染拡大とともに、個人事業主を始めとして働き方の多様化が加速する様相を見せている。政府は高齢者の就業機会の拡大を目指しているが、雇用以外の働き方が予想以上に拡大する可能性がある。せっかく拡大した支え手の人たちの成果を社会保障の機能強化に活かすためには、雇用・賃金にリンクした従来型の社会保障負担を見直す必要がある。そのためには、マイナンバーを中心とした所得・資産捕捉の拡充、税・社会保障のデジタル化が不可欠である。しかも、それは同時に、新たな働き方のために従来型のセーフティーネットでは救済の対象から外れがちの人たちに対する、迅速で効果的な支援を可能にするものでもある。例えば、低所得の人たちに対しては、社会保険料給付を税額控除で相殺することなどにより、効率的な支援を迅速に行えるようになる。

(出所)総務省「労働力人口」「人口推計」より小塩隆士作成
共同論考(緊急提言)参加者 ※順不同
森信茂樹 東京財団政策研究所研究主幹(とりまとめ責任者)
土居丈朗 慶応義塾大学経済学部教授・東京財団政策研究所上席研究員
佐藤主光 一橋大学国際・公共政策研究部教授・東京財団政策研究所上席研究員
小黒一正 法政大学経済学部教授
小塩隆士 一橋大学経済研究所教授
西沢和彦 日本総合研究所調査部主席研究員