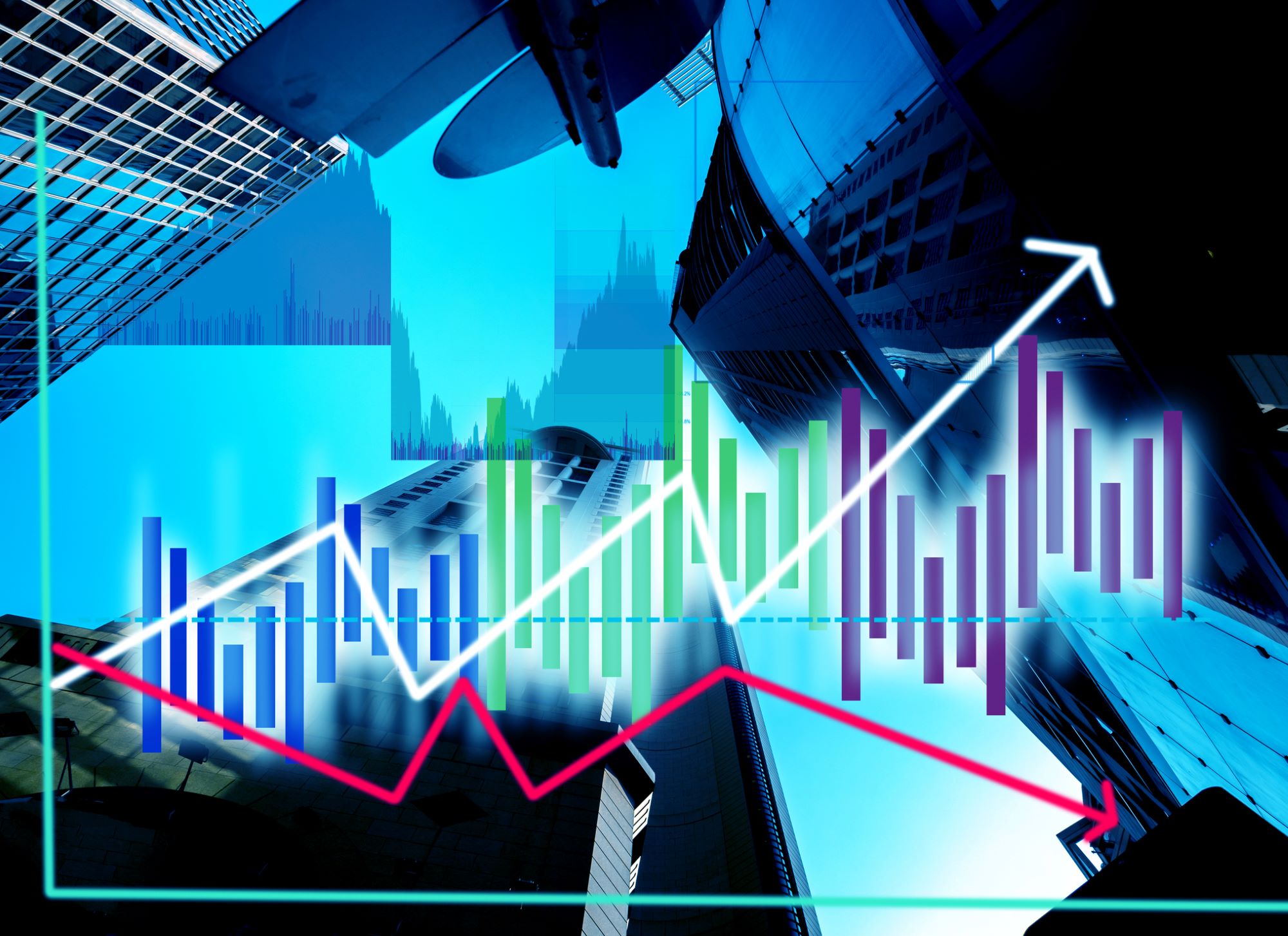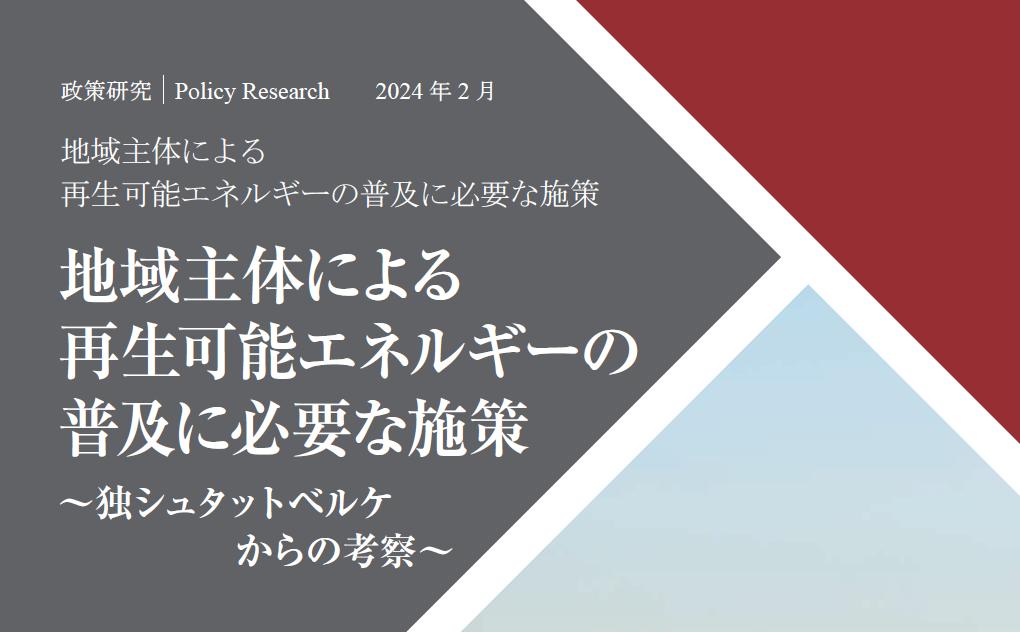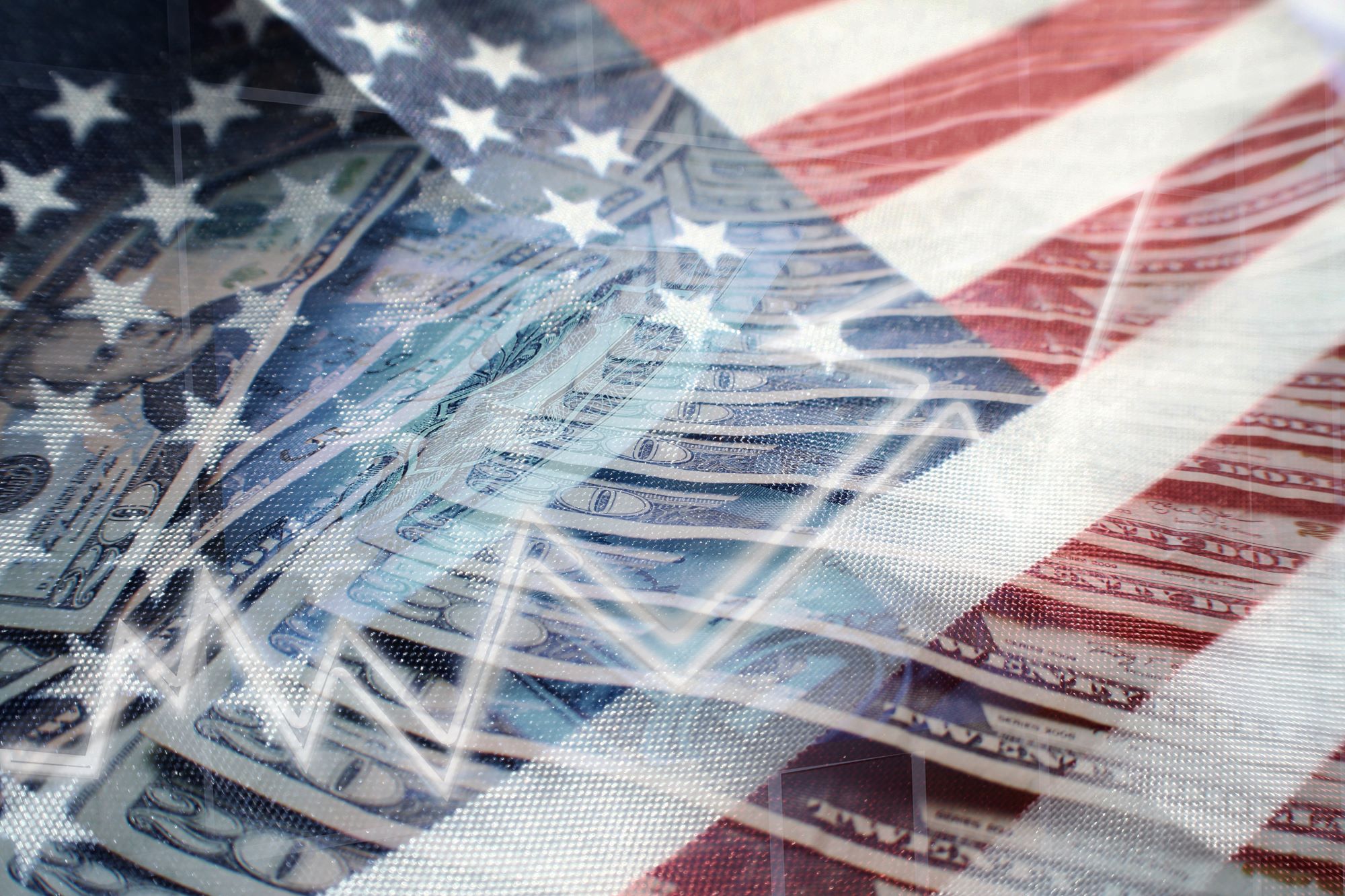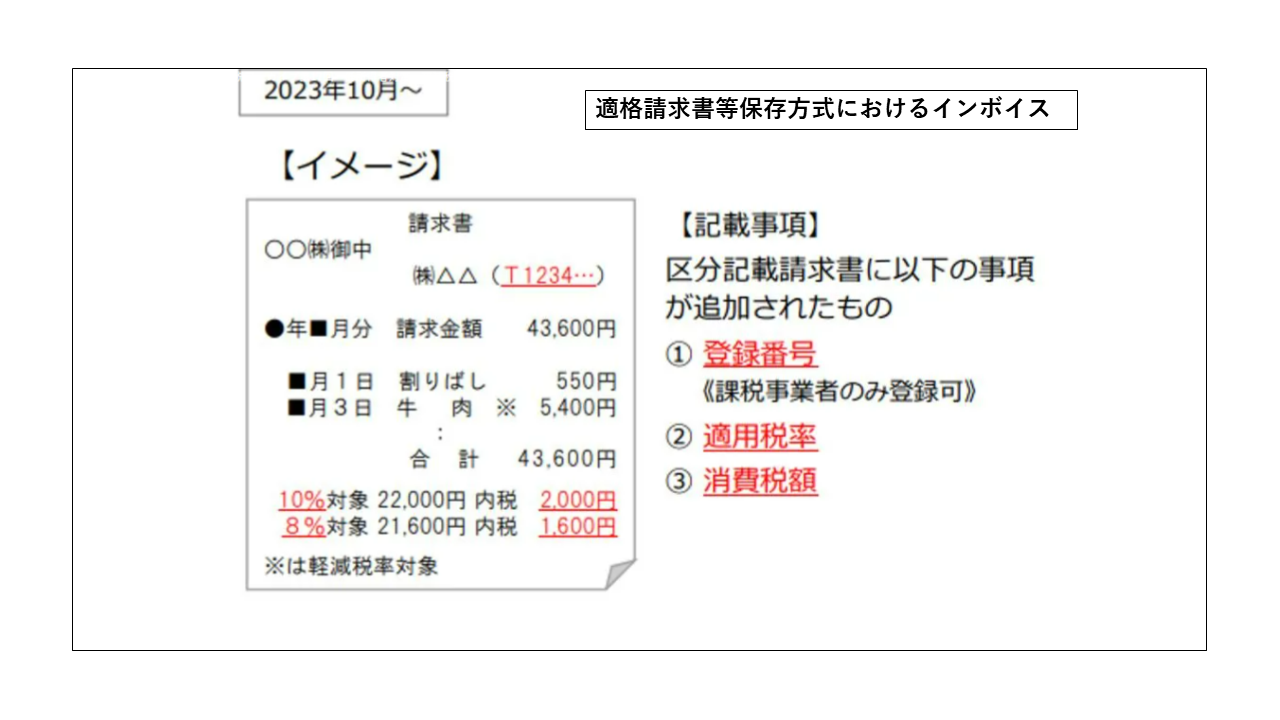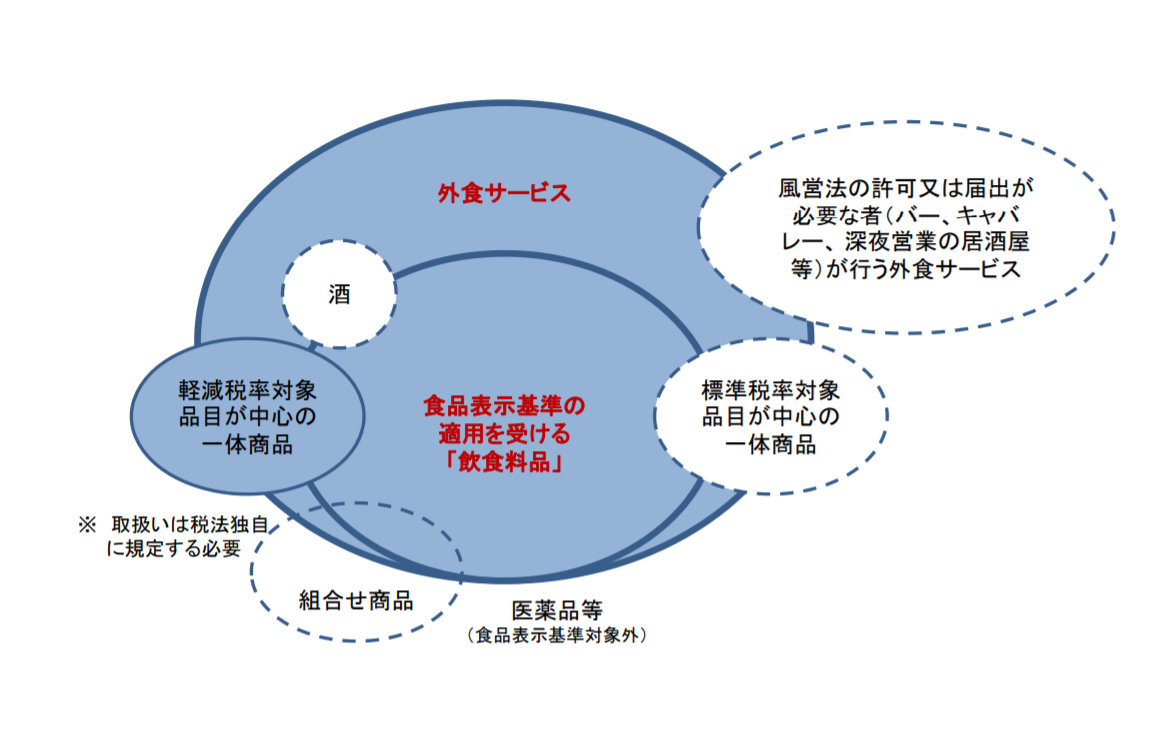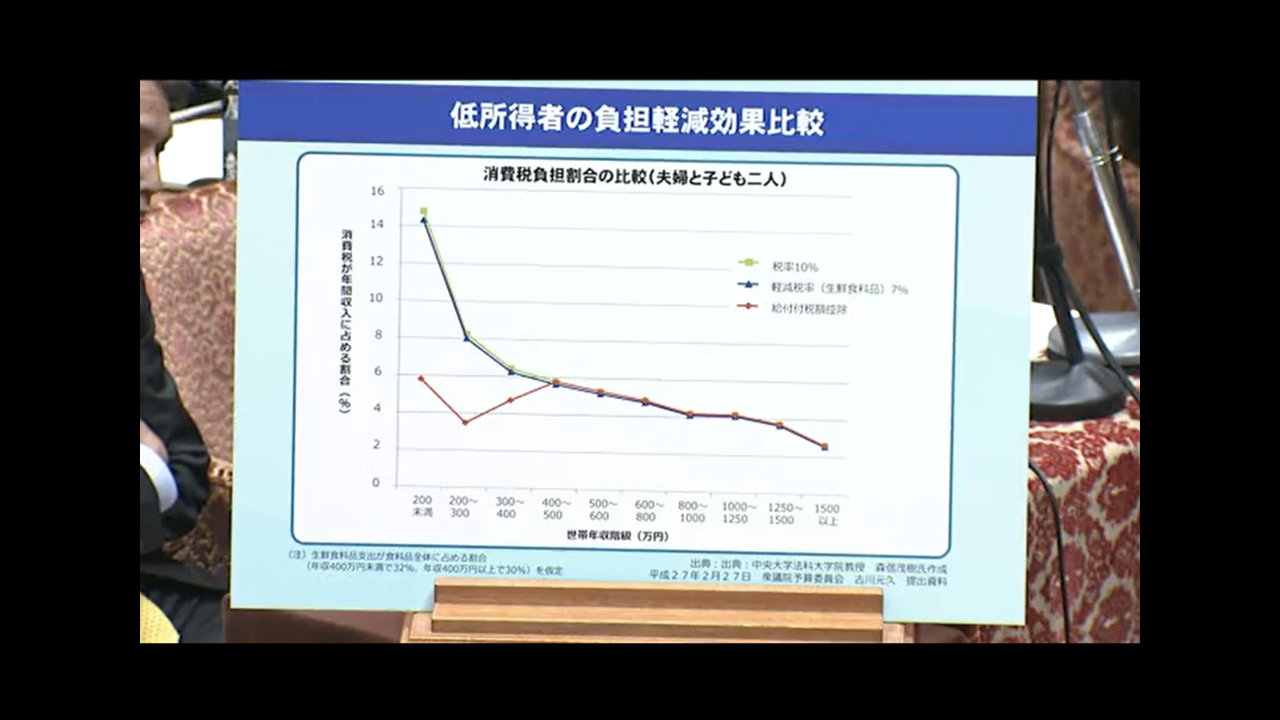2016年11月9日、米国大統領選挙においてドナルド・トランプ氏がヒラリー・クリントン氏を破ったことは、世界に衝撃を与えた。「トランプ氏が主張する政策を実行したら、国際秩序や経済活動はどうなってしまうのか」という問いが、現在にいたるまで日本のメディアにも溢れている。
しかし、実際のところ、トランプ氏がさらけ出した米国が抱える問題は、米国だけの問題ではないのだ。トランプ新大統領の誕生は、国際社会のなかでうねる大きな潮流のなかの一つの事象にすぎないといえる。経済的な利益を拡大するため、不要な軍事衝突を避けるため、各国は、国連の機能強化を支持し、地域統合も進めてきた。しかし近年、主として欧米先進諸国が、国境を強く意識し始めた。「統合」に向かっていた振り子は、逆方向に振れ出したのだ。その背景には、既存のグローバリズムでは機能を回復できなかった国家とますます貧しくなる国民がいる。国家が回復できないのは、「富の再分配」の機能である。
私たちは2017年を見通すにあたって、国際社会が第二次世界大戦後目指してきた「統合」と逆の方向に流れるこの潮流を理解しなければならない。このなかで、日本がどのように生きていくべきかを考えることは、まさに今、必要とされていることである。
【執筆分野】
国内経済 ( 小黒一正 財政推計プロジェクトメンバー) | 税制・社会保障 ( 森信茂樹 上席研究員) | 医療・介護 ( 三原岳 研究員) | 資源エネルギー ( 平沼光 研究員) | CSR ( 亀井善太郎 研究員) | 米国 ( 渡部恒雄 上席研究員) | 中国 ( 小原凡司 研究員) | 欧州 ( 鶴岡路人 研究員) | テロ対策 ( 長尾賢 研究員)
【国内経済】財政再建と景気循環―2017年度の税収は見積もりを上回るか
小黒一正
東京財団財政推計プロジェクトメンバー、法政大学教授
財政再建の「本丸」が社会保障改革であることは言うまでもないが、それ以外で重要な成否を握るのは「長期金利(利払い費)」と「税収」の動向である。
このうち、2017年に米大統領に就任するトランプ氏が、大規模な減税やインフラ投資といった強力な経済対策を打つという予測や、米国FRBの利上げが明らかになったことから、米国の長期金利が上昇し、日本の長期金利にも影響を及ぼし始めている。
長期金利の上昇で影響が懸念されるのは、GDP比で200%以上の債務を抱える日本財政の利払い費である。もっとも、現在のところ、日銀は「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を進めており、長期金利のターゲットをゼロ%程度に設定していることから、それによって金利上昇が抑制できれば、当分の間、政府債務の利払い費を抑制できる可能性もある(注:2018年頃に買いオペする国債が枯渇する旨の指摘もある)。
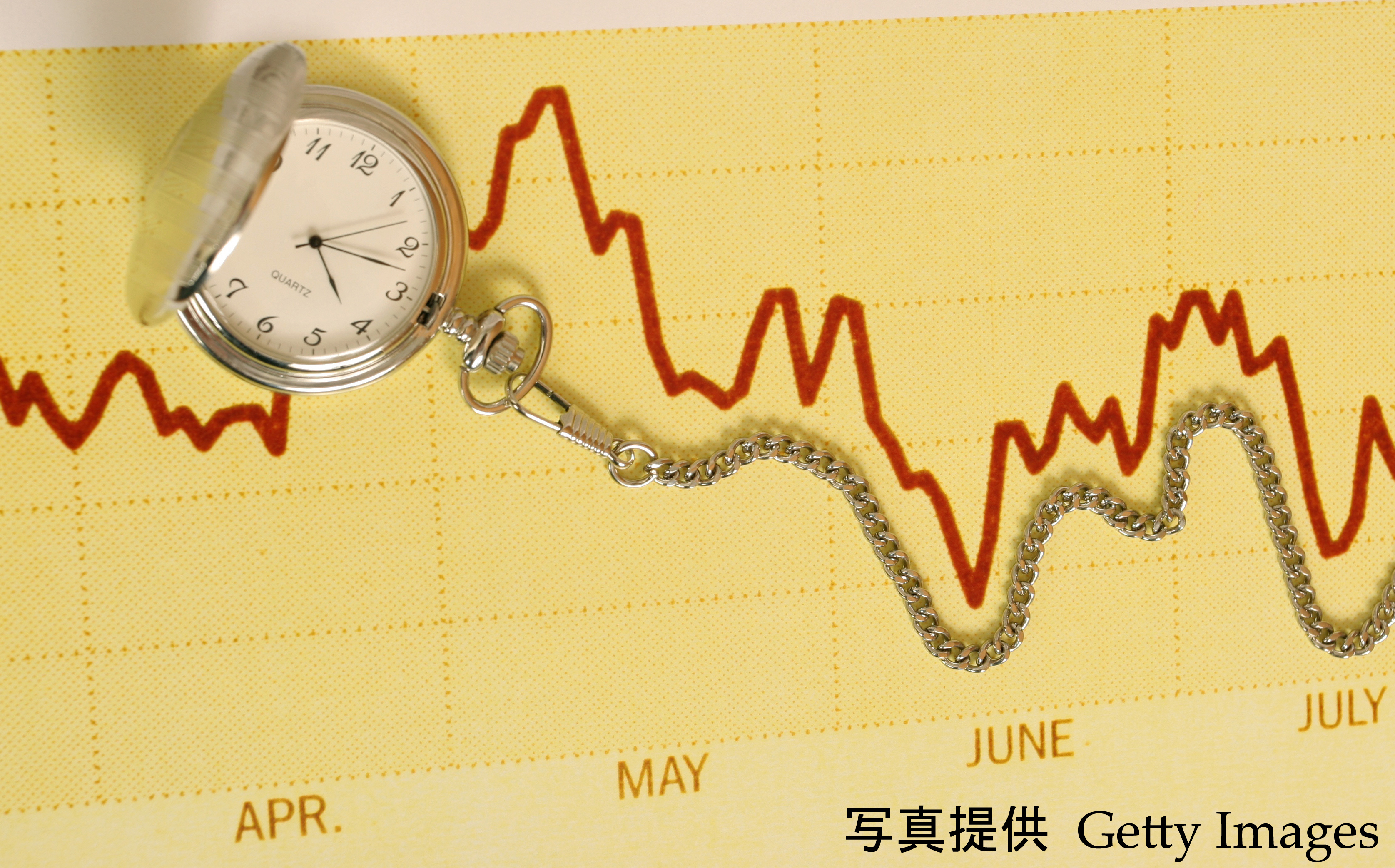 このような状況の中、財政再建との関係で、2017年の財政の先行きを占う注目点は「税収」の動向である。
このような状況の中、財政再建との関係で、2017年の財政の先行きを占う注目点は「税収」の動向である。
財務省は2016年度の税収を当初57.6兆円と見積もっていたが、法人税を中心に約1.7兆円下振れすることが明らかとなり、2016年度予算においては、赤字国債を約1.7兆円増発する事態に陥った。税収見積もりの下方修正は、リーマン・ショックの影響で景気が低迷した2009年度以来、7年振りであり、この意味を深く考える必要がある。
一つの可能性として考えられるのは、「景気循環」である。内閣府は、「景気動向指数研究会」(座長:吉川洋・元東大教授)の議論を踏まえて景気循環の判定をしているが、2009年3月からスタートした第15循環の景気の山を2012年3月、谷を2012年11月に確定し、その資料を2015年7月24日に公表している。
これは現在の景気回復が安倍政権発足直前の2012年11月からスタートしたことを意味するが、この資料によると、過去の景気拡張期の平均は約3年(36.2か月)であることが読み取れる。拡張期が6年近くに及ぶケースも過去にあるが、それは例外的なケースであり、景気拡張期はいつ終わってもおかしくない。
しかし、財務省は2017年度の税収を57.71兆円と見込んでいる。これは、2016年度(当初)と比較して1,100億円増という見積もりとなっている。1981年度から2015年度の約35年間において、国の税収見積もり額(一般会計の当初予算)とその決算額の誤差は上下に大きく振動しており、実際の税収が見積もりよりも5%以上も減少してしまった年度は10回、1割以上減少した年度は7回も存在する (図1) 。もし既に景気拡張期が終わりつつある場合、2016年度に続き、2017年度の税収も下振れする可能性があり、社会保障改革を含む財政再建の手綱を緩めてはならない。
なお、政府は2015年6月末、新たな財政再建計画を盛り込んだ「経済財政運営と改革の基本方針2015」(いわゆる骨太方針2015)を閣議決定しており、骨太方針2015では、2020年度までに国と地方を合わせた基礎的財政収支(以下、「PB」という)を黒字化する従来の目標のほか、2018年度のPBの赤字幅を対GDPで1%程度にする目安を盛り込んでいる。
また、内閣府は2016年7月の経済財政諮問会議において、「中長期の経済財政に関する試算」(いわゆる中長期試算)の改訂版を公表している。同試算によると、楽観的な高成長(実質GDP成長率が2%程度で推移)の「経済再生ケース」でも、政府が目標にする2020年度のPB黒字化は達成できず、約5.5兆円の赤字となることが明らかになっている。その意味でも、税収の上振れに楽観的な期待を寄せず、政府・与党は2019年10月の消費税率引き上げに向けた環境整備を含め、財政・社会保障の改革を進めることが望まれる。
図1 国の税収見積もり額と決算額の誤差(1981年度~2015年度)

(出所)財務省資料及び内閣府SNAデータから筆者作成
【税制・社会保障】グローバル競争、負の遺産を社会保障・税一体改革で
森信茂樹
上席研究員
2016年は米国のトランプ大統領の誕生や英国のBREXITなど、人々の予想を超える出来事が多かった。これらを見て気がつくのは、グローバル経済のもたらす負の部分にポピュリズムが芽生える大きな要因があるということである。グローバル経済は、有無を言わさぬ暴力的な市場の力で、競争の勝者と敗者を明確にする。勝者になるには、たゆまぬ努力と工夫があるとしても、それはしばしば理不尽な怨嗟の対象となる。だからといって、いまさら競争社会をかなぐり捨ててジャングルの中に逃げ込み自給自足の生活を送るわけにもいかない。とりわけ人口減少を続けるわが国としては、高度なモノづくりに比較優位を生かしつつ、グローバル競争に勝ち抜くことこそが唯一の生きる道であろう。
競争の根源的な問題点は、競争の「勝者」(一般消費者も)と「敗者」が明確に分かれるということである。とりわけアングロサクソンの国では、その果実が一部の金持ち、エリート層にだけ帰属することによって、ポピュリズムを育ててきた。幸いわが国は、日本型資本主義を皮一枚維持しつつ踏ん張っているものの、いずれこの波に飲み込まれるのは避けられないだろう。
 そうであればこそ、わが国は、競争の負の部分への対応を急がなければならない。今のうちに、グローバル競争のメリットが公平なメカニズムとして国民に広く行き渡るようなシステム(緩やかな再分配メカニズム)を考える必要がある。それを突き詰めれば、競争の「勝者」や競争のメリットを享受する国民(消費者)にある程度の負担を求め、「敗者」が自助努力で再チャレンジできる基盤、仕組みを構築することである。それは、社会保障、セーフティーネットを限りなく張り巡らせるということではなく、「敗者」個人の自助努力を国が支援するということである。アベノミクスの下で、「将来の期待」に働きかける政策が行われているが、国民に「将来の不安」があっては、消費は伸びず経済は拡大しない。加えて、アメリカのトランプ政権の誕生で、経済社会の不確実性はますます高まりつつある。
そうであればこそ、わが国は、競争の負の部分への対応を急がなければならない。今のうちに、グローバル競争のメリットが公平なメカニズムとして国民に広く行き渡るようなシステム(緩やかな再分配メカニズム)を考える必要がある。それを突き詰めれば、競争の「勝者」や競争のメリットを享受する国民(消費者)にある程度の負担を求め、「敗者」が自助努力で再チャレンジできる基盤、仕組みを構築することである。それは、社会保障、セーフティーネットを限りなく張り巡らせるということではなく、「敗者」個人の自助努力を国が支援するということである。アベノミクスの下で、「将来の期待」に働きかける政策が行われているが、国民に「将来の不安」があっては、消費は伸びず経済は拡大しない。加えて、アメリカのトランプ政権の誕生で、経済社会の不確実性はますます高まりつつある。
このように考えてくると、2017年のわが国の課題は、グローバル競争がもたらす負の部分に光を当て、それへの対応策を社会保障・税一体改革として再構築することである。競争の「勝者」からいずれその成果が「敗者」へと均てんしてくるというトリクルダウン政策ではなく、地道に税と社会保険料の負担のあり方を見直し、その延長上に働き方改革、同一労働・同一賃金、ワークライフバランスを見据え、健全な世論の基礎となる中間層を厚くしていくという方向に政策の軸を移していくことである。そのために、社会保障・税一体改革というコンセプトは依然最重要であるし、そこからグローバル経済への耐性力ができてくる。
さらには、米国や英国で、法人税率を引き下げる動きがわが国にどのような影響を与えるか、その場合財源をどこに求めるか、資本と労働への課税のバランをどうとっていくのか、なども興味深い論点となる。
本年1月下旬から東京財団内に、筆者が座長を務める「税・社会保障調査会」のウェブサイトが立ち上がるが、このような考え方に立って、具体的な政策提言をしていきたいと考えている。
【医療・介護】問われる地域での政策立案と合意形成
三原岳
研究員
医療、介護政策の今後を占ううえで、2017年は重要な年となりそうだ。2年周期の診療報酬、3年に一度の介護報酬と介護保険事業計画、5年サイクルの医療計画(次期計画から6年)が2018年度に見直されるため、2017年はさまざまな制度改正の議論が国・自治体で進む見通しだ。
これらの改革を考えるうえでのキーワードが「地域」である。現在、医療分野では地域医療構想、介護分野では地域包括ケアが重視されており、両者を後押しするかたちで一連の制度改正が進められる可能性が高い。
 このうち前者は病床の再編・削減を進めるため、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の機能別に区分された病床について、各都道府県が2025年時点における需要予測と現状を比較し、余剰または不足する機能を明らかにする。さらに、構想に沿って各都道府県が医療機関と協議、調整することを通じて、急性期の圧縮と回復期の充実、慢性期の削減と受け皿となる在宅医療の充実を図ることを目指す。
このうち前者は病床の再編・削減を進めるため、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の機能別に区分された病床について、各都道府県が2025年時点における需要予測と現状を比較し、余剰または不足する機能を明らかにする。さらに、構想に沿って各都道府県が医療機関と協議、調整することを通じて、急性期の圧縮と回復期の充実、慢性期の削減と受け皿となる在宅医療の充実を図ることを目指す。
その一例として人口1人当たりの病床数が最も多い高知県の事例 (表1) を見ると、構想は東部、中部、高幡、幡多の4つの区域で作られており、2015年と2025年の病床数を比較している。これを見ると、高知市を中心とする中央区域では高度急性期、急性期、慢性期が2025年に過剰となる一方、回復期が足りなくなるほか、慢性期を再編・削減した場合は受け皿も必要となる。この結果、高度急性期、急性期から回復期への移行と、慢性期の削減と在宅医療の整備が必要となる。構想に盛り込まれた数字がそのまま削減目標となるわけではないが、こうした認識のうえに立ち、病床再編・削減に向けた医療機関との協議に加えて、次期医療計画を策定することが求められる。
表1 高知県の地域医療構想に基づく病床の予想

出典 高知県地域医療構想
注1)2015年は病床機能報告、2025年は需要推計に基づく必要病床数、将来の需給は2015年から2025年を差し引いた数字。
注2)高知県の地域医療構想では2025年の慢性期について、「在宅医療の整備と一体的に検討する必要があるが、現状では慢性期医療を入院医療と在宅医療とに明確に区分することは難しい」として、「以上」と表記している。
もう一つの地域包括ケアは医療・介護サービスを含めて、住み慣れた地域で最期まで暮らすための仕組みづくりを目指す政策である。ここでは市町村が中心になった取り組みの必要性が強調されており、各市町村は2018年度から始まる次期介護保険事業計画に向けて、地域包括ケアの考え方を反映させる必要がある。
前者では20万人程度の医療圏(2次医療圏)、後者では主に中学校区を指しており、「地域」の範囲・規模が違う点に留意する必要があるが、いずれも「地域」に着目しているのは理由がある。これは各地域で高齢化や人口減少のスピード、医療機関や病床数、介護施設数などに差異があるため、従来のような全国一律の政策が難しくなり、各地域の特性や課題に応じて最適な提供体制や資源分配を考える必要性に迫られているためだ。
こうした流れは世界的な潮流とも合致している。英国や北欧など一部の国では脱中央集権化(decentralization)を図る一環として、1990年代から自治体への権限・財源移譲などを進めており、その目的として地域のニーズに沿った政策立案や資源分配が挙げられている。日本においても2018年度の改定に合わせて、都道府県や市町村は地域のニーズや実情、課題に対応した医療計画、介護保険事業計画を作る必要がある。
さらに、脱中央集権化の目的として、住民や現場の専門職の意向を反映させる重要性も指摘されている。多様な意見を包摂することを通じて、サービスの質向上などが期待できるためであり、地域医療構想や地域包括ケアにも共通している。
地域医療構想に関して言うと、日本の医療提供体制は民間が大半を占めており、都道府県が構想や計画を策定するだけでは実効性をもたない。このため、病床の再編・削減に関しては医療機関との調整、協議が不可欠であり、住民の理解も求められる。さらに、医療必要度の低い人を受け入れている慢性期の病床を削減した場合、その受け皿として自宅や介護施設におけるケアを充実させる必要があり、そのためには在宅医療だけでなく、介護保険事業所や介護保険財政を司る市町村との調整も欠かせない。
地域包括ケアにも同じことが言える。生活支援は医療、介護サービスに限らず、住民組織やボランティア、民間企業など広範な地域での支え合いが必要となる。その際には住民や現場の専門職の知恵やノウハウを生かしつつ、地域の課題や実情に即した体制構築が求められる。
各地域にとって、「惑星直列」と呼ばれるほど制度改正のタイミングがそろう2018年に向け、今年は特色ある医療・介護政策を策定できる機会になる。政策立案や合意形成に関する自治体の 実力と姿勢が問われる。
【資源エネルギー】トランプ政権のエネルギー政策に振り回されない独自の政策を
平沼光
研究員
2016年は世界のエネルギー動向にとって激動の年であった。特に、パリ協定の発効は、世界が化石燃料依存を減らし再生可能エネルギーをはじめとするクリーンエネルギーの普及を大胆に進めるエネルギー大転換を目指すことを示した大きな出来事であった。また、エネルギー政策に大きな影響を及ぼす気候変動問題に対して懐疑的な考えをもつトランプ氏が米国大統領選挙で勝利したことは、2017年のさらなる激動を予感させるものであった。トランプ氏は選挙期間中、気候変動問題について中国がでっち上げたものだという姿勢を示していた。しかし、選挙後の米紙ニューヨーク・タイムズのインタビュー(11月22日)では、気候変動問題に対してオープンな考えをもっていると発言するなどその真意は不透明な状況にある。目下のところ、トランプ政権がどのようなエネルギー政策を打ち出してくるかに多くの関心が寄せられているが、果たしてどのようなことが考えられるだろうか。また、2017年は日本にとって第5次エネルギー基本計画策定の年でもある。激動する世界のエネルギーシーンのなかで、日本はどのような政策を採るべきであろうか。
トランプ政権のエネルギー政策は産業経済政策
トランプ政権のエネルギー政策はいまだ不透明ではあるが、エネルギー政策に影響を及ぼす閣僚やブレーンの人事は見えてきている。昨年12月14日にはエネルギー政策を担う重要ポストの一つであるエネルギー長官に、リック・ペリー元テキサス州知事が任命されている。日本の報道ではペリー氏について、石油・天然ガスが豊富なテキサス州の元知事という紹介のされかたが大半であるが、実はテキサス州は風力発電の導入で全米1位であり風力発電関連の製造施設も多い州である。ペリー氏は州知事在職中、“American energy”と称して州経済の活性化を目的に州の資源である石油・天然ガス開発と風力発電の導入政策を推進してきた人物であり、今回のペリー氏エネルギー長官の任命は、その手腕とテキサスにおける成果が評価されてのこととなる。
テキサス州のみならず、米国は国としても風力発電の導入量が中国に次いで2位の風力発電大国である。また、風力発電機の市場シェアでも米国のゼネラル・エレクトリック社(以下、GE社)が世界3位と健闘している。GE社は米国の風力発電の有力な担い手であるが、昨年12月2日にトランプ次期大統領の政策助言機関として発足した「大統領戦略政策フォーラム」にはGE社の前CEOジャック・ウェルチ氏がメンバーに選ばれており、GE社を象徴する人物が今後トランプ政権の政策立案にかかわってくることになる。ペリー氏がエネルギー長官に任命された同日となる12月14日、GE社は2017年の経営説明会を開催しているが、そこでは売上高を5%成長させる方針が公表されるとともに風力発電などクリーンエネルギー分野の順調な拡大が予想されていることは興味深い。
「大統領戦略政策フォーラム」は、ウェルチ氏を含め米の著名なビジネスリーダーを中心に構成されているが、クリーンエネルギー推進派と言える世界最大のスーパーマーケットのウォルマート社CEO、ダグ・マクミリオン氏がメンバー入りしていることも興味深い。ウォルマート社は昨年11月に2025年までに自社で使う電力の50%を再生可能エネルギーで賄うことを公表している。さらに、電気自動車や高効率蓄電池、太陽光パネルなどを手がけクリーンエネルギー界の風雲児と呼ばれるテスラモーター社CEO、イーロン・マスク氏もメンバーに入っている。エネルギー専門家として著名なダニエル・ヤーギン博士も名を連ねており、ヤーギン博士は石油や石炭など特定のテーマに偏ることなく、環境・エネルギー問題を総合的な視点で考察するバランス感覚のある人物だ。
トランプ氏の選挙期間中の発言を聞いていると、いかにも化石燃料の活用に特化していくような方向が読み取れるが、先述したような人事を見てみると、トランプ氏の選挙期間中の発言だけでは今後の米国のエネルギー政策を推し測ることは難しい。特に、化石燃料からクリーンエネルギーまでテキサス州内にある資源で使えるものは全て使い州の産業と経済を活性させてきたペリー氏のエネルギー長官への登用を考えると、特定のエネルギーにこだわることなく、米国の産業経済にプラスになるのであれば多様なエネルギーを積極的に活用していく政策もありうるだろう。それは環境政策と結びついたエネルギー政策ではなく、多分に産業経済政策と結びついたエネルギー政策といえる。
エネルギー大転換は日本の好機
トランプ政権のエネルギー政策を占ってみたが、これらに一喜一憂する必要はない。もちろん、諸外国の動向を分析することは重要だが他国の動向に引きずられてはならない。重要なのは、日本は今後どのようなエネルギー政策を採っていくかということだ。3.11福島原発事故を経て2014年に策定された第4次エネルギー基本計画から早くも3年が経ち、今年は第5次エネルギー基本計画の策定を始める年となる。第4次エネルギー基本計画策定から今日にかけて、電力自由化の開始、福島原発の廃炉費用の大幅な増大、核燃料サイクルの事実上の破綻、パリ協定の発効による世界的なエネルギー大転換の動きなどさまざまな状況の変化が起きており、変化に対応するエネルギー政策の構築が必要だ。
 特にエネルギー大転換の動きは日本にとって好機といえる。これまで日本は化石燃料を海外に依存するエネルギー小国として常に資源の供給不安に晒されてきた。一方、日本にはクリーンエネルギーである再生可能エネルギーの大きなポテンシャルとそれを利用するための高い技術力がある。化石燃料の利用を減らしクリーンエネルギーを活用する世界的なエネルギー大転換の動きは、化石燃料の供給不安という日本のエネルギーリスクを大きく減らすだけでなく新たに構築される160兆円規模とされるクリーンエネルギー市場を日本の高い技術力で獲得していくチャンスにもなる。仮に、トランプ政権が化石燃料回帰の政策を打ち出したとしても日本はそれに振り回される必要はない。日本にとってチャンスとなるエネルギー大転換を日本みずからが高い技術力を持って主導していくことを考えるべきだ。日本はこれまでにも自動車産業など、高い技術力を背景に数々のイノベーションを実現し世界を牽引し利益を得てきた。日本の高い技術力の代名詞といえる自動車産業では、1973年に自動車の厳しい環境基準を定めた米国のマスキー法をクリアする車を米国に先んじて日本が世に送り出し、省エネ小型車という新たな分野を切り開いている。そして1997年にはハイブリッド車という新たな価値を創造し、2010年には世界に先駆けて量産型の電気自動車を市場に投入している。現在では水素という新しいエネルギーを実用化する水素燃料電池車の一般向け販売という新たなイノベーションに取り組んでいる。日本の自動車産業は独自のイノベーションにより世界を牽引することで大きな利益を得てきた。
特にエネルギー大転換の動きは日本にとって好機といえる。これまで日本は化石燃料を海外に依存するエネルギー小国として常に資源の供給不安に晒されてきた。一方、日本にはクリーンエネルギーである再生可能エネルギーの大きなポテンシャルとそれを利用するための高い技術力がある。化石燃料の利用を減らしクリーンエネルギーを活用する世界的なエネルギー大転換の動きは、化石燃料の供給不安という日本のエネルギーリスクを大きく減らすだけでなく新たに構築される160兆円規模とされるクリーンエネルギー市場を日本の高い技術力で獲得していくチャンスにもなる。仮に、トランプ政権が化石燃料回帰の政策を打ち出したとしても日本はそれに振り回される必要はない。日本にとってチャンスとなるエネルギー大転換を日本みずからが高い技術力を持って主導していくことを考えるべきだ。日本はこれまでにも自動車産業など、高い技術力を背景に数々のイノベーションを実現し世界を牽引し利益を得てきた。日本の高い技術力の代名詞といえる自動車産業では、1973年に自動車の厳しい環境基準を定めた米国のマスキー法をクリアする車を米国に先んじて日本が世に送り出し、省エネ小型車という新たな分野を切り開いている。そして1997年にはハイブリッド車という新たな価値を創造し、2010年には世界に先駆けて量産型の電気自動車を市場に投入している。現在では水素という新しいエネルギーを実用化する水素燃料電池車の一般向け販売という新たなイノベーションに取り組んでいる。日本の自動車産業は独自のイノベーションにより世界を牽引することで大きな利益を得てきた。
エネルギー小国である日本はこれまで資源国の情勢など外部要因に振り回されてきたが、再生可能エネルギーの世界的なコスト低下とエネルギーマネジメント技術の進歩により現実化してきたエネルギー大転換の動きは、日本がエネルギー小国からエネルギー先端国に生まれ変わるチャンスである。
日本の自動車産業が数々のイノベーションを実現してきたようにエネルギー分野でも、再生可能エネルギーのポテンシャルと高い技術力をもって日本がイノベーションを起こし世界を牽引することは可能だろう。本年から始まる第5次エネルギー基本計画の策定においてはエネルギー大転換の動きを日本がどのようにして主導していくかという視点をもつべきだ。
【CSR】SDGsを社会の視点として企業経営に採り入れていく
亀井善太郎
研究員
2016年と言えば、多くの人が思い出すのが、英国のEU離脱に関する国民投票結果、米国のトランプ次期大統領選出だろう。日本にいると気づきづらいかもしれないが、2016年の先進国の内政のテーマは雇用問題であり、移民問題であった。1989年11月9日 [i] のベルリンの壁崩壊以来続いてきたグローバリゼーションという歴史の一つの転換点に私たちは立っているのかもしれない。
英オックスフォード大学出版局は、2016年の言葉として「post-truth」を選んだ [ii] 。客観的な事実や真実が重視されない時代の象徴だという。英国でEU残留を支持した人びとは膨大なデータを駆使してその意義を訴えたし、米国のトランプ氏の発言の真偽については常に注目の的だ。客観的なデータや科学的な予測よりも、感情的な発言が支持される現実を私たちは受けとめなければならない。
各国の世論は分断されつつも、グローバリゼーションへの反発や反対を訴える声が大きくなる一方、企業活動は、次なる市場の拡大へと、低廉な生産現場を求め、さらに国境を越えているのが現実だ。国境を越えられない政治とこれを自由に越えていく企業の差を、はっきりと見ることができるようになったのが2016年なのかもしれない。
 他方、CSR(Corporate Social Responsibility)の分野に目を転じてみれば、忘れてはならないのが2016年はSDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)スタートの年であったことだ。2016年1月1日から2030年を期限とする17の目標からなる国境を越えた人類共通の行動計画がSDGsである。2015年までの目標であったMDGs(Millennium Development Goals、ミレニアム開発目標)の成果と課題をふまえ、3年に及ぶステークホルダーによる対話を経て国連総会において全会一致で採択されたものである。
他方、CSR(Corporate Social Responsibility)の分野に目を転じてみれば、忘れてはならないのが2016年はSDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)スタートの年であったことだ。2016年1月1日から2030年を期限とする17の目標からなる国境を越えた人類共通の行動計画がSDGsである。2015年までの目標であったMDGs(Millennium Development Goals、ミレニアム開発目標)の成果と課題をふまえ、3年に及ぶステークホルダーによる対話を経て国連総会において全会一致で採択されたものである。
では、これらの2016年の動きを踏まえ、2017年はどのような年になるのであろうか。私たちはこうしたさまざまな分断を受けとめ、乗り越えていくことができるのであろうか。よくよく社会の分断の元を探れば、その多くは企業活動に辿り着くわけで、それだけに企業の責任は重大だと言える [iii] 。
まさにCSRは、企業にとっての「社会に応答する力」だ。企業活動が社会に与えるの最大の影響の一つが「雇用」であり、「環境」である。「持続可能な消費や生産」も重要だ [iv] 。企業が持続可能な存在となるためには、社会からの要請と事業活動の「統合」が不可欠である [v] 。「統合」は一見困難な道のりのように見えるが、短期の視点や評価を排し、社会にあるさまざまなステークホルダーの視点を導入し、長期の視座で企業経営や事業運営に取り組むことができれば、両者の統合は決して矛盾するものではない。SDGsを「社会の視点」として経営に積極的に採り入れていくことが「統合」を意義あるものにしていくわけだが、ここで日本企業が直面する課題を示しておきたい。
東京財団では、日本の企業を対象にCSRに関するアンケート調査を毎年実施しており、2016年で4回目を迎えた [vi] 。今回の調査結果の特徴として、SDGsを意識した社会課題の視点から企業活動を観る設問に対し企業の反応の鈍さが挙げられる。具体的な各企業の声は、「政府がまだ方針を示していないので [vii] 、自分たちはまだSDGsに対する方針を決定していない」というものだった。
社会課題の原因ともなっている企業活動がこれでは心もとない。一般に、政府や政治は、社会の動きに後追いするものであって、最も反応が遅い主体の一つだ。その後を追いかけているようでは、企業として社会に対する責任を果たせているとは言えないだろう。
「私たちは歴史の転換点に立っているのかもしれない」という自覚を企業がもつことができるかどうか、それは組織人である一人ひとりの責任でもある。社会を変えるのは政治だけではない。企業であり、一人ひとりの市民なのだ。
[i] トランプ氏が大統領の勝利宣言をしたのも同じ11月9日であった。
[ii] Oxford University Press, Oxford Dictionaries Word of the Year 2016 https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
[iii] さらに言えば、日本において、現政権の重要課題の一つに「働き方改革」があるが、実際のところ、政府ができることはきわめて限られている。企業の自主的な活動がもっとも効果的な手段であることは言うまでもない。また技術革新の担い手としての企業の存在も忘れてはならない。2016年はAI(人工知能)による変化を随所で実感した年でもあった。
[iv] 企業活動はSDGsすべての項目に影響を及ぼすわけだが、紙幅の都合でもっとも影響が大きいと思われる点に絞った。
[v] 亀井善太郎(2016)「あらためて「統合」の意義の確認を――SDGsの導入は日本企業をどう変えるのか」 http://www.tkfd.or.jp/research/csr/s97yri#_ftn1
[vi] アンケート調査の分析は、これまでと同様『CSR白書』の形で本年夏にも発刊する予定。
[vii] 政府は、2016年12月22日、官邸に設置された持続可能な開発目標(SDGs)推進本部において「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」を決定した。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/
【米国】米国トランプ政権の誕生と国際秩序へ与える影響
渡部恒雄
上席研究員
2017年の米国の外交・安保政策は、トランプ政権の誕生で、多くの政策課題の行方が不透明となる。その理由は、第一に、トランプ次期大統領に政治経験がなく大統領選挙中も整合的な政策を準備してこないまま大統領に選出されたこと、第二に、選挙後も「脱エリート」「脱ワシントン」で政権人事を進め、ワシントンのシンクタンクに在籍するような既存の専門家にたよらない姿勢を示していること、第三に、主要な政策において共和党議会と異なる主張をしていること、第四に、トランプ氏本人の主張が往々にして整合性がなく、容易に変更されること、である。
米国の政権は、行政府の次官補級(日本でいえば局長)以上のすべてのポストが政治任用であり、その人事は議会の承認が必要だ。第一の注目課題は、トランプ政権がどのような布陣で政策を遂行できる体制をつくるのかということになる。これが遅れれば遅れるほど、外交安保や経済で、危機的な状況への対応が遅れ、世界の秩序を不安定化させることになる。
 現時点での外交安保チームの指名候補の顔ぶれとトランプ氏の主張の双方から判断すると、トランプ政権の外交・安保政策の中心は、シリア・イラクを拠点にする過激派組織「イスラム国」(IS)対策とロシアとの関係改善だ。マイケル・フリン次期国家安全保障担当大統領補佐官、およびジェームズ・マティス次期国防長官は中東での経験が豊富で、イスラム国対策を重視した布陣だ。レックス・ティラーソン次期国務長官はロシアとの関係が深く、ロシアとの関係改善を意識した人事である。
現時点での外交安保チームの指名候補の顔ぶれとトランプ氏の主張の双方から判断すると、トランプ政権の外交・安保政策の中心は、シリア・イラクを拠点にする過激派組織「イスラム国」(IS)対策とロシアとの関係改善だ。マイケル・フリン次期国家安全保障担当大統領補佐官、およびジェームズ・マティス次期国防長官は中東での経験が豊富で、イスラム国対策を重視した布陣だ。レックス・ティラーソン次期国務長官はロシアとの関係が深く、ロシアとの関係改善を意識した人事である。
したがって第二の注目課題は、この二つの中心課題を、トランプ政権がどこまで本気で遂行するのかという点だ。ある意味、ロシアの関係改善とイスラム国対策は、相互補完的である。特にシリアにおいては、ロシアとの関係改善は、イスラム国対策の面で、ロシアおよびロシアが支援するアサド政権と協力して、同国内で猛威をふるうイスラム国に圧力をかける利点がある。トランプ氏は、当選後の11月14日、プーチン大統領との電話会談を行ったが、ロシア政府の発表によると、両者は「国際テロリズムや過激派との戦いなどにおいて建設的な協力関係」の構築を目指すことで合意したということだ。
問題は、これまで米欧はシリア内の反政府勢力を支援して、アサド政権と対峙してきており、アサド政権やロシアと共闘することは、かなりアクロバティックな外交で地域をさらに混乱させかねない。また、トランプ氏の足元の共和党議会や米国有権者のロシアへの不信感と警戒感が、冷戦後では最悪の状況にあり、国内の支持を得るのも難しい。
第三の注目課題は、対中政策の行方だ。トランプ陣営は、ロシアと関係改善を図る一方で、中国に対しては、経済・貿易上も、外交・安全保障上も、敵対的な姿勢を示している。特にトランプ氏は、これまでの米中の最低限の合意であった台湾をめぐる「一つの中国」にかならずしもとらわれない、という姿勢で中国を警戒させている。国家通商会議を創設して、そのトップに対中強硬派のピータ・ナヴァロ、カリフォルニア大学教授を起用して、中国との「貿易戦争」を仕掛けるような動きもみせている。ロシアとの関係を改善し中国に敵対するという文脈では戦略的な整合性があるが、中国との貿易摩擦は共和党議会が支持する米国のビジネス界の利益にも反するという矛盾がある。トランプ氏は、中国にルールを遵守させるための有効なツールともなるTPPを放棄する姿勢を変えておらず、対中政策も大いなる矛盾を抱えている。
そして、上記のすべての課題で焦点となるのが、NATOや日米同盟なども含めて、すべての外交要素が、トランプ氏がこれまでのビジネスで行ってきた「ディール」(取引)というゲームのバーゲニングチップ(取引材料)となる可能性だ。トランプ外交の行方次第では、ロシアと中国だけでなく、関係する同盟国に対しても緊張を強いることになり、国際秩序の波乱要素となるだろう。
【中国】トランプ新大統領の対外政策をにらみながら、国内政治のパワーゲームに注力する年
小原凡司
研究員
2017年の中国は、秋に開催予定の中国共産党第19回全国代表大会(以下、19大)に向けて、国内政治のパワーゲームが激化するだろう。一方で、国際システムの潮流が変化することによって対外政策にも多くの問題を抱える年になると考えられる。
国内政治に関しては、2017年秋に予定されている19大において、習近平主席への権力集中が進むかどうかが最大の注目点である。習近平主席は、政治、経済、軍事における改革を進めるためにも、自身への権力集中を進めようとしている。さらに習近平主席は、一般的に主席の職にある2期10年を超えて、主席の地位を維持しようとしていると言われる。
19大における人事が、習近平主席の思惑どおりに事態が展開するかどうかを左右する、重要なカギとなる。19大では、7名で構成される中央政治局常務委員会の内、習近平主席と李克強総理を除く5名が、「7上8下」と呼ばれる68歳定年制によって退官すると見られ、新たに常務委員となるのではないかと予想される人物は、ほとんどが胡錦濤氏の出身母体である中国共産党青年団(以後、共青団)出身者である。
 しかし、「7上8下」は明文化されたルールではないため、党内の合意さえ得られれば、いつでも変更できる。ルールの変更には、党内の反発が予想されるが、習近平主席がこれを抑え込んで王岐山中央規律検査委員会書記の退官を阻止できれば、2022年の20大における習近平主席の任期延長の布石となり得る。
しかし、「7上8下」は明文化されたルールではないため、党内の合意さえ得られれば、いつでも変更できる。ルールの変更には、党内の反発が予想されるが、習近平主席がこれを抑え込んで王岐山中央規律検査委員会書記の退官を阻止できれば、2022年の20大における習近平主席の任期延長の布石となり得る。
中国国内政治は、日本でよく言われるような、太子党(習近平派、紅二代とも)、共青団派(胡錦濤派)、上海幇(江沢民派)の間の権力闘争といった単純な構図ではない。たとえば、習近平主席がもっとも信頼を寄せる栗戦書中央書記処書記も共青団出身者である。中国国内政治は、継続して細かい動きに至るまで観察していなければ、理解することはできない。
対外的には、トランプ新大統領の誕生が、中国外交を根本的に転換させることになる。中国は、欧米先進諸国の自国中心主義に代表される国際社会の潮流が、みずからの経済発展にとって不利であると認識している。新たな国際社会の潮流を象徴するトランプ新大統領の誕生は、中国にとって、懸念の現実化を予期させるものだ。中国の発展を妨害するために米国が軍事力を行使するのではないかという懸念である。
その発言を見る限り、トランプ氏が中国に求めるのは、貿易不均衡の是正等、経済問題における譲歩である。しかし、トランプ氏は、選挙後の12月10日、「貿易関係などで合意を得られなければ、なぜ『一つの中国』政策に縛られないといけないのか」と発言し、経済問題で中国の譲歩を得るために、外交及び安全保障の問題を取引材料として利用する意図を明らかにした。なかでも、台湾問題は中国にとって譲歩できない問題である。
台湾問題は、中国共産党にとって、統治の正統性にもかかわる。また、台湾が独立を宣言すれば、チベットや新疆ウィグルなどで独立の機運が高まり、中国国内が不安定化する可能性も高くなる。さらに、1996年、台湾総統選をけん制するために中国がミサイル演習を実施した際、米国が空母戦闘群(当時。現在は、空母打撃群と呼称する)を台湾海峡に派遣したことに対し、手も足も出なくなってしまったことが中国のトラウマともなっている。増強した軍事力を誇示して、米国の妨害に対抗する能力があるのだと主張してきた中国は、今度は、米国の軍事力の誇示に対して退くことはできない。
中国はすでに、トランプ新大統領に対して、建前の議論で問題を解決することは難しいと考えているように見受けられる。中国では、習近平主席が大統領選挙勝利の祝意を述べるために行ったとする、トランプ氏との電話会談の中で、習近平主席が「米中新型大国関係」という言葉を使用しなかったことが話題になっている。一方のトランプ氏は電話会談自体を否定しているが、中国国内の議論は中国の米国対応の変化を示唆している。
さらに、トランプ氏は、ロシアとの関係改善を示唆している。中国は、これまで対米けん制のために対中協力姿勢を示してきたロシアの積極的な支持を得られなくなるかもしれない。そもそも、ロシアが対中協力姿勢に転じたのは、西欧諸国が「実質的な軍事侵攻」と言うクリミア併合後に、欧米から経済制裁を課されたからである。
中国が考える米中ロの大国間のゲームが崩れる可能性があるのだ。こうした状況の中で、中国には日中関係改善の動きが見られる。このままでは、日米ロすべてと対立することになりかねない。一方でトランプ氏は、日米同盟見直しを示唆する等、日本に対しても厳しい対応をする可能性がある。中国は、少なくとも日本との厳しい対立を回避し、日中関係を改善できる可能性もあると考えているのだ。2016年12月の稲田防衛大臣の靖国神社に対する中国の反応が非常に低調なのも、このことを示唆している。しかし、日本との関係改善が難しいと考えれば、対日強硬姿勢に転じる可能性もある。
中国は現在、トランプ新大統領の実際の政策を慎重に見極めようとしつつ、種々の可能性を探っている。2017年の中国は、横目でトランプ新大統領の対外政策をにらみながら、国内政治のパワーゲームに注力することになるだろう。
【欧州】選挙の年、欧州にトランプ現象は伝播するのか
鶴岡路人
研究員
EU離脱を決定した英国の国民投票とキャメロン英首相の辞任、ブリュッセル、ニース、ベルリンと相次いで発生したテロ事件、国民投票の敗北を受けてのイタリア・レンツィ首相の辞任、終わりの見えないシリア内戦と周辺化される欧州の役割など、2016年の欧州を振り返ると暗いニュースばかりが頭に浮かぶ。次こそよい年をと願いつつ、なかなか楽観的になれないのが2017年の欧州である。
 欧州の2017年は、何よりもまず「選挙の年」である。主要なものだけでも、4~5月のフランス大統領選挙、秋のドイツ連邦議会選挙に加え、3月にはオランダでも議会選挙が予定されている。状況は国によって異なるものの、共通する懸念はポピュリズム、反EU、反エリート、反エスタブリッシュメント、排外主義などの勢力の伸長である。
欧州の2017年は、何よりもまず「選挙の年」である。主要なものだけでも、4~5月のフランス大統領選挙、秋のドイツ連邦議会選挙に加え、3月にはオランダでも議会選挙が予定されている。状況は国によって異なるものの、共通する懸念はポピュリズム、反EU、反エリート、反エスタブリッシュメント、排外主義などの勢力の伸長である。
別の言い方をすれば、「トランプ現象」が欧州に伝播するのかという問題でもある。トランプ政権の誕生を受けて、欧州におけるポピュリストや反エリート勢力はさらに勢いづくのか、あるいはその反動として、有権者の間に安定志向が強まるのかは予断を許さない。ただ、前者の懸念があるために、トランプ候補当選への衝撃度は欧州において特に高かったのである。昨年6月の英国民投票でのEU離脱決定を受けて、一時は「離脱ドミノ」の他国への波及が懸念されたものの、少なくとも現在までのところ実際に起きているのは、市民がEU離脱による混乱を恐れ、結果としてEUへの支持が高まるという、揺り戻し現象だともいわれている。希望的観測の要素が含まれつつも、これは明るい材料かもしれない。
そのうえで、今年の各国での選挙結果を左右するのは、第一にテロの動向である。テロが頻発する場合、それを阻止できない現政権への批判が高まるとともに、排外主義が台頭する可能性がある。1件のテロ事件が選挙の結果を変えてしまうようなこともあるかもしれない。しかも、テロの実行犯のなかにシリアからの難民・移民が含まれるような場合は、テロ事件の発生が政府の難民・移民政策への批判に直結しかねない。
第二は、既成政党の側でいかに、増大する市民の不安や不満に耳を傾けることができるかである。英国民投票のキャメロン首相の失敗と、米大統領選でのクリントン候補敗北から得られる共通の教訓の一つは、ポピュリズムや排外主義的言説を批判するだけでは有権者の支持を得られないということだったはずである。
第三に、フェイクニュース(偽ニュース)に代表されるディスインフォメーション(disinformation:偽情報の意図的な流布)への対応が急務になっている。各国の国内のポピュリズムや排外主義勢力による「デマ」も深刻であり、「ポスト真実(post-truth)」の時代を迎えたとさえいわれている。英国の国民投票でも、事実に反する数字や議論が氾濫し、有権者の選択に大きな影響を及ぼした。
加えて懸念が高まっているのが、ロシアによる活動の拡大である。ロシアはさまざまなチャネルを駆使し、欧州各国のポピュリズム、反EU、反エリート、排外主義などの勢力への財政その他の支援を行い、情報戦を通じて現政権批判、さらには欧州社会の分断化・不安定化の試みを強化しているとみられる。2015年以降の難民・移民問題は、各国政府批判や社会の分断化のための格好の材料となっている。今年は各国で選挙が相次ぐために、ハッキングや情報戦を含めたロシアによる介入への懸念が特に高まっている。関連する報道が増加しているほか、たとえば、ドイツや英国の情報機関トップがロシアによる活動の拡大に警鐘を鳴らす状況になっているのである。
2017年は英国のEU離脱問題の行方からも目が離せないが、EUを離脱しても英国は今後も英国であり続けるだろうし、英国離脱後のEUもEUであり続けることがどうにか可能であろう。しかし、ドイツ、フランスで極右やポピュリスト、反EU、排外主義の政権が誕生するような事態になれば、EUは拠り所を完全に失うことになる。それはEUの崩壊であり、第二次世界大戦後の欧州の歩みは、根本から覆されることになってしまうのであろう。
現時点では、フランスで国民戦線の大統領が誕生する可能性も、ドイツでメルケル首相が再選に失敗する可能性も高いとは考えられていない。しかし、「専門家の予想」がことごとく間違ったこ とも、忘れてはならない2016年の教訓であった。
【テロ対策】国際社会の対テロ協力体制に暗雲を投げかける国家間対立
長尾賢
研究員
トルコのイスタンブールのナイトクラブで銃の乱射事件で2017年も幕を開けた。公安調査庁のホームページ「世界のテロ等発生状況」 [i] をみれば、ここ数年のテロ事件の頻回を確認することができる。中東、アフリカ、南アジア以外に、欧州でもフランスで5回、ドイツで3回、ベルギーで2回、デンマークとスウェーデンで1回ずつ起きており、決してイスラム教徒を多く抱える国だけで頻発しているわけではないことがわかる。昨年は花火大会やクリスマスの市場にトラックが突っ込み、バングラデシュで日本人の犠牲者が出たことも記憶に新しい。こうしたテロ事件の頻発と対策の不全が、移民や難民の排斥ムードを高め、昨年の米大統領選挙におけるトランプ大統領の勝利につながった側面も指摘できよう。米国トランプ政権誕生、欧州の選挙を控える今年は、テロの脅威と対策に着目すると、どのような一年になるだろうか。
 特にイスラム国(IS)をはじめとするイスラム過激派の動向に着目すれば、今年は、テロ対策を行う各国の協力体制が整うかどうか、問われる年になるだろう。
特にイスラム国(IS)をはじめとするイスラム過激派の動向に着目すれば、今年は、テロ対策を行う各国の協力体制が整うかどうか、問われる年になるだろう。
たとえばヨーロッパで昨年起きたイスラム過激派によるテロ事件は、ヨーロッパで生まれ、ヨーロッパで育ったイスラム過激派によって実施された例が少なくない。しかし、そのようなテロリストも、みずからと民族的・宗教的つながりがあるシリアやイラクなどの情勢に感化されてテロ事件に及ぶ傾向があることから、シリアやイラクなどで政府の統治能力が上がり、国内情勢の安定化が図られることは、テロを起こす環境を減らすことにつながり重要だといえる。しかし実際には、たとえばシリア、イラク、イエメン、リビア、エジプト、トルコ、キルギス、アフガニスタン、パキスタン、ナイジェリアなどの各国では、政府の統治能力が低いゆえにテロリストを生み出しやすい状況になっている。これらの国々がみずからの力だけでは統治能力を上げることができない以上、テロ対策としては、国際社会が一致協力してこれらの国々の統治能力向上に向け支援をしていく必要がある。
しかし、2016年に起きたいくつかの国家間対立は、国際社会の対テロ協力体制に暗雲を投げかけている。単純化してみると、たとえばシリアでは、アサド政権を支援するロシアに対し、米国は反体制派を支援する立場だ。米国とロシアは、国連安全保障理事会で非難しあい、拒否権を行使し充分協力できていない。
米国と中国の対立も影を落としている。昨年、インドが国連安全保障理事会の場で、パキスタンが支援しているとみられるカシミールのイスラム過激派組織の指導者をグローバル・テロリストとして正式に認め、資産凍結や移動の禁止を行うよう要求した。これに対し、米国をはじめ国連安全保障理事国のうち14か国は賛成の立場を表明したが、中国だけが決定を先延ばしにし続けている。これは中国が一帯一路構想のカギを握るパキスタンを守ろうとしたもので、一致してテロ対策に協力するよりも国益にもとづき同盟国支援を重視した結果である [ii] 。このように、国家間の対立がテロ対策における協力関係構築の妨げとなっており、その裏で、テロ組織が生き残り活動を継続する可能性を与えているのだ。
今年、米国で新しく成立するトランプ政権が、ロシアと協力してイスラム過激派対策を強化する可能性を指摘する意見もある。だが、トランプ氏は、ロシアとの協力関係の一方で、ロシアと歩調を合わせているイランとの合意は破棄することを示唆しており、各国の協力関係を分断する政策も掲げている。このような観点から見れば、国益重視、内向き外交という潮流のなかでテロ対策で各国の思惑の完全な一致をみるには至らず、テロ事件の発生を防ぐことは難しい一年になると想定しておくべきである。
[i] http://www.moj.go.jp/psia/terrorism/index.html
[ii] なお、インドの申請に基づいて国連安全保障理事会にかけられているパキスタンが支援するテロリストについての審議は、2016年12月31日で時間切れ終了となった。だが、インドが再び申請することを計画しているため今年も同じような状態が続くことが予想される。日本はインド側に賛成の立場であり、2016年11月の日印共同声明の中でも、パキスタンを名指しして、より強い取り組みを求めていて、パキスタンは日本に対して遺憾の意を表明している( http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000203259.pdf )。そのため、このテロ対策では、日米印と中パとの間で、はっきりと立場が分かれた状態にある。